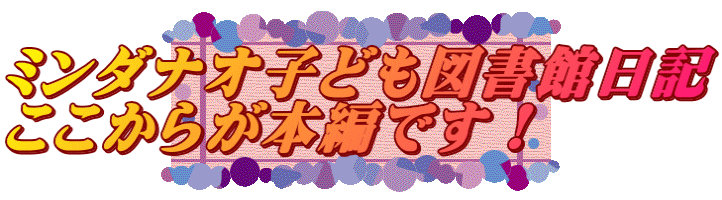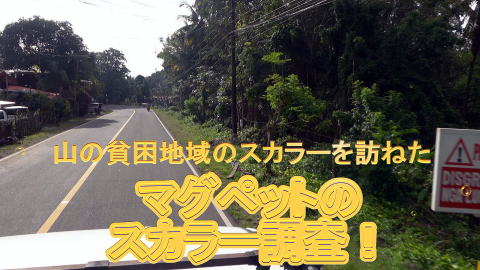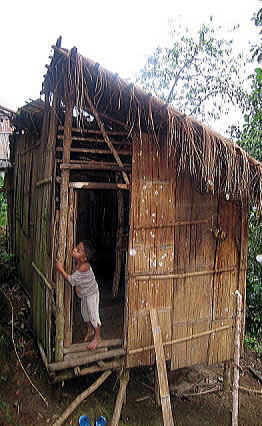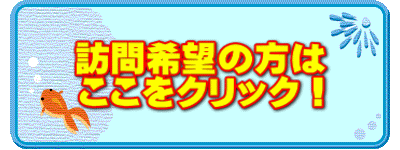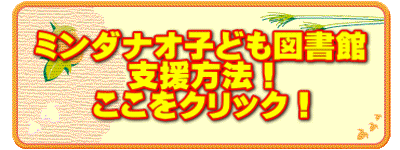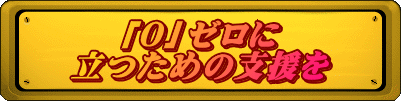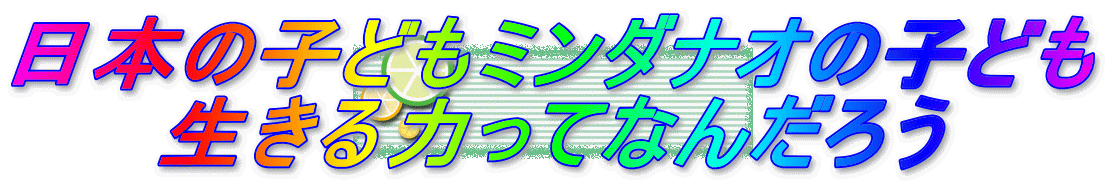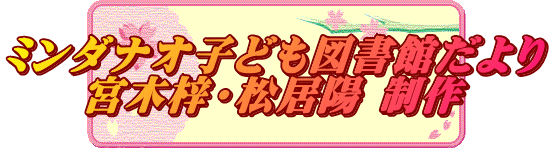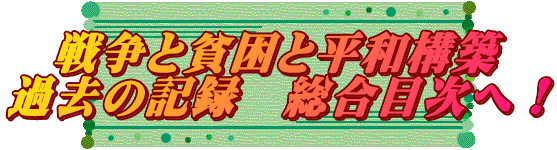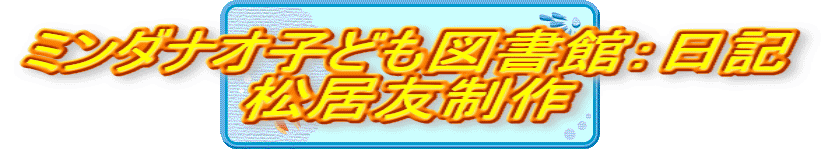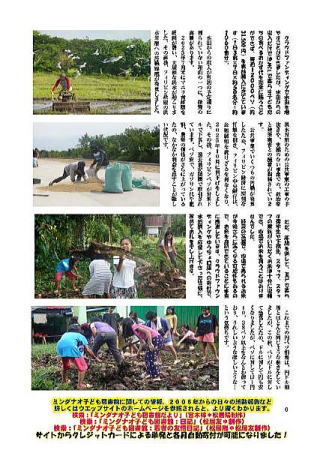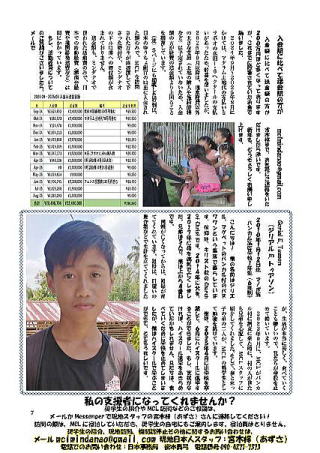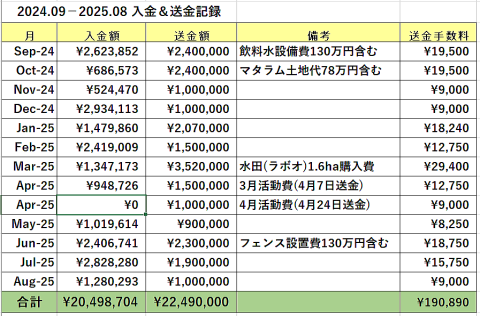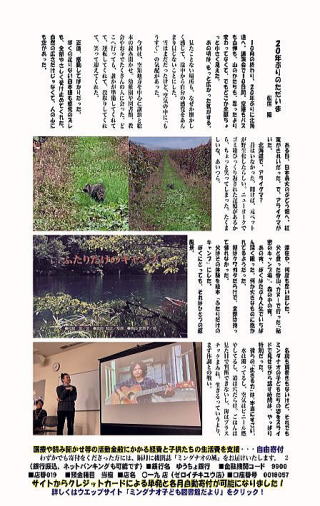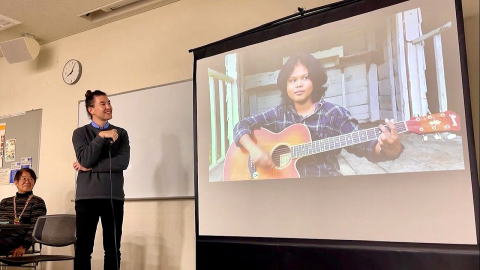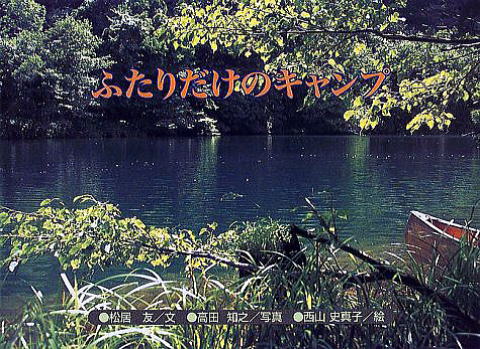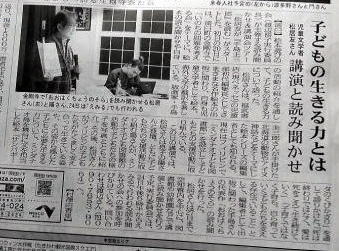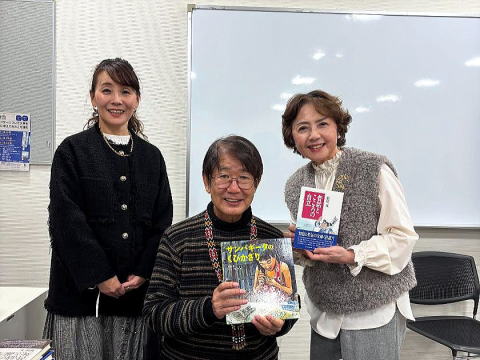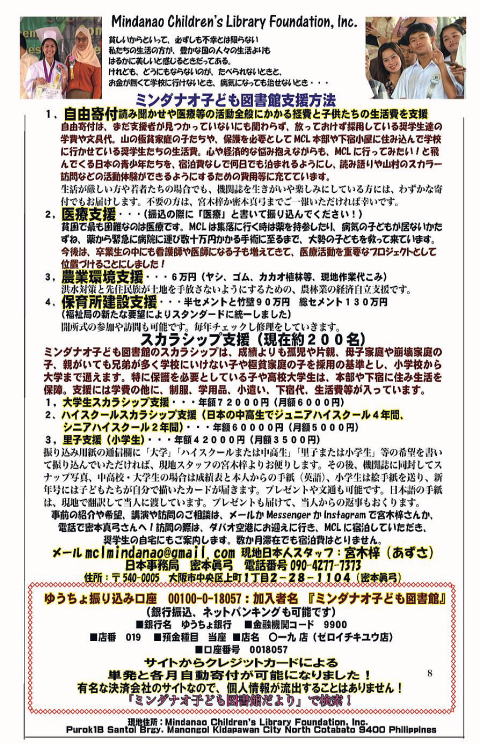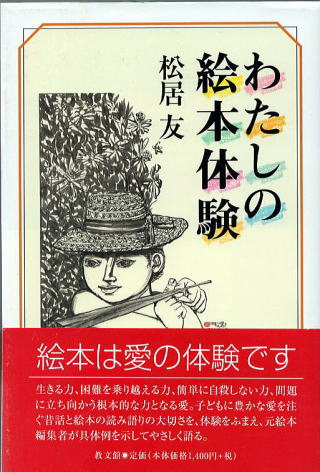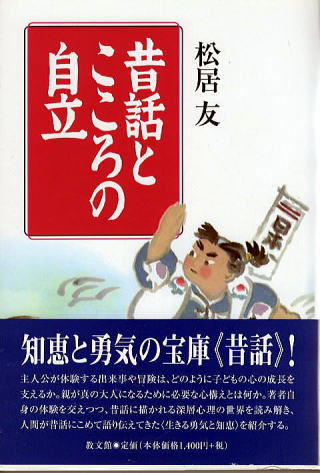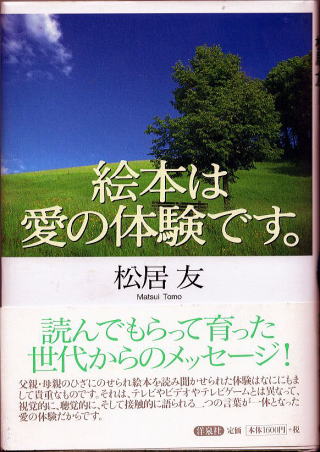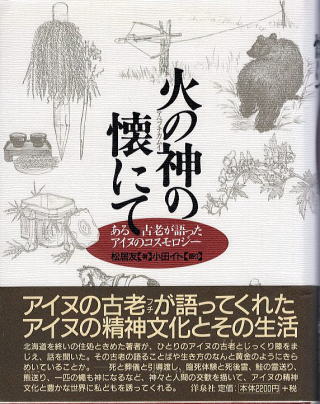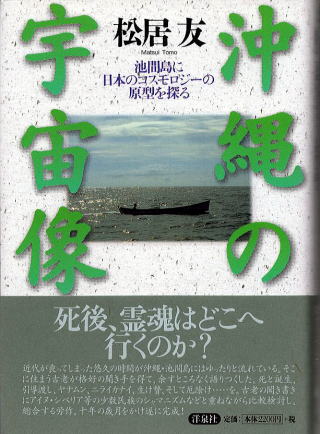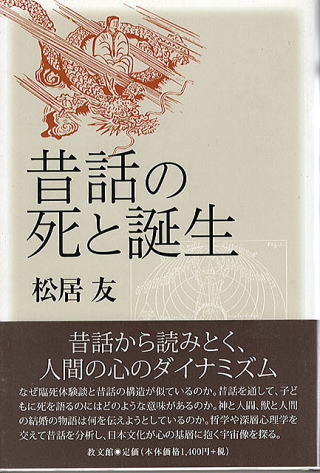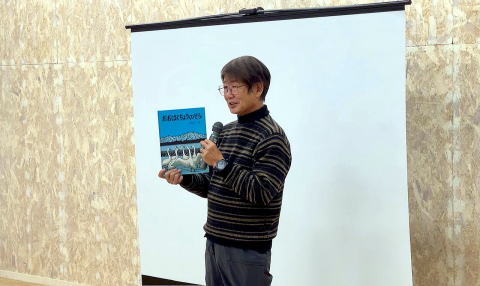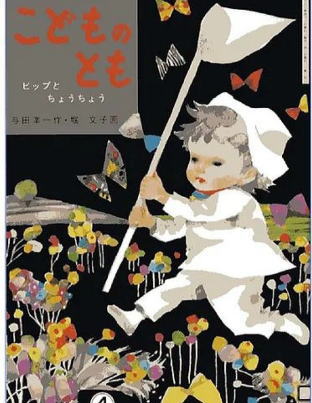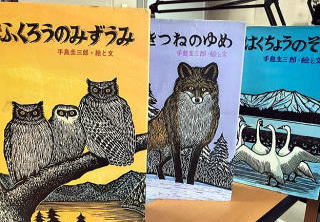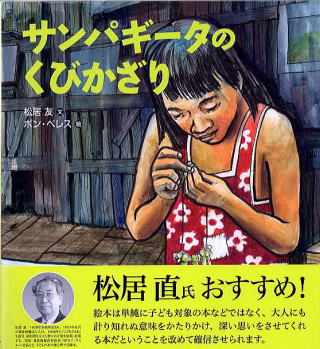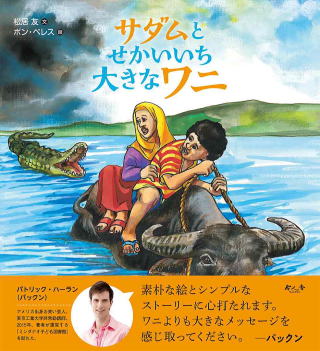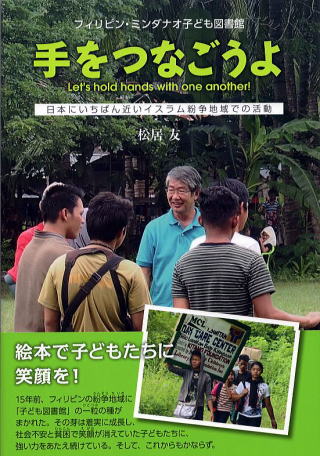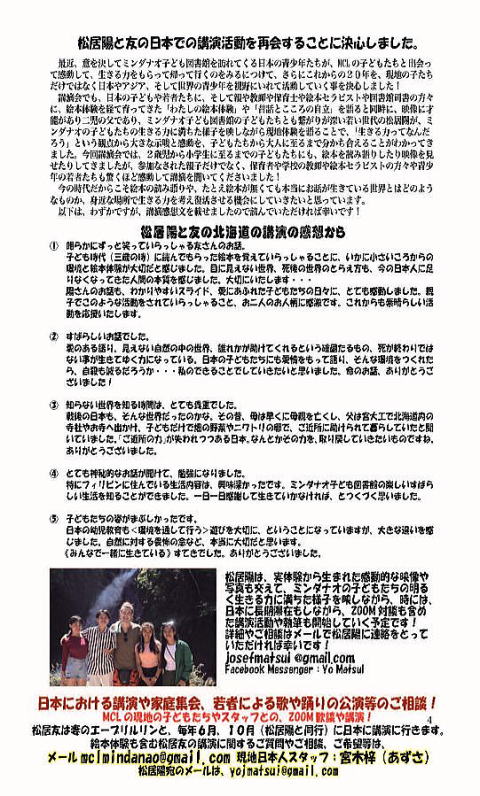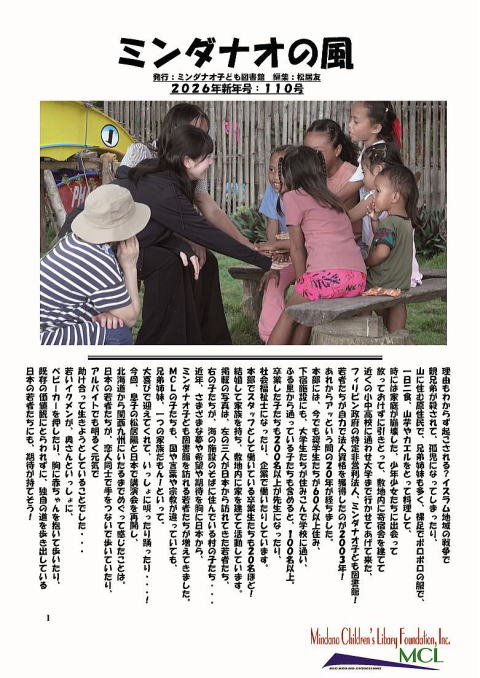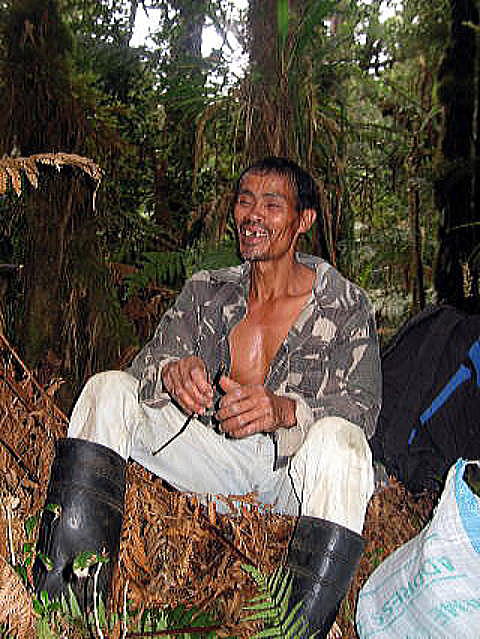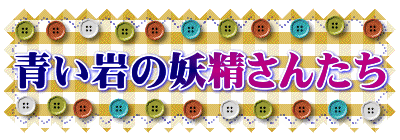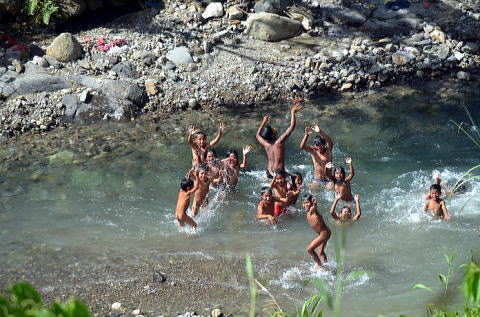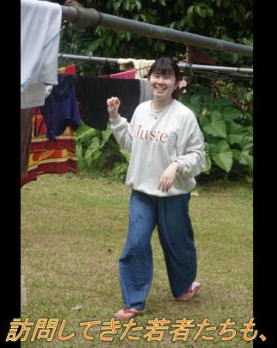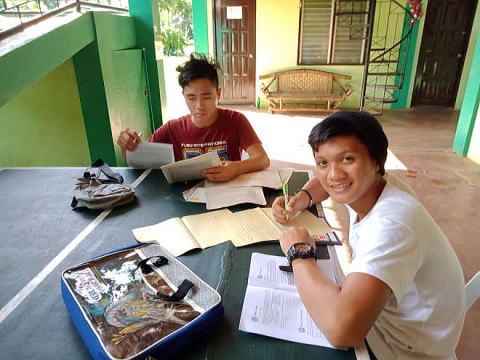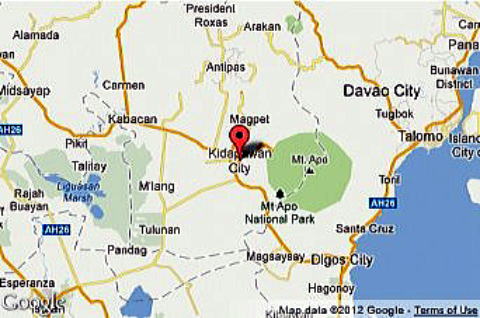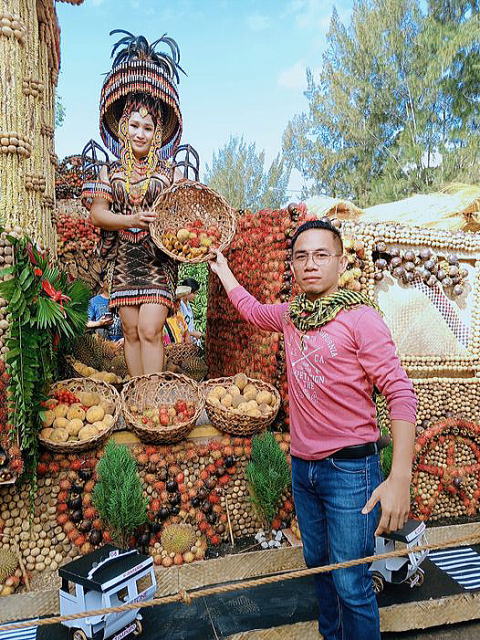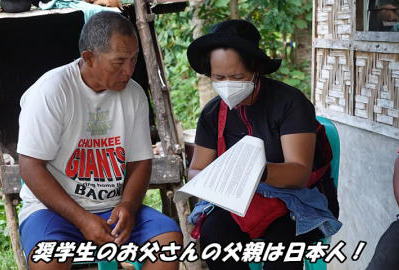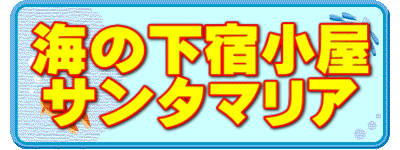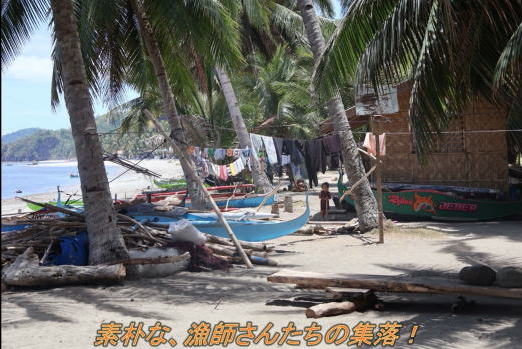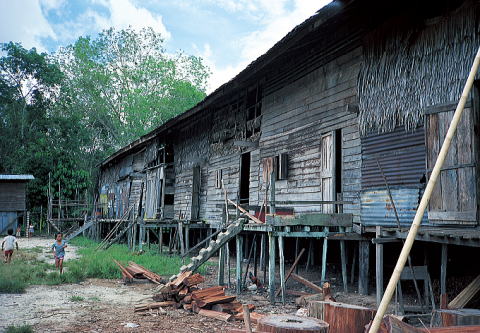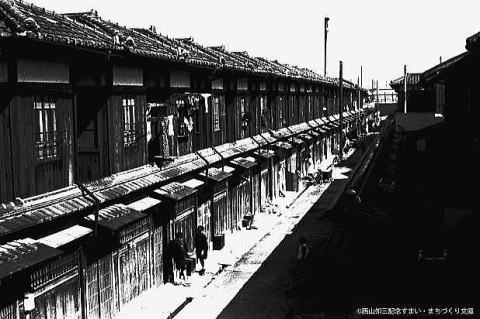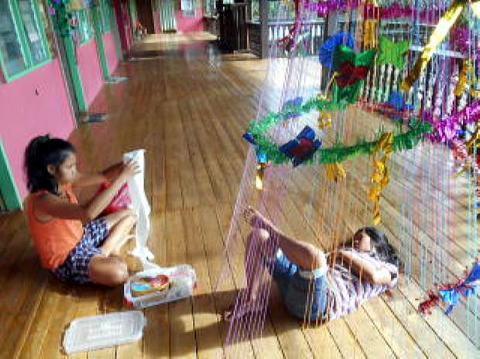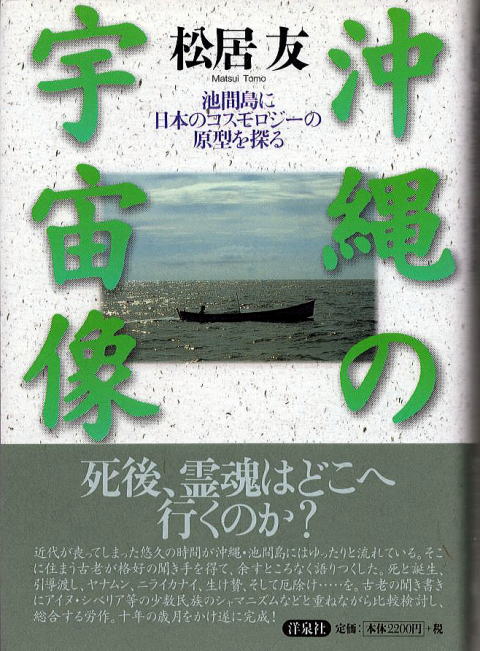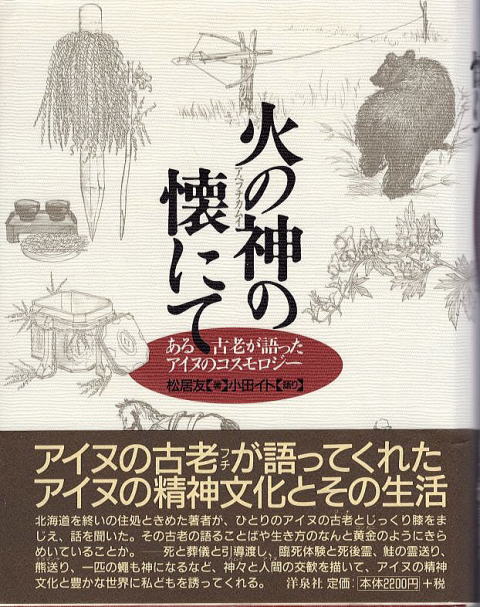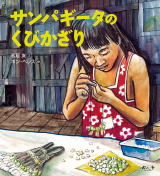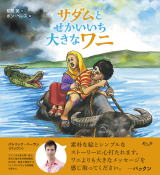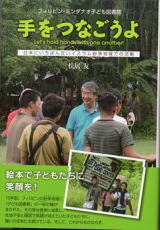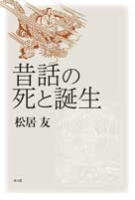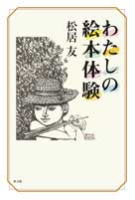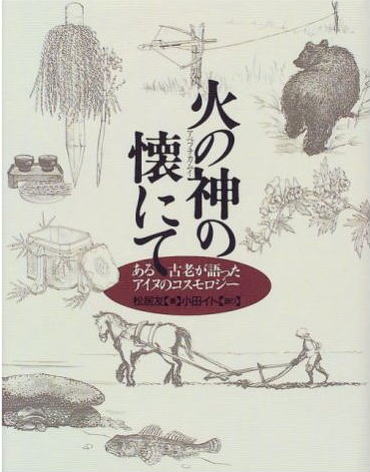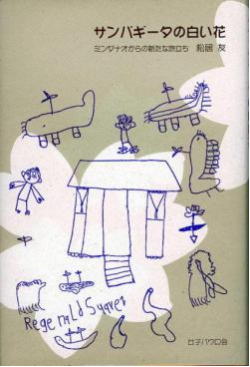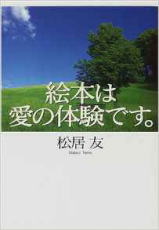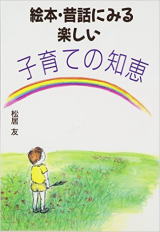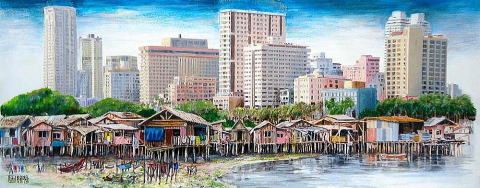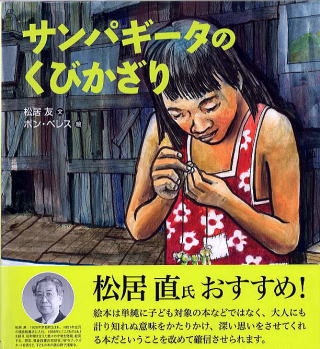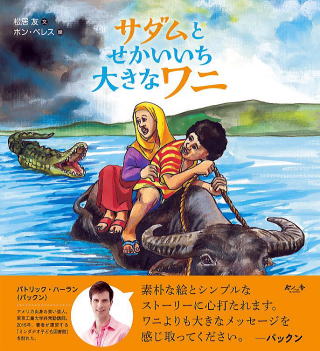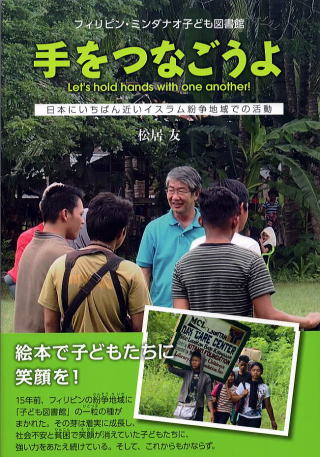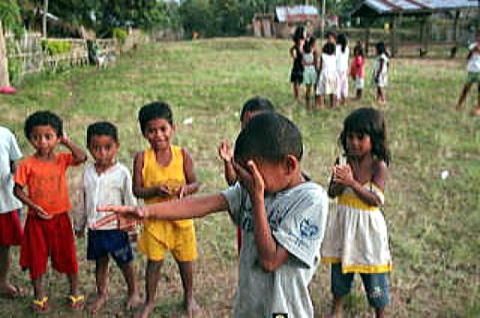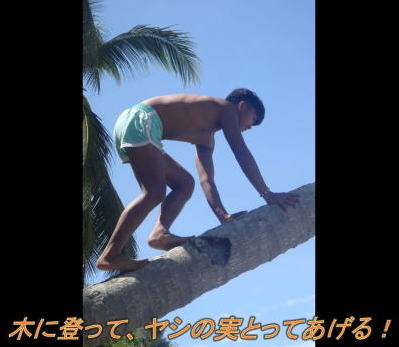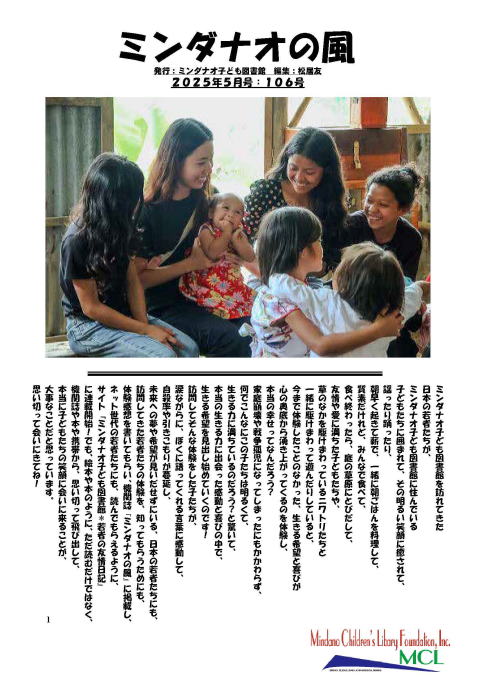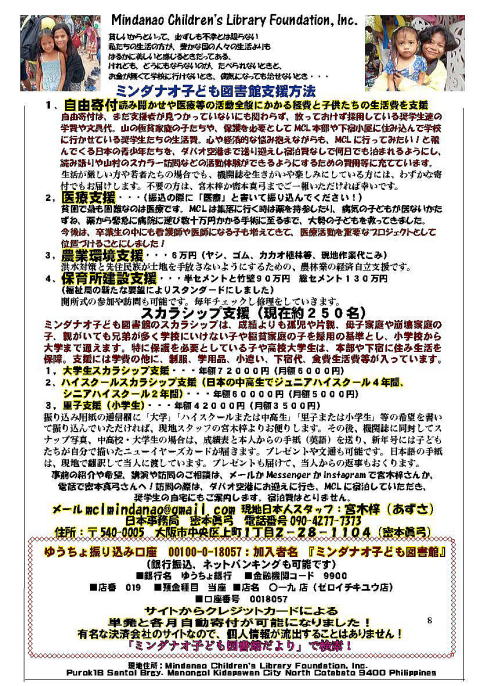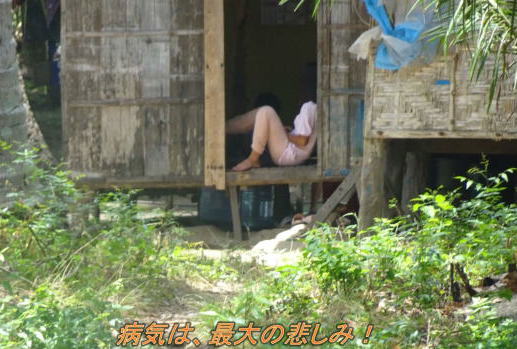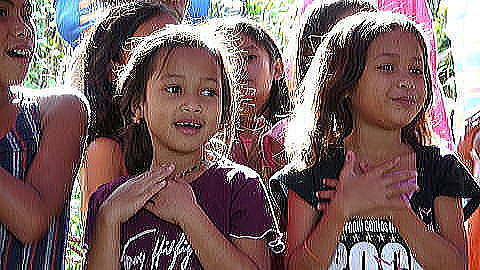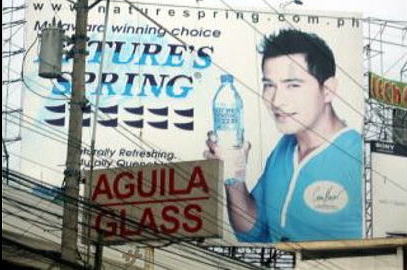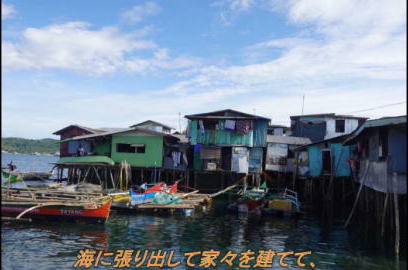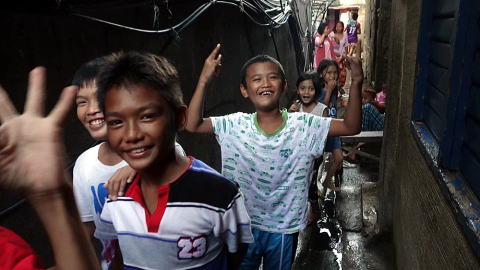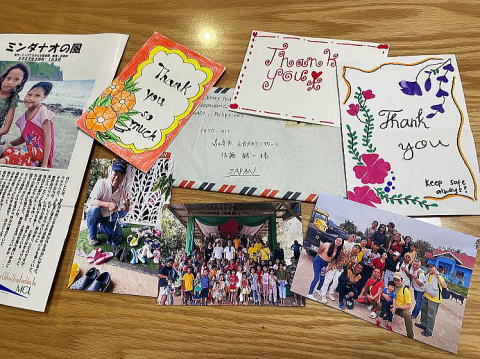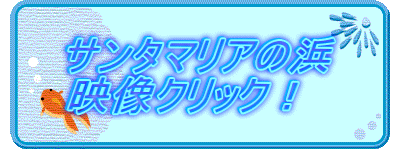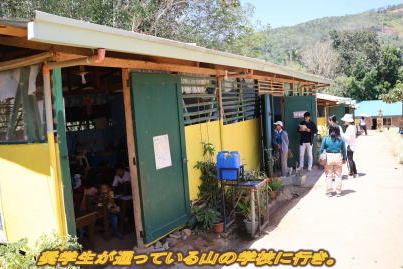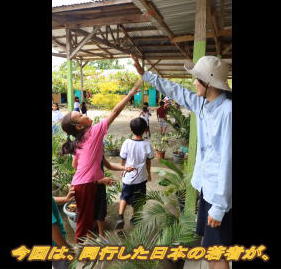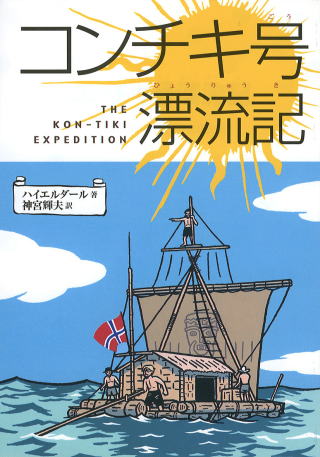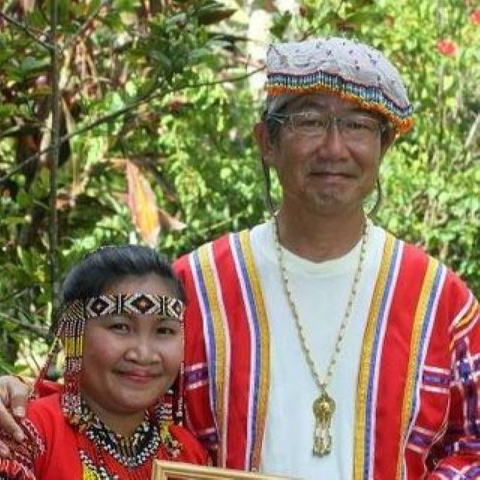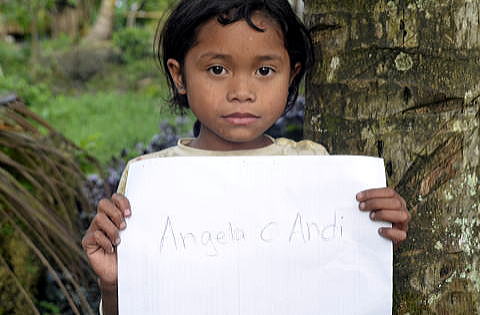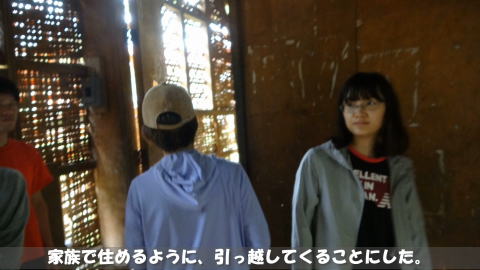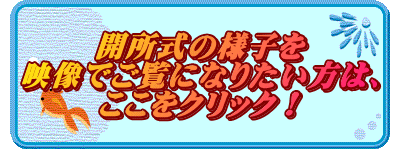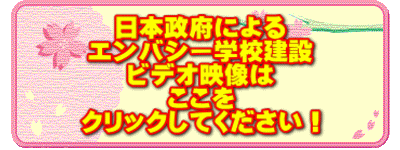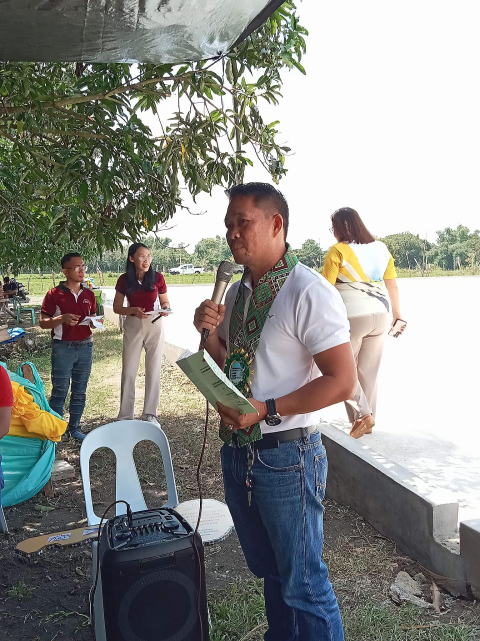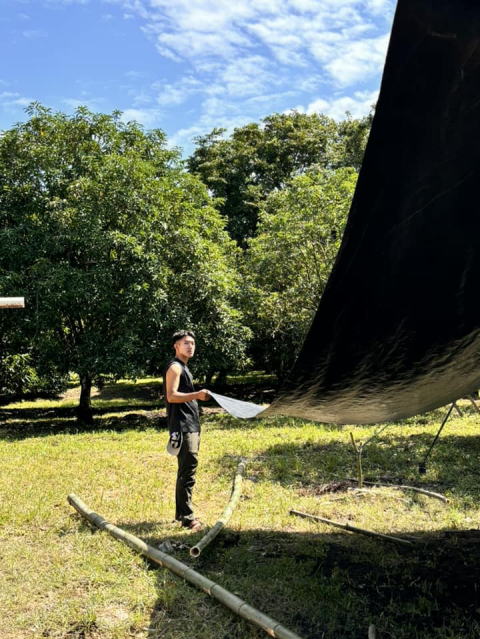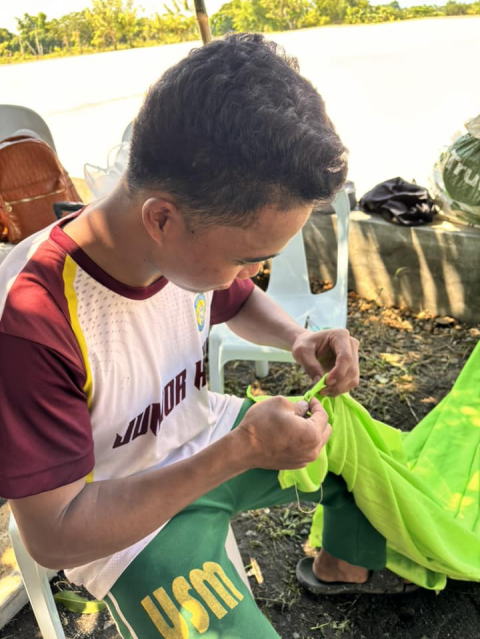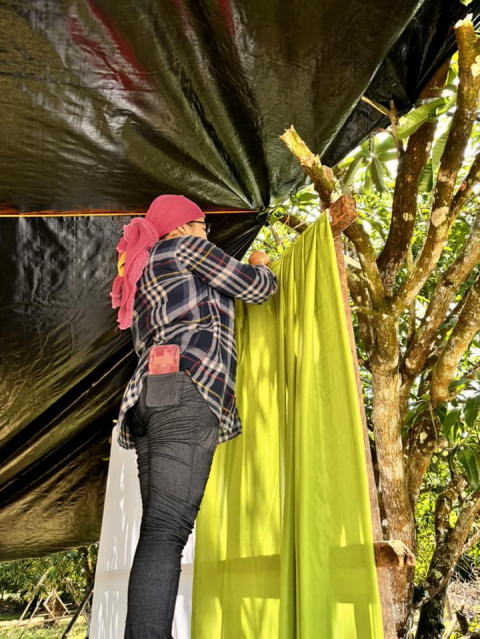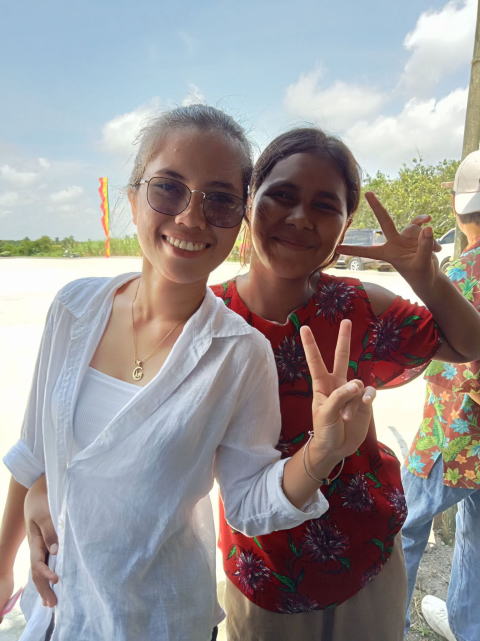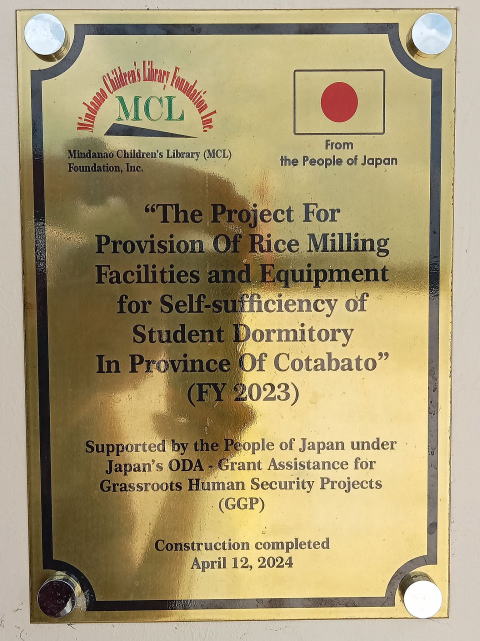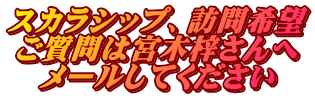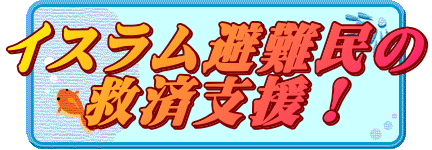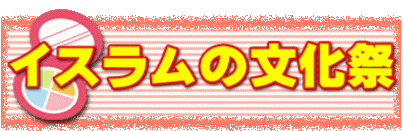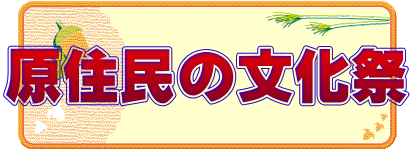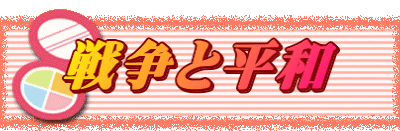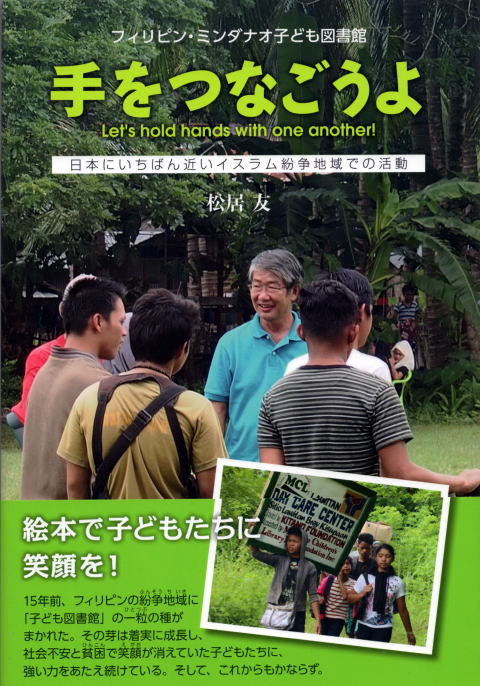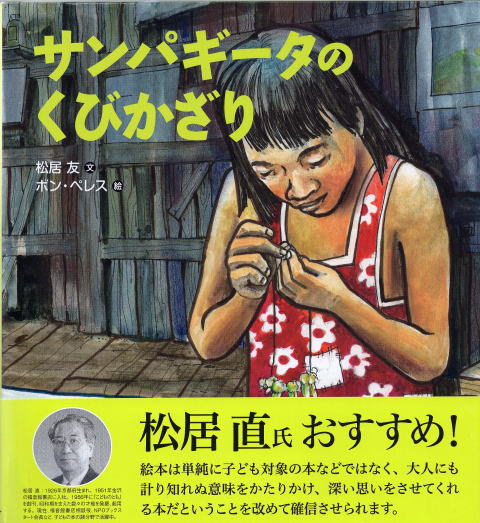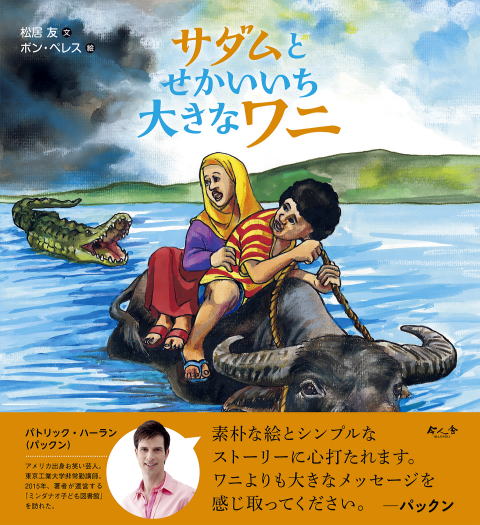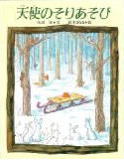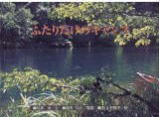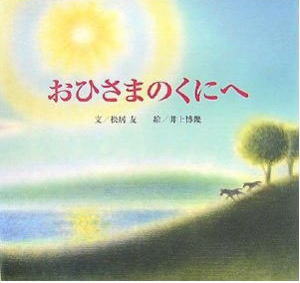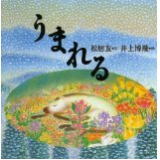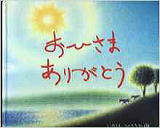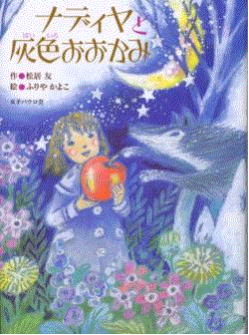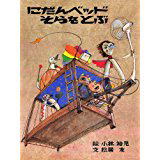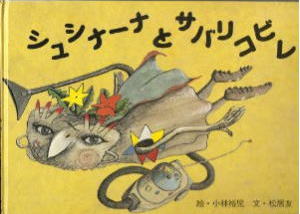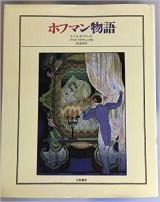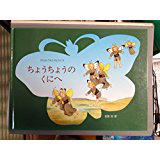minda2024-5
ミンダナオ子ども図書館:日記
2024後期~5年前期の活動から!
全目次
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
日本の若者たち海辺の子たちに会いに(1)
サンタマリアの海の家
目次 |
❶ミンダナオ子ども図書館の日常から |
1)なぜミンダナオ子ども図書館を建てたか
①子ども図書館を建てることにしたのは
②スーザン インカルさんを紹介
③岩の上で妖精と一緒に作っているの!
④アポ山はフィリピンでは最高峰の山
⑤アポ山という死者の集まる祈りの場所
2)ミンダナオ子ども図書館の日常から
①ミンダナオ子ども図書館の台所。
②ニワトリをつかまえて首を切って!
③早朝から起きて薪でご飯を炊いたり!
3)日本の若者たちもいっしょに洗濯!
①お洗濯をはじめたり!
②若者たちもいっしょに洗濯!
4)みんなで遊ぼう!
①おかずの野菜を植えようよー!
②バライバライは楽しいよ!
③竹馬も作るよ!
④ちまたで遊ぶ友情が生きている!
5)運営しているのは子どもたち!
①運営しているのは子どもたち!
②果物がたべたかったらとってあげるよ!
③食べ終わったらみんなで遊ぼう!
④最後に枯れ葉と草のお掃除!
⑤わたしたちはお米干し!
6)さあ、海へ行くよーーー!
①さあ海へ行くよーーー!!!
②何日でも滞在できますよ! |
❷かつての日本もこんなだった! |
1)サンタマリアの海へ向かった!
①キダパワン市は!
②サンタマリアの海へ向かった!
③海ってどんな所なの?
④素朴な生活が生きている!
⑤この素朴な村の浜に家を建て 
⑥海の子たちと友だちになって 
2)奨学生の村を訪ねた
①サンタマリアの町に着く
②奨学生の状況を把握
③お父さんは日本人!
④お父さんたちも家族のために
3)ミンダナオ子ども図書館の海の家に到着
①海の上に浮かんでいるのは養魚池!
②最後に浜から半島の丘を越えて!
③クラクシン集落に到着!
④ミンダナオ子ども図書館の海の家!
4)日本もこんなだった?
①素朴な漁師さんたちの集落!
②愛と友情が生きる力
③日本もかつてはこんなだった?
④ふとんをひいて雑魚寝していた!
⑤子どもが生活する建物は
⑥その子の部屋の前にあつまって |
❸こんな体験、生まれて初めてー! |
1)愛と友情を前面に出して
①みんなで寝ている子が多い!
②ふる里の家では竹の床のうえに
③ぼくも雑魚寝した体験から
④長屋が生活の場で
⑤ミンダナオでも山岳地域や漁村では
⑥孤立化が浸透して
2) 平和を創っていくのは若者たち?
①本来は日本の文化のなかにも
②若者たちの幸せな未来は
③平和な世界を創っていくのは若者たち?
④日本だけでなく世界の若者たちと
⑤体験こそが大事な気がして
⑥ふる里に対する想いは変わらず
3)生きる力は子どもたち同士が!
①なぜこんなに自殺率が低いのかな?
②いたるところに子どもたちの姿が
③孤独で死ぬってどういうこと?
4)村の子たちが遊んでいるよ!
①海なんか行ったことも無い!
②浜に着くと感動して
③ミンダナオ子ども図書館の子が来た!
5)日本の若者たちも視野に入れて!
①訪問してきた若者にたいしても
②我が家に帰ってきたような気持になる
③こんな体験生まれて初めてーーー!
④この子たちもMCLの奨学生の子たち
⑤ありのままの体験ができるように |
❹生きる力ってなんだろう! |
1)生きる力は子ども同士がつちかって!
①なぜこんなに自殺率が低いのかな?
②村の子たちが遊んでいるよ!
③子ども図書館の子たちが来た!
④この子たちもMCLの奨学生の子たち
2)友情と愛こそが生きる力!
①みんなおいでよいっしょに遊ぼう!
②遊びのなかでつちかわれる!
③友情と愛こそが生きる力!
④木に登ってヤシの実とってあげる!
⑤みんなで食べて。おいしいよ!
3)なかよしが何よりもの幸せ
①なかよしが何よりもの幸せ
②だいじょうぶ?
③いっしょに遊ぼう!
④なかよしが何よりもの幸せね!
4)おいしいよ!!
①これ食べられるかなあ?
②おいしいよ!!
5)とつぜん難病で亡くなった!
①定期的に奨学生の家を訪れて
②母と娘と二人で訪問・・・
③村の奨学生たちの家々をめぐって
④最後に奨学生だった子の家を訪ねた
6)涙がこぼれて止まらなかった!
①言ってくれたら助けたのに!
②涙がこぼれて止まらなかった!
7)病気は最大の悲しみ!
①薬一つ買えない貧困の子たちにとって
②病気は最大の悲しみ!
③この子も同じ難病の奨学生で
8)お母さんのお別れ会
①お母さんが先に帰られるので
②お母さん私が歌ってあげる!
③お別れの挨拶の後
④夕暮れとともに家族のために |
| |
日本の若者たち
海辺の子たちに会いに(2)
大都会の海に張り出した貧困地域ササ
目次 |
ダバオの町の海に張り出した貧困地域
❺ササの子たちに会いに! |
1)ササの奨学生たち
①靴も無く服もボロボロ!
①-B ふる里から通いたい子はそれもOK!
②町の海沿いの貧困地帯
③ダバオの町はずれのササ
④海に張り出した木材の上に
⑤ササの奨学生たち
⑥妹のスカラーに手紙を渡し
⑦病気の子がいると病院に運んで
2)日本の若者たちも大感激!
⑧日本から来た若者たちと
⑨同行してくれた若者たちから
⑩日本の若者たちも大感激!
⑪国籍や宗教が違っていてもひとつの家族
⑫今回のササ訪問の目的は
⑬お母さんも大喜び!
⑭こんな体験を日本の若者たちに
⑮みんな元気にしているね! |
| |
日本の若者たち
新年度スカラー調査の旅
目次
|
貧しくとも幸せそう
深い山奥の村にも向かった!  |
1)フィリピンでは8月が新学年なので
①進学への意思や状況を知るために
②奨学生が通っている山の学校に行き
③子どもたちに会って状況を把握!
④進学祝いの学用品とお土産を渡す!
⑤古着や靴をあげているので
⑥大喜びで駆けてくる!
2)今回は、同行した日本の若者が
①同行した日本の若者が
②訪問した若者たちの体験記
③ふる里の学校に通いたい子は
④はるか麓の学校に歩いて通わねばならず
⑤MCLの本部に移り住むのを希望
3)どうしても放っておけなくなり採用
①家庭が崩壊した子を推薦されると
②どうしても放っておけなくなり
③この子たちが幸せに育ち
4)ここは先住民優先の小学校
①地震で倒壊し
②山麓への避難生活を強制されて
③空き地に作られた小学校だ
④マノボ族の奨学生もこの学校に通って
5)山里の我が家には帰れない!
①四年以上もひなん場所で生活をしている
②山里の我が家には帰れない!
③仮設住宅としてはまだ良いところで
④ビニールシートで暮らしている避難民!
6)深い山奥の村にも向かった!
①調査のためにたくさんの学校を巡る
②福祉局や先生たちや先住民の酋長から
③学校に通えない子を奨学生に採用!
7)スカラーだった子に出会った!
①驚いたことにはスカラーだった子に
②16歳で結婚したけれど子供も生まれて
③貧しくとも幸せそう
④妹が高校に行きたくても行けない
8)遊びで培われる愛と友情が生きる力!
①また別の子たちの調査に向かった!
②家庭が崩壊して置き去りにされたり
③子どもたちは本当に愛らしく
④遊びで培われる愛と友情が生きる力!
9)こんなところを歩いて通っているんだ!
①先生から依頼された子に導かれて!
②その子の家に向かった
③毎日こんなところを歩いて
10)家庭が崩壊して
①叔父さんの家に住まわせてもらっている
②学校に通わせるのは無理との事!
11)おばあさんは泣き出した!
①さらに村の福祉局で依頼された
②別の子たちの調査に向かった!
③必ず住んでいる家を訪れて
④成績は優秀だけれど
⑤食べさして行くのも大変!
⑥その場で採用を決定!
⑦大学まで行けるなんて夢みたい!
12)貧しいけれど7人は子どもがいる!
①また別の子の家に向かった!
②平均して7人は子どもがいる!
③子どもこそが家族の宝!
④姉兄ちゃんも下の子の面倒を見たり!
13)将来家族を助けたいの!
①だから下から二番目の妹とわたしが
②年下の女の子が選ばれる
③圧倒的に女性が多い!
14)地震で教会と家が倒壊して
①お母さんとがんばっていましたよ!
15)『地震の悲しみで父さんが」映像から
①地震避難民の支援をしにいった
②絵本の読み語りと歌と踊りと
③日本から送られてきた靴を配り
④家族が集まって今後の事を話し合った
⑤5人の子どもたちを奨学生に採用
⑥崩れた山の生家に向かった
⑦山崩れの現場にも向かった
⑧家族で住めるように引っ越してくる
⑨若者たちががんばって修理費を!
⑩家族たちは大喜び! |
| |
日本の若者たち
日本政府のODAによる精米所が完成!
目次 |
序章:天から降りてきた? |
1)日本政府のODAとの連携
2)先住民地域で地震が繰り返し起こり
3)水田を購入していく事
4)一年間に2.5期作の収穫
5)外部に依頼せねばならず
6) コンクリートのお米干し場と精米所
7)敷地内のお米干し場と精米機では
8)厳しい状況になってきました!
9)精米を外注することなく
10)地震で倒壊した学校のODAによる再建
11)石川総領事様と織田副領事様が
12)天から降りてきた言葉のよう
13)日本から来る若者たちにも |
本章:日本政府のODAによる
米干し場と精米所が完成! |
1)開所式の準備を始めた!
2)マンゴーの木陰は来賓席で
3)日本から来た若者もお手伝い!
4)日本の国旗を貼られて行かれた
5)倉庫の前に張られた記念ボード
6) 訪問者にも食事を提供
7)いよいよ授与式が始まった!
8)大喜びしたのは子どもたち! |
| |
国や言語が違っていても兄弟姉妹!松居友
目次 |
kyou0
国や言語が違っていても兄弟姉妹! |
1)国や言語が違っていても兄弟姉妹! 
2)ポーチでおおはしゃぎ! 
3)交流もできる場所 
4)生きる力もすばらしい! 
5)どこのNGOなのですか? 
6)でもやってみる! 
7)日本人のぼくが 
8)救ってもらっている 
9)どうしてあんなに語る力が? 
10)本当にお話が生きている世界 
11)愛と友情で溶け合って 
12)日本の子どもや若者たちも 
|
| |
ミンダナオ子ども図書館を
立ち上げた理由とこれからの子たち 松居友 
目次
|
子ども図書館を創設したきっかけは
日本そして世界の青少年を視野に入れて
|
1)ミンダナオ子ども図書館の設立 
2)雨が降ったら大変だ!
3)サダムとせかいいち大きなワニ 
4)表情を失っている子どもたち 
5)戦争は繰り返し勃発し 
6)可哀そうなのは子どもたち 
7)山に追いやられた原住民たち 
8) そういった子を目の前にすると 
9)住んでいる家を訪ねて 
10)そうした子たちの場合 
11)ふる里はなつかしの場所 
12)この子が我が子だったら 
13)子どもたちが率先して 
14)ここが一番いい! 
15)子育つ社会ミンダナオ 
16)まるで探検旅行のよう! 
17)夢と希望と生きる力 
18)孤独で死ぬんだよ 
19)これからの20年! 
20)平和に子育つ 
|
| |
機関紙『ミンダナオの風』
2025年新年号特別紹介!
目次 |
ここは君たちのホームだからね!松居友 
世界に広げていく手助けを 松居 陽
貴重な体験をありがとう
石黒はるな(11歳)小学校5年
|
機関紙「ミンダナオの風」が100号を迎えた! 
|