
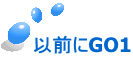

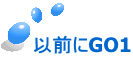
 ..
..
ミンダナオ子ども図書館:新しいスカラシップ希望者たち 12月24日
クリスマスおめでとうございます。
ここ一週間ほど、新しいスカラシップ候補者の調査に山を飛び回っていました。
家庭調査は、抜き打ち的に訪問するもので、今回は特に戦闘のひどかったイスラムのピキット、コランボク村とNPA反政府ゲリラの多いと言われているマキララ山岳地域のバゴボ族の村から候補者を21名、第一次候補として選考しました。
家庭調査は、ミンダナオの現状を肌で知る最も貴重な活動です。
スカラシップ支援を希望の方は、メールで直接、この子を支援したいと言うお便りを下されば年明けにお返事いたします。先着順で決定していきたいと思いますが、すでに来年度支援登録をなさっている方を優先いたします。
候補者の写真、家族や家の写真と、家庭の状況説明は、ホームページに新しく
「来年度2007年・スカラシップ候補者の紹介」という項目を載せましたので、表紙からクリックしてお入り下さい。
若者たちの写真、家族の写真、家の様子などを写真と文章で掲載しています。
支援方法などは、ホームページ表紙から「ミンダナオ子ども図書館支援方法」をクリックしてお読み下さい。

以下総括的な報告をいたします。
*************************
9月に400名を超える応募があったスカラシップ。その中のAランク(親のいない子や片親の子)を中心に最初の家庭調査をした。
今回は、戦闘のあったイスラム地域のコランボクと山岳地域のバゴボ族の村を重視した。
バゴボ族の地域は、前回読み聞かせで行ったバト村から調査を開始。
前回紹介した重病の母親を持った兄妹を訪ねたが、母親がライ病を患っていると知った。
わずかなお金もすべて母親の病気の薬に消え、子どもたちは学業をストップせざるを得ず、少年はゴムの木の汁を集める日雇いをしている。
高校に通える少年と今年6年生を卒業する妹を候補者とする。
少年は高熱で寝ていたが、写真を撮らせてくれた。
母親や家族の写真も感動的だ。
お姉さんは、学業をあきらめてそのまま母親の面倒を見ると言い、家族みんなで病気の母親を大事にして生きている姿は感動的だった。

同じ村から、21歳の若者が高校のスカラシップに応募してきたので訪ねた。
背が低く10歳ぐらいにしか見えない。子どもの頃に頭部を患い、矮小症になった。
ゴムの木の汁を集める日雇いを兄としているが、背が低いので大変。学問の道に希望を見いだしたい。
父親は死亡し、母親は再婚しているが、相手は若いアライアンスの牧師で良い人のようだ。
さらに4WDで山を登り詰め、それでも不可能になり徒歩で尾根上のバゴボの村に着いた。
地上の楽園のようで子どもたちはかわいい。
学校が遠くてほとんどが小学校低学年止まり。川を越えて山岳地帯を6キロ以上歩く。
ようやく、高校を卒業した子を一人、小学校卒業する子を二人見つけた。
今回は、女の子の応募が多かったが、学校が遠いので、小学校高学年の数名、高校生候補2名を大学生候補の子1名といっしょに、6名ほどミンダナオ子ども図書館に住みながら学校に通う可能性を検討する事にした。
イスラムの山岳地域の子も同じだが、友達や姉妹が一緒だと寂しさがやわらぐ。
写真で見てもおわかりのように、高校一年生は日本の中学一年生で、まだまだ幼くあどけない。

今後も、読み聞かせをしに、奨学生たちと訪ねたりしながら、長く良いおつきあいをしていきたいすてきな村だった。
イスラム地域の戦闘のひどかったコランボクは、大学の候補者を数名、高校の候補者とともに採用した。
悲しいのは、親兄弟を病気でなくしている子が多く、聞くと度重なる戦闘と難民生活のせいである。
悲しみを越えて、戦争のない世界を作る試みを、彼らこそ始められるのではないかと感じる。
イスラム地域の候補者は、男の子の若者が多い。
心の葛藤を持っている気がして、けなげな感じがする。何とか希望の実現と笑顔を快復させてあげたいものだ。
皆さん、どうか一人でも多くの若者が、未来に向かって一歩一歩歩み続けることが出来るように、支援をお願いいたします。
追伸:ルモット村から来た子が腹痛と下痢の病気で亡くなりましたが、そのまた2名運ばれてきて、こちらは快復してきています。

イスラムの村の高熱の子は無事快復し山に送り届けました。
26日から30日までは、親のない子や事情がある子たちと共に、クリスマスがさびしくないように、海にテントをはり海水浴に行きます。
良いクリスマスとお正月を!
ミンダナオ子ども図書館だより 12月23日
盲目のベルリーンさんを実家に送った。
場所は、戦闘のあったピキットの奥。マノボ、イスラム、クリスチャンが共生している村のさらに奥。
川には丸木橋が架かっている。
丸木橋を迎えに来たおじさんの背に乗って運ばれていくベルリーン。

実家は、トタンを組み合わせただけの粗末なものだ。
これでは、強い雨が降れば雨もしのげないのではないかと思うのだが・・・・

それでも、ベルリーンさんは、兄弟にも会えてうれしそうだ。
新しく赤ちゃんも生まれ、5人の兄弟姉妹がいる。
一家は、ビサヤ系移民。

お母さんと一緒に写真をとった。
お母さんも、右目が見えない。
戦闘のあった時期に、難民生活を余儀なくされ、そのときから片目が盲目となった。
このような症状の子どもは多く、過去何人も治療してきた。
戦闘時期に生じる症状の一つとして、戦闘の際に使われる兵器と関係があるのではないかと疑われている。

ミンダナオ子ども図書館だより 12月20日
ミンダナオに帰り、多くの仕事が一度に待ち受けており、休む間もなくクリスマスとお正月が近づいています。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
簡潔に、その間に起こっている事をお知らせしたいと思います。
最も大きな出来事は、17日のクリスマスパーティーをかねた、若者たちによるピーストーク(文化と宗教の違いを超えていかに平和なミンダナオを築いていくか)のパネルディスカッションとパーティーでした。
そのために、三つの記録映画を制作しました。
お分けすることも出来ますので、下記の記事の最後をご覧下さい。
最近の出来事
ダバオの障害者施設でリハビリ中のジョイの義足が完成し、歩行訓練に入った。
最初は痛がっていたジョイだが、がんばって一歩一歩あるいている。
まだ、歩行棒を握ったままの訓練。

あいかわらず笑顔を絶やさない子で、来年の6月からの新学期には、歩いて大学に通えるだろう。
すっかり背が高くなった?ジョイは見違えるようだ。
「支援者のI様、感謝しています。これから大学に行ってがんばりますね!」
本人の話では、コンピュータプログラミングを勉強したいとのこと。歩行に障害が残ることを考えると良いと思う。
カニのような手でコンピュータを打つことになるが、すでに施設で練習をしている。
26日から30日までは、ミンダナオ子ども図書館の子たちの中で、親がいなかったり何らかの事情で家に帰れない子たち20名ほどで、海にキャンプに行く。
(家族のまねごとのような事をする)が、ジョイも参加する。
クリスマスシーズンは、家庭の状況が複雑な子、片親の子、親のない子には、一番さびしいシーズンとなる。他の学生たちが、皆喜々として親元に帰るので、寂しさがいや増す。
先日も一人がさびしそうにしているので(だいたい私の部屋の外あたりにいてわかるので)声をかけて、「さびしいの」と問う泣き出した。
互いに同じ境遇の子も多いので慰め合うのだが・・・
生き別れになった、お父さんやお母さんに会いたい子、亡くなった親を思い出す子が多い。
先日、ヘレンケラーの映画、「奇跡の人」を、DVDで映写会を家でしたが、赤ちゃんを抱いている母親の姿など、赤ん坊の時に捨てられた子などは、食い入るように見ている。
胸を打つ。
彼らには少なくとも、ミンダナオ子ども図書館が、時々さびしくても、安心していることの出来る居場所になっている。
「いつか、いい人を見つけて結婚して、幸せになってくれるといいなあ」
と言うと、うれしそうな顔に変わる。
「でも、ゆっくりと慎重に、結婚相手を選ぶんだよ」
そういうと、始めて笑顔を見せてうなずく。
「何か心底困ったことがあれば、帰るところがなければおいで」
そんな話をすると、安心した様子で
「でも、まずは勉強して、卒業しなくちゃね」
そのようなわけで、海に泳ぎに行くことは意外と大切なプロジェクトだ。
ダバオオリエンタルの方へ、テントを持って行く予定。
参加したい方はどうぞ・・・
先日、山から運ばれてきた子が、数日来下痢がひどく脱水状況だったが、今朝病院で死亡。
もう少し早くミンダナオ子ども図書館にこれば助かった命だった。残念でならない。
5日間、高熱が続いているイスラム地域の男の子が、今朝病院でチェックを受けた後に入院。
今、様子を見ている。
デング熱を疑われたイスラムの奨学生、ノルミナさんは、高熱だけで無事に退院。
クリスマスパーティーの後に、急性の下痢が広がったが、こちらの方は正露丸で乗り切った。
(正露丸が切れてしまい、どなたか送っていただけませんか?)
医療プロジェクトが続くが、予算が逼迫している。今年は東京メソニックからの支援がなく、図書予算をすべて医療に回しているが苦しい。
兎口など生命に影響しない治療は延期してもらい、緊急の患者を受けるようにしているが・・・
盲目でダバオの盲学校に行っているベルリーナさんがクリスマスに家に帰るために迎えに行った。
少し成長し、以前はほとんど話をしなかった子が、少しずつ話すようになった。ご飯もこぼさずにきれいに食べる。
ゆっくりだが確実に成長している。

盲目のジュンジュン君は、元気で積極的だ。クリスマスパーティでも歌って大好評。
目が見えないが、草刈りを始めたり、自転車に乗ろうとしたり・・・
村の教会まで行き、帰れなくなり、トライシクル(三輪バイク)で送ってもらって帰ってきた。運転手はお金を受け取ろうとしなかった。
クリスマスのキャロリングを村の家々を回ってして、お金をもらってくる・・・と言って出かけそうになったが、ソーシャルワーカーのリアがそれだけは止めさせた。
マッサージの資格も得て、クリスマス中はピキットで警察官のマッサージを頼まれてする。依頼者は、ピキットの福祉局でミンダナオ子ども図書館の役員を務めてくださっているグレイスさん。
ジュンジュン君は、自立に向けて大張り切り。
旅に出たくてしょうがないらしく、このままでは盲目のまま世界を旅しそうな勢いだ。
 マッサージの賞状をもらって大喜びのジュンジュン君
マッサージの賞状をもらって大喜びのジュンジュン君
クリスマスパーティーでピーストーク
12月第二週の土日は、クリスマスパーティーと決めている。
ただのお楽しみ会ではなく、イスラム教徒の文化祭、先住民族の文化祭、移住民族の文化祭と三度の文化を分かち合う日の集大成の日と決めた。
前日の土曜日から奨学生たちが100名以上集まり、その夜は、私の制作した三つの文化祭の記録映画を見て、思い出し楽しんだ。実に賑やかな笑い声が広がった映写会だった。
翌日は、前日見た記録映画から、三つの文化祭を思い起こしつつ、6っつのグループに分かれて、文化と宗教の違いについて話し合い、互いの違いを認め合いながらいかにミンダナオで平和を築いて行ったらよいかを討論した。
その討論を6名のパネラーが発表し、さらに全員でディスカッションした。
内容は今後文章化して、順次メールニュースでお届けし、さらに冊子にまとめる予定だが、少し時間を下さい・・・・
とにかく、忙しくてなりません。
その後のクリスマスパーティーは、イスラム教徒の歌や踊りも交えて皆で楽しんだ。
イスラム教徒の祈りも加わったクリスマスのお祝いも珍しいだろう。
皆、違和感なく喜々と楽しんでいるのは、ミンダナオの若者たちの特徴か?
ミンダナオ子ども図書館だより 12月7日
ミンダナオに帰りました。
10月11月、ほぼ毎日のように続いた長い講演会・報告会活動でしたが、多くの方々にお目にかかり、実り多い滞在でした。
まずは、新たにお目にかかった方々、支援者の方々、協力者の方々に心から感謝いたします。
以下、今回帰国して感じたことなどをまとめました。
ミンダナオの経済的貧困と日本の心の貧困
今回、何よりも強く感じたのは、ミンダナオの現状も去ることながら、日本の人々、とりわけ若者や子どもたちに対する、心の緊急支援の必要性だ。
10月に日本に着いてショックを受けたのは、自殺といじめのニュース、そしてちまたの人々の表情から笑顔やゆとりが消え、心の閉塞状態が強く感じられたこと。
未来が見えない、夢がもてない、生きている喜びがない・・・
そうした観点からも、今回は一般の方々、保育園幼稚園教諭、学校の先生、とりわけいくつかの高校や小学校で直接子どもたちと自殺やいじめに関する対話が出来た事は、大きな成果だった。
日本の着くなり、こうした現実を見せられ、急きょ講演内容を、単なる報告会から、日本の現状を見据えた内容に切り替えると共に、ミンダナオの子どもたちの生きる喜びに満ちた面を編集した映像、「朝の光・海から」を制作した。

映像の持つ説得力を背景に、日本人が忘れてしまった生活と生きている喜びを思い出してもらいながら、現在の閉塞状態を打ち破る可能性を語った。
幸せな面を強調した映像は、ミンダナオの不幸な現状が削がれているので、もう少し悲惨な面も強調した方が良いという意見もあり、過去「土地を追われるマノボ族」などの映像もあるが、今後はさまざまな観点から提供していきたい。
今回の滞在中、いくつかの学校から、ミンダナオのスカラシップ支援を通して、両国の子どもどうしを結ぶ活動をしていきたいと言う依頼を受けた。
互いの映像のやりとりも含めて、こうした交流が、両国の不足したものを分かち合い、互いに励まし合う場になればと期待をしている。
テロリスト掃討作戦は、テロリスト製造作戦である。
貧しいだけではなく、複雑な家庭環境におかれていた子どもや若者たちが、思いがけなく生き生きと助け合いながら生きている様子と同時に、今回人々の心をうったのは、イスラム教徒とキリスト教徒と先住民族の若者たちが、各々の文化を大切にしながらも友情をもって生活をしている姿だった。
日本を含む先進諸国のイスラム教徒に対する偏見は、今や目に余るものがある。
とりわけヨーロッパ諸国の対応は、移民対策問題と結びついているものの、西欧文化優位の観点から東洋のイスラム教徒を見下した観がある。
西欧文化優位の構造が崩れつつある危機感ゆえか、感情的になりつつあるのではないか。
世界情勢は、直接ミンダナオにも影響するので、詳細にチェックするようにしている。
例えば、前回のローマ教皇の発言など、イスラム地域でイスラム教徒のためにも活動している現場の神父やシスター、心ある信徒などには、度肝を抜かれるような発言だった。
さすがに、トルコにおいては、軌道修正に躍起になっていたように感じられたが、単なる舌禍で終われば良いのだが・・・

必要性が出てこれば、若者たちのミィーティングの折にでも、テーマとして取り上げる。イスラム教徒の若者たちの本音を聞いて知る必要もある。
12月第二週の土日は、クリスマスパーティーを企画しており、今年度に実施したイスラム教徒の文化祭、先住民族の文化祭、ビサヤ・イロンゴ移住民の文化祭の映像をみんなで観て、「ミンダナオで文化、宗教の違いを超えてどのように平和に生活していくか」を話し合う予定である。
世界情勢を不安定にしているのは、宗教文化対立もあるが、それをあおる根本には、石油や天然ガスなどの資源にたいする利権や覇権争いがあろう。
ミンダナオも天然ガスが眠っており、イスラム地域への攻撃や圧力も、テロリスト掃討という名目になってはいるが、資源獲得と結びついていることは公然となっている。
東ティモールの独立支援なども、現地沖の天然ガス資源の利権と結びついていると思われる。
爆弾事件なども、しばしば演出されることがあり、戦闘のあったピキットのカトリック神父は、イスラムの人々の側に立って、これ以上イスラム教徒を刺激しないで欲しいと、マラカニアン宮殿に直訴した。

現地のイスラム教徒地域は、農民が多く、電気もない村が大半で、テレビもなく学校教育も行き届いていないので、極端に言えば、日本がどこにあるかも知らず、ミンダナオ同様に椰子の木が生えていると思っている人々もある。
このような地域は、元来が平和でのどかであり、そこにヘリコプターで爆撃が加えられ、親兄弟が死んでいくのを見れば、誰でも武器を持って立ち上がろうとするだろう。
ミンダナオ子ども図書館に来ている若者たちの数名は、戦闘で父親や親戚を失っている。
戦闘の時には、死体を埋葬することもできずに、川に流したという。
地元で難民救済をしていたカトリック主婦は、「松居さん、ピキットのナマズスープを食べらますか?川で死んだ人々を食べて育ったナマズで、人の味がするのです」とおっしゃった。
イスラム教徒の若者たちの訪問へ
このような地で、イスラム教徒とキリスト教徒の若者たちが、ミンダナオ子ども図書館で寝食をともにして仲良く生活している映像を見ると、多くの人々が驚く。
宗教家のなかにも、「不可能だ」とつぶやく人々がいる。
別に驚くには当たらず、誰しもが平和を望んでいる。
同胞たちが、みな三食食べられ、学校に行け、病気を治すことが出来れば、好きこのんで危険な戦闘などしたくはない。

問題は、資本主義的、自由主義的な経済が、理想とは裏腹に貧富の格差を増長させる結果になってしまったことだろう。「自由」が単なる「エゴ」に変わり、真のグローバルな意味での平等や博愛に基づいた民主主義が機能しなくなっている。
ミンダナオ子ども図書館では、来年からミンダナオ文化プロジェクトを始める。
コンピューターを利用した映像編集、民話の収集保存と再生、デジタル技術を駆使した出版などを検討していきたい。
後進国であるがゆえに、手作業の段階だと考える発想に疑問がある。
一方で、農業部門も少しずつ充実させていきたい。
その一環として来年には、イスラム教徒の若者たち12人ほどが、大阪を中心に、民族楽器クリンタンの演奏や交流に10日間ほどうかがうことになってきた。
時期は、10月25日から10日間の予定で現在進めている。

土日はホールで、平日は、各地の学校、教会、老人ホームなどで交流を進める。かつてマノボのスカラーの時も泊まったが、大阪の釜ガ崎にも行く予定である。
民族博物館で自主的にクリンタンを練習している市民グループとも競演予定もある。
こういう場で、人々の偏見などが、少しでも緩和されていけばと願うのだが・・・
イスラム教徒の若者たちには、ほとんどがキリスト教徒ではない日本人は、イスラム教徒に対する偏見も少ないという期待がある。
一方で、戦中にミンダナオで日本兵が行った残虐行為も知っている。
興味深いのは、ミンダナオの若者たちは、日本には木や森が無く、土地は丸裸だと思っていることである。
ミンダナオは、山岳地域でわずかに大木が残っているだけで、丘陵や平地は無惨な草地や灌木地が多い。ジャングルはほとんど伐採され、ラワン材などは、1950年代からの日本の高度成長期に建材用として輸出された。

日本には、たくさんの森が残っていて美しい国だと言うと、彼らは非常に驚く。
ミンダナオの若者たちは、日本は自国の木をほとんど切ってしまったが故に、ミンダナオの木も切らざるを得なくなったと思っている。
日本人は、「美しい日本」を残すために、自国の木には手をつけずに、海外の森を切り尽くしていたのだと、気がついた。
それ以後、現地の若者たちや人々に、「日本には美しい森が残っている」と答えるのが恥ずかしくなってしまった。
「美しい日本」「豊かな日本」が、こうした貧しい国の資源剥奪と残された貧困を踏み台にして成り立っている事を理解しなければならない。
若干の不安もあるが、辺境から出たことのない地域の若者たち(エスカレーターにも乗ったことがない)の民族文化が、国際的に通用し、人々を感動させるものであることを経験し、将来の生き方に役立ててもらえればと思っている。

平和を築くのは、単なるお金の支援でもなく、物資でもなく、心を開いて互いを尊敬しあい、足りないものは分かち合う事だとつくづく思う。
今一番支援を必要としているのは、日本人の心だろう。
ミンダナオ子ども図書館だより;
目次 1,日本の若者の自殺に思う 11月4日
2,絵本などの読み聞かせの本質 11月6日 ![]()
3,語りの生きている社会とは 11月17日 ![]()
1,日本の若者の自殺に思う 11月4日
毎年、10月11月は日本で講演会、報告会をしています。
日本に来るたびに日本の情勢の気がかりな変化に着目します。
1、若者および中高年の自殺の問題
2,教育現場における自殺といじめの問題
3,北朝鮮をめぐる武装化の是非の問題
4,看護師をはじめとするフィリピン人労働者の受け入れの問題
5,日本政府のミンダナオを重点とする開発投資
6,日本における貧富の格差の広がり
まずここでは、日本における自殺の問題を、フィリピン特にミンダナオの若者との比較の中で考えてみたいと思います。
自殺の多い国と少ない国
2001年にニュージーランドに行ったときに、現地で大きな問題になっていたのが、ニュージーランドがアメリカをのぞく先進国で、青少年の自殺率がトップであるという記事だった。
その当時、日本は2位、その後に韓国、北欧の国々、スイスと続いていた。
自殺に関する本を読むと、一般的に、南より北に位置する国々、政変などの急激な社会変化が起きている国々(例えばソ連が崩壊した後のロシアや東欧など)ヨーロッパではフランス、イタリア、スペインなどのラテン系の国々より、北欧やスイスなどに自殺が多いという結果が出ている。
当時不思議に思ったことは、受験競争などが厳しい日本韓国は別にして、なぜ自然も豊かで生活環境や社会保障も満ち足りていると思える、ニュージーランド、北欧、スイスといった国々に自殺が多いのかという疑問だった。
これらの国々は、絵本や児童文学の出版もさかんであり、図書館を中心にした読み聞かせ活動の先進国でもある。
貧困国よりも裕福な国に自殺が多いと思われるが、マニラのあるフィリピン人神父は、先進国に自殺が多い理由は個人主義の行き過ぎによるものではないかと指摘していた。
確かに一族や部族社会的な傾向が強いフィリピンでは自殺は少ないのかもしれない。
自殺の多いと言われる北方の国や先進国は、孤独になる傾向が強いのではないだろうか。
絵本や児童文学、読み聞かせ活動の盛んな国は、自殺が多い国?
ミンダナオ子ども図書館では、読み聞かせ活動を中心とした図書館活動を行っているが、読み聞かせ活動はストーリーテリングと呼ばれ、ヨーロッパからアメリカを経由して近年日本や韓国でも活発に行われている。とりわけ絵本の普及は先進国の象徴でもあり、経済活動が活発になったイギリスやドイツ北欧でさかんになり、アメリカを通して日本にも入ってきた。
絵本、児童図書の普及にあわせるようにして、図書館を中心に幼稚園保育園や学校、家庭に普及していく傾向が強く、現在の日本では、イギリスにまねたブックファーストと呼ばれるゼロ歳児からの読み聞かせ奨励運動が起こっている。
編集者や図書館員の間では、児童文学や絵本、読み聞かせに対する社会的関心や出版状況は、ヨーロッパでは、イギリス、北欧、ドイツ、世界的にはアメリカ、ニュージーランド、日本、近年は韓国、中国などがさかんである。
経済的にある程度発展をとげた国にさかんな理由は、絵本や児童文学というもの自体が、経済的に豊かな国々の人々のために作られたものだからである。
読書のためには、識字率の向上が必要であり、また絵本を購入できるのは、フィリピンでも富裕層に限られている。
ミンダナオの貧しい子どもたちは、絵本を見たことも、手に取ったこともない。
しかし、このことを持って、こうした地域の子どもたちは可哀想だとは言い切れない、ように思える。
子どもたちの心の豊かさを比較すると、先進国の子どもたちよりも、貧しい子どもたちの方がはるかに生き生きとして、ある意味で健康的で明るいと言う事実に出会う。
また、「絵本もない国の子どもは可哀想」と思いこみ、経済的発展国である欧米や日本の絵本に翻訳をつけて、大量に送り込み現地で読み聞かせ活動をするNGOなどが増えているようだが、ミンダナオ子ども図書館でも、例えば先住民の地域に欧米の絵本を持ち込んで読み聞かせをするが、それが本当に良いことか否か、しばしば疑問に感じるときがある。
全く異質の、冷蔵庫でも何でもあるような文化を、これ見よがしに見せつけていくことは、自然と共存しながら生きている現地の文化を低く見る事ともつながり、お腹をすかせてトウモロコシの粉しか食べられない子たちの前で、これ見よがしにビフテキを食べているような不快感を感じる時がある。
しかも、昔話も多くがグリムや日本のものであり、現地の話を主体としたものは全くなく、絵本の話のみを子どもたちが記憶していくとするならば、伝承文化の破壊以外の何者でもない。
こうした反省から、ミンダナオ子ども図書館では、現地の現地語による昔話を収集し語る事を今後重視する体制を作ろうとしている。絵本も、若者たちが選ぶのは見ていると自然にフィリピンの絵本が多くなる傾向がある。それだけ身近だからであろう。
しかし、それもマニラの出版社が出しているタガログ語の絵本である。現地語はない。
後に述べるが、絵本や児童文学の読み聞かせ活動は、自殺を予防するための潜在的意識の活動であると考えられる。
なぜ日本では自殺が多いの?
ミンダナオ子ども図書館の若者たちに、「日本では若者や中高年の自殺が多い」という話をすると、非常に驚く。
そくざに、帰ってくるのは、「なぜなの?あんな豊かな国なのに、なぜ死ぬの?もったいない」という言葉。
貧困の中で家庭が行き詰まったり、崩壊したり、理不尽な戦闘で親を失った子の多い、ミンダナオ子ども図書館の若者たちにとって、豊かで満ち足りた日本は、精神的にも安定した理想の国と映っているようだ。
そこで、私は「日本の若者たちは、孤独で死ぬんだよ」と答える。
これを聞くと、一瞬ポカンと口を開けて「孤独で死ぬってどういうこと?」と聞いてくる。孤独で死ぬという事の意味が理解できないのだ。
自殺の大きな原因は、孤独からだと考えられる。その観点から見ると、確かに、フィリピンは孤独感をあまり感じさせない国かもしれない。特にのんびりとしたミンダナオは、そのような場所であると感じる。(と言っても、私はほとんどミンダナオしか知らないのだが)
ただし、日本の方々が誤解して、フィリピンに来れば孤独は癒される(ある程度事実)という考えで、余生をフィリピンで過ごそうとしたならば、かえって孤独感を味わうかもしれない。
理由は、金銭的に豊かな日本人は、おそらくセキュリティーの関係で、高いコンクリートの塀で囲まれたヴィレッジという閉鎖的な場所であまり外に出ずに過ごすか、個別住宅でも同様の高い塀の中で、時にはライフルを持ったガードマンに警護してもらいながら住むことになるからである。
外出時にも、護衛と車で移動し、貧困地域には、足を踏み入れないのが鉄則となる。
このライフスタイルは、中産階級以上のいわゆる金持ちと思われる人々の、当地でのライフスタイルでもあり。まるで動物園の中の檻に入れられた類人猿のような状態で、これでは孤独感もいや増しにます。
フィリピンで孤独感を感じさせないのは、貧しい人々とつながりを持ちつつ生きようとするとき。
都市型の貧困と山岳地帯の貧困は異なっているが、貧しい人々と接触を持とうとすると、それなりの覚悟が必要となる。自分の持ち物をすべて捨て去るような覚悟と、時には生命すら奪われても良いかと言った、想いがないと難しい時がある。
次に、何らかのアクション(行動)も必要だろう。日本人は財布が歩いているように見えるから、物見遊山的な好奇心で貧困地域を歩き回っても、施しをしても、取れるだけとってハイさよなら、と言った、感じになる。
日本からの多くの経済支援が、平気で途中で消えていく理由と同じで罪悪感はほとんどない。
貧しい人々と共に生きるというのは、言葉で言うのは優しいが、先進国の人間にはほとんど不可能であり、衛生状態も悪く病気にも対応できない劣悪な環境で、同じような生き方をしていく事は出来ない。
金持ちが天の国に入るのは、ラクダが針の穴をくぐるより難しい。
先進国の人間は、自力では不可能なので、彼らの情で、孤独な状態から引き上げてもらうしかない。
日本の若者の貧困な心が救われるためには、貧しい国の人々、特に子どもや若者たちのあふれる情の施しを受けることが必要?
フィリピンの若者たちが、孤独で死ぬと言う事の意味がわからないのはなぜか。
彼らが、孤独を知らないからではない。
ミンダナオ子ども図書館の多くの若者や子どもたちは、孤独を感じている。
親を戦闘で失ったり、貧困のために、母親がマニラや海外に出稼ぎに行き、父親が別の女性と一緒になったりして、家庭が崩壊した子などが非常に多い。
こうした子たちと共に生活していると、海外での出稼ぎが、フィリピン社会を崩壊させていると感じることがある。経済的には、外貨が入り、政府も奨励しているのだが・・・
日本は看護師などのフィリピン女性の招致を進めているようだが、海外に行く女性の多くは、貧困故に子育てや子どもの学費や病気で苦労している家庭の母親であり、また長女であることが多い。
日本人サイドから見れば、安い労働力で、介護などに献身的で情の深いフィリピン女性を雇えるわけで、それなりに満足が得られるが、家族の絆が強い彼らにとっては、海外での生活は実に孤独で悲しいものなのだ。
また、いったん海外に出稼ぎに行き数年稼いでも、その後、蓄えた資金がなくなると現地に仕事があるわけでもなく、再度出稼ぎに出なければならず、若いときなら体力もあるが、年齢を経るにしたがい難しくなり、最後は結局貧困に戻るというケースも多い。中には、出稼ぎで稼いだ資金で小ビジネスを始めて成功する場合もあるが。
しかし、出稼ぎの結果、家庭が崩壊する子が実に多いという事実を、外国人は直視しなければならない。
それでも、彼らは一応にたくましく、明るく、「母さんの出稼ぎは仕方ない、孤独だけれども、自分も親を助けるために、がんばって学校に行くのだ」とけなげに思っている。
それでも、「さびしくない?」と私が聞くと、一応に「さびしい」と答える。
顔を見て、それとわかるときもあり、何気なく声をかけたり、学校に行くのを手をふって見送ったり、みんなで海に遊びに行ったりという、家族のまねごとのような事もするが・・・それでも孤独感が完全に消えることはない。
当然なことだが、海外に出稼ぎに行かずとも、教育や医療に問題がない程度の生活がもっとも望ましいのだ。
フィリピンの若者たちも、彼らなりに深い孤独と悩みを抱えて生きている。それでも、自殺はしない。
フィリピンの若者が孤独でも自殺しにくいのはなぜか?
ある時わたしは、「フィリピンには、若者の自殺はないの?」と聞いてみた。
すると、「あるよ」と気軽に答えた。ちょっとびっくりして、
「へぇー、原因は何?」
すると意外な答えが返ってきた。
「ラブだね」
「???????」
ラブで自殺するというのはどういう意味?。
詳しくたずねると。
お金持ちの娘さんと貧乏な若者が恋をして、周囲に反対されて、心中をするという事だった。この種の自殺が多いらしい。
フィリピンの若者が孤独でも自殺しにくいのには、いくつかの理由が考えられる。
一つは、社会のあり方の違いである。社会というと抽象的なので、周囲の人々の子どもたちへの対応と言いかえても良い。
もう一つは、子どもたち同士の関係のあり方であろう。
116
2, 絵本などの読み聞かせの本質 11月6日
絵本や読み聞かせ活動が盛んな先進国は、青少年の自殺が多い、というショッキングな結果は、必ずしもこうした活動が自殺を助長していると言う結果を意味してはいない。
逆に、人々の心の問題が大きい先進国ほど、こうした問題を解決する方策の一つとして意識的に、また無意識に読み聞かせ活動を奨励しているものと思われる。
ミンダナオのような、絵本もなく読み聞かせ活動なども意識的に展開されていないような地域は、あたかも文化的後進国のように考えられ、「可哀想な貧しい国の子どもたちのために」絵本を支援し読み聞かせ活動やそのノウハウを助成する必要があると考える人々がいるが、こうした考え方の背後には、経済的富裕国の方がより先端を走っているという奢りが感じられる。
貧しい国や地域の子どもたちが、絵本や読み聞かせに触れることは、肯定的、否定的な両側面を持っている。
肯定的な面は、
1,識字率や学習意欲の向上に貢献する
2,読書意欲が生じることによって、より広範な知識を得ることが出来る
3,自分たちが住んでいる以外の地域の文化に触れられる
4,お話を楽しむことによって、心の快復が得られる(特に戦闘地の子どもなど)
否定的な面の多くは、絵本や本を経済的に出版できるのは富裕国が主であり、一方的な富裕国の文化の紹介になってしまい、貧しい地域独自の豊かな精神性や文化が子どもたちの心に意識化されず、逆に自分たちの文化や状況を低く恥ずかしいものと感じ、自己卑下が起こり、その結果、現地の美しい考え方や文化や心の破壊や崩壊に寄与してしまうと言う点である。
ミンダナオでは、マノボ族、バゴボ族、マンダヤ族、ビラーン族、アエタ族、トランギット族などの先住部族がおり、私たちの奨学生の3分の1は、こうした民族であるが、彼らは独自の言語を持っている。
また、イスラム教徒は、生活ではマギンダナオ語を話し、ミンダナオではマジョリティーである移住民の言葉、セブアノ語(ビサヤ語やイロンゴ語)を話せないか、侵略者の言葉として話したがらない。
タガログ語を話すが、地域の人々によっては、タガログ語も理解せず、逆にアラビア語を解する場合もある。
フィリピンは、このように実に多くの部族言語が存在しているが、当然こうした言語の本は出版されていない。
私たちは、現地の文化の破壊を可能な限り食い止め、また子どもたちが自分の言語や文化に誇りを持てるように、読み聞かせの現場においてはオリジナル言語を大切にしている。
学校教育では、タガログ語と英語が奨励され(学校によってはそれ以外の言語を話すとペナルティと称して小銭を出さなくてはならない)こうしたフィリピン政府の立場を考えれば、英語またはタガログ語で読み聞かせ活動をするほうが理にかなっている。
しかし、私たちはオリジナルな言語や文化を大切にするために、マノボ族の地域ではマノボの若者が中心になりマノボ語で、イスラム地域ではマギンダナオ語を中心に活動を展開し、現地語を話せない若者が物語る場合にのみ、ビサヤないしタガログ語を活用している。
彼らは、英語またはタガログ語の絵本をあらかじめ読んで記憶し、現地語で語る。
問題は、現地語で語ったとしても、絵および内容はほとんど英米諸国のものであり、色彩においてすら北方的な淡い色彩が多く、現地の熱帯地域特有の生命力に満ちた力強い濃い色彩の土地柄には違和感がある。
内容に至ってはなおさらである。
日本の絵本も、ミンダナオの生命力ある環境に出されると、魂という出汁の抜けた昆布のように貧弱に見えるときがある。
すべてとは言わないが、編集者も作家も画家も購買する人々も、生活感がなく魂の抜けたような状態でもがいているからではないだろうか。
日本でも読み聞かせる絵本は、絵本なら何でも良いと言うのではなく、生命力と魂の躍動にみちた絵本のさらなる出現が望まれる。
アメリカの場合も、かつて全盛期と言われた時代の躍動感が感じられない。
一時編集者として絵本の出版に携わった者としては、たとえ構成などにまだ多少稚拙な部分があっても、フィリピンのオリジナルな絵本の方が遙かに魅力的に見えることがある。
ミンダナオ子ども図書館では、読み手の本の選択や読み聞かせ方法、エンターテインの方法などは、99パーセント彼らの発想に任せている。
現地の若者たちがどのような趣向を好み、何を伝えようとするかをまず理解するためである。
選書の傾向は、海外の絵本では、グリムなどの昔話が最終的に多く選ばれる。
創作絵本ではマニラで作られたフィリピンの画家や作家によるものが多く選ばれていく。
現地における絵本等の選択は、まずはその国の出版社が出したオリジナルなものの量を多くし、優先させるのがよい。
その後に、様々な諸外国の絵本を、より広範な知識や文化に触れる目的で付け加えていく。その際、特定の国に偏ることなく、可能であればアジアの諸外国の絵本も加えていきたい。
私たちは、イスラム教徒の子どもたちのために、コタバト市で見つけたアラビア語の絵本とアラビア語のアルファベットチャートも活用している。
しかし、ミンダナオにおける問題は、大都市の書店で買える絵本の多くが英語であり(一般書物においては90パーセントが英語である)よって、英米圏の文化がほぼ独占していると言う状況である。
タガログ語の本が少ないばかりか、諸部族の言語の絵本や昔話は皆無に近い。
この問題を解決するためには、現地の昔話などを集めて現地語で出版する必要と、現地の物語を現地語で絵本化する必要があり、ミンダナオ子ども図書館では、この作業を若者たちと始める。
また、絵本ばかりではなく、オリジナルな昔話を学び、現地語で語っていく必要もある。
こうした活動に寄与するものとして、絵本だけではなく、素話や手作り紙芝居の普及などはアジアにむいている。
またDVDによる踊りや歌、生活風俗の記録、再現や習得、祭礼などの実践による伝承も重要である。
先進国では、なぜ絵本や読み聞かせの普及が奨励されるか
原因は、物質的経済的に豊かな国では、心の貧困や荒廃が急速な勢いで進むからであろう。
産業革命を経て、物質経済的な豊かさが急速に拡大してきたヨーロッパで、最初に起こることは、民話の収集と、収集した昔話を本にして出版することである。
ドイツのグリムなどはその先駆であり、白雪姫などは世界中で知られるようになった。
次に起こるのは、収集した民話を絵本化したり、また直接語ったりするような、ストーリーテリングと呼ばれる読み聞かせ(読み語り)運動である。こうした運動は図書館を中心に普及し、家庭や学校で奨励される。
こうした動きを側面から学問的に補強するのが、心理学者であり、ユング、フロイト、ベッテルハイム、日本では河合隼雄といった人々が知られている。
図書館を中心とした読み聞かせ運動は、イギリスで提唱されアメリカで普及し日本に入ってきた。現在では、イギリスで始まったゼロ歳児から絵本をと言うブックファーストなどの運動が、日本でも提唱されている。
物質経済的な豊かさを享受するこうした国々に、読み聞かせ運動が広がる原因は危機感によるものであると思われる。
こうした国々では、急速に民話の語り手が消滅し、社会や生活から、民話や昔話を物語る時間が失われていく。その結果、子どもや若者の心の荒廃が蔓延し、大人も含めた社会の心の貧困状態が出現する。
こうした状態に対する、潜在意識的な危機感から、意図的な快復手段として、読み聞かせ活動が奨励されると思われるが、こうした視点から見ると、なぜ絵本や読み聞かせがさかんな国々ほど、自殺率が高いかの理由が理解できる。
日本でも自殺は問題化しており、それと同時に読み聞かせ活動の奨励が強く言われ始めている。私は、すでに20年以上前から、著作や講演で警告を発し語ってきたことであるが、それがますます切羽詰まった現実問題になってきている。
現状は、焼け石に水のような気がするが、こうした活動はさらに奨励し、続けなければならない。
お話の生きている国、ミンダナオ
ミンダナオは、心の貧困という視点から見れば、意図的なストーリーテリングの必要性を感じさせない国である。
彼らは、現代の日本人に比べればはるかに心豊かであり、絵本がなくても、ほとんどの大人も子どもも民話を語れる。
ミンダナオ子ども図書館の若者たちも、時には絵本もなく、地域の素話を語るし(小学生でも語る)時には詩の朗読(吟唱)もする。
読み聞かせをやっても、絵本など見たことも触れたこともないにもかかわらず、堂に入ったものであり、軽々とこなしていく。
理由は、本がなくても、家で民話や昔話を聞いて育っているからである。
そうした観点から見ると、ミンダナオは、語りが生きている社会であり、一方先進諸国は、語りが死にかかっている社会である。
語りが死にかかっている先進諸国も、かつてはミンダナオ同様に語りが生きていた社会であった。物質経済を優先した結果、語りの魂が人の心から駆逐され、魂の抜けたような状態になってしまったと言える。
日本に帰ってくると、多くの人々、特に若者や子どもたちの魂が本当に抜けてしまっているような感じがする。沖縄だったら、マブイグミ(落ちた魂を取り戻して入れもどす、まじない。拙著「沖縄の宇宙像」)が必要とされるような状態に見える。
人々の心から語りが失われた社会は、心の荒廃や貧困が加速していくようだが、読み聞かせ運動はそれに対する補償として起こる。心の豊かな社会を取り戻したいと言う危機感からの運動である。
そうした意味では、先進国の流れからくる読み聞かせ運動の必要性を、私はミンダナオに感じない。
ストーリーテリングがどのような意味、役割、心の豊かさを実現しているか、といった本質、お話が生きている社会というのはどのようなものか、を学びたいのなら、欧米の図書館などに行かずに、ミンダナオの山村や海辺の村を訪ねる方がよい。
それだからといって、ミンダナオのような地における、絵本や読み聞かせの普及活動が無意味であるわけではない。
心の豊かさに上積みするような形で、現地の文化を大切にしながら、さらに識字や知識やより広範な文化に対する目を開くことは、必要で有意義なことだからである。
物質経済的な先進国は、心の豊かさが退化した国であり、ミンダナオのような地域の人々の支援を必要としている。日本は、こうした地域を経済的に支援すると同時に、心理的な面で支援してもらう必要がある。
1117
3,お話の生きている社会とは 11月17日
お話が生きている社会が、子どもたちの心を救うとするならば、人々の心にお話が生きている社会とは、どのようなものであるかを考察してみる必要がある。
お話の生きている社会は、必ずしも絵本や童話が出版され普及している社会ではない。また、読み聞かせや図書館活動が盛んな国でもない。
読み聞かせ活動を積極的に提唱し推進している国は、人々の心にお話が失われ、心の貧困が広がり始めたか、心の危機が深刻な状態になりつつある国である。
このことは前稿で考察した。
お話の生きている社会とは、見えない物を信じている社会である
ミンダナオの若者や子どもたちと、様々な村に読み聞かせに行っている経験から、お話が生きていると判断できる地域の人々には、いくつかの要素がある事がわかってきた。
その中でも特に、確実にお話が生きている地域を知る、大きな手がかりがある。それは、見えないものの存在を信じていることである。
見えない物とは、宗教による神の存在もあるが、とりわけ妖精や精霊、化け物や幽霊、自然界の不思議なスピリットの事である。
ミンダナオの人々は、大人も子どもも、妖精や精霊の存在を信じている。
彼らにとって、周囲の世界は人間と精霊が共に住む世界である。
一歩家から踏み出し、とりわけ自然の残る山や川や岩のある場所に入ると、そこは妖精の世界である。
ミンダナオ子ども図書館の若者たちは、しばしば妖精について語る。
図書館の敷地内には、アポ山の噴火で飛ばされてきた火山弾と思われる大きな岩があるが、以前から村人はその中には妖精が住んでいると語ってきた。
とりわけ夕刻にその側を通るときには、「ちょっと、ごめんなさいね、通りますからね」と妖精たちに声をかけて通る。
いつも声をかけるわけではないから、何か気配を感じるのだろう。
その岩のある場所は、以前はゴムの木の森であったが、現在は芋を植えたので、露出している。
そのせいで、妖精は引っ越したと言う話もするが、今でもそのあたりには妖精がいると思っている若者たちも多い。
大木は、ほとんどが妖精のすみかであり、時々白い女性が立っていると言われ恐れられている。神木のようなものであり、切ってはならない。
子ども時代、夜部屋のなかでこびとたちに会ったと言う子もいるし、学校の帰りに大きな巨人を見た子もいる。当時の様子を真剣に語る。
よく話されるのが、ワクワクと呼ばれる人間の姿をした妖怪で、夜になると体が半分離れて羽が生え空を飛ぶ。
屋根の上に降り、舌をのばして血を吸うが、ワクワクに血を吸われた人はワクワクとして生きる。
「ワクワク、ワクワク」という声で鳴くが、「あれがワクワクの声だ」「昨夜啼いていた」と言う話が良く出る。
私には鳥の鳴き声のように聞こえるが、彼らは本当に妖怪だと思っている。
深夜の山の家で、妖精の昔話や話をするときは、扉や窓を閉める。
理由をたずねると「向こう側の者が聞いているから」と言う。
向こう側の者とは、妖精のことである。
妖精(インカント)と言う言葉を使わず、隠語を使うのは、実名を使うと彼らが振り向くからだという。
妖精の話をするときに戸や窓を閉めるのは、彼らに聞かれないためである。
彼らが話を聞くと、自分たちの事が話されると知って入ってくる。
妖精は、必ずしも絵本のような可愛らしいイメージではなく、怖い物である。
アポ山に登ったときに、森の中や野原で美しい花の咲く場所に出ると、決して感嘆を声に出してはならない。
「きれいだなー」等というと怖い目をして怒られる。
そのような場所は妖精が多く潜んでいる場所で、感嘆すると、その人に取り憑くことがある。
こうしたことを、真剣に信じて生きている。
このような人々がいる地域、またこのような人々の心には、100パーセントお話が生きている。
日本もかつてこのような地域だった。大人たちがカッパや天狗や座敷童の話を真顔でしていた。
今では、沖縄や東北の一部にしか見られない。私が取材した沖縄の池間島は神ノ島と言われ、日常こうした話が飛び交っていた。
アイヌの人々も、自然界をカムイという、スピリットの世界としてとらえ語り継いでいた。
北海道時代、人間を超えた自然界をスピリットして感じたくて、ときどき一人で山に入り一晩過ごしたりしたが、確かに人間には把握できない何物かの存在を感じるように思えた。
冬の支笏湖湖畔で夜テントから出ると、月を片手に立つ透明で巨大な人の姿が見えた気がしたときもある。
アイヌのおばあさんにそれを話すと、コタンカラカムイだろうとおっしゃった。
このような人々の心には、お話が生きている。
ケルト民族も同様である。
かつてヨーロッパのオーストリアにいたときに、妖精の祭りがあり、居酒屋で待っていると化け物の姿をした村人が入ってきた。
観光客のなかに、アフリカから来た黒人の男性が一人いたが、扉を開けて入ってきた化け物を見るやいなや血相を変えてテーブルの下に隠れた。
周囲の白人の観光客や村人は、それを見て笑っていた。
アフリカの黒人が隠れたのは、本当に妖精の存在を信じているからである。
こうした人々の心の中には、お話が生きている。
語りが生きている社会のその他の特徴
1,子どもも大人も、基本的に語りが上手
ミンダナオ子ども図書館の若者たちは、絵本も本も見たことがないが、英語やタガログ語の絵本を読んで、すぐにビサヤ語、マギンダナオ語、マノボ語などで語れる。
最初はちょっと緊張するようだが、たちまちなれて小学校の子でさえも語る。
彼らが語りにはリアリティーを感じる。
小手先ではなく、心から語っている。聞き手を感動させたり怖がらせたり、心を揺り動かすのが非常にうまい。
ミンダナオの人々にとって、語りは、日常生活の一部である。
2,形式にはまらず、表現を心からのびのびと行う
彼らにとって語りは、どうやら野の花やジャングルの木々の一部のようなものである。
華道や茶道のような形式や格式ではない。
民話を学術的、心理学的に分析すれば原型としての形式は出てくるだろうが、形式を意識しすぎると、語りの本来の心が損なわれるおそれがある。
その場の状況や雰囲気における、多少の変形や付け加えや削除もかまわず、楽しむことを第一と考えている様子だ。
多少の間違えもあまり気にしないし、互いに批評もしない。物語を楽しんでいるうちに自然に上達していく。
3,子どもたちに聞く力がある
聞いている子どもたちは、驚くほど集中し聞く力がある。
心が全開になっているのが目や態度でわかる。
子どもだけではなく、大人たちも子ども同様に物語を楽しむ力がある。
普段から、さまざまな話を聞いて楽しんでいるからであろう。
語りの生きている社会は自殺が少ない
語りの生きている社会は自殺の少ない社会であると考えられる。
語りの場は、孤独とは正反対の場であり、生活している者たちが、心を完全に開ききって、心の機微の裏側にいたるまでを分かち合う場である。
語りの世界では、愛、憎しみ、恐れ、神秘、悲しみ、苦しみなど、日常では人前に表せずに心の奥にしまい込んでしまうような様々な感情が外部に表出され、全員が心を開いて共有する。
非日常的な世界で共に泣き悲しみ心を共有することによって、日頃のストレスが発散解放され、心の壁が消滅する。それが語りの場である。
感情や深層の心を共有することによって、互いに共感する力が生まれ、他人の心の機微にも敏感に反応し、心を開き慰め合える心を持った子どもが育つ。
物質経済的な競争社会では、経済力、学歴などで、他人より秀でていることが常に求められる。
競争原理のなかで他人を蹴落として生きていく社会は、人々との関係に壁を作り、壁の高さを誇り競い合うような社会である。
感受性豊かな子どもたちは、強い疎外感を感じるであろう。
疎外感が自殺につながる最も大きな原因であると思える。
自分たちの社会を競争社会ではなく、社会とは共感できる人々、心を分かち合える人々の多くいる場であると意識でききれば、疎外感が薄れ自殺が減ると思われる。
ミンダナオの若者たちにとって、生きることは、互いに孤独などを感じ取り壁を取り払い、励まし合い慰め合い助け合うことが出来る社会だ。
ミンダナオのように物語が生きている社会は、心を分かち合う社会である。
たとえ孤独を感じても、自分の周囲には妖精たちが棲んでいて、たくさんの見えない不思議な存在が現にいると思っていて生きている人々の方が、虚無的な孤独に陥りにくいと思える。
例をあげるならば、子どもを学校に送り出すときに「勉強して良い成績を取りなさい」「人よりも良い仕事に就きなさい」といって送り出すと、子どもは人よりも高い壁を作ることにひたすら心を傾け孤独になるだろう。
勝ち組負け組という言葉が象徴している。
「行く途中の橋で昨日**さんがカッパに会ったから気をつけていくのよ。」「あそこの大木には最近白い女の人が夕暮れ立っているそうだから、早く帰っていらっしゃい」と言って送り出すと、子どもはこの世が不思議な魅力的な世界と感じ、生きていて楽しいだろう。
大人たちも、職場やスーパーマーケットのレジで、「昨日冷蔵庫の隅を見たら、なんとこびとがいたのよ・・・」と言った話をする方が、心豊かな社会が実現するだろう。
この世を、競争社会ではなく、様々な不思議な物に満たされた魅力的な世界であると感じられるからである。
現に、日本もかつてはそうであったし、ミンダナオは今もそのような世界が生きている。
心に壁のない社会は、核家族社会でも実現できる。
ミンダナオの社会は、かつての日本のような大家族主義ではなく核家族である。結婚すると家から出て新たに家を作る。
崩壊した家庭の場合は、孤独になった子どもたちを兄弟や親戚、近所の人々が子どもを受け入れて育てる。子どもたち同士の偏見も少ない。
祖父母が一緒に暮らすことが多いが、社会的な構造から言えば部族社会である。首領がいて、部族のなかの一員、地域の中の一員として互いに助け合う。
その点では、アイヌ民族の社会に似ている。
ミンダナオの人々は、非常に宗教的を大切にする人々が多いが、見えない物を信じる力は、宗教を通して神を信じる事につながっていると思われる。
ヨーロッパの厳格な宗教理論家やプラクティカルなアメリカ流の宣教師の中には、フィリピンのクリスチャンは本当のキリストを理解していないと断じる者も多いが、経済的に発達し絵本が出版されている国の方がお話が生きていると考えるのと同様な、先進国病にかかっている患者のように思えることがある。
ミンダナオの若者たちが、宗教が異なっているにもかかわらず、根本的なところで心を通じ合えるのは、信仰の土台に共通した精霊崇拝があるからのように思える。
精霊崇拝を否定しない東アジアに特有のファジーな宗教観は、意外と宗教の本質を示唆しているように思えるときがある。
日本は、誕生するとお宮参りに行き、結婚式は教会でやり、葬式は仏式の人も多いというと、ミンダナオの若者は、「うーん、それもいいねえ」と言う。
宗教で対立し争うよりも、多少ファジーでも友達通し仲の良い方が良いといった考え方であり、思いやりと愛がまだ生きている社会であると感じる。
naze
「ミンダナオ子ども図書館」を始めた理由 10月5日
「ミンダナオ子ども図書館では、イスラム教徒の戦闘地域だったピキットの山岳部、カラカカン村の小学生35名にスカラシップを出していますが、5年生のロザリナさんが盲腸炎の破裂で緊急入院しました。この地域は極貧で竹の家もボロボロの家庭が多く医療から見放され、彼女の場合は、腹部の痛みが盲腸の破裂であるにもかかわらず民間療法によるマッサージを続けた結果、菌が腹部に飛散した状態でした。緊急に手術をしましたが、患部の全削除はかなわず現在は様子見で、生存は五分五分だそうです。
まつげの長いいたいけない子です。皆さんお祈りしてください!
お願いします!」
これは、私がミンダナオから流しているメールニュースの書き出しです。その後、多くの個人や教会、仏教やキリスト教の方々から祈っています、がんばって、と言うお返事をいただきました。
この時はロザリナさんとデング熱のオマールくんが同時に入院したのですが、彼らのカラカカン村は、皆さんからの里親支援で、子どもたちが全員5キロ離れた山下の小学校に通えている極端に貧しい村です。この地域は2002年、テロリスト掃討作戦という演習名目の実戦で、アメリカ軍に支援されたフィリピン政府軍が襲撃した場所の一つです。
当時、フィリピン海軍が海に面したコタバト市から、大きなプランギ川を戦闘用ボートで遡り、ヘリコプターによる空爆とあわせて、テロリストが潜むとされた同地域を、広範囲に攻撃しました。その結果5万人を超す難民が出たのです。
ロザリナさんの近くの家も、空から空爆を受けて全焼しました。村の人々は皆、家を捨てて国道沿いの空き地や農地に非難し、仮設テントもなく、棒と竹で建てた一畳ほどの仮小屋で半年から一年以上、半強制的に難民生活を強いられました。病気になって死ぬ子も多く食べ物は薄いお粥。ロザリナさんもそのような体験をしたのです。同じアジアの隣国でありながら、このことは当時日本の新聞では、ほとんど報道されませんでした。
ロザリナさんたちが帰ってみると、一年あまりたった竹の家は腐り四年後の現在も修復されていない家が多く見られます。一日3度の食事すらままならない人々にとっては、数千円の建材も、手の届かない高価なものなのです。
「支援活動の知識も皆無で、いったい何ができるだろう」
絵本の編集者としての体験と、心理学の勉強を少しして子どもの自立と、アイヌと沖縄文化に関する本を数冊書いていたにすぎない私が思いついたのは、読み聞かせが心的トラウマを持った子たちの回復に良いことぐらいでした。
表情がなく、ほほ笑みかけても、手を振っても答えようとしない子どもたちを目前にして、絵本を読んであげたいと思ったのです。
私的な事を加えるならば、思わぬ離婚という状況のなかで、深い孤独の谷に投げ出され、先の見えぬ闇をさ迷っていただけに、突然父親が殺されたりと言う状況の彼らが、我が子のように愛おしく思えたのかもしれません。l
当時の状況は小規模だったのでしょう。現場のNGOも少なかったようですが、多くの活動が各々限定された範囲でのみ許可されることが解りました。
つまりNGOというのは各々が専門地域や分野を持っていてフィリピンでは法人資格がなければ、活動は許されていないのです。
ミンダナオ子ども図書館は、現地法人として医療、読み聞かせ、奨学制度、孤児施設とシェルター、難民支援活動の法的認可を得ていますが、さらに活動地域の市長許可が必要で、認可外の活動は出来ないこともわかってきました。もしも日本人が、許可無く子どもを家に泊めれば、誘拐や売春で訴えられても仕方がないのです。
しかし、ショックだったのは海外のNGOも、その後のアフガニスタン紛争やイラク戦争が話題になると、まだ多くの難民たちが残っているのに、潮が引いたように現場から消えていったことです。
出発したばかりの小さな「ミンダナオ子ども図書館」の活動を批評して「松居さん、今さらミンダナオじゃないよ、アフガンやイラクさ」と、忠告して下さった方もいました。私は少しムカッとして思いました。
「テロに走る人々の現状は何も解決されていないのに・・・きっと、話題になる地域の救済をしなければ寄付が集まらないためだろう。」
今は、少し知識も出来て、緊急支援の大切さも理解できるのですが、どうやら目の前にいる一人一人子どもたちへの想いが強すぎたからなのでしょう。
どのような形態のNGOを考えたか
現場の子どもたちを見ながら、許認可の問題も含め、どのような形の活動をしたらよいのだろうか、と考えたときに浮かんだのが木のイメージでした。
この子たちの将来を考えたなら、単発の活動では不十分だ、読み聞かせ活動を幹として、教育と医療を枝葉に、最後に自立支援として、二つのカルチャーを果実とする必要がある。
二つのカルチャーとは、文化(カルチャー)と農業(アグリカルチャー)だったのです。
あれから4年、根幹である読み聞かせと医療とスカラシップは、ほぼ形が整いました。
文化はムスリムデー、マノボデー、ビサヤデーという三つの文化祭で始めました。
この成果を踏まえ、来年度から、ミンダナオ カルチャープロジェクトが出航します。
まず来年5月に、日本のクリンタンを演奏しているグループの招きで、イスラム教徒の若者たちが民族楽器を持ってムスリムの結婚式を演出するために行く予定です。
今後は、オリジナル言語を含んだ絵本書籍の編集、読み聞かせによる民話復活、ドキュメンタリー映画制作。目的は、こうした活動を通して、技術と経験とマネージメントを、彼らに伝えることです。
農業は、1・5ヘクタールの農地に野菜と果樹を植え、5ヘクタールの水田を自給用に管理していますが、今後はマノボ族の多い高地で、換金作物としてブドウ等の栽培実験を考えています。20年前にアジア学院を卒業したノラさんが近くに住んでいらして、協力してくださることになりました。
このように、地元から世界に文化を発信し、山岳地で作物が出来れば、若者たちに、安易に外国に稼ぎに行く事よりも、この地でがんばる事のすばらしさを伝えられると思います。
これが私が大きな木のイメージのなかで考えたことでした。
経済的自立支援というのは、経営理論に基づいて、新規事業を立ち上げることでしょうから、基盤作りに5年、軌道に乗せるだけで10年、相応の結果を出すには20年かかる事は、かつて編集長として新規事業部を立ち上げた体験で知っていましたから、当時50歳を超えた私にとってこの仕事は、この地に骨を埋める人生最後の仕事になるな、と予感しました。
それと同時に、離婚直後に妻子のいるニューヨークで起こった9・11事件とその後のアフガン侵攻イラク戦争という世界情勢の流れを見ながら、同じ荒波に飲み込まれた、紛争地域に足を踏み込んだ自分の運命が、偶然であるとは思えなくなってきたのです。
先日も朝日新聞で報道されていましたが、隣町のマキララで爆弾が炸裂し、新たな戦闘の噂がたつ地。外国人の誘拐も多々あり、今もイラクに次いで多くのジャーナリストが殺害されている地です・・・
この地に骨を埋める決意は、つねに死を意識することであり、かつての妻子との物理的な別れを意味している、と感じました。アメリカ人の血を引いた彼らには、この地はあまりにも敵意に満ち危険すぎます。
しかし、逆に言えば、小さな実験に過ぎなくとも、イスラム教徒とキリスト教徒、先住民族と物質文明、先進国と後進国の貧富格差といった現代の諸問題を全て抱えたこの地で、少しでも平和へ向かう可能性を模索してみるのは、我が子を含め次代を生きる子どもたちの事を考えますと、人生最後の仕事としては意味の無いことではないと思えたのです。
もちろん短期滞在で、土地出身の奨学生たちと共に、知った村に皆さんをご案内する程度ならば、マニラよりも安全かもしれません。しかし、住み着いて現地の人も近寄らない村を訪ねての活動となると、話は変わってきます。
このような活動は、日本人一人では不可能でした。そのような時に出会い、つねに支えてくれたのが、ひどい兎口と喘息持ちで少女時代から山奥の親戚をたらい回しにされて育ったあげく、母親が失踪し、それでも慕い続けている極貧の少女でした。
復活祭前夜、イエスの死を告げる鐘の音と同時に生まれたので、エープリルリンと名付けられたのですが、最初は親子ほども年が離れているので違和感がありましたが、やがて共に生きてこの仕事を成し遂げることが、互いの運命であると感じるようになりました。再婚した妻です。
私たちが読み聞かせ活動と平行して、最初にしたことは、医療活動とスカラシップでした。
医療活動は、難民キャンプで病気の子どもたちを救済する事から始まりました。ポケットマネーで始めましたが、当時私はまったく財産も持っていませんでしたから(今もですが)たちまち底をつき支援を求めました。
一般的に、小規模なNGOで実施されている医療活動は、メディカルアウトレットと呼ばれる健康診断的な活動が主流です。しかしミンダナオ子ども図書館では、簡単な投薬だけでは治りにくい患者から、時には重度の手術まで引き受けます。
入院や手術を伴う疾患は、医者にかかることの出来ない貧困世帯の子どもにとっては死を意味します。教育と同時に、本格的な医療は、最も必要とされる分野だと感じます。
子どもの命を救おうとする活動は、地域における心理的効果が大きく、結果イスラム地域の人々も、頑なで敵意に満ちた心を開き、読み聞かせ活動を受け入れ、奨学生として我が子を、喜んでミンダナオ子ども図書館に送り出すほど信用してくださるようになったのです。
誰でも、我が子の命が救われれば感謝しますし、いざという時の頼りになる存在として喜ばれ、驚くほど広範囲な山奥にまで噂が伝わっていきました。ミンダナオは、まれに見る口コミ情報社会だったのです。
「あの、日本人がやっているファンデーションに行けば、救ってもらえるかも知れない」
話を元にもどしますが、ロザリナさんの家があるイスラム地域は、一般のフィリピン人でも怖れる地域でした。
今でも怖れて入らない地域ですが、かつては不信感に充ち、硬い表情だった皆さんの顔もすっかり変わり、洗礼式に招待されたり、暖かく迎えてくださるようになりました。
竹小屋の壁に無造作に立てかけられた連射式ライフルを初めて見たときは、さすがにたじろいだものですが、今はそれにもなれてしまいました。私たちを守るためだそうです。
先日、JICAのトップである緒方貞子さんがコタバト市を訪れ、日本政府の代表として、反政府組織であるMILFやMNLFといったグループとの友好的関係を模索しつつ平和を構築する試みを開始したニュースが入りました。
5年おきにくり返されてきた戦闘の結果、西欧キリスト教文化に対する深い失望と疑念にとらわれているイスラムの人々が先進国の中で唯一非キリスト教国であるとされる日本に期待する気持ちをくんで、戦中日本がこの地で犯した大きな過ちも忘れず、経済大国として傲慢に振る舞うことなく、実のある活動ができれば、さらに大きな成果を生むことでしょう。
それにしても、ミンダナオは何故貧しいのでしょう。
ご存知のようにミンダナオでは、バナナやパイナップルは豊かに実り、広大なプランテーションから日本、最近は中国やサウジアラビアにまで農作物が出荷されています。また南端のジェネラルサントスは、日本向け南洋マグロの一大出荷港ですし、大地の下には豊富な鉱石や天然ガスが眠っています。
とりわけ西部のイスラム地域には相当量の天然ガスの埋蔵が確認されており、2002年の戦闘後アメリカ軍が埋蔵調査に入っていますし、春にはオーストラリア軍も加わって共同演習がなされた背景には、天然ガス資源をめぐる権益が絡んでいると言われています。
このようにミンダナオが、農業生産物や鉱物資源に恵まれた豊かな地であるにもかかわらず80パーセントが貧困層と言われているのはなぜでしょう。
物の本を読みますと、これら農産物や鉱物資源から生じる利益の大半が、日本を含めた海外のグローバル企業、それらとつながりを持ったマニラの大資本そして地元富裕層の懐に入るからだと言われています。
その背後には、何万という貧しい人々や先住民族が、土地もなく日雇いで、開発によって山地に追われたまま自給自足に近い生活をしているのです。こうした土壌が、テロリストを生み出す温床となっているのは、世界中で共通した現象ではないでしょうか。
「ミンダナオ子ども図書館」の奨学生の多くは、こうした地から選ばれて来た子たちです。
なぜ「ミンダナオ子ども図書館」のスカラシップが、貧困層の若者たちに、あえてお金のかかる高等教育を授けることを重視しているのか、おわかりいただけるかと思います。
彼らこそ、社会の矛盾を体験し、貧者の良い面も悲しい面も理解し将来のミンダナオ、フィリピンの、そして日本を含めた世界の未来を考える感性と力を秘めた子たちだと、考えるからです。
と言っても、ミンダナオ子ども図書館は、社会的リーダーを育てることを目的にしてはいません。それは本人次第であって困難な家庭状況から来た不幸な子が多いだけに、まずは幸せになって欲しいと思っています。しかし時には高校生大学生に、「武器を取っても物事は決して解決しないと思うよ」等と語り合っています。
反面、安いバナナを食べ、第三世界から出る石油や鉱物資源を浴びるように使って利益を上げ、快適な暮らしをしている日本の方々には、あなた方の日常生活は、日々の食べ物にも事欠くこうした貧しい人々の犠牲の上に成り立っているのですよ、と言いたい。この事実を心の片隅でも良いから置いて欲しい。
自国の利益のみを考えずに、豊かさの一部でも分かち合うための小さな行動を、多くの方々がとって欲しいと願うのです。貧しい国の若者たちが、テロに走ることのないように。そして日本の若者たちが、心の貧困の中で死んで行かないためにも。
「ミンダナオ子ども図書館」は、基本的に多くの個人の善意によって支えられている小さな現地法人ですが、それだけに両国の人々が、人と人として向き合える工夫をしています。
とりわけ支援者の方々が誇りに思って下さる事は、支援している若者たちが、学校に行かせてもらうだけの受け身的存在ではなく、読み聞かせや医療活動や識字教育活動に参加して、自ら貧しい子たちを助けている点でしょう。
毎月行われる全奨学生が集うミーティングでは、支援者に感謝の手紙を送るだけではなく、相互の文化を分かち合い互いに平和についても語り合います。
支援してもらう喜びから支援する喜びへ、イスラム教徒と先住民族とキリスト教徒が共に平和に暮らす喜びに、彼らの心が向く時です。
ロザリナさんも、皆さんからの支援がなければ学校にも行けないどころか、盲腸炎で医者にもかかれず、亡くなっていたことでしょう。
娘を失った父親は、貧困のやるせない矛盾と怒りの中で、壁に立てかけてあったライフルを握ったかも知れません。
酸素吸入マスクをつけながらも、手術後にパッチリと目を開いた彼女を見て喜んだのは、御両親と医師と私と、そしてメールニュースに載せた写真を見てともに祈ってくださった日本の多くの支援者の方々でした。
ロザリナさんの写真と共にホームページの記録には、こう書かれています。
「まずはうれしい知らせです。本当にうれしく思いました。手術後のロザリナさんの状態が、執刀医も驚くほど良いのです。
前夜、ダバオから帰り、ロザリナさんのご両親などに、日本ではたくさんの方々が祈ってくれましたよと、皆さんの事をお伝えしました。
彼女は、月曜日には病院を出て、ミンダナオ子ども図書館に移り、そこから当分二日おきに病院に通うことになりました。完治ではないので、再発の危険も残っており、まだイスラム地区の山には戻れませんが、とにかく山は越した感じです。皆さんの祈りの力があったと思います。
執刀医は、いつもお世話になるドクターモダンサさんと、ダバオの医師2人の3名チーム。ドクターは給与を返上して執刀して下さいました。」
私は、祈って下さった皆さんのおかげだな、と思いました。
その後、カラカカン村に招待され、イスラム教徒の子どもたちの洗礼式に出席させていただいた時、ロザリナさんとデング熱で緊急入院したオマール君が涙を流しながら自作の詩を吟誦してくれました。
想いが深く心に伝わり、沸々と感動が私の胸にわき上がってきました。
日本人の皆さんのおかげで、小さな平和が生まれたんだな、と思いました。
日本での講演会・報告会のスケジュールを載せました。お目にかかれれば幸いです。
関東地区
10月7日(土): 横浜 14:45〜 横浜市大岡地区センター3F 市営地下鉄弘明寺下車5分
045−743ー2411 演題「絵本・愛の体験」
10月13日(金): 飯田橋 18:30〜20:30 第4回「読書の会」 飯田橋西口下車 家の光会館6F
演題「松居友さんが語る・絵本そしてミンダナオ」 参照クリックpdf
090−8341−6760
10月18日(水): 集中講義 9:00より午前と午後
東洋英和女子大 参加是非に関しては東洋英和へ 045−922−5511 横浜市緑区
10月20日(金): 横浜市戸塚 10;00〜12:00
横浜市戸塚 男女共同参画センター横浜(旧;横浜女性フォーラム)
お申込み・お問合せ:渡辺千春 電話/FAX 045-864-1674 chiharu−w@par.odn.ne.jp
資料添付
大阪
10月22日(日): 11:00〜 大阪千里ニュータウン 場所;カトリック千里ニュータウン教会
問い合わせherb-lea@canvas.ne.jp 多湖敬子
11月11日(土); 大阪市保育連盟 「育つ力、育てる力」 問い合わせ;06−6328−4019 風の子保育園
11月12日(日): 13;30〜15;30 大阪市立中央図書館 5F 「ミンダナオよりこんにちわ」 連絡先;06−6539−3326<mailto:s-shimakami@city.osaka.lg.jp>
関西地区
11月2日(木); 午後4時30分〜6時頃 福崎東中学校
11月3日(金); 10;00 福崎町立図書館 「講演会と語り部発表会」 参照ファイルpdf
11月5日(日): 10;30〜 門真市立図書館 06−6908−2828
11月7日(火); 10;00〜 富田林子ども文庫連絡会 金剛図書館 「絵本は愛の体験です」電話・FAX 0721-29-3451 村上 紘子
11月8日(水): 10;30〜 泉佐野市立図書館 子ども文庫連絡会
11月9日(木): 能登川高校 主催;永源寺図書館 「ミンダナオ子ども図書館の活動について 〜青少年がつなぐこどもと絵本〜」
11月10日(金): 市原小学校 主催;永源寺図書館 「ミンダナオ子ども図書館の活動について 〜青少年がつなぐこどもと絵本〜」
11月13日(月); 安曇川高校 絵本による街づくりの会
11月14日(火); 今津北小学校 絵本による街づくりの会
姫路
11月15日(水);姫路淳心高校 2時より
11月19日(日);姫路カトリック教会 午前のミサ後 11時より
愛媛・松山
10月28日(土); 2;00〜3;30 松山市石井公民館 「あふれるおもいを 絵本にのせて」
松山市石井公民館 電話 089−957−4120 資料添付参照
徳島・市内および鳴門
10月30日(月); 1;30〜3;00 四国大学付属保育所 徳島市内
10月30日(月): 7;30〜 鳴門カトリック教会 問い合わせlenmiomi@guitar.ocn.ne.jp
086−86−2774
九州
佐世保
11月24日(月); 潮見幼稚園 佐世保市潮見町 095−31−4588 hide018@force.nifty.jp
行橋
11月26日(日); 行橋カトリック教会 yukucath@coral.plala.or.jp カトリック行橋教会
どこかでお目にかかれることを楽しみにしています。
松居友

















スカラシップとマノボの村へ 9月6日
9月1日から、来年度スカラシップの募集が始まりました。
去年は、12月まで応募期間を設定した結果、350人の応募が来て、毎日大変だったので、今年は9月だけにしぼりました。ところが、早朝から応募の学生が来て、5日目の今日ですでに100名ほどになる勢いです。圧倒されます。

スカラシップ支援を見ていただけるとポリシーがわかるのですが、優先順位があって
1,片親または両親がいない子、または孤児で貧困家庭。
家庭状況が複雑な子、(戦闘の犠牲者、また種々の家庭問題の犠牲者の子)
2,両親がいても極貧家庭で土地もない家庭の子
となっています。
しかし、応募に来る学生以外に、私たちは、独自に候補者を捜しに山に行きます。
先日は、ここから2時間の小さな町アラカン市のマノボ族の首領のいらいで、山の村に行きました。
2時間のアラカンから、さらに乗り合いバイクで山道を行くこと1時間半。やっと20件ほどの竹小屋のかたまるマノボの村に着きました。

見渡す限り山が続く美しいところ・・・しかし、貧しい所です。小学校まで8キロの道を歩いて通います。ここの村の小学6年生、女の子二人、男の子一人、高校一年生の男の子一人他の子も合わせて7名ほどを奨学生候補に決めました。(写真)そうそう、この村は首領を始めほとんどが、クリスチャンのバプテストの村ですが、伝統文化も大切に守っていて、首領はダバオのバプテスト神学校を出て牧師(だった?)のですが、マノボ族の習慣で奥さんが二人います。マノボ族は一夫多妻ですから。

貧しくても子どもはかわいらしく、挽き臼でトウモロコシの粉をひいている子もいました。また驚いたことに、一人だけイスラム教徒の女性がいました。写真の左端の高校一年生の男の子は、バプテストのマノボの村のたった一人のイスラム婦人の息子です。マノボの方と、再婚されたのですね。その日は、大雨が午後に降り、山を下りられずに泊まりました。特別に米のご飯を出してくれたのですが、おかずは塩とお酢だけでした。

このようなとりわけ貧しい地域の子たちは、募集しても応募も知らず、旅費があるわけでもなく、図書館まで来ることが出来ないので私たちの方で探しいに行くのです。
首領は、かつて教会系のスカラシップがあったけれども、スタッフが現地まで行って本人に会って、家庭も見て決めるのは始めてだと・・・感心されていました。しかし、ミンダナオ子ども図書館のスカラシップは、一人の子に一人の支援者がつくので、日本の支援者の応募で初めて最終的に決まるのであって、まだ候補にすぎないのだと話しました。これから、来年の4月まで、候補者捜しに私が奔走しなければなりません。
去年は38名だけ見つけられました、今年は????


山道をバイクで登っていくときに、私はある小さな村で、兎口の子をチラッと見ました。
そこで、帰りにその村で人々に聞いて、当人を見つけ出しました。マノボの女の子です。(写真)
ご両親の強い願いもあり、さっそく手術する(お金が出せるわけもないので医療プロジェクトで)手続きを進めることになりました。幸い、兎口の手術は、私たちの懇意にしている、ダバオのマハリカファンデーションが受け入れてくれます。
最近は宗派に興味があるので聞いてみたら、この村はメソジストの村で、女の子の一家もメソジストでした。

教会関係の方々、御自分の宗派の貧しい子たちや村を応援したいのでしたら、ぜひともご一報ください。スタッフは喜んで対応します。どんな宗派の子でも、救われていったり、叶わぬ願いがかなえられていくお手伝いが出来ればうれしいですから。

驚いたことは、キダパワン市から悪路を2時間、着いたアラカン市からバイクで1時間の山道を走ったメソジストのマノボの村で、兎口の子の親が、ミンダナオ子ども図書館の無償の手術の噂を知っていたことでした。知っていてもお金が無くて訪ねることも出来なかったのです。話をたどっていくと、私たちが懇意にしている、マノボの牧師さん経由で回り回って伝わったようです。この牧師さんは、アライアンスですから複雑ですね。
皆マノボ族なのですが・・・・ちゃんとつながり、助け合って生きているのはすばらしい!

電話より早く確実に情報が伝わる、マノボネットワークの威力を思い知りました。
ビサヤイロンゴデー
ビサヤイロンゴデーが終わりました。
フィリピンのナショナルダンスであるバンブーダンスや、窓の外で恋歌を歌うハラナが実演されました。
様子は、映像記録として編集し、ムスリムデー、マノボデー、ビサヤデーにおける若者たちの記録映画として皆様にもお送りできる体制にしたいと思っています。来年初旬には可能であると思います。講演会などではすでに一部上映していますが、若者たちの自由な試みではあるものの、文化的にもかなり貴重なものだからです。

今回の最も緊張し点は、豚の丸焼きを出すことでした。イスラム教徒の若者たちにとっては、初めて見るグロテスクなものであることは間違いありません。事前に話し合い、テーブルや食器を別にすることなどを約束して実現しました。彼らも、一つのカルチャー体験として受け入れてくれました。
イスラム教徒のためには、山羊を料理し、共通の食べ物としてシーフードである魚や蟹を用意しました。
結果的には、イスラム教徒の若者たちはよく我慢してくれた、というのが本音でしょうか。
私たちも普段イスラム教徒と一緒に生活しており、ミンダナオ子どもと図書館では豚を料理していないので、久しぶりの豚料理のあの独特の臭いには閉口しました。
イスラムの若者にとって可哀想なのは、前回のマノボデーのニシキヘビと蛙の料理も食べられないもので・・・・食文化の問題は、最も根源的で難しいのですが、逆に食べられるものもたくさんあり、まずは体験自体が貴重だと感じました。
さて、今年の初めから、ムスリムデー(イスラム教徒)、マノボデー(先住民族)、ビサヤデー(移民族の日)と三つの大きく異なった日を実現してきました。この北海道ほどの島で、私が来た頃は、クリスチャンのスカラーはイスラム教徒を恐れ、逆もあり、先住民族を見下していたり、相互にこれほども理解や交流が無いのかと思うほどでしたから、現在の状況、共に食事をしたり、話し合ったり、文化交流をしたり、生活したりと言うのは多くの障害が消えつつある事を意味しています。
しかし、一方で世界情勢に翻弄されて、戦闘などが起こればあっという間に元の木阿弥にもどる可能性もあります。しかし、若者たちを見ていますと、この体験はどこかで忘れられない貴重な想い出として残り、将来何らかの心の中での働きを生み出すことは確実だと思います。
三つの文化デーの試みは、まだ出発したばかりです。対話や交流は基本ですが、それが一時的なものであるならば、まだ足りない様な気がしています。毎年テーマを変えながらさらに展開していく必要があります。
今年は初めての試みとして、異文化のカルチャーショックがテーマでした。三つの文化のプレゼンテーションが終わり、今後は10月11月と全体ミィーティングで平和について話し合います。具体的にはこの狭いミンダナオという島で異なった文化がどのように理解し合い共存し、互いに異質であることを認め尊重し合いながら平和に生活していけるかを議論する予定です。
具体的には、100名強のスカラシップ学生を5チームに分けて、今までのカルチャーショックに対する率直な気持ちと、それをどのように受容または克服して平和な社会を築けるかをディスカッションしていきます。
12月のクリスマスパーティー(第二集の全体ミィーティング)の日に、「ピーストーク:平和について語り合う」と題して各グループが発表をします。その後に、私が編集した思い出深い三つの文化の日の映像と三つの食事を楽しみます。

この試みは、始まったばかりであり、来年のテーマは「ホスピタリティー:心から迎え歓迎する事」をテーマとします。具体的には三つのことをやります。
1,誕生と洗礼の儀式、2,貧しい人が家に訪れたときにどのように迎えるか、3,宗教や文化の違う隣人をもてなす時はどうするか、以上の三つを演じます。
その後、ムスリムの場合はビサヤと先住民、先住民の場合はムスリムとビサヤ、ビサヤの場合はムスリムと先住民を心からのホスピタリティーで迎えるための食事を用意し、ともにテーブルを囲みます。
こうした試みは、若者たちの楽しみの場でもあり、民族や文化や宗教的エネルギーの発散の場にもなっているようです。
また、こうした試みと平行しながら、日常毎回顔を合わせたり、とりわけ貧しい地域の子どもたちに読み聞かせ活動をしたり、医療活動をしたりといった共通のプロジェクトを一緒にこなしたり、特にミンダナオ子ども図書館内で一緒に生活する事は若者たちに大きな変化を呼び起こしています。
よろしかったら、いらしてください。
日本文化のプレゼンテーションをやられてはいかがでしょう????
肺が癒着した女性のための家など 8月26日
明日は、ビサヤ・イロンゴデーです。ミンダナオ子ども図書館で、移民系文化を分かち合います。ミンダナオの外の島々、セブ等から渡ってきたフィリピンの人々の文化です。同じ先住民の文化の上にスペイン等の文化が重なっています。
ビサヤ・イロンゴ系の若者たちの張り切りようはすごく、イスラムの若者やマノボの若者たちも一緒に手伝っています。たった今、山から地豚を運んできました。明朝未明に丸焼きにします。バナナバナナというバナナに似た葉を持った花(極楽鳥花だと思う)も飾りように採ってきました。午後から、最終練習です。

以前お伝えした、肺の癒着した女性のための家が、ミンダナオ子ども図書館の一角に完成しました。写真
以前の経過をお知りになりたい方は、ミンダナオニュースでごらんになれます。
これで、へんぴな場所から馬で通うことなく治療に専念できます。お母様とも一緒の生活になります。お母様は、ミンダナオ子ども図書館のスタッフです。 しかし、手術が不可能な状態で、酸素吸入が欠かせません。すでに数年の歳月ですから、さらに長い闘病になりそうです。基本的に食事も治療費もミンダナオ子ども図書館でみますので、ご本人の家族に対する負担の気持ちは和らぐでしょう。長く親子で過ごすこともなかったでしょうから、まずは心の重荷を下ろしてもらえたらと思っています。お祈りいただければ幸いです。モルモン教徒です。
家は、ミンダナオ子ども図書館のニワトリ小屋をつぶした廃材も使ったので、3万円ほどで出来ました。ニワトリは、野菜をついばんで食べてしまうので、みんなで食べてしまいました。

ミンダナオ子ども図書館は、基本的に非政治、特定宗派無しの団体です。
ここにいる子は、イスラム教徒や精霊崇拝に近い先住民族もそうですが、プロテスタントでは、アライアンス、バプテスト、ロードオブジーザス、ペンテコスタ、セブンスデーアドベンティスト、イグネシアニクリスト、フィリピン合同教会、メソジスト、ラサリアン、チャーチオブクライストなど、まるで宗派の見本市みたいですね。モルモンの子も3人いますし、スタッフにも一人いますよ。
フィリピンのアライアンスの子は、先住民族に多く、独特で貧しい生活に耐えながら頑張っているので、アライアンスの若者だけ神学校のスカラシップを出しています。牧師の勉強をしている子が二人います。
皆けっこう開けていて、いろいろな教会の礼拝に顔を出しますし、イスラムの祈りで食事を始めるときもあります。この世を創られた神は一つですから。イスラム教徒もモルモンの子も精霊崇拝(日本の神道のようなもの)も含めて、皆ここでは家族です。

新しくスカラーで、17歳の盲目の子が入りました。ダバオの盲学校に通います。写真添付。ドイツ系ミッションの良い学校です(すでに盲目の少女がスカラーになっています)。戦闘地だったピキットの子で、ピキット市のDSWD(福祉局)所長のグレイスさん(私の尊敬しているソーシャルワーカーでクリスチャンだが戦闘地のイスラム教徒の救済に命がけで奮闘してきた人、ミンダナオ子ども図書館の役員の一人)から、うちのソーシャルワーカーのリアに連絡が入り会いに行きました。
父親はなく母親も遠くに行き、極貧家庭の叔母の家でほとんど放置状態。食事は近所の人がバナナを与えたりしていました・・・全くひどい状態ですが、歌が上手です。
ミンダナオ子ども図書館は、とても平和です。
よろしければ、いつかいらして下さい。
末期癌の母親の幸せ
来週の8月27日(8月の最後の日曜日)は、ビサヤ・イロンゴデーです。
ミンダナオ子ども図書館では、3っつの特別なミィーテイングをします。ムスリムデー(イスラム教徒の日)2月末の日曜日、マノボデー(先住民族の日)4月末の日曜日、そしてビサヤデー(移民族の日)8月末の日曜日。100人ほどの奨学生が全員集まり、互いの文化を分かち合って理解を深め発表します。伝統的な歌、儀式、踊り、そしてみんなで伝統料理を食べます。日頃粗食の子達なのですごい勢いで食べます。
昨日は、ビサヤ・イロンゴの子達と、来週のための食材を採りに山と市場に行きました。山では椰子の実と、カカオをとりました。カカオからはチョコレートを作ります。市場では、ブリナウという小魚を買い、ギナモズという塩辛を作ります。それに塩のきいた干し魚(ブラッド)を作ります。ともに貧しい人々の食材ですが、フィリピン人の原点だと思います。
この日だけは、イスラム教徒がいるので普段禁止の豚の丸焼きを料理します。
当日用の、椰子の葉葺きの家の制作もはじまりました。この家に娘が入り、外で若者がハラナと呼ばれる伝統的な恋歌を歌い、やがて結婚式が始まるという想定です。竹を使ったバンブーダンスも練習しています。マノボデーもムスリムデーも、専門家が見て驚くほどの文化度の高い充実したものでした。よろしかったらいらして下さい。

山に入ったときに、ジクジク、アルメリン、ラライ、バンダン姉妹のお母様を訪ねました。以前からお伝えしている末期ガンの方です。 腰が立たなくなり病院にお連れしたときはすでに骨がガンで犯され、1年半の命という診断で、お一人だけ山に置いておけずに(ご主人は亡くなっています)引き取った方です。奇跡的に3年近くミンダナオ子ども図書館に住まわれたのですが(幸せな日々だった)、いよいよ覚悟されて、若者や子どもたちに自分の死ぬところを見せたくない事と、娘達は勉強に集中して欲しいと言う願いから、生まれ育った山に戻り結婚している長女のもとに帰ったのです。
お元気そうでしたが、さすがにやせ細っていられます。
しかし、長女も孫もいますのでこうして亡くなれば幸せだろうと、感じました。興味深いのは、ご自身が産婆でマナナンバル(民間医師)で、お父さんも同じなのですが、父親も現在病気で、マナナンバル同士が近くに住むと互いに体力を消耗して早く死ぬので、父親を逆に町に移したことです。
娘達は、4人、孤児として残りますが、ミンダナオ子ども図書館で育てていくことになります。それでも、ジクジクは来年卒業ですし(設立から一緒に頑張って同じかまの飯を食ってきた子で、来年5月に結婚します。彼氏は図書館のスタッフになってくれています)アルメリンは大学一年生で看護を勉強していますし、ラライも高校生、バンダンは小学年生ですが、すっかりうちの子になっていますので、お母様も安心でしょう。皆で撮した写真を添付しました。

その他の子の医療状況
イスラムのオマール君(父親におぶられている写真を添付)は、デング熱も軽く今日退院します。
尿に血が混じっているハッシム君の方が、少しかかりそうです。腎臓を痛めています。
盲腸をこじらせたロザリンダさんも、医師も驚くほどの回復ぶりで(皆さんのお祈りのおかげだと思います)もう歩いていますし、来週には帰れるようですが、患部を完全に削除していない事と、帰ると学校まで山道を5キロ以上も歩いて毎日通うのが不可能なので、ご両親からミンダナオ子ども図書館に住めないか打診されています。従姉妹もここにいるのですが、本人が親から離れて寂しくないかが問題で、良く両親と本人と話し合わなければなりません。
4歳の子が、緊急に入院しました。高熱と喘息の発作です。
未婚のまま4人の子を産み、父親が別の女性と結婚してしまい、母親は働きに出ていて、祖母が駆けこんできました。祖母のご主人も職が無く監獄にいたとか・・・・・おばあさん一人で小卒の末娘と5人の孫の面倒を見ていますが・・・・
:ロザリナさんのその後の経過など 8月20日
ここのところ医療プロジェクトの報告が続いていますが、病気の多い時期なのでお許しください。

まずは、うれしい知らせです。本当にうれしく思いました。
手術後のRosalina
Guiandalさんの状態が、執刀医も驚くほど良いのです。(写真)
前夜、ダバオから帰り、Rosalina
Guiandalさんとご両親などに、日本ではたくさんの方々が祈ってくれましたよと、皆さんの事をお伝えしました。
彼女は、月曜日には病院を出て、ミンダナオ子ども図書館に移り、そこから当分二日おきに病院に通うことになりました。完治ではないので、再発の危険も残っており、まだイスラム地区の山には戻れませんが、とにかく山は越した感じです。皆さんの祈りの力があったと思います。
執刀医は、いつもお世話になるドクターモダンサさんと、ダバオの医師2人の3名チーム。ドクターは給与を返上して執刀して下さいました。
この時期はデング熱のシーズンですが、ロザリナさんの朗報と平行して、同じイスラムの村から2人の男の子が、5日間高熱の後に血を吐いた(典型的なデング熱の症状)とやはり高熱と尿に血が混じる(UPIの症状)が出ていると連絡が入り、慌てて向かいました。Omar
MonibくんとGarry
Hasimくんです今は病院で
すから大丈夫ですよ。状態を見ていますが輸血が必要になるかも知れません。
また山から来た大学生のEdmon
Linatoくんもデング熱で入院しました。輸血が必要で、A型ですので私も献血しました。今後は、少し日本人の血が混じるね、などと冗談を言いつつ・・・彼は極貧ですが屈強の体なので辛い病気ですが大丈夫でしょう。
お祈りして下さっている方々、寄付を送ってくださっている多くの方々、ありがとうございます。

この日、ひどい皮膚病の子を治療する決定をしました.。お姉さんとミンダナオ子ども図書館で撮った写真を添付しました。かなり膿んでいてかわいそうです。時間がかかるでしょうが、命に別状があるわけではなさそうです。写真
こちらの子の場合は、病気がそのまま生命の危険に結びつくケースが多いので大変です。
イスラムの少女の緊急手術 8月19日
ミンダナオ子ども図書館では、イスラム教徒の戦闘地域、ピキットの山岳部、カラカカン村の小学生35名にスカラシップを出していますが、5年生のRosalina
Guiandalさんが、盲腸炎が破裂して緊急入院さ
せました。この地域は極貧で竹の家もボロボロの家庭が多く、当然医療は受けられず、腹部の痛みが盲腸の破裂であるにもかかわらず、腹部マッサージを続け菌が腹部に飛散した状態です。
緊急に手術をしましたが、患部の全削除はかなわず、現在は様子見で、生存は五分五分だそうです。
まつげの長いいたいけない子です。皆さんお祈りしてください!お願いします!

この地域は、政府軍とアメリカ軍のテロ掃討作戦で爆撃を受け、ガンなどの患者が増えている地域です。共にイスラム教徒のために活動しDSWD(市の福祉局)所長であり、ミンダナオ子ども図書館のボードメンバーのクリスチャングレイスさんは、劣化ウランを疑っています。彼女自身も喉頭ガンです。
先日は、キダパワン市で二つの爆弾テロが起こり、マノボ族の農業指導をされている20年前の卒業生に会いに来られた際に、私たちの図書館を訪ねてきたアジア学院の日本人とドイツ人の青年が近くを通りヒヤッとしました。(マノボの貧しい村で私たちがスカラシップを出しているプロックエイトに言って現状に驚きまた感動したときの写真を添付。この日、ひどい皮膚病の子を治療する決定をしました)

爆弾事件は当地に来て3度目です。4年間で三度ですから、マニラより安全ですね。幸い小さな爆発でけが人はありませんでしたが、私たちの奨学生が来ているイスラム地域のピキットでは戦闘が同時刻に起こり3人が亡くなりました。こうした戦闘は、テロリストのしわざであると言い切れない部分があります。政府軍側によって作られることがある、と言われているからです。
Rosalina
Guiandalさんの様態は、またご報告いたします。
日本にて報告会スケジュール/ 8月11日(日曜日)
ミンダナオ子ども図書館だより;日本にて報告会スケジュール
お元気ですか。
10月から11月いっぱい恒例で日本にうかがいます。
講演会、報告会、ミンダナオ子ども図書館の話を聞く会、家庭集会など、ご希望の方はお知らせ下さい。
10月8日(日曜日)〜21(土曜日)東京中心に関東、上信越、中部地方にうかがいます。
10月22日(日曜日)から29日(日曜日)大阪京都など関西中心に徳島高松地域までうかがいます。
11月22日(水曜日)から29日(水曜日)土日を除く、は九州から山口広島地域にうかがいます。
タイトル例;「松居友さんから、ミンダナオ子ども図書館の話を聞く会」
イスラム教徒とキリスト教徒、先住民族が混在し、しばしば戦闘の起こるフィリピン、ミンダナオの地において、現地の子どもたちを支援する読み聞かせ活動、医療プロジェクト、スカラシップなどを現地法の許可に基いて行っている「ミンダナオ子ども図書館」。先住民族の現状やイスラム地域での読み聞かせ活動などの様子を、ビデオ映像も交えながら、「ミンダナオ子ども図書館」ディレクターの松居友さんにお話しいただきます。(参考:大阪市図書館フェスティバル講演のキャッチフィレーズ)
取り寄せ販売可能な著書は、
「サンパギータの白い花」(女子パウロ会)
「マディヤと灰色オオカミ」(女子パウロ会)
「ふたりだけのキャンプ」(童心社)
「絵本昔話に見る楽しい子育ての知恵」(エイデル)
その他の著作に関してはこちらのサイトで確認下さい
http://www12.ocn.ne.jp/~mcl/bunkenlist.htm
講演会(著作、絵本の講演会)
松居友の一般講演会の演題またはプロフィールはこちらをご覧下さい。
http://www12.ocn.ne.jp/~mcl/
ミンダナオの子どもたちの事を多くの方々に知っていただき、一人でも二人でも支援してくださる方々を見つけたいのです。
家庭集会的な集まりから、人数や規模、謝礼に関わりなくうかがいますので、「友さんが来てくれるよ、みんなで一度お話を聞いてみようよ」といった気持ちで、気軽にお声をかけてください。
本当は、人前で話が出来るような人間ではないのですが、ミンダナオの極貧で時には親のない子達が、どうも我が子の一部のように思えるので、出来る限りの事はしてやりたいので、よろしくお願いいたします。
現在、横浜丸岡地区センター、東洋英和女学院、四国大学附属保育園、大阪福崎町図書館、大阪市立保育園連盟50周年記念講演、大阪市図書館フェスティバル講演、大阪門真市立図書館、高島市立今津北小学校、安曇川高校、マキノのNPO「絵本と街づくりの会」、姫路淳心高校、姫路教会、行橋カトリック教会などでスケジュールが決まっています。
具体的なスケジュール日程は、後ほど公表いたしますのでお目にかかれれば幸いです。
医療プロジェクトより 8月7日
肺の癒着が進んでいる女性がダバオの私立病院で診察を受けた。病気の発端は喘息だった。
初期においては薬の治療で治る病状だったので、当時はデパートで働いて薬を買い治療していたが、肺の異常に気づいたデパート側は、病気を理由に解雇した。
(大都市ダバオのデパートなどの雇用は、比較的恵まれた職なのですが、終身雇用ではなく5ヶ月契約がほとんど。理由は、半年未満の契約であれば正規の雇用ではなく、健康保険や年金の法的責任がない。)
解雇後はもちろん薬は買えず貧困のなかで、母親が近くの町で住み込みお手伝いをしながら面倒を見ていたが、薬を買ったり買えなくなったりをくり返し、現在の状態になってしまった。
彼女の存在を知ったのは、スカラシップに応募してきた一通の手紙からだった。調査に行くと、田んぼの側に車を乗り捨てて川沿いのあぜ道を吊り橋や丸木橋を渡りながら、行くこと30分あまり。緑の田んぼの中に孤立した島状の土地があり、3軒ほどの竹家が隔離されるように建っている内の一軒だった。
そこに寝かされている女性は、明らかに顔色も悪くやせ細り、一見して大学進学どころではない事は明白だった。その時母親は居なかったが、話を聞くと、母親の給与では食べるのがやっとで薬は買えないとのこと。
進学は論外でまずは病気を治すことが先決だが、ミンダナオ子ども図書館の規定である、「医療は17歳以下」に当てはまらない。そこで、母親に現在の家事手伝いから図書館に移り、もう少し給与の良いハウスマネージメントに雇い、その給与で薬を買ってもらう事にした。
それから半年、残念ながら喘息の薬だけでは回復は見込めず、呼吸困難になったと聞いて、例外規定でダバオメディカルセンターに入院する事になった。
病院に見舞ったときは、酸素吸入を受けやせ細り、方肺が機能不全で心臓も弱り、手術は不可能との診断。薬の投与で病状を見守るという結果になった。
話を聞いていると、本人は元気になりたいのだが、薬が買えず、病気で仕事も出来ず家からも出られず、自分が生きていることによって親兄弟に精神的経済的な負担をかけていることが重荷なようだ。しかも病状はゆっくりと進行し、かといって死ぬことも出来ない。
しかし、本人の生きたいという意欲も確かだし、ミンダナオ子ども図書館では、いったん引き受けた患者は、可能性がある限り最後まで面倒を看るという原則から、薬物治療に賭けることにした。
ダバオに見舞ったとき、偶然ではあるが、貧しい人たちが15人近く寝ている病室の隣のベッドで、老人が息を引き取っていく瞬間を見た。
老人はすでに意識はないらしく、風船を手で圧すという原始的な方法で、家族が人工呼吸を続けていたが、ようやくやってきた医師の心臓マッサージもむなしく、その場で息を引き取っていった。
鼻や喉に差しこまれていたビニールのチューブが一つ一つ抜きとられ、最後には病院の薄汚れたシーツにくるまれて、運び出されていくのを見ながら、死ぬという事は、自分の体から離れることだとは思うのだけど、それにしても大変な一仕事だなとつくづく思った。
死んだ後、周りを囲んでいた家族も、むしろホッとしたようだったが、本人も死臭漂う体から離れて、どんなにかホッとしたことだろう。
ちなみに、肺が癒着した女性は、長く病院に置かれるのも嫌だし費用も馬鹿にならないので退院したいと言い、かといって不便な実家にもどれば、診察のたびに馬で道路まで運ばなくてはならないので、意を決して、ミンダナオ子ども図書館の道路側の開いている土地に、小さな竹の家を建てて、そこで母親と生活しながら回復まで面倒を見ることにした。
半年以上はかかるだろう。
ミンダナオ子ども図書館では、昨年は105名の子どもたちの病気を治したが、その半数はスカラシップの学生や里親の子どもたちだ。
全員が全員、極貧家庭から来た子たちだから、健康保険に加入していなくて当たり前だし、病気になっても親が医療費を払えるわけがない。
言ってみれば小学生から大学生まで、合わせて200名近くの栄養不良で、しかも健康管理の行き届かない地域の子達がいるのだから、病気の子が出て当然なのだ。中には、長期治療を続けている子もいる。
そのようなわけで、肺の癒着が進んでいる女性の対応に追われている間にも、大学生クリスティーン・パデルナルさんがデング熱で緊急入院した。幼いときに両親と死別し完全な孤児だから、私たちが助けなければ他に助けてくれる人もいない。
デング熱というのは、夏の時期になると流行する病気で、蚊によって媒介される。高熱がくり返し襲い、体が極端にだるく食事が進まず、ひどくなると鼻や口から出血する。点滴と輸血をすれば、だいたい治まるが、そうした最低限の治療費も出せない一般の貧しい子どもたちにとっては、これといった治療法もなく薬も効かない恐ろしい病気で、僕もかつて7キロも痩せた経験がある。
クリスティーンの場合は試験があり、熱があるにもかかわらず終了まで頑張ったのも良くなかったようだ。図書館に住んでいればすぐにも入院させたのだが、仲間のスカラーと下宿生活をしていたので知らずに入院が遅れてしまった。鼻から出血したと聞いて慌てた時にはすでに輸血が必要な状態だった。
血液型はタイプA。奨学生やスタッフの支援を仰いだが、自分の血液型も知らなければ、注射もしたことがない子達なので恐れて献血をしようとしない。キダパワンの血液バンクが登録ドナーに電話して、ようやく最低限の血液を確保した。
4月にはコナナン君が同様の状態で輸血を受けているので、今回の反省から全体ミィーティングで全員の血液型検査をして緊急時のドナーを登録することにした。
ミンダナオにおける
医療の現状と課題
肺の癒着した女性を一時入院させたダバオメディカルセンターは通称DMCと呼ばれ、日本のジャイカからの支援が多い公立病院で、私立病院にとても入ることの出来ない多くの貧しい人々にとっては大きな救いとなっていると感じます。
日本のODAに関しては様々な問題も指摘されているようですが、ダバオメディカルセンターなどは成功している例だと感じます。極度に制限された予算のなかで活動している私たちにとっても頼もしい存在です。
こうした比較的安く利用できる公立病院には、多くの人々が殺到するので、診察に関する待ち時間が異常に長かったり、手続きが煩雑だったり、ジャイカ病棟とも呼ばれている診察棟は近代的で設備も整っているのですが、重要な入院棟と救急患者セクションは老朽化したままで通路や体育館にまで患者があふれているばかりでなく、トイレなどの衛生面にも問題がありそうです。
医療プロジェクトを実施しつつ多種多様な患者のお世話をしてきて、意外と助かるのが、マハリカファンデーションやジェロームファンデーションといった医療ファンデーションの存在です。
マハリカファンデーションは兎口と目の異常を専門に取り上げているファンデーションで、衛生的な手術室も完備していますし、ジェロームファンデーションは、設備の整った私立病院でポリオのジョイの足の手術を無料で実施してくださいました。私たちは、点滴や医薬品を供給しました。
これらのファンデーションは高額な治療費のかかる手術を低額または無料で行ってくれるのですが、背景にはダバオのライオンズクラブ、ロータリークラブ、メソニックファンデーションなどが資金援助をしており、その背後では同団体の日本部門が深い関わりを持ち活動していることもわかってきました。
かつてダバオは、東洋一の日本人町があったほど歴史的にも日本とのつながりが深く、日比混血も多いの
で、ミンダナオは日本と深い関係を持った地域なのです。
また、ジョイの歩行訓練を引き受けてくださったカトリック系の障害者更生施設Our
Lady of
Victoryやドイツミッションが運営している盲学校。また、複雑で困難な瘤のパルコン君などの場合は、手術が高額でミンダナオ子ども図書館では手に負えず、地元の民放テレビが主催している子供支援基金に応募して放映され、どっと支援金が集まりました。その結果、私たちは患者の搬送などのお手伝いだけですみました。
感動的だったのは、戦闘地ピキットから来た頭部の瘤のある難しい手術の子を、ダバオメディカルセンターでお願いしたとき、ミンダナオ子ども図書館の活動に常々行為を抱いてくださっていた複数のお医者様方が、執刀治療費を無報酬のボランティアで引き受けてくださった時です。
こうした様々な方々やファンデーションの協力や連携で、ミンダナオ子ども図書館の医療プロジェクトが一歩一歩進み続けて行くことが出来るのは、本当に感謝としか言いようがないことです。
ミンダナオにおける医療の課題は、こうした良い病院やファンデーションがありながら、大都市ダバオに集中しておりミンダナオの山岳地や僻地の貧しい人々がなかなかその功徳にあずかれないことです。
当然のことながら、ミンダナオの貧しい人々の大半は、大都市ダバオからはるか離れた山岳地や海岸地域に住んでいます。
こうした人々は、ダバオにまで行く公共の乗り物費用すらも高額で出ず、また治療費がただになっても病院などから要請される点滴や輸血用血液、薬代が払えない状態なのです。何しろ家にいても、三度の食事すらままならないのですから。
また格安で治療をしてくれるファンデーションの存在も知らず、知っていても文字が書けなかったり、出生届がないといったハンディーを抱えていて、面倒な書類整備の段階で挫折してしまうのです。
ミンダナオ子ども図書館に運ばれてきた子達の場合は、スタッフが献身的に複雑な書類整備や登録、役所への出張を同行し代行するので治療が可能になるわけです。
せっかく日本の政府や団体から支援金がありながら、本当に貧しい人々の救済にまでいたらないのは見ていて残念でなりません。
ファンデーションのなかにはマハリカのようにときどき車で僻地を訪ねて治療したり、ジャイカの支援を受けているダバオメディカルセンターのように、スマイルファンデーションと連携をとり地方の役所やラジオで無料の兎口の治療も行っている団体もあるのですが、地方に拠点を持っていないために散発的であったり需要の高い病気や手術にまでは手が届いていないのが現状です。
そうした観点から見ますと、ミンダナオ子ども図書館の医療プロジェクトは、山岳地帯の先住民族やダバオに出ることの難しいイスラム地域の子どもたちを対象としていますので、痒いところにまで手が届く活動になっていて、その結果僻地の人々に安心を提供していると、先住民族リーダーやイスラム教徒の人々から喜ばれています。ここ数年で、近隣のロハス市やグリーンヒル市、先日はキダパワンのガールスカウト教会から盾や賞状をいただきました。
地図でごらんになるとおわかりになるように、ミンダナオ子ども図書館のあるキダパワンはミンダナオの中心部近くに位置しており、アポ山周囲はマノボ族などの山岳民族の地域で、西はイスラム地域の接点にあります。
また、読み聞かせ活動を常時することで、たえず山岳地や僻地へ行き、現場の子どもたちの健康状況を確認していることも大きな意味を持っています。
ミンダナオのこれからの課題は、こうしたより僻地にある小さなNGOと、大都市ダバオの大きな医療機関やファンデーションが相互に連携を持ちながら、本格的に救済を必要としている人々に支援の手を差しのべていくことだと思われます。
また、ダバオ一極集中を是正しより深く先住民族やイスラム貧困層を支援するためにも、要所要所に散在する公立病院の設備の拡充や医師の常駐が望まれます。
例えばキダパワン市に隣接したアマス病院などは、多くの貧しい人々が利用するのですが、建物の衛生状態も悪く患者が通路に寝ているしまつです。
アマス病院は地理的に北は、現在日本の商事会社がバナナ農園を次々に開発し、土地なし山岳民族が自給地から追われ、狭い土地に移転させられる結果自給が困難になりつつあるロハス、アラカン、グリーンヒルといった山岳地域と隣接し、西は政府軍と反政府ゲリラの間に戦闘の絶えないイスラム教徒のマギンダナオ自治区を結ぶ、いわばミンダナオの交通の接点部という地理的には恵まれた位置にあり、その利点を生かして広大な敷地を持つ北コタバト州庁舎が設置され、病院は隣接しているのですが、医療担当者が常駐していることが少なく医療設備もなく充分な治療が行われていないのは残念なことです。
(アマス病院に入ると死ぬと言う噂が立つほど)
私たちの患者もそこから回されてきたり、治療が完了されずに来る患者がいて、入院が必要な患者は遠いダバオに運ぶか、キダパワンにおいては結局、治療費の高い私立病院に入院させている現状があります。
日本政府のODAも、このような病院にもう少し費やされると地域にさらに大きく貢献するように思われます。
ミンダナオ子ども図書館便り:スカラシップと里親・・2006年度最後の子達のお願い
7月28日
お元気ですか。日本も暑い夏に入ったことでしょう。
2006年度のスカラシップと里親も、数名をのぞいてほとんど決まり、皆元気に学校に通っています。
しかし、スカラシップの高校生2人と里親の小学生6名だけが、また支援者になってくださる方を見つけられないでいます。
これら残った8名が、今年最後の支援希望者のお願いになると思います。
ご支援可能な方、支援希望の子の名前を書いてメールを送信頂ければ折り返しご連絡いたします。
スカラシップ候補
1,Saloay-ay Ardianさん >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 支援者が見つかりました
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 支援者が見つかりました
17歳です。両親はいらっしゃるのですが、ブロークンファミリーです。ブキッドノ
ンの先住民族の首領のところで生活していました。
少し寂しがりやですがとても素直でよい子です。セブアノ系で「ミンダナオ子ども図
書館」に住んで高校に通っています。今年4年生ですが、来年から大学に行ければう
れしいです。5人兄弟の4番目です。
2,Maangue
Janetさん ・・・・・・・・・・支援者が決まりました
・・・・・・・・・・支援者が決まりました
16歳ですが、高校一年生です。父親が亡くなり、母親が別の人と一緒になったので
すが、色々と問題がある人なので家にいると危険なので母親の強い要請もあり3姉妹
を引き取ったうちの長女です。おとなしいのですが明るく、家事や掃除を嫌がらずに
手伝ってくれる家庭的な子です。マノボ族でミンダナオ子ども図書館に引き取って高
校に通っています。
里親支援
里親支援の子は、プロックエイトのマノボ族の子達です。うち3名の写真を貼付して
ありますが、全部で6名います。写真の無い子も、決まり次第こちらから写真とプロ
フィールをお送りします。
1,Rim-Rim Enangeob さん: ,・・・・・・・・・・・・・支援者が見つかりました
,・・・・・・・・・・・・・支援者が見つかりました
写真貼付、女の子、小学校2年生、1994年1月
6日、12歳、「いつか先生になりたい」、父は日雇い農夫
2,Jomar Enangeob 君: ・・・・・・・・・・・・・・支援者が見つかりました
・・・・・・・・・・・・・・支援者が見つかりました
写真貼付、男の子、小学校1年生、1996年7月4
日、10歳、父は日雇い農夫
3,Nela Monasca さん: ・・・・・・・・・・・・支援者が決まりました。
・・・・・・・・・・・・支援者が決まりました。
写真貼付、女の子、小学校4年生、1992年5月1
5日、14歳、「いつか先生になりたい」父は日雇い農夫
4,Kenneth Rasoable君:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援者が決まりました・
男の子、小学校5年生、生年月日不明、母親は亡くなり
父親も不明、「いつか先生になりたい」
5,Omar Monib君:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援者が決まりました
男の子、小学校4年生、1995年7月2日、11歳、「いつ
か良い先生になりたい」父は日雇い農夫
6,Norhaidain Bateg君:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援者が決まりました
男の子、小学校1年生、1997年12月1日生まれ、
9歳「いつかエンジニアになりたい」父は日雇い農夫
よろしくお願いします。
patt
ミンダナオ子ども図書館便り:昨年度の医療報告 7月27日
季刊誌を購読の方々には、決算期の春5月に郵送でお送りしたのですが、ウエッブサイトをごらんの方々のために2005年1月から2006年3月まで、去年に治療した子供たち、105名の名前と病名と完治か継続かのリストを添付しました。寄付を下さっている方々には、春にこれ以外にフィリピン政府に提出している会計監査士作成の全会計報告書をお送りしています。
January
2005-March 2006
|
Name of Patients |
Defects |
Assessment |
|
1. Ali Kasim |
Eye Defect |
Finished |
|
2. Jaymarck Anthony Ordas |
Meningitis |
Under Medication |
|
3. Samirudin Landasan |
Eye Defect |
Finished |
|
4. Dominic Ortega |
Severe Malnourishment |
Deceased |
|
5. Mariane Canete |
Urinary Tract Infection |
Finished |
|
6.Rene Alilian |
Tuberculosis |
Finished |
|
7. Norfie Sacandal |
Skin Disease |
Finished |
|
8. Abdul Rahib Makalimpas |
Eye Defect |
Finished |
|
9. Angelo Villarubia |
Hydrocephalus |
Under Medication |
|
10. Princess Shane Montawal |
Colostomy |
Under Medication |
|
11. Melecia Lumbay |
Cancer of the Bone |
Under Medication |
|
12. Mary Mae Rodriguez |
Harelip |
Finished |
|
13. Cherry Mae Ondoy |
Colostomy |
Finished |
|
14. Abdulnasser Hussain |
Ear Infection |
Finished |
|
15. Noeme Aguana |
Arm Fractured |
Finished |
|
16. Ilonah Jean Espanola |
Kidney Defect |
Under Medication |
|
17. Alexander Acenas |
Histiocytosis |
Finished |
|
18. Ma. Isabel Bermudes |
Colostomy |
Finished |
|
19. Neil John Cabalum |
Right Leg Fractured |
Under Medication |
|
20. Princess Sophia Silverio |
Hydrocephalus |
Finished |
|
21. John Paul Cabug-os |
Harelip |
Finished |
|
22. Wilvie Jay Castillo |
Asthma |
Finished |
|
23. Nora Mae Saac |
Leukemia |
Finished |
|
24. Hanna Grace Rafayla |
Harelip |
Under Medication |
|
25. Glency Lord Montales |
Infected Wound |
Finished |
| 26. Jurry Caalim |
Rheumatic Heart Disea |
Deceased |
|
27. Dolorosa Zamora |
Rheumatic Heart Disease |
Under Medication |
|
28. Christ Mark Vinzon |
Hernia |
Finished |
|
29. Duldulao, Albert |
Partial Seizure |
Finished |
|
30. Jenefer Getuya |
Rheumatic Heart Disease |
Finished |
|
31. Ginalyn Gravanto |
Leukemia |
Finished |
|
32. Jassen Mampo |
Eye Defect |
Finished |
|
33. Jaher Mamalo |
Eye Defect |
Finished |
|
34. Maranatha Cunado |
Tonsillitis |
Finished |
|
35. Joselito Gamut |
Rheumatic Heart Disease |
Finished |
|
36. Wilmar Nebrida |
Arm Fractured |
Finished |
|
37. Mary Grace Punate |
Eye Defect |
Finished |
|
38. Mary Jane Tacadao |
Heart Disease |
Deceased |
|
39. Aiza Mait |
Toxic Goiter |
Under Medication |
|
40. Idion Langote |
Dengue |
Finished |
|
41. Berlyn Luna |
Eye Defect |
Finished |
|
42. Romeo Dumas |
Cerebral Palsy |
Finished |
|
43. Lovely Girl Dumas |
Asthma |
Finished |
|
45. Honey Dave Igaan |
Diarrhea |
Finished |
|
46. Jemro Magao |
Hernia |
Finished |
|
47. Phil Jay Delegencia |
Fever |
Finished |
|
48. Jonard Pansa |
Hernia |
Finished |
|
49. Kimberly Ondoy |
Cleft Palate |
Finished |
|
50. Monaliza Magsayao |
Eye Defect |
Finished |
|
51. Vanessa Daquis |
Inborn Abnormality |
Under Medication |
|
52. Rovil Parcon |
Wilms Tumor |
Under Medication |
|
53. Harrieth Mae Delgado |
Kidney Defect |
Under Medication |
|
54. Jerelyn Lumondang |
Heart Disease |
Under Medication |
|
55. Montaser Sabil |
Cerebral Palsy |
Under Medication |
|
56. Denmark Calexterio |
Cerebral Palsy |
Under Medication |
|
57. Michelle Sacandal |
Eye Defect |
Finished |
|
58. DonDon Etang |
Harelip |
Under Medication |
|
59. Gerald Calibay |
Diarrhea |
Finished |
|
60. Rene Pepito |
Rabies |
Finished |
|
61. Marivel Gubat |
Anemia |
Finished |
|
62. Samuel Dizon |
Infected Wound |
Finished |
|
63. Clinton Chavez |
Hernia |
Finished |
|
64. Tristan Castaneda |
Rabies |
Finished |
|
65. Richard Amora |
Cancer |
Finished |
|
66. John Mark Laranjo |
Fever |
Finished |
|
67. Joel Etang |
Amoeba |
Finished |
|
68. Rose Salana |
Infected Wound |
Finished |
|
69. Jenny Albaira |
Infected Wound |
Finished |
|
70. Irene Matunog |
Eye Deffect |
Finished |
|
71. Leah Maangue |
Anemia |
Finished |
|
72. Rhea Sevilla |
Urinary Tract Infection |
Finished |
|
73. Noemi Flojimon |
Ribs Defect |
Finished |
|
74. Nilo Pautan |
Rabies |
Finished |
|
75. Margie Dizon |
Amoeba |
Finished |
|
76. Albert Yupalan |
Headache |
Finished |
|
77. Sandato Alibay |
Harelip |
Finished |
|
78. Dimaanu Rizza |
Cyst (Neck) |
Finished |
|
79. Ailyn Dizon |
Dengue |
Finished |
|
80. Norhana Biang |
Dental Check-Up |
Finished |
|
81. Aiza Lansangan |
Fever |
Finished |
|
82. Rowena Hashim |
Skin Disease |
Finished |
|
83. Samraida Naga |
Harelip |
Finished |
|
84. Kuliling Panambay |
Eye Defect |
Finished |
|
85. Janice Umali |
Urinary Tract Infection |
Finished |
|
86. Adas Brian Andreo |
Dengue |
Finished |
|
87. Weldie Albacite |
Infected Wound |
Finished |
|
88. Jonnafel Elbani |
Tuberculosis |
Under Medication |
|
89. Melojen Lumbay |
Fever |
Finished |
|
90. Fairudz Bateg |
Cyst |
Finished |
|
91. Grace Espanola |
Cough |
Finished |
|
92. Maydhelyn Cuizon |
Eye Defect |
Finished |
|
93. Armelyn Lumbay |
Eye Defect |
Finished |
|
94. Jessame Lumbay |
Ear Defect |
Finished |
|
95. Stephanie Soriano |
Fever |
Finished |
|
96. William Bacea |
Ulcer |
Finished |
|
97. Bryan Dizon |
Dengue |
Finished |
|
98. Cunanan Pagayao |
Dengue |
Finished |
|
99. Paul Cunado |
Fever |
Finished |
|
100. Sunshine Gubat |
Fever |
Finished |
|
101. Salamia Tacubungan |
Harelip |
Finished |
|
102. Ronnie Espanola |
Skin Allergy |
Finished |
|
103. Rowena Impoc |
Fever |
Finished |
|
104. Edwin Umpan |
Fever |
Finished |
|
105. Kristine Joy Santua |
2nd Degree Burn |
Finished |
The Mindanao Children’s Library Foundation Inc. catered one hundred five
(105) patients on the year January 2005 to March 2006 and seventeen (17)
of them are under medication.
2005年度から2006年3月までの医療プロジェクトで治療した患者の氏名、症状、完了か継続かの報告です。
ミンダナオ子ども図書館だより:医療 7月26日
肺の癒着が進んでいる女性が、ダバオの私立病院でチェックを受けた後に、ダバオメディカルセンターに入院する事になりました。ダバオメディカルセンターDMCは日本のジャイカからの支援が多い公立病院で、私立病院にとても入ることの出来ない多くの貧しい人々にとっては大きな救いとなっています。日本のODAが成功している大きな例の一つであると感じます。ライオンズクラブ、ロータリークラブ、メソニックファンデーションの支援を受けて兎口や目の異常を取り上げているマハリカファンデーションや、キリスト教系の障害者更生施設Our
Lady of Victoryと 連携をとり手術を実行しているジェロームファインデーションも大きな貢献をしている団体です。ミンダナオ子ども図書館の患者たちも救われており、こうした本格的なファンデーションの貢献は大きいと思います。
問題はその所在地がダバオに集中しており、こうしたファンデーションがあるにも関わらず、ミンダナオの僻地の貧しい人々がなかなかその功徳にあずかれないことでしょう。80パーセントを超えるという貧しい人々の多くはダバオにまで行く費用が出ず、また治療費がただになっても病院などから要請される点滴や輸血用血液、薬代が払えない状態にあるからです。せっかく日本などからの支援がありながら、本当に貧しい人々の救済にいたらないのは残念でなりません。ファンデーションのなかには、マハリカのようにときどき車で僻地を訪ねて治療したり、ジャイカの支援を受けているDMCのように、スマイルファンデーションと連携をとって地方の役所やラジオで無料の兎口の治療も行っていますが、僻地に拠点を持っていないために散発的であったり、需要の高い病気や手術にまでは手が届いていないのが現状です。
その意味では、ミンダナオ子ども図書館の医療プロジェクトは、山岳地帯の先住民族やダバオに出ることの難しいイスラム地域の子どもたちに貢献と安心を提供していると、先住民族のリーダーやイスラム教徒の人々から言われています。地図でごらんになるとおわかりになるように、ミンダナオ子ども図書館のあるキダパワンは、ミンダナオの中心部近くに存在しており、周囲は山岳民族の地域で、西はイスラム地域の接点にあるからです。また、読み聞かせ活動を常時することで、絶えず僻地へ行き、さまざまな現場の子どもたちの健康状況を確認していることも大きな意味を持っています。
ミンダナオのこれからの課題は、こうしたより僻地にある小さな活動機関と、大都市ダバオの大きな医療機関やファンデーションが連携を持ちながらより広範囲の貧しい人々(本格的に救済を必要としている人々)を支援していくことだと思われます。
また、ダバオ一極集中を是正するためにも、要所要所に散在する公立病院。例えばキダパワンのアマス病院などをジャイカや日本政府がもう少し支援できれば、さらに貧しい人々の福音となると思われます。アマス病院などは、多くの貧しい人々が利用するのですが、建物の衛生状態も悪く患者が通路に寝ているしまつで、広大な州庁舎のそばにありながらその設備や医療担当者が常駐していることが少ない結果充分な治療が行われておらず、私たちの患者もこちらから回されてきたり、治療が完了されずに来る患者がいて、キダパワンにおいては結局、治療費の高い私立病院に入院させている現状があります。ミンダナオの中央、東西南北の接点に位置し、山岳民族とイスラム教徒を結ぶ接点になりながら残念なことです。
肺の癒着が進んでいる女性は、喘息が発端で初期においては薬の治療で治る状態でした。当時はデパートで働いて薬を買って治療していましたが、デパートの職を追われてしまい、貧困のなかで薬を買ったり買えなくなったりをくり返し、現在の状態になってしまいました。
(こうしたダバオのデパートなどの雇用は、比較的恵まれた職ですが、終身雇用ではなく、5ヶ月契約がほとんどです。理由は、半年未満の契約であれば正規の雇用ではなく、健康保険や年金の法的責任がないからです)
昨日、病院に見舞いましたが、酸素吸入を受けやせ細り、方肺が機能不全で心臓も弱り手術は不可能で薬の投与で病状の進行を見守るという診断です。キダパワンでは回復不可能という診断ですが、ミンダナオ子ども図書館では、いったん手がけた患者は可能性がある限り支援し続けると言うポリシーですので、本人の希望もあり、ダバオに運び最後の可能性をさぐりつつ治療を進めています。

新たに私たちのスカラーで、親と死別し完全な孤児である大学生、クリスティーン・パデルナルさんがデング熱で緊急入院しました。試験があり、熱があるにもかかわらず試験終了まで頑張ったのも良くなかったようです。仲間のスカラーと下宿生活をしていたので知らずに入院が遅れました。現在、点滴と輸血を受けています。デング熱は大変ですが、設備のととのった私立病院で治療を受けていますので生命の危険はないものと思います。4月にはコナナナ君が同様の状態で輸血を受けています。治療を受けられない貧困状態の人々の場合は、死に至る病です。
同じデング熱のアイリーンは、初期の状態で入院したので輸血を受けずに退院しました。200名近い奨学生がいますと、皆極貧家庭から来ているので基本的な体力や健康状態、栄養状態が悪く、誰彼となく病気をし、その健康管理も大変ですが、一人一人を我が子のように考えて、出来るだけの事をしていくのが私たちの役割だと思っています。
ミンダナオ子ども図書館便り 7月23日
お元気ですか。今年の夏は暑くなりそうですね。
ジョイさんの手術が終わりOur Lady of
Victoryに移りました。
車椅子ですが、傷も癒えて、うれしそうです。義足を作り歩行訓練にはいります。
6ヶ月の予定で、退院後は来年度から大学に通います。

フィリピンインサイドニュースから http://www.t-macs.com/
◆マギンダナオの避難所でさらに4人死亡
マギンダナオ州の民兵とモロ・イスラム解放戦線(MILF)強硬派との戦闘で発生
した避難民に関してこのほど、避難所で赤ちゃんを含む4人が病気で死亡、避難所で
病気のため死亡した人は合計7人となった。当局では、住民の一部が政府側の医師を
拒否してゲリラ側の研修医に治療を求めていることが原因ではないかとみている。
(Inquirer)
マギンダナオの難民が出ている地域に関して、ピキットのDSWDの所長さんで、ミンダナオ子ども図書館のボードメンバーであるグレイスさんに問い合わせたのですが、現在その地はとても危険で入れない状態だという事で、緊急の支援を延期しました。
難民センターで赤ちゃんが死亡することは良くあることですが、残念でなりません。
ミンダナオでは、政府軍と新人民軍NPAとの衝突も各地で起こっています。
先日は、私たちのスカラーの居るアラカンでも戦闘が起こり数名が亡くなりました。

先日は、マキララ地区のバゴボ族の村に読み聞かせに行きました。集団で読み聞かせをした後、ジナが一対一で読み聞かせをしている様子を写真にしました。ジナはマノボ族、女の子はバゴボ族、お互いに言葉がわからないのには驚きました。
この村出身のマハールさんは、バゴボ語で読み聞かせをしました。お父さんもうれしそうでした。
新人民軍の多いところですが、戦闘が起こらないことを願っています。
子どもたちはかわいいですから。
ミンダナオ子ども図書館便り 7月20日
ダバオメディカル病院にジョイをたずねました。
手術が終わり、少し疲れた顔でしたが、穏やかで元気そうでした。手術前と後の写真を添付しました。
早いもので、明日には退院し、ダバオの障害者更生施設Our
Lady of Victoryに移ります。そこで治療後の足の回復を待ち、その後義足の制作に移り、6ヶ月歩行訓練を続けます。Our Lady of
Victoryは、現在私たちの
スタッフでポリオのノノイ君が車椅子の訓練を受けたところです。今回の手術は、ジェロームファンデーションの協力で、ダバオドクトル病院の先生が手術代を無償で執刀してくださいました。私たちは、薬や点滴血液などその他の費用を負担しています。

添付したもう二枚の写真は、購入した田んぼの田植えが終わった様子です。田んぼは個人購入5ヘクタールですが、ここでとれる米をミンダナオ子ども図書館に寄付して56名の食費の負担を軽減します。今までも、井戸を掘り雨水をためて使うことで水道代を大幅に削減し、奨学生達が野菜を自給させることで主食代を削減、今回の水田で50キロの米袋が二日で消費され月々20000ペソほどかかった食費が削減され、さらにバナナを500本順調に生育していますので福祉局からの要請のある果物代が削減できます。肉と魚をのぞいてほぼ自給体制が今年中に確立します。削減できるものはとことん削減して、浄財である寄付はなるべく貧しい子どもたちの医療などに使えるような体制にしていきます。


農業部門は、3名が担当していますが、一人はマネージメント、残りの二人は親が無く小学校中退で兄弟姉妹のために働いている若者です。同じ貧しい家の子でも、奨学金を受けて大学に行ける子の場合は、それだけで人生の出発点で特典があるので、農業部門で雇う子は小学校レベルで苦労している子を選んでいます。将来は、もう少し広い果樹園を購入して、高地農業の可能性を試験したり、低学歴の貧しい若者たちを雇用できる場になればと思っています。彼らの最低給与3000ペソは、米を寄付するミンダナオ子ども図書館から出しますが、それ以上は余剰米を売却して収穫のある年二回にボーナスとして支給する体制にします。収穫が多ければボーナスも高くなる形で労働意欲が高まると同時に、農業=低賃金労働といったイメージからの自立的脱却をめざしたいのです。低学歴でも努力すれば高学歴者と変わらない賃金が得られるようにしたいのです。
ミンダナオ子ども図書館便り06711医療 7月11日
医療活動報告
医療活動は、予算が限られた状態でぎりぎりに活動しています。
ポリオのジョイさんの手術が始まります。
ジョイさんは昨日、ダバオドクトル病院に入院しました。先天的に膝から下が30センチほどで細く萎えており、それでも膝にゴム草履を履いて歩く状態でした。手も指が3本しか無く、本人の表現を借りるとカニの手だそうです。家庭は極貧ですが、高校までピキット市の市長が面倒を見て、高校を卒業しました。今はミンダナオ子ども図書館に住み大学に行く準備をしていましたが、私たちの懇意にしている障害者自立施設を運営しているアメリカミッション系のファンデーション、Our
lady of Victoryに相談し、せめて彼女特有の靴
を作ろうと思いたちうかがったところ、膝下を切断して義足を入れれば歩けるという結論に達しました。本人と両親も強く希望。今回の手術となりました。
手術後、Our
lady of
Victoryで半年間、歩行訓練を受けます。この施設では、滞在期間中にコンピューター指導や絵画指導をしています。彼女はコンピューターを使えるようになりたいという希望を強く持っていますので練習を始めることでしょう。将来はミンダナオ子ども図書館を手伝ってもらえたらと密かに思っています。
ミンダナオ子ども図書館でハウスマネージメントをして下さっている方の娘さんが、片肺癒着で緊急入院しました。この娘さんは高校卒業後デパートに勤めたのですが、肺炎の疑いありで停職処分、ミンダナオ子ども図書館に奨学生として応募してきたときに調査すると、水田の奥の奥で、小さな竹小屋に隔離されるように一人で住んでいました。やせ細り喘息のような発作もあり、奨学生になるのは無理と判断。父親は病死、母親は住み込みのお手伝いをして口糊をしのいでいますが、薬を買うことも出来ない状態なので、ミンダナオ子ども図書館のハウスマネージメントで雇いました。その後、喘息の薬は買うことが出来るようになったのですが、昨日緊急入院しました。今後、医師の指示に従って手術などがはじまります。
長く喉のガンが転移し骨ガンになり、母子ともどもミンダナオ子ども図書館で暮らしてきた、ジクジク、アルメリン、ラライ、バンダン姉妹のお母さんが、緊急入院しました。歩行不能で治癒も不可能、ガンも最終段階でせめて山ではなく図書館で子どもたちと日々を過ごせればと3年前に引き取りました。夫はすでに病死。ご本人も一昨年にはすでに命は無いだろうと宣告されていたのに今まで持ったのが奇跡です。今回の緊急入院が最後になるのではないかと懸念しています。母親が亡くなれば子どもたちは完全な孤児となります。
ジクジクは来年卒業し学校の先生を目指します。支援し続けて下さっている瀬川神父様ありがとうございます。アルメリンは今年大学一年生で看護士の勉強を始め、ラライは高校生、バンダンは小学校5年生です。今後は、ミンダナオ子ども図書館で自立まで面倒を見ていくことになると思います。
デング熱で緊急入院したアイリーンは無事に退院しました。
いよいよデング熱の季節が始まり、大きな手術もひかえている子もあり。お断りしている子も多く、予算とのにらみ合いが続いています。
医療以外のプロジェクトは順調に進行しています。
読み聞かせプロジェクトとスカラシップは、キダパワンのダバオよりの山岳地帯、マキララの学校の先生からこちらの方にも活動をのばして欲しいという依頼を受け、今年はそちらに力点を置くことに決めました。
マキララ地区は山岳地帯で貧しく、マハールさんというバゴボ族の子が奨学生で来ていますが、アロヨ大統領が一掃するように指示を出した共産ゲリラNPAが大きな力を持っている地域となっていますが、そうした政治的な事は子どもたちとは関わりが無く、戦闘が起こらなければ良いと願っています。
そのような地域は、先住民が多く、子どもたちにとっても医療は大変重要な意味を持っています。
ボードメンバーの紹介 7月10日
ミンダナオ子ども図書館では、当然の事ですが、法人として月一回のボードメンバーによる会議が開かれて議事録が取られています。たった今、月例のボードメンバーによる会議が終わりました。
午前から午後に渡って様々なことが話し合われました。
皆様にも、私たちのボードメンバーを紹介いたしますと・・・・
マノボ族で先住民族協会に属するスウーザンさん:父親はフィリピンでも歴史的に有名なマノボ族の首領インカル一族でキダパワンにはその名をかむせた通りがあります。
州立大学の敷地も寄付していますが、ご本人はミンダナオ子ども図書館に土地を譲ってくださった後に質素に住んでいらっしゃいます。
建築家で銀行や病院を初め広くこの地区の建築を手がけている顔の広いダニー氏:ご本人が苦学生でスカラーの気持ちが良くわかると同時に、才能に恵まれた建築家ですがとても気さくで謙虚な方です。ミンダナオ子ども図書館の趣旨に賛同して図書館の設計施工を格安でしてくださいました。仕事上、銀行、病院、商工会など多くの人々と懇意の方です。奥様は地元の銀行に勤めてらっしゃいますが、仕事のプロの立場から色々的確な理解とアドバイスを下さいます。
戦闘のあったピキット市のソーシャルワーカー(社会福祉部)で部長を務め、オブレード会OMIの司祭と共にイスラム教徒を助けているグレイスさん:命がけで戦闘地のイスラム教徒救済の活動に奔走したり、私の非常に尊敬しているソーシャルワーカーです。喉に腫瘍が出来ているようで劣化ウランの影響ではないかと心配していますが、活動的で魅力的な方です。専門の立場から常に的確で公平なアドバイスを下さいます。
アポ山麓に住み、先住民の子供たちのためにデーケアセンター(保育所)を開いているビックビクさん:ご本人も山での生活なので先住民の立場が良くわかっておられると同時に、キダパワン司教区とのつながりも深く、正義と平和協議会の運動にも関わっている方です。
最後が、ミンダナオ子ども図書館を代表して、経理担当者のエープリルリンがなっています。
このボードメンバー5名に、プレシデントのベビンさんとディレクターの松居友が加わって、会議が進行します。
今回、話し合われた内容は、四半期の会計報告とスカラーの現状報告。
戦闘が起こり始めたミンダナオの情勢分析:難民がどこで出ているかなど・・・今年度のスカラシップの状況と来年度の方針:来年度は比較的割合として少ないイスラム教徒と先住民族の高校生を増やすことになりました。また選考の難しさとベストと考えられる公平な選考のあり方が再度確認されました。孤児を優先すること、土地なしの日雇い家庭を第二に優先することなどです。
医療プロジェクトの現状と今後の展開:医療支援が少なく、地元での要望が非常に強いこと、今後多くの難民が発生する可能性があることなど、医療プロジェクトの重要性と打開策が話し合われました。
日本の支援者の考え方とフィリピンの考え方:ミンダナオ子ども図書館が今後さらにインターナ
ショナルな視点、他国で支援してくださっている方々が期待していることなどを、ある程度理解した上で活動していく必要がある事、文化の違いを超えてそうした視点を順次スタッフやスカラーも養っていくことの必要性が議論されました。
現在のボードメンバーは私欲が少なく献身的な人が多いので、すがすがしく進みます。
現状の認識もしっかりしており、スタッフもようやく方向性を見失うことなく議論を進められるようになってきました。
今後も時間をかけて、日本方式でもなく、フィリピン方式でもない、アジア的で国際的にも通用する独自のミンダナオ子ども図書館方式の運営を模索して行ければ良いと考えています。
ミンダナオ子ども図書館だより 6/11/2006 新学期始まる
マノボ族の村、プロックエイトの子どもたちへの学用品の支給と学校での炊き出しの準備が終わりました。
グリーンヒル小学校に米と粗挽きトウモロコシをそれぞれ1サックづつ届けました。
6月から、公立学校と一部の大学が授業を開始しました。ミンダナオ子ども図書館に住み込みの子どもたちは、今年は46名ですが、新しく高校一年や大学一年に入学する子は、学校に行けるがうれしくてエキサイトしているのでしょうか、朝の4時に目覚めて4時半には起き出して準備をして、6時には皆で朝食をとって、6時半には学校に行きました。とうぜん学校では先生も来ておらず、「ミンダナオ子ども図書館の子はちょっと早く来すぎる」と注意された?ようです。興奮していたのですね。帰ってくると、一生懸命ノートを開いて勉強しています。あまり頑張りすぎると続かないぞ、と言いたくなりますが、まあ良いか・・・・
一〇代前半か半ばでティーンエイジャーなのに、まるで初めてランドセルをしょった小学校一年生のような張り切りようです。
こちらの食生活について簡単にお話ししますと、一般的には米が主食になっていますが、貧しい家庭の場合は粗挽きトウモロコシが主流です。一見米と変わらない粒状ですが、値段が安くなっていると同時にトウモロコシは斜面でも育つので山岳民族など山の民の主食になっています。しかし、トウモロコシも年中食べられるわけではなく、そのためにカサバイモが植えられていて、さらに貧しい家はこのカサバイモと蒸かしバナナ、と言う感じになります。しかし、それも3度は食べられず、お弁当を持ってこられない子がいるので、今回の炊き出し計画はその子たちが午後も授業に出られるためのプロジェクトです。米にトウモロコシを混ぜて炊くのですが、米だけにしなかった理由は経費の節約というよりも、米だけという豪華な昼食は豪華すぎてアンバランスだからです。
こちらでは米が食べられると言うのは、ステータスでもあり、しかも三食米が食べられるというのはそうとう生活環境が良いのです。ちなみにミンダナオ子ども図書館に住んでいる子は、質素な食事ですが、三食米が食べられます。五五名が、ほぼ一緒に食べます。私も子どもたちと一緒に同じものを食べています。訪問者は、私が一緒に生活し、一緒に食事をしているのを見て、一様に驚かれます。何故かと言いますと・・・
フィリピンは、土地所有者であるオーナー家族、使用人、労働者、日雇い労働者とそれぞれ食事の順番も内容も、食事をする場所も決まっているという、まるで植民地時代からの階級制度のような生活があります。
ファインデーションであっても、オーナーやスタッフは別の時間に別のものを使用人に料理させて食べるのが通常だからです。
ある結婚式では、新郎新婦と家族身内と特別ゲストが高いところで食事をし、一般ゲストがその後に食事をし、その後、スタッフや使用人等が別の低い場所で食事をし、一番最後に日雇い労働者や就労学生などが、別の小屋の中のベニヤ板にまるで捨てられたように投げられる残飯をむさぼり食べると言う光景を見ました。見たと言うよりも、一緒にそこで私も残飯を食べたのですが・・・・
(就労学生=住み込みで働きながら学校に行かせてもらっている貧困家庭の若者たちで、お手伝いよりも経費がかからない安価な労働力として使われる。大学に行かせてもらう場合は少なく、ほとんどが経費がかからない公立高校までの支援で、夜間授業や日曜日だけの授業が多い。それでも何とか卒業したくて、多くの貧しい子が応募するが、早朝から深夜に至る労働のきつさや、復習する時間もなく、睡眠不足や疲労などで力尽きる子が多い)
この経験が、ミンダナオ子ども図書館のスカラシップを始めたきっかけの一つです。
このような状況を見て、こうした貧しくとも頑張ろうとしている子にこそ、大学まで行けるスカラシップを作りたいと思ったのです。
「こんな貧しい子たちに、高等教育を施しても無駄ですよ、教育のない親に育てられて、まともな人間に育つわけがないのです」と言われましたが・・・・確かに、卒業した後も、縁故や大金を積んで就職や資格試験を通らなければ、それなりの仕事や地位に就けない仕組みがあるのですが・・・・・・それでも風穴を開けてやるぞ!
ムスリムの小学校にカバンと文具を届ける 2006/6/6
日本滞在中は、本当にお世話になりました。
大阪中央図書館や大阪保育連盟での講演が決まり、5月のマノボとムスリムの若者たちの招待が進みはじめ、実現すると良いですね。こちらの若者たちにも話しましたが、狐につままれたような顔をしています。
公演の準備のために、マノボのクリンタンとアゴンを手に入れなければなりません。
両方で18万円ほどと少し高価なのですが、民族文化を守り伝承していく図書館としての役目を考えると、思い切って手に入れた方が良いと思っています。ムスリム地域で唯一製造しています。
ミネハハさんのコンサートでの募金を使わせて頂いても良いでしょうか?いつかお世話になった行橋や小倉でも演奏しに行きます。
フィリピンにもどって、さっそくイスラム地域のカラカカンの子供たちに鞄や定規やノートを持って行きました。
彼らの村は山の上なのですが、小学校は麓です。
校長先生も大喜びですが、校長先生のズボンにも継ぎが当たっていて、生活が大変なんだなあと思いました。
子供たちも母親たちも大喜びです。
写真を貼付しました。

ミンダナオ子ども図書館だより 日本滞在とミネハハさんのチャリティーコンサート
ミネハハさんのミンダナオ子ども図書館支援チャリティーコンサートは感動しました。
ミンダナオの私の撮したイスラム地域の読み聞かせの映画映像とサトウキビ畑の歌・・・
現地の子どもたち、とりわけ劣化ウランと思える奇形で亡くなっていった、水頭症や白血病の子のこと、図書館の子どもたちの事が次々と頭に浮かび、涙がでました。
山元神父さまを始め、涙を流された方も多かったようです。
早く平和と貧困が無くなる時代になれば良いのですが、日本は悪い方へ動いているようにも思えます。
30日は小倉のカトリック教会でコンサートがあります。
私は31日にフィリピンに戻るので無理ですが、いらしてください。
夜7時からです。
ミネハハさんは、3000ものコマーシャルソングを歌っていらっしゃいますが、歌を聴いて、癒し系などを遙かに超えた深く真実の心と驚くほどの歌唱力を持った希有の方だと感じました。
あちらこちらでミネハハさんを招いて、ミンダナオ子ども図書館チャリティーコンサートを開いていただければ幸いです。ウエッブサイトは以下です。
http://www.minehaha.com/
今回は、11月の大阪市立図書館、関西保育連盟などでの講演を始め、少しずつ秋の講演会予定が埋まってきました。
10月上旬は、東京、関東、東北新潟などに講演報告会をしたいと思います。
下旬は、九州です。
11月は大阪を中心に兵庫、関西、四国地区です。鳴門や徳島高松にもうかがいたいと思っています。
小さな家庭集会から報告会、講演会、どのような規模でも謝金を問わず、話にうかがえたらと思いますのでご連絡下さい。
今回は、なにより来年五月のイスラム教徒6名、マノボ族の若者6名で、すばらし民族楽器の演奏と踊りを、私たちの図書館の若者たちが招待され、大阪と九州での交流会が実現に向けて動き始めたことです。
大阪の民族博物館関係者からも貴重な文化財だと言っていただいたもの、家の若者たちが持っているとは私も驚きでした!
色々な交流が生まれると良いですね。
それから、鳴門のカトリック教会の方々、4WDありがとうございました。
強力8Vのチェロキーがこれから山で活躍します。
頼もしい見方です。
滞在中、皆様ありがとうございました。
またお目にかかれる10月を楽しみに、そして5月に向けて頑張ります。
日本の子どもや若者にミンダナオの健康な風を少しでも届けるために。(日本の子どもたちの心が心配ですので少しでもお役に立てれば幸いです)
ミンダナオ子ども図書館だより 2006/5/1
マノボデーとアポ山登山

マノボ族の若者たちでマノボデーを行いました。
フィリピンは、北のルソン島ではマニラを中心にタガログ語圏、南はビサヤ語圏でビサヤミンダナオは貧しく北に出稼ぎに行くと差別されます。しかし、ミンダナオでは、ビサヤ語が幅をきかせ、ムスリムやマノボ族などの少数民族が差別されます。
ビサヤ語圏の人々は、スペインからの影響とアメリカの影響を受けた文化を中心に自分たちをよりすぐれたものとして、土着の文化を軽蔑しひくく見る傾向があります。
言い換えれば、先住民族やイスラム教徒は肩身の狭い思いをしている。これはここの若者たちも言うことです。
イスラムの若者たちは宗教を背景にした反発力を持ち、若者くして、クリムタンなどの楽器を見事に奏で、料理もうまく、ムスリムデーでわかったように自分たちの文化やアイデンティティーを保持している。しかし、マノボ族などの場合は、親の世代と若者たちの世代の断絶が始まっている。子供たちの世代は、楽器を奏でる力を失い(観光化では別ですが)日常の中での文化が消滅し始めている現状です。
今回のマノボデーはそれを打ち破る試みでした。結果的に、親の世代が、若い世代に自分の文化を使える必要を痛感し、若者たちは、自分の文化の美しさを自覚し、それを恥ずかしいと感じなくなる、一歩だと感じます。
マノボの料理では、とりわけカエル(これは食用蛙ではなく、日本のアカガエルに近いものかと思われます)カエルのアドボ(煮込み)やギナタアン(ココナツ煮)が田んぼで取るところから、解体料理方法(竹筒にカエルを入れて煮込む)この竹筒料理はカサバイモや鳥も煮込まれました。もう一つは、ニシキヘビで、ニシキヘビの解体も撮影できましたし、ニシキヘビをウナギのように焼き、鱗を削り、さらに煮込むことで、腰があっておいしいニシキヘビ料理が出来ました。
イスラムの若者たちは、カエルとニシキヘビは食べないのですが、文化として色々な面で協力してくれました。相互の文化を尊重する方向が生まれてきているのはうれしいことです。また、喧嘩の仲裁のための生け贄儀式で、踊りながら白い鶏を歯でかみ切って殺し捧げる様子の中には、旧約と新約聖書の世界につながるものを感じました。
マノボデーの様子は、映像でDVDにまとめます。それをさらに見ることによって、彼らが自分たちの文化の美しさと貴重さを再認識できるからです。
ミンダナオ子ども図書館は、こうした現地の若者たちの日常から活動が開始され、自分たちの文化やアイデンティティーを自覚したり、独自にプログラムやプロジェクトを生み出し、より貧しい子供たちや消えゆく文化を救済する場としてゆっくりと動き始めています。

アポ山にも登りました。
3泊でした。10名の若者たちと、早朝3時に麓を出発し夕方6時に山頂に着き2泊。
下から見ると単純だと思っていたアポ山が、上では九つの見事な岩峰で出来ていて、クレーターなどもあり、複雑で実に面白い山であることがわかりました。縦走でも出来ます。
また何より、山頂近くにいくつもある池や湖が美しく、色々な方角から登ってみる価値がありそうです。
山頂近くはコメツガの木が多く、山頂の至る所にブルーベリーがあって食べ放題でした。
キダパワンはアポ山の最も良い登山基地です。世界中から登山に来ますが、登山の好きな方、ミンダナオ子ども図書館に泊まって若者とたちも交えて登りませんか?必ずガイドが必要ですが、ガイドもポーターもこちらで雇えます。良いガイドの方で、ミンダナオ子ども図書館のボードメンバーの友達の方です。
ミンダナオ子ども図書館便り 2006/1/29
ムスリムデー
今日、全体ミーティングがあり、90名近いスカラーが集まりました。
今日は、ムスリムデーとして、昨日からイスラム教徒のスカラーが朝から準備をはじめました。
当日は、イスラムの食事をします。そして、イスラムの歌、踊り、最高潮に達したところでイスラムの結婚儀式でした。
イスラムの結婚式の飾り付けに、外に幟まで立ち、スカラーのアブドゥル君たちがクリムタン(イスラムの楽器)を奏で、奇妙な獅子舞のようなものも出て、すべては本格的。これはちょっとした体験でした。
言葉では言い表せない・・・・この準備のために、父親軍も5人応援に来て、山羊を殺して料理するところから独特のお菓子や食事作りまで、徹夜で手伝ってくださいました。それにしても、イスラム教徒の父親は子煩悩で、しかもイスラムの男性は本当に料理に誇りを持っている。料理もここでは男の力仕事の一つだとしみじみ思いました。
この体験は、ちょっと言葉では表せないので、ビデオを撮りましたので編集して機会があればDVDなどでお見せしたと思います。
こうした交流は若者たちにも絶大な効果を及ぼし、イスラムに対する敵対心などが見事に仲間意識に転じていきます。
毎年、1月最後の日曜日はムスリムデー、4月最後の日曜日はマノボ族デー(先住民族の日)8月最後の日曜日はイロンゴ・ビサヤデー、12月第二日曜日にはクリスマスデーがあります。よろしかったらご参加ください。
ビデオに熱中して良い写真が撮れませんでしたが、結婚式(本当ではない)の一場面を添付しました。
松居友
スカラシップの家庭調査
新年、お元気ですか。
今は、毎日応募してきたスカラシップの候補者の家を回って家庭状況のチェックをしています。
遠くから応募してきた子も数人います。
先日は、ブキッドノンの子を訪ねました。同時に、ブキッドノンの先住民族協会の首長から、こちらの先住民族の子のためにも活動範囲を広げてくれないかとの要請がありましたのでうかがいました。
山奥には、4泊かけて入り、裸で生活している民族もいるそうです。こちらの先住民族が置かれている様々な状況をうかがいました。いつかインタビューしてみたいと思います。そこで不幸な子に出会いました。先住民族の15歳の女性なのですが、父親がわからず、母親が妊娠して、老夫婦の元に捨てられたのですが、その老夫婦の面倒をみています。しかし、家の状況がひどく人がとても住めるような状態ではないのです。

老夫婦の問題が解決すればこちらで引き取っても良さそうです。
ジェネラルサントスにも3人候補がいてたずねました。その先のバロットアイランドにも候補者がいるのですが、船で4時間、都合がつかずに諦めました。ビラーン族が多く、こちらも裸で生活している種族がいるようです。今後の課題です。
イスラムとキリスト教徒の対立が続くコロンビアからもイスラム教徒のスカラーが応募してきており訪ねました。貧しい中でがんばって大学に行っていますが経済的に続きません。下宿が払えず友達の家を転々としながら通いましたが新学年は無理。家も貧しいものでした。非常に危険な地域と言われていますが、ここのスカラーも採用する予定でいます。警戒していたイスラムの方々も緩和して、この人たちは一応信用しても良いのではと言う話になったようです。
レイクセブのさらに奥の山岳ひいきの麓からも一人応募していました。車でダートを1時間半、どん詰まりから徒歩で山を登りましたが、帰りは馬で送ってくれました。
その奥の山々には、ビラーン族が住んでおり、この一家は人望もあり助けています。
この一家を中心に今後この地域のビラーン族の里親制度を検討しています。
クリスマスおめでとうございます。
クリスマスに関しておもしろいことがわかりました。
フィリピンでは、熱心にクリスマスを祝います。ミサデガリオといって、クリスマス前の一週間は、4時の早朝ミサにカテドラルがいっぱい。年間の最大のお祝い・・・と考えていたのですが。
実は、フィリピン独特と言われる山岳民族に多いアライアンス教会とイグネシアニクリストは、クリスマスを祝いません。
クリスマスを12月25日に祝うのは、ヨーロッパの古代の習慣に聖書の降誕物語が重なったからだというのが理由でしょうか。復活祭と正月の方を重視するとか・・・・クリスマスを祝うのはカトリックだけだと思っているフィリピン人が多いのも驚きました。さらに、カトリックの人にきいても、クリスマスは教会では盛大に祝うけれども、家では正月の方を祝う、貧しい家庭ではクリスマスは普段の質素な食事だけども、正月だけはせめてご馳走を食べる、理由は正月にご馳走を食べないと一年中貧しい食事になるかもしれないと言う迷信を信じているから・・・・
24日の夜は、カトリックでは大晦日と同じように徹夜します。夜半には、スパゲッティーを食べます。ヤキソバの場合もあるのですが、麺を食べるのは長生きするため。同様のことは、もっと盛大に必ず正月の夜に行います。こちらは宗教を超えてイスラム教徒も同じ。どうもクリスマスと正月がゴッチャになっていて、クリスマスの基本は小正月のようです。
貧しい家の山のクリスマスはどうするかというと、ラジオでミサを聞いて普段と同じ粗末な食事をするだけ、クリスマスは家庭というよりも教会で祝うと思っている様子。しかし、正月の方は家庭で祝います。フィリピンはキリスト教徒でも一皮むくとアジアです。
今日25日、9月に生まれた娘、アンジェラ 舞花の洗礼式を行いました。カテドラルで沢山の子といっしょに。
フィリピンでは、洗礼親に複数の人がなります。アンジェラの洗礼親には、イスラム教徒の4人のスカラー、アライアンスのマノボの子、カトリックの4名がなってくれました。イスラムのスカラーたちは大喜びで名付け親になってくれ、生まれて初めてミサに出席しました。感動していた様子です。ちゃんと祈り、照れながらマンデー神父とも挨拶して。正式に洗礼親としてカトリックの記録につきます。これは本当に画期的なことで、ここまで心の垣根がとれていると言うことは、驚きと感動の一言!実に感動したミサでした。
しかも、フィリピンのカトリック教会では、イスラム教徒も名付け親になれるのです!!!ヨーロッパでもアメリカでも、イスラム教徒がどんどんキリスト教徒の洗礼親になると良いのに。
舞花の写真を貼付しました。
その後みんなで、山に泳ぎにいきました。ひさびさに温泉にも入りました。
今、ミンダナオ子ども図書館には、20名ほどが残っています。この時期に家に帰っていない奨学生は、ほとんどが父親のいない子です。亡くなったりいなくなったり。
何故母の元に帰らないかって、極貧家庭でほとんど食べ物らしいものがなかったり、他の男性と一緒だったりして自分の場所がなかったり。
家族で祝うクリスマスは、彼らにとっては、孤独で寂しい気持ちを強める時期なのです・・・・顔を見ているとよくわかります。そこで、みんなで支え合います。見ていると涙ぐましい。このようなときますます、本当に可愛い子たちだなあ、と思います。イスラムのスカラーも同じ、名付け親になってもらったのは、あるスカラーが、何故私にはメリークリスマスと言わないの、寂しいでしょ・・・と言ったことがきっかけ、皆さん、イスラム教徒にもメリークリスマスと言いましょう、イスラム教徒もキリスト教徒にラマダン明けおめでとう、と言えばいいのでした。
さて今日からクリスマスの始まりで、皆で海に行きます。海を見たこともないスカラーもいます。山から出たことがないので。
松居友
行橋カトリック教会の山元神父、イスラム教徒の村を訪ねる
21日にミンダナオに帰り、25日にまた日本に発ち30日に行橋カトリック教会の30周年式典に出席、その後山元神父とミンダナオへ、昨日マニラにお送りして、今日ようやくメールとも向かい合えるようになりました。
ヘトヘトのフラフラですが、こちらでの業務が待っています。
それでも、心待ちにして待ってくれていた30名の若者たちの顔を見ると疲れが吹き飛びます。結局、この子たちを人生の旅に送り出すこと、そして色々な地域の子供たちが少しでも希望を持って病気にならずに安心して育っていく環境を作ることがミンダナオ子ども図書館の役割なのだと思います。
とても基本的なことを、とても単純に実行していきたいと思います。
山元神父は、気さくに若者たちとつきあってくださり、とりわけイスラム地域の読み聞かせ、先住民族の医療、ダバオのイスラムのスラムでの活動に感動。イスラム地域の読み聞かせでは、ともにイスラムの人々の前で歌ったり踊ったり・・・ムスリムの人々に新鮮な驚きをあたえてくださいました。
ミンダナオ子ども図書館の若者たちも、最初は神父が泊まると言うことで緊張していましたが、その気さくさにイスラム教徒の若者たちも、ファーザー、ファーザーと慕われました。
教会からの医療支援金は、イスラム地域の子どもの救済に使います。

12月中にやることは、300名におよぶスカラーの選考を開始すること。
家を訪ねて貧困状況、家庭状況を調査。
17日にはミンダナオ子ども図書館のスカラーが全員集まりクリスマスパーティー。
キダパワンから車で3時間ほど離れたブキドノンの先住民協会から、MCLの活動をブキドノンでも展開して欲しいという要請の手紙が来ています。スカラーも一人候補者が来ているので訪ねます。
3年目で活動の形が整い、スタッフも著しく成長して、運営や仕事を任せられる体制になってきました。
来年4月で3年ですが、1月から3月には経験豊かなソーシャルワーカーのヘレンに入ってもらい、以前のソーシャルワーカーのリアが、図書館が懐かしくどうしてもここに戻って働きたいというので、受け入れる予定です。
この二人に認定法人の準備をしてもらうことになりました。
理事、役員などを全面的に見直し仕事の流れを整理します。初年度は、かつての理事がファンデーションを私物化しようとしたり(辞めてもらいました)、経理が初年度不明金が多かったりして(二重チェックを徹底して解決しました)とことんメスを入れましたが、ようやく責任ある若者たちの役員が成熟してきたので、防衛策をゆるめ少し私の手を離れて動くでしょう。その分私は、出版を含むカルチャーに関わる仕事に比重を移して行く予定です。
ミンダナオはクリスマス一色になりつつあります。
クリスマスから正月にかけては、少し体を休めたいと思っていますが・・・
前回、劣化ウランに似た症状の子のことですが・・・
今、ダバオメディカルセンターにいます。
介護を勉強したイスラム教徒のスタッフ、ダバオのスラム出身のエーフロアさんが献身的に面倒を見ています。
彼女の話によると、情況はあまり良くありません。
前の病院では、治療は無理、死を待つしかないと宣告されたようですが、DMCの医師団は、その結論を出すのは尚早で、CTスキャンをしてから親と話し合う、と言う結論を出し、CTスキャン待ちです。DMCのスキャンがダウンしたとのことで、別の病院のスキャンでします。
エーフロアさんによると、本人は
「僕もう疲れたよ、早く高いたかーい所に行きたいよ」
「母さんも僕を抱っこし続けて疲れたでしょう、さすってあげるね、ぼくも疲れたから早く死にたい」
と言っているそうです。
ハウスオブジョイの烏山さんアイダ夫人とも相談して、民放テレビABS−CBN主催の子ども基金に治療の依頼をしたらどうか、関係者を知っているからと言う話をいただきました。多くのガンの子どもの救済をしていますが、今はレイテで起きた地滑りの事もあり、どれだけ受け付けてもらえるかです・・・
スキャンの結果によっては、あきらめてもらうことも視野に入れています。
追記:この子の治療は、民放テレビABS−CBN主催の子ども基金で報道され、手術費が集まり、7月現在でもまだ治療の試みが続いている。完治には、数年かかるものと思われるが元気である。
行政のシティープラニングで依頼された子どもの家を訪れる
たった今、行政から依頼された子の家を訪ねました。今回のプランは、いくつかのファンデーションが行政を中心に役割を分担して一人の子を救うプロジェクトへの参加を依頼されたもので、初めてのケースです。病院は私たちの重傷の患者をお願いしている、日本政府の支援で運営されている市立病院DMC(ダバオメディカルセンター)で、今回はミンダナオ子ども図書館には外の薬代をお願いしたいとの打診でした。外の薬は、おそらく一番お金がかかり、ファンデーションでは(製薬会社との利害があり)なかなか手が出せない部分だからだと思います。
そのこと自体は良いのですが、しかし、私たちの医療プロジェクトのポリシーとして、最初の状況から常に付き添いながら完治を見届けていくという方針に立つと、いったい完治にいたるまで、またその後のケアにいたるまで、誰が付き添い、どこが責任を持つかという点で今回の企画には不明な部分が多くあります。案の定、患者は一度あるファンデーションがダバオの病院に連れて行ってくれるというので車で行ったのですが、ただ連れていっただけでそこに放りっぱなしで非常に困った経験があり、患者も非常に不安そうでした。
今回は、最初の部分は、行政が2000ペソほど(ガソリン代と初診ぐらいでしょう)だしてDMC病院に連れて行くものの、煩雑な再度の検診やレントゲンや入院手続きを誰がこなすのか?誰がくり返しダバオに車を出し、患者には解りづらい手続きを手を取り足を取りしていくのか・・・また、入院中の付き添いの母親の食費などは誰が見るのかといった様々な部分が不明です。行政は、最初のきっかけだけを作って後は種々のファンデーションに任せるにしても、その連携や細かい部分での責任が明確になっていないので、患者の不安も考慮してミンダナオ子ども図書館ですべての行程をチェックして、一人のスタッフが完治まで付き添いながら進めていき、問題があればすぐに対応する事を約束しました。
(あるファンデーションでは、部分的に手術などを受け持ってもその後のケアが無く、山に読み聞かせに行ったときなど再度入院しなければならない患者を見ているので、全体を統括する責任を誰が持ち、どのように行動するかが問題になります。)
ミンダナオ子ども図書館では、今年度の純医療予算が、戦闘地ピキットの奇形の子の複雑な手術を多く取ったことと(長期の手術になります)今年は政府も注意報を出すほどのデング熱の流行で、山岳民族の子どもたちの入院が相次いだことで、予算が底をついています。しかしスタッフと協議した結果、この政府との協賛のプロジェクトは、一つの重要な過程としてGOサインを出すことに決めました。
子どもの写真を貼付しました。患者は1歳4ヶ月ですが、栄養不良と病気せいで極端にやせ細っています。

この子は残念ながら亡くなりました。
ドールの農地開発で追われた先住民のファミリーを受け入れ
ドールの大規模バナナ農園開発で、バゴボ族の一家が強制移住させられることが、その家族の娘さんが高校のスカラシップに応募してわかりました。
娘さんは現在高校2年ですが、強制移住によってへんぴな場所に移され、高校をストップしなければならないとのこと、ミンダナオ子ども図書館の住み込みのスカラーになれないかと打診してきました。現地を見に行きましたが、はるか彼方の山裾まで広大な敷地がドールの所有で、家の前も裸地となり、トラック用の道路が開発されていました。以前は多くの先住民が住んでいたが、今は彼らが最後の家族だそうです。
彼らの場合は、親戚の土地に移り、とりあえずドールの日雇いで働けます。月給、健康保険費引きで日本円で3000円ほど。10人の子どもを養っていかなければなりません。
しかし、それ以上に驚いたのは、その後ろに、ぼろぼろに破れたビニールシートの下で、一家三人住んでいたバゴボの家族。(写真)定職はなく、箒を作っては売ってかろうじて口糊としていました。服はぼろぼろ。本来ならば小学生の子どもも学校に行っていませんでした。
強制移住の勧告は出ていても、行くところがないとのこと。しかし、ここにいては農薬の散布で下手をすると生命が危ない。(同行したスタッフの一人のおじさんは、別の場所のドールの農薬散布で亡くなっています)それで、ミンダナオ子ども図書館の一区に竹の小屋を造ってあげてそこに住むことに決めました。昨日今日と、建材の竹とニッパを購入したので、月曜には建つと思います。今は私たちのところに住んでいます。子どもはスカラシップを出して学校に通うことが決まっています。
これにしてもこのお父さん、インドの賢者のような風格があり、作る箒は芸術品のようです。
先日は、子どもの頃から、父の代からどのように土地を(無知故にだまされたような形で)手放してきたかを語ってくれました。父は二束三文で広大な土地を寄付したり売り渡したりして、その後妻と住んでいた5ヘクタールは、税金が払えずに銀行の差し押さえになって、今の暮らしに入ったそうです。
ミンダナオ子ども図書館だより
アクマッド君の突然の結婚とミーティングの事
毎月一回の全体ミーティングがありました。先住民、イスラム教徒、プロテスタント各派、カトリックのスカラー達78名が一同に集まり、スタッフを含めて90名以上が図書館に集合しました。
朝から、図書館のスカラーとスタッフは、炊き出しで大忙しです。夜の食事は、その月の誕生日祝いもかねて、90名強の若者達の胃袋を満たさなければなりません。
(これは私の個人費用)。飼っている鶏5羽、畑の作物、買ってきた魚と牛肉(豚は料理しない)、そして50キロの大型米袋が夕食と朝食で見事になくなります。
とりわけ、下宿をしている若者達の食生活はひどく、炊いたご飯に醤油をたらして食うというありさま、醤油が買えないときは塩を水に溶かして唐辛子を入れて、それをご飯にかける・・・そんなわけで、月一回のミーティングは、彼らの栄養を補給する日。日本のスタッフが持ってきてくださった、ビタミン剤(アリナミン)も皆に配ります。
今回から、最初に発表会も始めました。今回は、マノボ族のアルベルト君が、マノボの文化、とりわけ結婚の儀式について発表。その後、一夫一妻か多妻かで、マノボの若者たちにも意見が分かれ、またイスラムの若者やキリスト教の若者達からも質問が出され、実に活発な交流がされました。
次回は、マノボの宗教観。当分マノボですが、次はイスラム教徒の考えなどを分かち合っていきます。
イスラム教徒のアクマッド君が来ないので、噂でどうしたのかと心配しましたが、今日やってきて、結婚した(させられた?)とか、聞いてみると、ピキットの市長の姪が彼を好きになりたまたま誘われて市場を歩いていたのを、ある人が見て、彼女の親兄弟から結婚しなければ100,000ペソを払うか土地をよこせと言われたようで、(しかたなく?)結婚式を挙げたとか・・・・びっくり!!!
イスラム教徒の習慣では、一緒に市場を歩いていても結婚しなければならないようです。
アクマッド君は、大柄でハンサムで気持ちも優しい、友達も多い、おそらく彼女と彼女の一家から将来性を見込まれて政略的(計略的)に持って行かれたようです。
彼の父親は、早すぎると言って、式場の外で泣いたとか・・・とにかく、今日来て、勉学は続ける気持ちがあることを語りました。
ミンダナオ子ども図書館は、女性を孕ませて逃げると、アウト(奨学金停止)ですが、結婚は認められています。
彼に、「妊娠させたの?」と聞くと、とんでもない!!!ただ一緒に並んで歩いただけ・・・
松居友
| |
|||
 |
 民話、絵本原稿、青少年から大人までの読みものを 自由購読で提供しています。 |
 何故ここに日本人などのテレビ映像 その他の貴重な活動映像を掲載 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|||
| スカラシップや訪問希望、 また種々のご質問やお問い合わせは 現地日本人スタッフ宮木梓(あずさ)へ ! mclmidanao@gmail.com |
登録していただければ、サイトの更新等の情報を メールで配信しています |
松居友メール mcltomo@gmail.com |
|