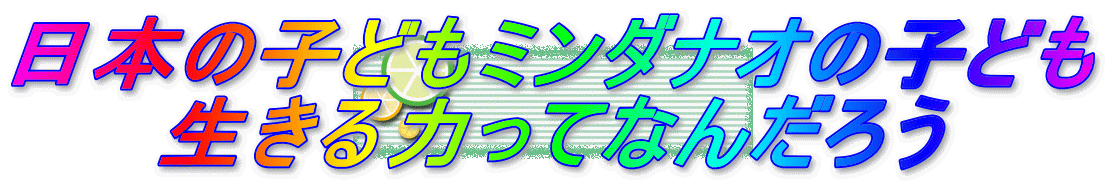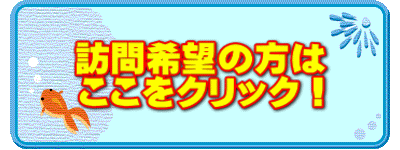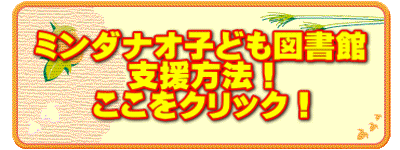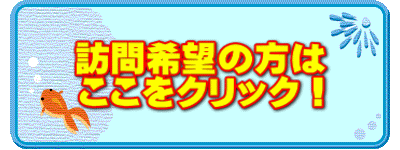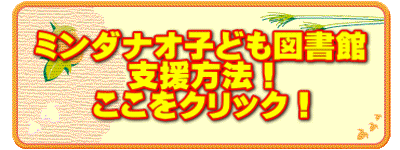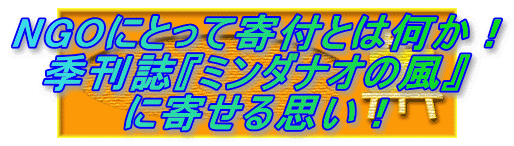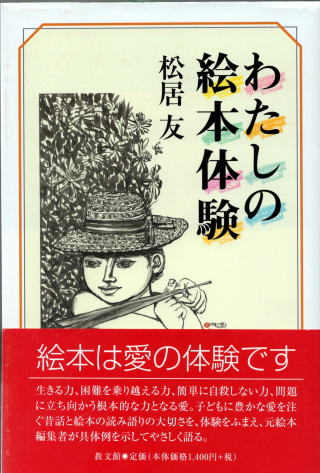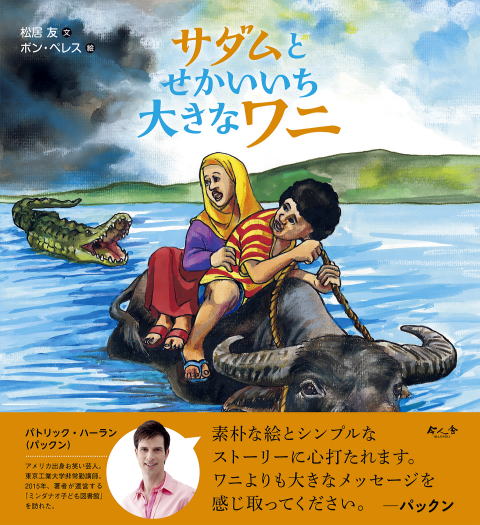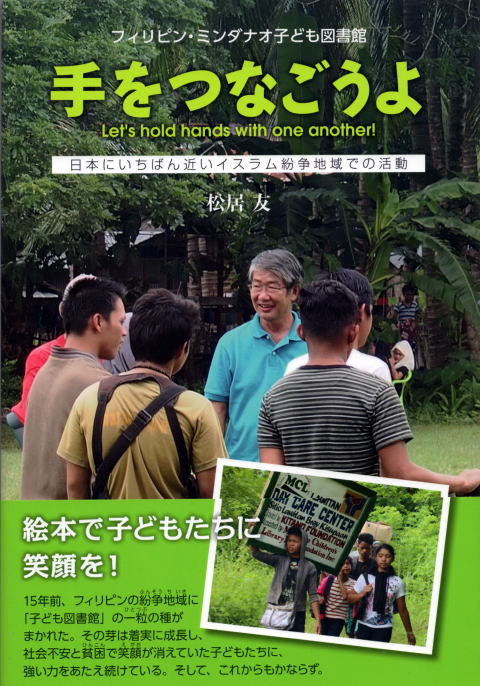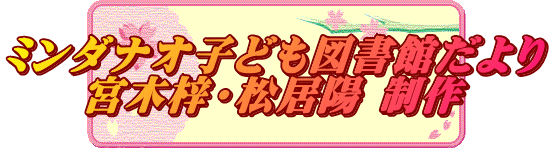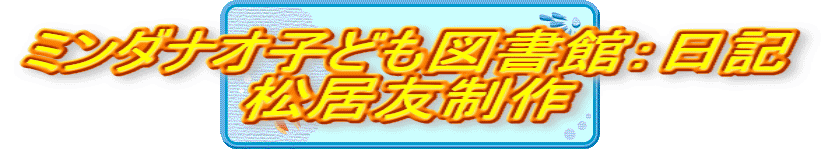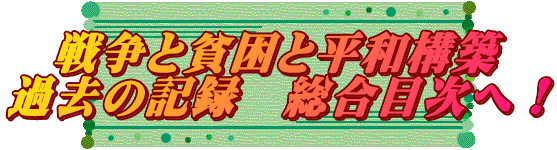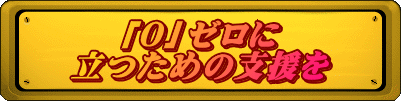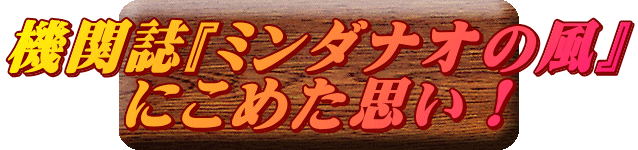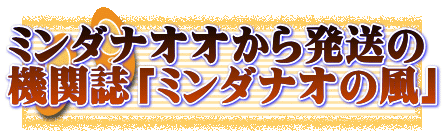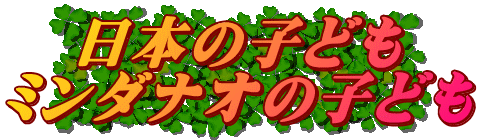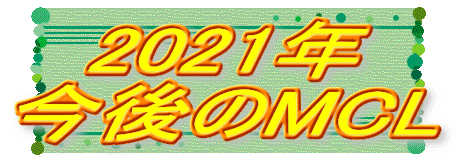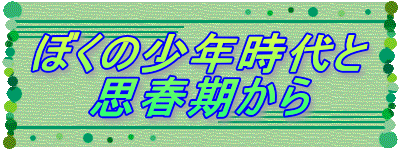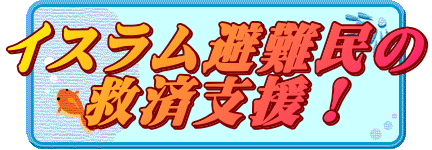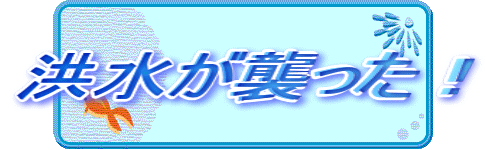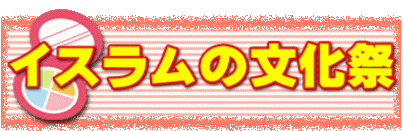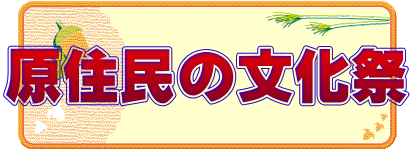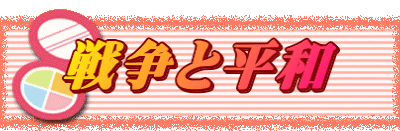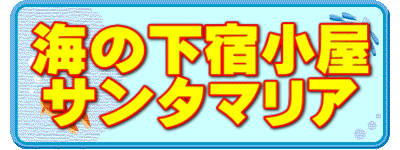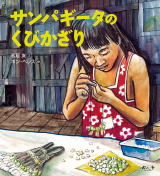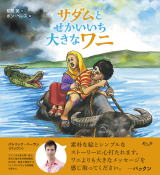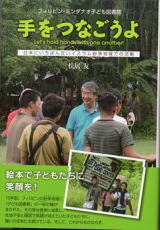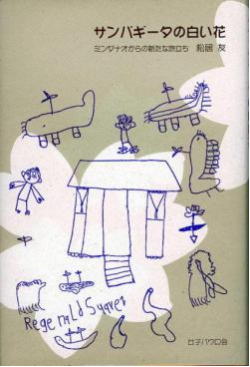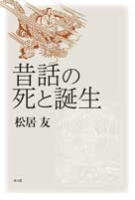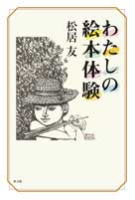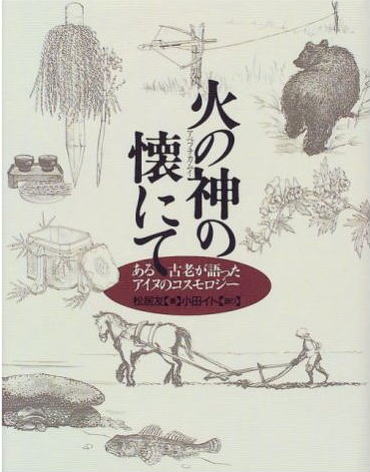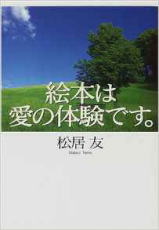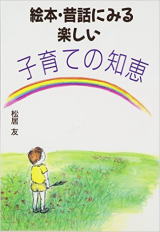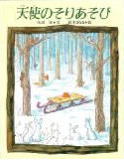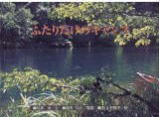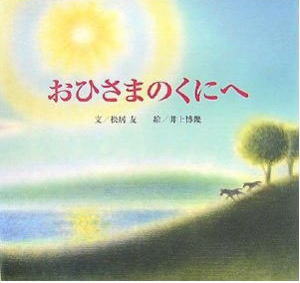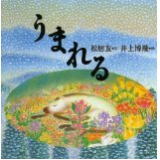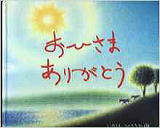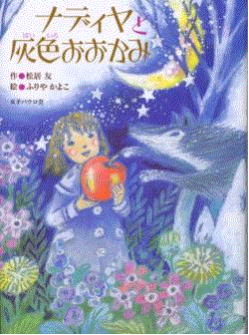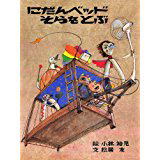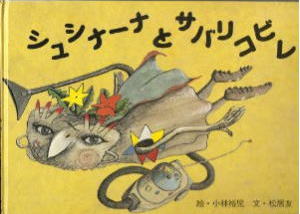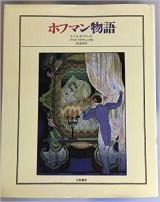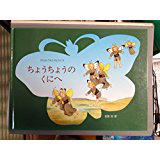先生になっている子です。
May God fill your life with a brighter smile and
more joy than ever.
Thank you for being the superman in our life.
You always made us feel special with your love and
care together with my dear siblings in MCL Family.
I want you to know that you are truly an inspiration,
a friend and a teacher to all of us.
I feel truly lucky to have such a loving, caring, and
encouraging father. Wishing you an entirely
peaceful day, full of pleasant and joyful moments!
Wishing to the Almighty for your better health and
great days in the future. May you always be happy
because you deserve it.
I wish nothing but absolute best for you as this is
what you truly deserve! Proud to call you PapaTOMO.
Thanks for making all the sacrifices silently and
working hard all day and night just to get us
a better life, you are one of the most important
persons in my life.
Thank you for always showering us with your kindness
and fatherly love. Thank you for making our life
beautiful with your existence.
You are truly one of a kind!
No exact words could measure how grateful i am to
Almighty God for giving you as our PapaTOMO
in our big Family.
Without you, I could never be the person
I am today.You are my true hero! You have always
inspired me and will always continue to do so.
May you witness the unlimited amount of joy in the
future years and expand through great possibilities.
You are an inspiration, you make days brighter
and night warmer.
HAPPY HAPPY BIRTHDAY PapaTOMO BestWishes in life
stay healthy and keep safe always po.. Please continue
to be someone's blessing not just mine and live a life
that honor and glorify God Godbless You and Family
************

Happy birthday Tomo san.
To the man who always stand as our second parents,
thank you is not enought but
Allah/God counts and witnessed for everything
you did to us.. Wishing you more years to come
and have a good health always..
************
 
日本公演の天才ギタリスト!
Belated Happy birthday tomo san.
stay strong. God bless you!
Walter Jhon Magbasa
************

Before this day would end, I would like to greet a
Happy Happy Birthday to our Papa, Tomo san!
Thank you very much for all the support and love you
gave to my family! God bless you always.
I pray for your good health and strength.
Take care always.
We love you and hope to see you soon.
Stay happy with your whole family!
This is the only photo I have with,
and i will treasure this. Thank you so much To...
彼女の亡くなったお母さんとの映像をご覧になれます。
 
************
 
Happy bday tomo sang more bdays to come stay
who you are and good heart ..salamat sa tanan nga
kaayu nmu sa mga scholars ...miss you 💓💓
|

日本の英会話スクールで教師になっているクインクイン
Happiest Birthday Tomo San
The man behind the success of many children
in Mindanao.
May the Lord bless you more and your family.
You are a great blessing especially to the people
in Mindanao. We will always be grateful to you.
Our prayers and love are always with you.
May you have an amazing year ahead.
Thank you for helping me and my family.
Whenever I am right now, I owe this success to you
and ate Aprilyn Getuya Dizon Matsui
Thank you so much!
************

Happy Happy birthday to the Loving Father of MCL
Happiest birthday tomo San,god Blessed you olwiez
Thank you sa support
************

Happy birthday papa tumo.. I hope nga daghan pang
katuigan nga moabot sa imoha... Og i hope pud nga
padayon japon ka tabang sa mga bata para maka
skwela.. Og onta naa ka sa maayong panglawas..
Stay strong lang mo ate aprilyn .... Padayon sa pag
alagad sa ginoo .... Onta naa ka sa maayong panglawas..
Padayon sa pag ka buotan papa tumo.. Salamat sa
tanan. Wala nako masoklii imong tabang ngari nako saona... ...
Pero.. Sige lang papa tumo.. Kaloy an.. Maka padayon
pako skwela puhon.....
Og salamat osabon nako..
"'"""" HAPPY BIRTHDAY PAPA TUMO""""""
GOD BLESS
************

Happy Birthday Tomo Matsui (Tomo San)
Di royd koopput dos konamin mgo nongo inguma
koungkay na kurso kun di pomon kikow
Sokkad kon sumbanan to langun, pomot moura ked no
Tribu Kos nongo PROFESSIONAL pomot I'd tavang du
konami no SCHOLARSHIP.
Nanoy ponayun ka nod boggayat Monama to Konokka
amoy moura Pon mgo anak no iling doy dongan I'd
ponganduy ra nod pokoipongga to kod-eskwela.
We're here tungod sa imong pagpaningkamot
Dakkon Solamat
************
  |