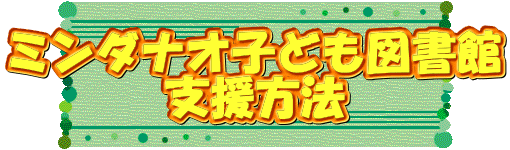山菜売りの少女の原稿
出版が決まり次第、場合によって削除します。
感想等をお寄せいただければ幸いです。
mcltomo@gmail.com
第一章
1,起なくっちゃ 2,山菜つみ 3,妖精たちの森 4,ばあちゃん 5,山の生活
第二章
1,三本角のカブトムシ 2、姉ちゃんの村 3,サリサリの犬 4,大きな岩
第三章
1,町で 2,市場で 3,ストリートチルドレン 4,シンカマス売りのお母さん 5,ボス
第四章
1,子ども図書館の子どもたち 2,あなたがジサね! 3,母さんとばあちゃんも 4,助けにゆくための準備
第五章、避難民救済
1,ボアイボアイ村をめざして 2,村についた 3,姉ちゃん 4,読み語り 5,ギンギンの昔語り
第六章、
最終章

1,起なくっちゃ 2,山菜つみ 3,妖精たちの森 4,ばあちゃん 5,山の生活
1,起なくっちゃ
コッケコッコー。
ニワトリがないた。
目をあけると、まだ外はまっくら。
ギンギンは、寝たまま手をよこにやると、布にふれた。布には母さんの、かすかな暖かみが、のこっている。
となりで寝ていた母さんは、もう外にでて、わたしたちが、山菜をつみに山にゆくための準備をしている。 ギンギンの家は、谷底に一軒だけたっている、一部屋しかない、そまつな竹のほったて小屋で、竹壁のすきまからは、谷の水音がきこえてくる。
「起なくっちゃ。
眠たいなあ、でも、起なくっちゃ。
山菜をつみにいく約束だもの。町に売りにいくために!」
妹たちは、まだ寝ている。
ギンギンは、起きあがると、ガラスもなにもない、あけっぱなしの窓から外を見た。
「わーっ、たくさんのお星さま!」
夜空には、巨人が無数の宝石をばらまいたように、星たちが輝いている。黒いかげになった、山なみの上に見えるのは、南十字星だ。
木々のあいだを、たくさんのホタルたちが、とんでいる。
「でも、夜明けは、もうすぐのはず。
あっちこっち飛びまわっていた、妖精さんたちも、ホタルさんたちといっしょに、花や岩のお家に帰るころかな。」
ギンギンは、足もとで、すやすやと寝息をたてている、妹たちの体を、つまさきでゆすった。
「クリスティン、ジョイジョイ、起なさい!
山菜つんで、町に売りにいかなくっちゃ。母さん、もう起きて、ごはんのしたくしているよ。」
するととつぜん、空から声が、きこえてきた。
「山菜売りのお仕事は、子どもたちだけでするの?」
ギンギンは、ちょっとビックリしたけれども、空にむかってこたえた。
「赤ちゃんのビビィは、まだ小さいから、いっしょにゆけないし。インダイ姉ちゃんは、のこって、ビビィのめんどうをみなくちゃならないの。
山菜をとりに、山にゆくのも、山菜を売りに、町にゆくのも、わたしと下の二人の妹の、三人だけでするお仕事なの。
山にゆくときは、よいけれど、帰りは、黒いタライに山菜をいっぱいつめて、頭にのせて、けもの道をおりてくるから、けっこうたいへん。泥の道は、すべりやすいし、タライは重いし。
でも、がんばらなくっちゃ、わたしたちが、町に山菜を売りにいかなければ、毎日のごはんは、たべられないから。」
「お父さんやお兄ちゃんは、いないの?」
「お父さんは、死んでしまった。
一番上の兄ちゃんは、町に仕事をさがしにいったきり、どこにいるのか、わからない。
一番上の姉ちゃんは、十四歳で結婚して、赤ちゃんもいるけれど、住んでいるアポイ集落は、ここからは何時間も歩いて、ボアイボアイ村についたあと、そこからさらに、急な山道を馬で登って、やっとたどりつける、マノボ族の貧しい村なの。
姉ちゃんのいるアポイ集落にはね、おじいちゃんやひいおじいちゃんが、日本人だったっていう人たちも、いるんだよ。
むかーし、大きな戦争がある前まで、ミンダナオ(註:ミンダナオは、フィリピンの南のルソン島につづく、北海道と四国をあわせたほどの、赤道にちかい南の島。)には、たくさんの日本人が住んでいて、アバカ(註:マニラ麻とよばれていて、当時はロープをつくる原料になった。)をうえていたんだって。戦争で日本軍が攻めてきたとき、ひどいことになって、その人たち、おくさんがマノボ族だったから、いっしょに山に逃げたんだって。
わたしのひいおじいちゃんも、そんな日本人のひとりだったんだよ。」
「お母さんは、いっしょにゆかないの?」
「母さんの仕事は、洗濯女。
だから村の家々をまわっては、『洗濯物ありませんかぁ。洗濯物ありませんかーーぁ。』って、たずねて歩くの。
たのまれた洗濯物は、川にもっていって洗って干すけど、もらうお金はわずかだし、仕事がないときもあるから、わたしたち子どもも、山菜売りをして手伝うのよ。」
「学校、いってないの?」と、まただれかが、たずねた。
「不思議だなあ。お空にだれかいるのかなあ?」
ギンギンは、ちょっと首をかしげて、夜空を見つめた。でも、星いがいは、何も見えない。
大きな木の枝に、妖精がすわって、こっちを見おろして、話しかけてくるような気もしたけれど、ギンギンは話をつづけた。
「わたし、学校、だいすきだったのよ。
一年生のときは、たのしかったわ。友だちもたくさんできたし、成績もよかったから進級できたの。クラスで一番、表彰もされたのよ!」
「すごいねぇ!」
「ありがとう。でも二年生になって落第した。ほんとうは、今三年生だけど、落第してからは、学校にいっていないの。」
スーッと、流れ星が落ちてくるように、声がまた落ちてきた。
「一年生のときは、成績がよかったのに、なぜ二年生になったら、落第したの?」
「出席日数が、たりなかったからよ。
一年生のときは、授業が、午前ちゅうだけだったから、朝はやくおきて、山菜をとりにいって、帰ったら、大いそぎで学校にかけていって、お昼前に家に帰ったら、町へ山菜売りにでかけられたの。
でも二年生になると、午後にも授業があって、欠席だらけ。」
「なぜ、午後の授業に、でなかったの?」
「山菜売りに、町までゆかなければ、ならないからよ。」
不思議な声は、少し怒ったようにいった。
「山菜売りなんかしてないで、学校にゆくべきだよ!」
「でも、山菜を売らないと、エンピツもノートも買えないし、お弁当をもってゆけないし・・・。」
「なぜ、お弁当をもってゆけないの?」
「わたしたち子どもが、山菜を売らないと、お米も買えないからよ。
姉ちゃんのインダイは、もう学校にいくのをあきらめている。母さんが洗濯にいったら、姉ちゃんが子守りをしなきゃならないし、ごはんの用意も、しなくちゃならないから。
でも、わたしと妹のクリスティンとジョイジョイは、とっても学校にいきたいの。」
「なぜ、学校にいきたいの?」
「大きくなって、少しでもよい仕事について、母さんや姉ちゃんや、妹たちを助けたいからよ。
あーあ。父さんが生きていればなあ。」
「姉ちゃん、だれと、お話ししているの?」
ふと、よこを見ると、クリスティンとジョイジョイが起て、いっしょに窓から外を見ている。
「妖精さんいるかな?」
小さなジョイジョイが、目をまんまるに見ひらいて、窓から夜の闇を見ながらいった。
「ぜったい、いるよ!」と、クリスティンが、こたえていった。
「会ってみたいなあ。」
「会えるって、兄ちゃんいってたよ。
森のなかで寝たときに、夜目がさめたら、おーーーきな、おーーーーーきな、巨人がたっていたって。月にとどくほど、大きかったって。」
「カプゴだ、それ!」ギンギンがこたえた。
「姉ちゃん、しってるの?」
「ばあちゃんが、お話してくれただけ。見たことないなあ。」
「何ぶつぶつ話しているの!」
外の窓の下から、母さんの声がした。
「ごはんできたよ、はやくおいで。食べたら、山菜つみにいくんでしょ。わたしは、町に洗濯しにいくからね。」
「はーい!」
2,山菜つみ
ギンギンは、妹のクリスティンとジョイジョイをさそって、山菜つみにでかけた。
夜空には、まだ、いちめんにお星さま。
沢ぞいのけもの道は、流れをわたったりしながら、上流へとつづいている。人がとおる道というよりも、イノシシさんたちのとおり道、といった感じ。
「流れをわたるときは、そのまま川に、ジャブジャブ入っていくのよ。靴なんて、はいてないもん。はだしだもん。」
するとまた、かすかな声がした。
「はだしじゃ、とがった石ころや、落ちている小枝が刺さって、痛いでしょ?」
ギンギンは、森のなかを見まわしたけれども、そよ風が、木の葉っぱをゆする音しか、きこえない。
「はだしだと、足のうらが、少し痛いときもあるけど、でも小さいときから、いつもはだしだったから、なれちゃった。」
「足の皮が厚くなって、靴になったのね。」
「そう、でもはだしのほうが、よいときもあるよ。ぬれた急斜面を、登ったりおりたりするとき。ツルツルでしょ。靴やゾウリじゃ、すべってとても歩けない。」
ギンギンは、かた手で、頭の上の黒いタライをささえると、小さなジョイジョイの手をひいて、沢ぞいのけもの道を登っていった。
元気でお茶目なクリスティンは、先頭にたっていく。
やがて、ふみあとが消えて、草のはえた沢の斜面を登りきると、とつぜん平らな、バナナプランテーション農場のなかに飛びだした。
プランテーションというのは、外国の会社と契約して、バナナをうえている大農場のこと。とってもとっても広くって、町から、はるか山のふもとまで、ずーーっと広がっている。
「あのバナナ、まいてある日よけの新聞、外国語で書かれているよ!何語かなあ?」と、ジョイジョイがさけんだ。「売っている国から、もち帰った、古新聞だね。」
ギンギンが説明すると、不思議な声が、少し怒ったようにいった。
「昔は、ここらへんにはね、マノボ族しか住んでいなかったのよ。でもね、外からきた人たちが、土地をどんどん買いしめて、もともと住んでいた人が、じゃまだからって、おいだしたあとに、バナナ農園をひらいていったの。」
ギンギンは、ちょっとびっくりして、声をだした。
「あなた、いったいだれなの。ずいぶんいろいろ、しっているのね。」
声は、悲しそうにいった。
「昔から住んでいた先住民たちは、住んでいた場所からおいだされて、山にうつり住んで、あげくのはてには、前よりももっとひどい、貧しさになってしまった。
あなたのお父さんも、殺されて、あなたたちも、住んでいた土地から、おいだされたのよね。」
「・・・・・・・。」
夜明け前の、闇のなかのバナナプランテーションは、ぶきみだ。一れつにバナナが、植わっているだけで、下草もはえていない。
少しずつ、あたりが、明るくなってきた。
ギンギンたちは、プランテーションを通りぬけると、ふたたび沢ぞいの、けもの道に入っていった。けもの道のまわりには、いろいろな花や、食べられるすっぱい草の実も、はえている。
クリスティンは、赤い草の実をおると、皮をむいてかじった。赤い実は、すっぱい。でも、ちょっぴりあまい。ギンギンとジョイジョイも、かじった。
ときどき川をわたったり、泥沼をよこぎったりしながら登っていくと、小さな滝が、いくだんにも重なりながら落ちている、峡谷にゆきあたった。
さらに、そこを登りつめると、とつぜん目の前がひらけて、池のほとりに飛びだした。
三人の子どもたちは、頭にのせていたタライをおろすと、ホッと息をついた。
対岸には、背の高いラワンの大木が一本、夜明け前の東の空にむかって、うかびあがってたっていた。
「あの木、まるで、天までとどきそう!」
さらに、はるか上流を見あげると、ジャングルでおおわれた斜面に、白いすじが見えた。
「あれ、なあに?」
まだ、ここにきたことのないジョイジョイが、指をさしていった。
「大きな滝よ。」ギンギンが、こたえた。
池の後ろには、ふかいジャングルが広がっていて、高い木々がそびえたち、シダ草がはえている。シダ草は、草というよりも、背が高くてまるで木のよう。
「ホタルさんは、お家に帰ったみたい。」クリスティンがいった。
夜明け前のうす明かりのなかで、セミたちの鳴き声がしはじめた。
「もうすぐ、お日さまのぼるね。」と、ジョイジョイがいうと、クリスティンがこたえた。
「マノボ族の、昔からのいいつたえだとね。ここには、たくさんの妖精さんが、住んでいるんだって。」
「そうそう、ばあちゃんいっていたよ。ときどき、あの大きな木の下に、白い女がたっているって・・・。」
「馬鹿なこといっていないで、はやく山菜をつみなさい!そんな話は、ここではしないの!」
ギンギンが、顔をまっ赤にしていった。
「どうして?」と、ジョイジョイが、たずねると、ギンギンがこたえた。
「どうしてって、あっちの人たちにきかれたら、どうするの!」
「あっちの人って?」
「もう、あんたたちもマノボ族でしょ。だったらわかるでしょ。ほら、あれよ。」
そして、ギンギンは、ふたりの耳もとでささやいた。
「妖精!」
「ここはね、天のさらに上と、地のさらに下の世界につうじている道がある、とくべつな場所なの。
ほら、あそこに見える、背の高いラワンの木、あれはねえ、ただの木じゃなくって、妖精さんたちが天にのぼっていく、道なのよ。
それからこの池。ずーーっとずっと、ふかく地の底までつづいていてね、うらがわの世界にある、池の底にでるの。
そんなとくべつな場所だから、ここには妖精さんたちが、たくさん住んでいるの。妖精さんたちだけじゃなくて、いろんな、妖怪やお化けもね。
そんなわけでね、この場所にきたら、じゃましないように、しずかにしなければいけないの。
とくにしてはいけないのは、『妖精』という名前を、大きな声でいったり、話したりすることよ。自分たちの事が話されているとおもうと、ふりむいて、よってくるからね。」 ジョイジョイは、びっくりして、滝を見あげている。
「『きれいだな!』とか、『すてきな場所だなあ!』とか、いってもだめよ。
『わたしのことを、きれいだな!っていってくれた。こっちの世界においで…。』と、いって、あっちの世界に、ひっぱられていったら、もどってこれないよ。
山菜をつませていただいたら、すぐに帰るの。」
あたりは、うっすらと、あけはじめてきた。
「わたし、池のなかのカンコンをつむね。だからクリスティンは、タクワイをつんで。ジョイジョイは、パコパコよ。」 子どもたちは、池のほとりにちらばると、山菜をつみはじめた。
3,妖精たちの森
ギンギンは、素足のまま池のなかに、入っていった。
池の底は、泥でぬるっとしていて、たくさんのカンコンがはえている。緑色した長めの葉っぱのカンコンは、つむとプチンと、小さな小さな音がする。
「カンコンさんのなかにも、妖精さんたちが、住んでいるかなあ。
この池には、いろいろな妖精さんが、いっぱい住んでいて、昼間でも水の上で、踊ったりあそんだりしてるって、ばあちゃんいってたけど。いっしょに踊ったら、たのしいかなあ。でも、帰ってこれなかったら、どうしよう。」
ギンギンは、そういうと、ためしに、ぬるぬるの泥の上を、妖精になったつもりで、すべってみた。
タクワイをつんでいる、クリスティンは、水べに立つと、小さな目をいっぱいに見ひらいて、池を見わたした。
クリスティンも、妖精のことばかり、考えていた。
「たしかに、妖精さんたちいるみたい。夜になると、あの大きな木のまわりを、ぐるぐるめぐって、お星さまのところまで、のぼっていくのね。
お星さまや天使たちと、お空であそんで、おひさまがのぼるころ、池のお家に帰ってくるんだ。
妖精さん、そこにいる?」と、クリスティンは、小さな目で、大きな木を見あげていった。
ジョイジョイは、パコパコをつみながら、つぶやいた。「パコパコの妖精さん、葉っぱのさきにぶらさがって、ブランコしながら、あそんでいるかな。わたしも、葉っぱのさきで、ブランコしてみたい。」
ジョイジョイは、パコパコの茎をつかむと、葉っぱのさきをゆらした。
子どもたちは、妖精たちのことを、いろいろ想像しながら、山菜をつみはじめた。つんだ山菜は、手にいっぱいになるたびに、岸べにならべた黒いタライに、つめていく。
あたりは、しだいに明るくなり、とつぜん太陽の光が、東のほうからこぼれだし、山の高みを赤くてらしだした。
蝉たちの声にまじって、小鳥たちがさえずりだした。 夜明けの光は、しだいに山をくだりはじめ、滝がオレンジ色に輝きだし、朝日が、池のほとりの背の高いラワンの木のこずえにとどいた。
そのとき、ギンギンの目の前を、カエルが、スーッとよこぎった。
「あっ、カエル!」
ギンギンは、おもわず手にしていたカンコンをほうりだすと、しぶきをあげて、カエルのあとをおった。
カエルは、カンコンのしげみに入り、頭だけだして、こちらを見ている。
ギンギンは、ソーッと近づくと、カエルが逃げようと、向こうをむいたとたん、飛びかかった!
「つかまえたよー、カエル!はやくはやく!」
不意をうたれたカエルは、ギンギンの手のなかでもがいている。
ギンギンは、カエルを、水のなかからひきだすと、朝日のなかにさしあげた。
ギンギンのさけび声をきいて、クリスティンは、腰にさげていた小さな竹カゴをはずし、水しぶきをあげながら、池に入っていった。
「姉ちゃん、これにカエルいれて!」
姉ちゃんは、クリスティンの少し前を指さすと、さけんだ。
「クリスティン。そこにもいるよ。つかまえて!」
クリスティンは、そくざにカゴを、カンコンの上におくと、姉ちゃんの指さすところにいるカエルに、襲いかかった。
「やったー、つかまえたよ!」
朝日のなかで、クリスティンは、うれしそうにカエルを高くかかげた。
「やったねー。二匹とれたね。」
二人は、カエルをカゴにいれると、フタをした。
「これで、おかずができたね。」
「ごちそう見つかって、よかったね。カサバイモだけじゃ、さびしいもんね。」
岸のほうを見ると、ジョイジョイも大喜びをしている。
そのあとも、六匹ほどカエルがとれた。
「さあ、もうたくさんとったから、帰ろう。」
子どもたちは、たくさんのカンコンとタクワイとパコパコがつまっている、黒いタライのおいてある、岸べに集まった。
まず、小がらなジョイジョイが、腰にさげてあったタオルをたたんで、頭にのせ、ギンギンとクリスティンが、パコパコがいっぱいつまったタライをもちあげると、ジョイジョイの頭にのせてあげた。
つぎにギンギンとクリスティンが、カンコンとタクワイのつまったタライを、頭にのせた。
子どもたちが、タライを頭にのせたとき、池ぜんたいに、朝の光が流れこんできた。
光は、まるで妖精たちが、水しぶきをあげてはねているみたいに、ぐるぐる踊りながらうずをまいて、カンコンやタクワイやパコパコの上を、走りまわった。
「わー、光がうずをまいている!」ギンギンがさけんだ。
「しぶきをあげてる、きれいだね!」と、クリスティンもさけんだ。
「妖精さんたちが、踊っているよ!」
大きな目をくりくりさせながら、ジョイジョイが、『妖精』という言葉を口にしたとたん、光のうずは、三つにわかれ、子どもたちが頭にのせている、タライの上にドッと降りそそぎ、光のしぶきをまきちらした。
「あーっ!」子どもたちがさけんだ。つぎのしゅんかん、ジョイジョイが、びっくりしてクリスティンを見あげていった。
「なにか、タライの上にのったみたい!」
「・・・・・・・・・。」
「さあ、お家へ帰ろう。」
ギンギンの言葉にわれにかえると、三人は、池からぬけだし、川ぞいに歩きはじめた。
「でも、だれかタライの上に、のってるような気がする。」こんどは、クリスティンがつぶやいた。
でも、だれも何もこたえなかった。
4,ばあちゃん
家が近づいてくると、外で弟のビビィをおんぶして、子守りをしていたインダイ姉ちゃんが、笑顔でむかえてくれた。よこの岩には、ばあちゃんが、杖にあごをのせてすわっている。
「おかえりなちゃい。」ビビィが手をふっている。
「ただいま。」
「たくさん、山菜とってきたよ。」
「カエルも、とれたよ。」
子どもたちは、頭から、山菜がいっぱいつまっている、重いタライをおろした。
「まあまあ、カエルもとれたのね。これでおかずが、できるわね。」
母さんは、カエルのはいったカゴをうけとると、たきぎに火をつけて、昼ごはんの用意をはじめた。
岩にすわっていたばあちゃんは、帰ってきた子どもたちを、笑顔でむかえるといった。
「あれまあ、三人のお客さまもいっしょにつれて、帰ってきたんだねえ。」
ジョイジョイは、目をまんまるにすると、クリスティンにいった。
「ばあちゃん、また不思議なことをいってるよ。」
ばあちゃんは、タライをじっと、見つめるといった。
「青と赤と黄色の服に、きれいな刺繍を縫いこんで着ていらっしゃる。それに、頭にまいた刺繍の帽子に、ビーズの胸飾りまでつけて、着飾って。
あんたたち、これからだれかに、会いにでもゆくのかね?」
ギンギンは、ばあちゃんにちかよると、不思議そうにたずねた。
「ばあちゃん、だれと話しているの?」
「あんたらには、見えないのかい。
ほら、赤い服着ているのが、カンコンさんで、青い服がタクワイさん。パコパコさんは黄色い服だね。三人の妖精さんたちが、タライの上に、すわっていらっしゃるだろうに。」
ばあちゃんには、何かが見えているようだけど、わたしたちには、何も見えないし、きこえない。
ばあちゃんは、首をたてにふって、うなずきながらいった。
「マオンガゴン酋長に、おねがいがあるんだって。
そうかい、そうかい。
酋長さんは元気かね。会ったら、わたしからもよろしくって、つたえておくれ。もうじき、そっちにゆく日も近いだろうって。
そうかい、そうかい。」
どうやら、ばあちゃんの話している様子を見ていると、ギンギンが頭にのせてきたタライの上には、カンコンの妖精さんが、クリスティンのタライには、タクワイの妖精さんが、ジョイジョイのタライには、パコパコの妖精さんが、マノボ族そっくりのかっこうで、きれいな刺繍の入った赤と青と黄色の服を着て、すわっているらしい。頭には、刺繍の入った帽子をかぶり、胸にはビーズの首飾りをつけて。
「カエルの煮こみ、できたわよ。冷めないうちに、食べましょう!」
母さんの声がきこえた。
「ばあちゃん、おいでよ。カエル食べよう。」
ギンギンがさそっても、ばあちゃんは、タライのほうを見ては、ぶつぶつ何かをつぶやいている。
「おいでよ、ねえちゃん。」ジョイジョイがいった。
「ばあちゃん、妖精さんたちとのお話にむちゅうなのよ。あとで、食べるとおもうよ。わたしたち、さきに食べなくっちゃ。町に山菜を、売りにいくんだから。」
5,山の生活
カエルの煮物と、ふかしたカサバイモをたべおわると、ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、山菜のいっぱいつまった黒いタライへと、かけていった。
ばあちゃんは、小さな岩に腰かけて、いつのまにか、すやすやと眠っていた。くんだ両手を杖において、その上にアゴをのせたまま。
子どもたちは、ばあちゃんをおこさないように、タライを頭にのせると、そっと谷間の家をあとにした。
ふみあとを少しくだって、川までおりたら、対岸にわたる。
お姉さんのギンギンが、さきにたち、妹のクリスティンとジョイジョイが、あとにつづいた。
水のなかから頭をだしている、石の上を、注意ぶかく、すべらないようにわたって、三人は、斜面にできた、ジグザグ道をのぼっていった。
ギンギンは、ときどきふりかえっては、一番後ろの小さなジョイジョイが、ついてくるかどうかを、たしかめながら歩いた。パコパコは、山菜のなかでは軽いけれども、小さなジョイジョイには、けっこう重い。
「すべらないように、気をつけてね。」
ギンギンが、後ろにむかってさけんだ。
ほんとだったらジョイジョイは、今年から一年生になるはず。でも去年、保育所に入れなかったから、小学校にはあがれない。
「かわいそうな、ジョイジョイ。」
そうおもったとたん、また声がきこえた。
「なんで、保育所にゆかないと、小学校に入れないの?」
ギンギンは、声がするのに、なれてきた。
「わたしにも、ほんとうのことは、わからないの。
小学校にゆく子は、せめてABCが書けないと、先生が困るからって、きいたわ。新しい規則だって。」
「でも、山おくの貧しい村だったら、保育所なんか、ないでしょう。どうするの?」
「木の下で、勉強するんだって。
姉ちゃんが嫁いだ、アポイ集落なんか、貧しくて保育所も建てられないし、先生もいないんだって。」
「なぜ?」
「せめて高校を卒業しないと、先生になれないからよ。
姉ちゃんの村は貧しくて、エンピツも買えなかったり、お弁当も、もってゆけなかったりする子が、ほとんどなの。ときには五日も、ごはんが食べられなかったりするのよ。」
「五日も食べなかったら、お腹ペコペコになるでしょう!」
「ペコペコをこえて、とっても痛くなってくるのよ。
小学校までゆけば、幼稚園もあるんだけれど、山道を八キロも歩かなければならないの。小学生たちでも、朝四時半には、家をでなくちゃならないのよ!」
「幼稚園の子どもたちじゃ、とってもむりね。」
「雨が降ると、川があふれて、わたれなくなって、家まで帰れないこともあるのよ。ながされて、死んだ子もいるって。」
「小学校を卒業するだけでも、命がけね。」
「卒業できればまだいいけど、一年生に一〇人入ったら、二年生までに、七人はやめていくんだって。ほとんどが、貧しいマノボ族の子どもたち。」
「どうして?」
「二年生になると、午後の授業があるからよ。」
「なぜ、午後の授業にでられないの?」
「お米も買えないし、お弁当もってゆけないの。
とくに男の子たちは、小学校のころから、父さんといっしょに山にいって、お仕事をてつだうでしょ。下の弟たちも、森や野原に、食べ物をさがしにゆかなくちゃ、ならないのよ。」
「何を、見つけてくるの?」
「森や野原にはえている、山芋や野生のバナナ。沢だったら、カエルやカニ。トカゲも食べるわ。
年上の男の子だったら、狩りにでかけて、猿やイノシシをとったり、ニシキヘビをつかまえることもあるのよ。これはめったにない、大ごちそう。ニシキヘビは、蒲焼きにすると、とってもおいしいよ。
女の子も、働くのよ。
姉ちゃんは、家にのこって、赤ちゃんをおんぶして、小さい子のめんどうを見るでしょ。妹たちは、洗濯と水くみ。谷底まで一時間もかけて、洗濯物をかついでいって、川で洗ってから干すの。
洗濯が終わったら水浴び、これはとってもたのしい。帰りには、干しあがった洗濯物といっしょに、谷の水を大きなボトルにいれて、急な斜面を登って帰るの。」
「なんのためのお水?」
「飲み水や、お皿を洗ったりするためのお水。
男の子たちは、森に落ちている木の枝をひろいあつめて、肩にかついで帰ってくるの。」
「何で、木の枝を、ひろったりするの?」
「ごはんをたくための、たきぎにするのよ。
夕方に、父さんや母さんたちが、帰ってくるから、山芋やバナナをふかしておくの。」
「お米のごはんは、食べないの?」
「お米って、買わなくっちゃならないでしょ。だからめったにしか、食べられないの。
父さんたちが、山の斜面でそだてている、トウモロコシの収穫があったり、兄ちゃんが、下の村の田んぼの草刈りなど、日雇い仕事で働いたりして、お金が入ったときとか。母さんが、洗濯女をしたり、子どもたちが、山菜売りに町にゆけば、お金が入ってお米がかえるわ。」
「そうだよね。お米って、買わなければならないもんね。」「だから、ふだんは、家のまわりに植えてある山芋や、野生のバナナを、蒸かしてたべるの。
父さんや母さんや兄ちゃんは、お仕事で疲れているし、おかずのカエルを料理したり、おイモやバナナをむしたりするのは、女の子たちの役わりなの。」
「そんなにたくさん、お仕事があったら、学校どころじゃないよね。」
「二年生になって、午後の授業がでてくると、学校をやめてしまう理由よ。」
「夜、勉強したらいいのに。」
「電気がないから、夜はまっくら。光っているのはホタルさんだけ。小学校を卒業して、高校生になるだけでも夢のまた夢。」
「そんなわけだから、保育所の先生になれる人も、いないんだ。」
「わたしは、小学校の二年生までいったけど、三年生には、なれなかった。父さんが死んでいないし、町に山菜を売りに、いかなくっちゃいけないから。だけど、ジョイジョイは、一年生にもなれない。」
「かわいそうな、ジョイジョイ。」
ギンギンが、後ろを歩いている、ジョイジョイのほうをふりむくと、ジョイジョイの頭の上にのっているタライのパコパコが、チカッと光って、光のしずくが、キラキラポロリと地面に落ちた。
三人は、森からでると、ゴムの木の林のなかにつづいている、小道をぬけていった。お日さまは空高くのぼり、あわい緑のゴムの木の葉かげからは、木もれ日が落ちてくる。














第二章
1,三本角のカブトムシ 2、姉ちゃんの村 3,サリサリの犬 4,大きな岩
1,三本角のカブトムシ
ギンギンが、後ろをふりかえると、ジョイジョイが、おくれぎみについてくるのが見えた。さすがに、少し疲れた顔だ。
「休もう。」
ギンギンはいうと、木かげに入り、山菜のつまったタライを、地面において、大木の根もとにすわった。
「姉ちゃん、どうしているかなあ。」
ギンギンは、十四歳で結婚して、山のおくに住んでいる、姉ちゃんのことをおもいだしていた。
「結婚してから、いちども会ってないね。」
クリスティンがいった。
「姉ちゃん、赤ちゃんが生まれたって、母ちゃん、いってたよ。お産のときにいったもんね。男の子だったって。」
ジョイジョイがいった。
そのとき、ブルルルルルルルル、ブルルルルルルルルルと、大木の上のほうから、ヘリコプターがおりてくるような、音がした。あんまり大きな音なので、ビックリして見あげると、大きなカブトムシがとんでいる。
「大きなバコカン!」
(バコカンというのは、カブトムシのこと。ミンダナオのカブトムシは「ヘラクレスオオカブト」とよばれていて、とても大きくて角が三本ある。)
大人の手のひらほどもある、大きなカブトムシは、ヘリコプターのように、三人の子どもたちの頭上をまわると、ドサッと音をたてて目の前におり立った。
カブトムシは、ビックリしている子どもたちの前に、着陸すると、三本の長い角を、ニョキッと前につきだして、黒くキラキラ光る目で、子どもたちを、じーーっと見つめた。
「キャッ!」ジョイジョイが、悲鳴をあげた。
「見たこともないほど、大きな大きなカブトムシ!」
カブトムシは、ギュッギュッと、きみょうな鳴き声をたて、三本の角を動かしながら、子どもたちのほうへと歩きはじめた。
ジョイジョイは、ビックリして、クリスティン姉ちゃんの腕にしがみついた。クリスティンは、となりのギンギン姉ちゃんの、手をにぎった。
そのとき、三人の頭上で、ゴーーーッ、ゴーーーッという、ものすごい音がしはじめた。
見あげると、大木の枝葉が、大風がふいているかのように、大ゆれにゆれている。つぎのしゅんかん、予期していなかったことがおこった。
目の前のカブトムシが、飛びあがったとおもったら、ギンギンとクリスティンとジョイジョイの体が、カブトムシのあとをおうように、スゥーとうきあがった。
すると、三人の体は、ものすごい勢いでこずえのあいだをすりぬけて、上へ上へとのぼりはじめたのだ。
まわりで、木の葉や小枝が音をたてて、はげしくゆれた。
木の枝にいた、たくさんの猿たちが、悲鳴をあげながら、となりの木へと逃げていく。
ギンギンとクリスティンとジョイジョイの勢いは、どんどんまして、三人の子どもたちは、おたがいに手をにぎったまんま、とつぜん、大木のこずえのてっぺんから、空のなかへと飛びだした。
あっというまに、森が下のほうへと、遠ざかっていく。
左に谷間が見え、いっしゅん、ギンギンたちの家も見えた。足もとに、緑のジャングルが、どんどん広がっていく。
ギンギンたちは、手をとりあったまま、まるで、カブトムシにひっぱられるかのように、ジャングルの上を、谷ぞいに上流へと飛びつづけ、今朝、山菜をとってきた池に飛びだした。
池のほとりには、大きなラワンの木が見える。
「手をふっているよ!」ジョイジョイがさけんだ。
見おろすと、青や赤や黄色の服を着た、妖精たちが、池や湿地や木々のかげから飛びだして、しきりに手をふっているのが見えた。
2、姉ちゃんの村
目の前に、真っ白な滝が見えた、とおもったら、つぎのしゅんかん、三人は、広いひろい青空のなかに、高く高くまいあがった。
前方に、大きな高い山が見えた。
「わー、アポ山だ!」ギンギンがさけんだ。
ばあちゃんの言葉が、うかんできた。
「アポ山は、世界で一番高い山。昔っから妖精たちの住んでいる、神聖な山なのさ。
死んだ人たちの魂は、みんな、アポ山に集まってくるんだよ。そして、そこから天国にのぼっていくんだよ。人だけじゃなくて、動物たちも、木や草花も、岩や水にいる妖精さんたちも、みなこの山に集まってくるんだ。」
(アポ山は火山で、山頂には小さな噴火口もある。フィリピンの最高峰で2954メートル。)
「すっごいね!」
「わあっ、遠くに、海も見えるよ!」
「海見たの、はじめてだね。大きくてきれいだな。」
ビックリしているのもつかのま、カブトムシは、とつぜんすごい早さで、急降下しはじめた。
それに、引っぱられるかのように、空高くまいあがった子どもたちも、ジャングルにむかって、急降下していく。
緑の森が、どんどん近づいてくる。
すると、森のなかに、少しひらけた場所が見えはじめた。「村だ!」ジョイジョイがさけんだ。
村のまんなかには、小さな広場があり、草ぶきの竹でできた、貧しい家々が、まわりをかこんでいる。
「村のようす、何だかへんだよ。」と、クリスティンがいった。
大ぜいの人たちが、家のなかから走りでてきたり、広場で大声でさけんだり、家のなかに、飛びこんだりしている。「何だか、あわてているみたい!」
ギンギンたちの下降するスピードは、しだいにおそくなり、集落の左はじにたっている、草ぶきの家の前に、大きなカブトムシといっしょに、ふわっとおりたった。
目の前のベンチに、赤ちゃんをだっこした、若い女の人がすわっている。
「あっ、姉ちゃん!」
クリスティンは、おどろいてさけんだ。
「姉ちゃーん!」
ギンギンとジョイジョイも、さけんだ。
ところが、姉ちゃんは、ちょっと不思議な顔をしただけで、何も気がつかないようすだ。
いたたまれなくなって、三人の子たちは、目の前にいる姉ちゃんに飛びついた。
すると、不思議なことがおこった。
飛びついたとたん、姉ちゃんの体をするりとぬけて、竹壁もぬけて、家のなかに飛びこんだのだ。
びっくりしたけれども、子どもたちは、あいている家の戸口から外にでると、姉ちゃんの前にたって、赤ちゃんをだいている、姉ちゃんに話かけた。
「姉ちゃん、元気?」
「わたしたちよ、ギンギンとクリスティンとジョイジョイ!」
大きな声でいっても、姉ちゃんには、きこえたようすが少しもない。なぜか緊張した顔をして、広場をゆき来している人たちのほうを、見つめている。
すると広場から、一人の男がかけてきた。ご主人だ。
姉ちゃんは、立ちあがって、夫を迎えるといった。
「どうだった?」
「たいへんだ。兵隊たちがやってくる。ここも、戦闘になるぞ!」
遠くの山おくの森で、パンパンパンという銃声がきこえた。
広場のほうから、キャーッという悲鳴がした。
「どこに、逃げるの?」
姉ちゃんは、泣きだしそうな顔でいった。
「ボアイボアイ村へ、いこう。」
「姉ちゃん!」ギンギンは、おどろいてさけんだ。
姉ちゃんは、ふっとまわりを見て、不思議そうな顔をすると、夫にいった。
「何だか、妹たちがいるような、気がするの。」
「馬鹿なこといっていないで、はやく、避難するんだ。」
そのとき、カブトムシが飛びあがった。
ゴーーーッという音がして、風がふきぬけた、とおもったら、ギンギンたちは、自分たちが、山菜売りにゆくとちゅうで休憩した、森のなかの大きな木の下に、すわっているのに気がついた。
目の前にいる、三本角の大きなカブトムシは、急に羽をひろげると、ブルルルルルルと音をたてて、木の高みをめざして飛び去ていった。
上の枝からは、キャッキャッと、猿たちの声がする。
「姉ちゃんのいる村に、いったような気がする。」ギンギンがいった。
「戦闘がおこりそうだって、とってもあわててたよ。」と、ジョイジョイがいった。
「ボアイボアイ村に避難しよう、って話していた。」と、クリスティンがいった。
子どもたちは、みんながみんな、大きな木の下で休憩しているあいだに、おなじ夢を見たことを不思議におもったけれど、おいてあった山菜のタライをかつぐと、歩きはじめた。
3,サリサリの犬
丘をこえ、谷をぬけて、それからどれだけ、歩きつづけたことだろう。
ギンギンたちは、自動車がやっと通れるような、でこぼこのじゃり道に、ようやくでた。
後ろのほうから、荷台にバナナをつんだ、ボロボロのトラックがやってきて、すぐよこを、ゆっくりと走りぬけていった。
道の両脇には、ところどころに、土台が竹ではなくって、コンクリートでできている、家が見えはじめた。小作人の家だ。このあたりに住んでいる人たちは、地主のもっている農場にはえている、ゴムの木の汁をしぼったり、バナナ農場の仕事をうけおったりして、生活しているから、そこそこ収入もあるし豊かなほうだ。
(註:地主自身は、医者や弁護士や銀行家、政治家や会社の経営者だったりして、大きな町の大きな家に住んでいる。)
自分の土地に住んでいるわけじゃないけれど、家もあるし、サリサリをもっていたりする。サリサリというのは、個人の家にある、小さなお店のこと。ばら売りのキャンデーや、小さな袋にわけられて入ったビスケットや、石けんなどを売っている。
ギンギンたちには、お金がないから買えないけれど、近所の子たちは、小さな子どもでも、キャンデーを買ったりしている。
サリサリの前を歩きながら、ギンギンたちは、声をだした。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買ってくださいなあーーー!」
ときどき、サリサリにおくために、山菜を買ってくれる家もあるけれど、なぜか今日は、ぜんぜん売れない。
ワンワン、ワンワンワン!
とつぜん、サリサリのよこから、犬が飛びだしてきた。
小さなジョイジョイが、悲鳴をあげたしゅんかん、頭のタライがひっくりかえって、パコパコが、足もとにちらばった。
そのとき、クリスティンには、ジョイジョイとはべつの、小さな悲鳴が、きこえたような気がした。
ギンギンとクリスティンは、ジョイジョイの前に立ちはだかると、犬にむかってさけんだ。
「シッシッ。」
「あっちいけ!」
ジョイジョイは、ギンギンたちの後ろにかくれた。
黒と灰色のしましま犬は、大きな口から、赤い舌をべろりとだして、白い歯をむきだして、うなりながら吠えかかる。
サリサリの小さな扉があくと、なかから、太った女の人がでてきて、大声で犬をしかった。
それでも、犬は吠えつづける。
そこで女は、そばに落ちていた木の枝をひろいあげると、犬にむかってふりあげた。
キャンキャンキャン
犬は、女主人の怒った顔と、ふりあげた小枝を見て、悲鳴をあげて逃げだした。
ギンギンとクリスティンは、頭の上のタライをおくと、ちらばったパコパコをひろって、ジョイジョイのタライにもどしはじめた。
太った女は、子どもたちを見て、一瞬あわれそうな顔をしたけれども、手をポケットにつっこむといった。
「ぼろをまとった、ネイティボ(先住民)だね。このあたりじゃ、山菜買う人はいないよ。町にでもおいき。」
そういってポケットから、5ペソだまをだして、わたしていった。
「これで、キャンデーでも買いな。」
4,大きな岩
ふたたび、頭にタライをのせると、ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、町にむかって歩きはじめた。
「子どもだけで、山菜売りをしていると、よいこともあるんだけれど、怖いこともあるの。
子どもの山菜売りは、あわれにおもって買ってくれるから、大人が売り歩くよりも、よく売れるんだって。
でもねえ、とっても、こわーーーい、お話もきいたの。
人さらいがいて、車が止まってドアがあくと、そのまま車におしこめられて、どっかにつれさられてゆくことがあるって。」
今度は、ギンギンのほうから、不思議な声にむかって、話しはじめた。
すると、不思議な声が、かえってきた。 「そうよ。とくに女の子をさらっていって、外国に売るのよ。だから、用心しなくっちゃだめよ。」
「でも、わたしたちが働かなくっちゃ、一家は食べていけないし・・・。」
お日さまは、頭の上まであがって、お昼が近づいてきたのがわかる。ひたいから汗が、タラタラと流れはじめた。
「重たいなあ、売れないと。」
「売れたら、軽くなるんだけどなあ。」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買って、くださいなあーーー!」
やがて、でこぼこ道は、マノンゴル村に入った。
日かげのない道は、暑くてどうしようもない。
村に入ってから、家は増えたけれども、高い塀にかこまれているし、暑いせいか戸が閉まっていて、人がいる気配がない。
さすがに疲れてきたので、三人は、バナナとマンゴスティンの植わっている、果樹園の小道に入って、そのさきにある大岩のかげで、休むことにした。
大岩のそばには、火のようなまっ赤な花を、たくさんつけた、大きな木がたっている。ファイアーツリーの大木だ。
「ファイアーツリーって、『火の燃えている木』という意味なんだって。緑の葉の上に、たくさんの花が咲いているけど、まるで、木に火花が飛びうつって、燃えているような感じでしょ。」
ギンギンたちは、大岩につくと、ホッと息をついた。
岩の後ろは、日かげになっていてすずしい。
山菜のつまった、タライを頭からおろすと、三人は岩かげに、ドッとたおれこむようにして、腰をおろした。さわやかな風がふいてきて、汗がスーッとかわいていく。
しばらくそこで、ウトウトしていると、村のほうから、子どもたちの歌声がきこえてきた。大ぜいで歌いながら、大岩のほうへとやってくる。
「ロラロラローラ ロラロラレ、ロラ ローラーローラー ロラロラレ、ヘイ!」
ギンギンたちは、大岩の上に登ると、はいつくばったまま、ソーッと岩から頭をのぞかせた。
「ロラロラローラ ロラロラレ、ロラ ローラーローラー ロラロラレ、ヘイ!」
どうやら、小学校の子どもたちが、十人あまり、午前の授業を終えて、帰ってくるところのようだ。
「いいなあ、あの子たち。学校にゆけて。お昼ごはんを食べに、帰る家もあって。」
クリスティンが、ため息をついていった。
「わたしたち、お弁当ないから、学校いけないもんね。」
ジョイジョイがいった。
すると、ギンギンが、ちょっと強い調子でいった。
「山菜売れなければ、夜ごはんだって、食べられないんだからね!」
「そうだよね。」
歌っているのは、小学校の子どもたちだ。野の花をつんで耳にさしたり、小枝をふりまわしたり、跳んだり、はねたりしながらやってくる。そのなかには、車いすの少女もいて、ほかの子たちが、かわるがわる後ろからおしている。 子どもたちは、大岩の手前までくると、立ちどまった。すると、髪の毛のちぢれた小柄な少女が、ちょっとかすれた声でいった。
「この岩。妖精さんのすみかなんだよ。」
子どもたちのおおくは、色も黒いし、どう見ても先住民族だ。ベールをかむっている子たちは、イスラム教徒にちがいない。
「昔は、このまわりで、マノボ族の人たち、踊ったり歌ったりしてたんだって。」
「酋長をかこんで、お祈りもしてたんだよ。」
「インカルばあちゃん、いってたよ。今もこの岩には、妖精さんが住んでいるって。」
さっきの男の子が、神妙な顔をしていった。
「『タビタビ ポー。』って、いって、妖精さんたちにあいさつしながら、ここは通らなくちゃだめなんだ。とくに、夕暮れどきにはね。」
「それって、どういう意味?」
「『おねがいします、通してね。』と、いう意味。」
そういうと、子どもたちは、大声で「タビタビ ポー。」「タビタビ ポー。」と、いいながら、大岩の前を通りはじめた。
ギンギンたちは、大岩の上から、わずかに頭をだして、子どもたちが、通りすぎてゆくのを見まもった。
ギンギンが、ひそひそ声でいった。
「あの子たち、みんなおなじリュック、しょっているよ。」
「ほんとうだ。赤と緑の布地に黒で、MCL(エムシーエル)って書いてある。」
学校がえりの、子どもたちは、大岩のそばを通りぬけると、歌いながら、お昼を食べに帰っていく。
ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、大岩の上から、子どもたちを見おくった。子どもたちがあんまりたのしそうなので、ギンギンは、おもわずため息をついていった。
「わたしも学校、ゆきたいなあ。もし大学卒業できたら、もっと母さんたち、助けられるのになあ。」
「姉ちゃん、大学まで考えているの。小学校すらたいへんなのに。」と、クリスティンがいった。
「夢は、高くもつものよ。」
ギンギンは、そうはいったものの、どうしたら大学までゆけるのか、見当もつかなかった。
小さなジョイジョイも、クルクルした目を見ひらきながら、うらやましそうにいった。
「いいなあ。わたし、小学校だけでもいきたいなあ。字が読めて、計算できて。」
「計算だったら、わたしできるよ。」
クリスティンがいった。
「カンコン一束、5ペソ。タクワイ一束10ペソだから三束で30ペソ。パコパコ一束5ペソだから二束で10ペソ。あわせて45ペソ。」
三人は、大岩から飛びおりると、おいてあった、山菜のつまったタライを頭にのせて、大岩から離れて、歩きはじめた。町までは、まだまだ遠い。
ギンギンたちが、大岩から遠ざかっていくとき、大岩の上から、ギンギンたちが去っていく後ろ姿を、しずかに見まもっている影があった。
刺繍の入った、青と赤と黄色の服をまとった、妖精たちだ。山菜の入ったタライにのって、山からおりてきた、カンコン、タクワイ、パコパコの、三人の妖精たちだった。
さらにその後ろには、刺繍の入った、紺色の衣装と茶色のズボンに身をかため、頭に紅い頭巾をかぶり、胸までとどく長いひげをはやした、マノボ族の酋長がたっていた。
酋長は、去っていく子どもたちのほうを、じっと見つめながら、妖精たちにつぶやいた。
「あの子たちは、わたしのかわいい、孫たちだよ。」







第三章
1,町で 2,市場で 3,ストリートチルドレン 4,シンカマス売りのお母さん 5,ボス
1,町で
マノンゴル村でも山菜は売れず、ギンギンたちは、コンクリートの道を、町にむかって歩きはじめた。
道の両脇には、高い壁でおおわれた、お金もちの家々がつづいている。ガレージがあって、自動車がおいてある家もある。
そのとき、緑色の軍用車が、五台つらなってやってきて、山菜売りの少女たちのすぐよこを、ものすごい勢いで走りぬけた。後ろの座席には、鉄砲を手にもった兵隊たちが、ひしめきあいながらのっている。
「山でまた、戦争がおこっているのね。」
クリスティンがそういったとたん、つづいて二台のオートバイが、緑の服を着た兵隊をのせて、エンジンの音をたてながら、トラックのあとをおいかけていった。
「姉ちゃんのいる、山かなあ。」
ジョイジョイがつぶやいた。
「こわいね。」と、ギンギンがいった。
コンクリートの坂道を、くだっていくと、やがて三人は国道にでた。
子どもたちは、パン屋さんの角を、左にまがると、キダパワンの町のなかにむかって、歩きはじめた。
大きな教会の前を通り、町の中心に近づくにつれて、自動車、トラック、バスやジプニーが多くなり、それらにまじって、たくさんのトライシクルやバイクが、ぬうように走っていく。
運転手も、のっている人たちも、ゆくさきをじっと見つめたまま、山菜売りの子どもたちがいることなど、気づかない。たとえ気がついても、はげしく警笛をならすだけで、止まって山菜を買ってくれるわけではないし・・・。
歩いているのは、山菜売りのわたしたちと、お金がない浮浪者とストリートチルドレンぐらいで、みんな、バイクの後ろやトライシクルにのって、移動している。元気なはずの、若者や子どもたちまで、自転車つきのトライシクルにのったりしている。
「山だったら、歩いている人が、ほどんどなんだけれどなあ。お金がなくちゃ、町にはすめないね。」と、クリスティンがいった。すると、ギンギンもつぶやいた。
「わたしたち、ここに住だら、浮浪者かストリートチルドレンになるしかないな。」
町に近づくにしたがって、お店の数が増えはじめた。
オートバイの修理屋さん、ペンキ屋さん、金物屋さん、看板屋さん、家具屋さん、そして町の中心に近づくにしたがって、文房具屋さん、日用雑貨屋さん、中古のテレビを売っているお店もある。
町のまんなかには、大きな市場があり、そのあたりまでくると人通りも多く、買い物をしている人たちも増えてくる。さまざまな食堂やパン屋さん、お菓子屋さん、床屋さん、古着屋さん、電器屋さん、薬屋さんなどなど、ありとあらゆる店がならんでいる。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買ってくださいなあーーー!」
ギンギンたちは、薬屋さんの前までくると、売り場にいるお姉さんたちに、声をかけた。
みんな、ちょっとビックリしたようだったけれど、一人のお姉さんが、貧しいかっこうの少女たちを見て、ほほ笑んでいった。
「何のお野菜、もってきたの。」
「カンコン、タクワイ、パコパコ。」
ギンギンたちは、薬がならんでいるガラスのショーケースの上に、山菜の入ったタライをおいた。
ほかのお姉さんたちも、よってきていった。
「キャベツとか、ニンジンはないの?」
「あれまあ、山菜だけなのね。」
「・・・・・・・。」
黙ってしまった子どもたちを見て、最初に声をかけてくれたお姉さんがいった。
「わたし、買うわ。タクワイとパコパコにしようかな。」
長い髪の毛を、リボンで後ろ手にむすんだお姉さんが、タライのなかから、タクワイを二袋と、パコパコの束を二つとりだしてたずねた。
「おいくら?」
「タクワイ一袋10ペソ、パコパコ一束5ペソだから、全部で30ペソ。」
クリスティンがこたえると、お姉さんは、ポケットからお財布をだして、なかから30ペソとりだすと、ジョイジョイにわたした。
それを見て、ほかの売り子のお姉さんたちも、「わたしも、買おうかしら。」といって、少しずつだけれど、山菜を買ってくれた。
ギンギンもクリスティンもジョイジョイも、大よろこびで、ふたたびタライを頭にのせると、薬屋さんをあとにして、市場にむかって歩きだした。
急に、人通りが増えてきた。
道ぞいの、あいている場所には、鳥の串焼きや丸焼きを焼いている屋台や、バナナやマンゴーなどの果物をならべている、売り台がある。
ギンギンたちは、木の台の上で、シンカマス(砂糖大根)を売っている、おばさんたちがいる角をまがって、市場のなかに入っていった。
2,市場で
市場のなかは、ものすごい人混み。
果物屋の前には、バナナ、マンゴー、パイナップル、マンゴスティン、ランソネス、ランブータンといった熱帯果実が、ところせましとならんでいる。トゲトゲのドリアンもある。
ギンギンたちは、果物屋の前の石だんをのぼると、市場の大きな建物のなかに、入っていった。
はだか電球の下で、たくさんの魚屋さんが、所せましと軒をならべて、商売をしている。
魚売りの女たちが、さけんでいる。
「いらっしゃい、いらっしゃい。マグロもテラピアも、バゴスもあるよ。安くしとくよーっ!」
「とりたてのイカだよ。アジはどうだい!」
「ナマズだよナマズ、新鮮だよ、生きているよ!」
売り台の前を、ショウガやニンニクや、小粒のトマトをいれた、ザルをもった子どもたちが、歩きまわって買い物客にすりよると、下から話しかけてくる。
「ねえ、これ買って。」
「おねがいだから、買ってちょうだい。」
母さんたちの、お手つだいをしているのだ。
ギンギンたちが、山菜の入ったタライをさしだすと、哀れにおもったのか、数人の人たちが買ってくれた。でも、ほとんどの人たちは、自分のお店のものを売りさばいたり、買い物をするのにいそがしく、ボロボロの服をまとった少女たちのほうを、見むきもしない。
はだか電球の下で、飛び交う人々の声や、すごい活気にもかかわらず、売れない山菜を頭にかついで歩いているギンギンたちは、何だか、さびしい気もちになってきた。
「はやく、山に帰りたいなあ。」と、ジョイジョイがいうと、クリスティンがこたえた。
「でも、山菜うれないと、母さん、がっかりするよ。」
子どもたちは、屋根のある大きな市場のなかをくぐりぬけると、道にでた。野菜を売っているお店が、ずらーっとならんでいる。
「山菜、買ってくれない?」ギンギンがいうと。
「山菜なら、たくさん売れのこっているからなあ。」
「そんな、しなびた山菜、ここじゃ、だれも買わないよ。」
あんなにたくさん人がいるのに、ほとんどの人たちが、ふりむきもしない。
ギンギンたちは、ひどく場違いなところに、来てしまったようなきがした。
3,ストリートチルドレン
市場をぬけて、ふたたび大通りにでると、パン屋があった。おおぜいの人が、店のショーケースの前にたって、パンを買っている。
ギンギンたちは、パン屋の前に立ち止まると、できるだけ大きな声でさけんだ。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買って、くださいなあーーー!」
でも、お店の人もお客さんも、パンのよい香りにはひかれても、山菜の入ったタライを頭にのせた、服もボロボロの子どもたちのことなど、見むきもしない。
パン屋のなかには喫茶店もあって、おやつにパンやケーキといっしょに、コーラやジュースやアイスクリーム、ハロハロや煮こみうどんを食べながら、おしゃべりしているご婦人たちがいる。
「なかに、入ってみようよ。何か、買ってくれるかもしれないよ。」と、クリスティンがいった。
ギンギンは、ほんとうにだいじょうぶかなあ、と不安におもったけど、ぜんぜん売れないで帰るわけにはいかないし。母さんや妹や弟たちの、お腹をすかせた顔をおもいだしていると、ゆうかんなクリスティンが、あいている入り口から、喫茶店のなかにさっさと入っていった。
それにひかれて、ジョイジョイとギンギンがつづいた。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買ってくださいなあーーー!」
二度ほどさけんだとき、調理場から、白い調理服を着た男が、手にオタマをにぎって、飛びだしてきた。
「きたないガキ、店のなかに入るな!
こんなところで、どこからとってきたかわからない、山菜を売られたりしたら、たまったもんじゃない!」
店のなかで、パンやコーヒー、アイスクリームやハロハロを食べたり、コーラやジュースをのんだり、煮こみうどんをすすっていた人たちは、いっせいに、山菜売りの少女たちのほうを見やった。
子どもたちは、あわてて店からでようとした。けれども、頭に重たいタライをのせいているので、さっと動くことができない。
うろうろしている子どもたちを見て、男はさらに声をはりあげて、大またでちかよってくると、タライを頭にのせた三人の子どもたちを、店のなかから、むりやりおしだそうとした。
おどろいて、クリスティンが、外にでようとしたときのことだ。あわてたせいか、入り口のしきいにつまづいた。
「あっ!」 声をあげたのと同時に、ゆっくりと体がたおれ、頭にのせいていた山菜の入ったタライがかたむき、手からはなれていった。
店のなかにいた人たちが、「キャー!」と、さけんだ。
「山菜が落ちる!」
クリスティンが、悲鳴をあげたつぎのしゅんかん、クリスティンは、だれかに抱きかかえられていた。
まわりで、男の子たちの声がした。
「だいじょうぶ。山菜、うけ止めたよ!」
クリスティンが、顔をあげて見ると、自分より大きな男の子が、しっかりとクリスティンを抱きとめていた。
山菜の入ったタライも、べつの男の子たちがかかえている。ひっくりかえって落ちる直前に、うけ止めたにちがいない。
ギンギンとジョイジョイも、あわてて店から外にでた。
店の男は、出口に立つとさけんだ。
「きたないガキども!店の前から立ち去れ!」
男の子たちは、山菜売りの少女たちを、守るように取りかこむと、店の男にむかって、両手を耳のそばにたてて舌ベロをだして、「あっかんべー!」をしたり、滑稽な顔をして、馬鹿踊りをしはじめた。
よく見ると男の子たちは、ボロボロの破れた服を着た、五人のストリートチルドレンたちだった。
調理服の男は、顔をまっ赤にして、オタマを左手にもちかえると、売り台にのっているパンを、石のかわりにつかんで投げようとした。
すると、ストリートチルドレンたちは、口をいっぱいにあけて、パンをここに投げこんでほしい、といわんばかりに、指で自分の口をさして踊りはじめた。
周囲にいる人々が、さすがに大笑いしはじめると、男はきまりわるそうに、「パン屋にはなあ、衛生規定ってものがあるんだ!」と、捨てゼリフをはいて、店のなかにひっこんでいった。
クリスティンを抱きかかえた、大がらな少年がいった。
「だいじょうぶ?」
「ありがとう、助けてくれて。」
クリスティンがこたえると、少年は、顔を首すじまでまっ赤にして、頭をかいた。ほかの子たちが、はやしたてた。
一人の男の子がいった。
「山菜売り、てつだってやろうよ。」
「オッケー、レッツゴー。」
ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、ひょんなことから友だちになった、五人のストリートチルドレンたちといっしょに、町なかを歩きはじめた。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買って、くださいなあーーー!」
ギンギンたちがいうと、五人の男の子たちが、大声でさけぶ。
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「カンコン、タクワイ、パコパコ!」
「山菜買って、くださいなあーーー!」
4,シンカマス売りのお母さん
国道の角の道までくると、そこにかんたんな台をだして、小さな娘といっしょに、シンカマス(砂糖大根)を売っている、貧しいお母さんがいた。
たった今、おこったことを、遠くから見ていて、ちょっと心を痛めたこともあって、そのお母さんは、子どもたちに声をかけた。
「その山菜、少しだったら買ってあげるよ。ここにおいておいたら、売れるかもしれないしね。」
「ありがとう。」
「二束づつで、わずかだけれど、ごめんね。おいくら?」
「カンコン二束で10ペソ、タクワイ二袋で20ペソ、パコパコ二束で10ペソ、ぜんぶで40ペソ。」
お母さんも貧しいらしく、ポケットから、なけなしのお金をだすと、山菜をうけとって、売り台においてくれた。
「あんたたち、マノボ族みたいだけど、学校にもいってないようね。」と、お母さんはいった。
だまってしまった子どもたちを見て、お母さんはたずねた。
「学校にゆきたいの?」
ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、首をたてにふった。けれども、五人の男の子たちは、はげしく首をよこにふった。
お母さんは、大笑いをすると、山菜売りの子たちにたずねた。
「なぜ、学校にゆきたいの?」
「少しでもよい仕事について、家族をたすけたいの。」
「だったら、MCL(エムシーエル)にいってみたらいいのに。」
「MCL(エムシーエル)って、なに?」
ジョイジョイがたずねると、ストリートチルドレンたちがいった。
「ぼくたち、しっているよ。」
「『ミンダナオ子ども図書館』の、ことだよ。」
「貧しい山の村や、町でもぼくたちみたいなストリートチルドレンなんかに、絵本の読み語りをしているんだよ。歌や踊りや劇もやってくれて、とっても、とっても、たのしいよ。」
シンカマス売りの、お母さんがいった。
「うちの娘のジサは、眼に白い膜ができて、手術もできないし、お金もなくて、学校にもゆけなかったの。
だけど、クリスマスに、町の役所の広場で、ストリートチルドレンための読み語りと、炊き出しがあってね・・・。」
「そのとき、ぼくらも、そこにいたよ!」と、ストリートチルドレンたちが、さけんだ。
「そこに、ママ・エープリルという人がいてね、ジサを見て、あわれに思ったのか、こういってくれたの。
『あなた、片眼が見えないようね。もし良かったら、お医者さまに手術をしてもらう?ぜんぶ、費用は、こちらで出すからだいじょうぶよ。』
ジサもわたしも、もうビックリ。
ジサは、大喜びでうなずいたわ。そして病院で、眼を治してもらったの。
しかもそのあと、ジサにはお父さんもいないし、わたしだけでは、学校にもいかせてやれないことがわかったら、こうもいってくれたの。
『うちのスカラシップに、応募したらいい。成績よりも、貧して親のいない孤児や、片親の子が優先だから。
本人と保護者がよければ、ミンダナオ子ども図書館に住んで、近くの学校にかようこともできますよ。もどりたくなったら、いつでももどって、家から学校にかよってもいいしね。』
それをきいて、ジサと、ミンダナオ子ども図書館にいってみたら、子どもたちは、なんと80人ぐらいも住んでいて、とっても明るくって、みんなとってもなかよしだし、ジサは、たちまち気にいって、今はもう、そこに住んで、幸せそうに学校にかよっているわ。」
ストリートチルドレンの男の子が、ビックリしていった。
「ぼくらの友だちだったスイーツも、今はそこに住んで、学校にかよっているよ!
彼女、お父さんもお母さんもいなくなって、自分が外国に売られそうになったとき、助けてもらったっていってた。
将来は看護師になるって、大はりきりだよ。」
ギンギンは、MCL(エムシーエル)って、なんだか、見たことある名前だなあ、とおもった。
「それって、どこにあるの?」
「マノンゴル村。」
「あっ!今日ここにくる前に、大きな岩のそばを通っていった子どもたち。そういえば、リックサックに、『MCL』って、書いてあった!」
お母さんは、5人のストリートチルドレンのほうを見るといった。
「あんたたちも、学校にいったら?」
男の子たちは、はげしく、首をよこにふった。
まわりでようすを見ていた人たちも、大笑いをしている。
そのなかの、焼き鳥を口にほおばっている男が、大声でいった。
「学校にいったからって、どうってことないからなあ。」
すると、そのとなりの工事現場の、日雇い職人ふうの男が、うけこたえた。
「でも、金もちだけが、大学教育をうけられて、よいところに就職できるってのも、へんだよなあ。」
さらに、その後ろにたって、ようすを見ていた、肩にオートバイの重い部品を背負っている、油で汚れた男がいった。
「おまえたちのような、社会から、見すてられたようなのが、大学をでて、よい働きをしたら、少しは社会がよくなるかもしれないぞ。」
ストリートチルドレンたちがいった。
「ぼくらも、いっしょにいってみよう。スイーツに会えるかもしれない。偉くなりたいとはおもわないし、学校にもいかないけどね。」
「マノンゴル村まではわかるけど、村のどこにあるのか、しらないなあ。」
「そうだ、ボスだったら、場所をしってるかもしれないよ。きいてみよう。」
「そうだ、それがいい。」
5,ボス
ボスというのは親分のことだけど、わたしたちには、どんな人か、わからなかったの。
ストリートチルドレンの親分って、どんな人だろう。
なんだか怖い人を、想像していると、少年の一人が、国道の反対がわにある銀行を、指さしていった。
「ほら、あそこにいるよ。」
親分が銀行のもち主だったら、きっと、お金もちなんだろうなあ。そうおもって、山菜売りの少女たちは、ストリートチルドレンたちのあとに、ついていった。
男の子たちは、入り口までくると、銀行のなかには入らずに、そばの路上にすわっている、男のほうへと近づいていった。
男は、かた手を前にさしだしては、物乞いをしている。
顔はあさ黒く、口のまわりはひげだらけで、あごひげはのびっぱなし、お腹のあたりまでたれている。服はボロボロ、胸のあたりは、はだけて半分はだか。ズボンも破れて穴だらけ。靴もはかずに裸足だし、体から臭いにおいも、ぷんぷんしてくる。
男は、はんぶん眠っているような、トロンとした目を、していた。けれども、ストリートチルドレンたちがかけよっていくと、ゆっくりと顔をあげた。そしてそのあとから、山菜売りの少女たちが、ついてくるのを見たときに、男の目は、キラリと光った。
物乞いをしている浮浪者の前に、少年たちは立つと、クリスティンを助けてくれた、大がらな男の子がいった。 「ボス、つれてきたよ。」
男は、まるで、ギンギンたちを、まっていたかのようにほほえんだ。
「ぼくたち、ミンダナオ子ども図書館にいきたいんだけど、ボスなら、しっているよね。」
浮浪者は、膝をたてて、すわりなおすといった。
「もちろんだとも。アオコイ酋長とは、友だちだ。
あそこには、たくさん子どもたちが住んでいる。とりわけ、親のない子や片親の子がね。
マノボ族の子もいるけれど、戦争で親が殺されたイスラム教徒の子どもたちや、親のいなくなった、キリスト教徒の子どもたちも、みんないっしょに仲よく暮らしている。
あそこにいくと、昔をおもいだすなあ。昔は、宗教や部族がちがっていても、ミンダナオは平和だったんだ。」
お姉ちゃんのことをおもいだして、クリスティンがいった。
「戦争はいやね!世界じゅうが、昔のミンダナオのように、平和だったらいいのになあ。」
すると、ひとりの男の子が、政治家が演説する調子をまねて、おどけていった。
「戦争も、貧困もなく、平等で、とりわけ子どもとお年寄りが、幸せに生きることができる社会を、実現しよう!」
浮浪者は、よこにおいてあった木の棒を杖がわりにして、「よっこらしょ。」と、立ちあがるといった。 「昔は、だれも、『これはオレたちの家だ。』なんていわずに、家のない人や親のない子がいれば、家族のように迎えていっしょに暮らしたものだ。
『ここはオレの土地だから、おまえたちはでていけ。』などともいわないで、喜んで土地をわけてあげて、野菜を植えさせてくれたものだ。
お金のない社会は、よいもんじゃった。」
浮浪者は、山菜売りの少女とストリートチルドレンたちに、自分のあとについてくるように、といって歩きはじめた。
ボロボロの服をまとった浮浪者のあとを、ストリートチルドレンたちがつづき、そのあとに、頭に黒いタライをのせた山菜売りの少女たちがつづく。
今まで無関心だった人々も、このときばかりは、ちょっとビックリした顔をして、子どもたちをながめた。
車も、スピードをゆるめて、なかには、わざわざ窓をひらいて、声をかけて通りすぎる運転手もいた。トライシクルの座席からも、大人や子どもたちが、身をのりだしてながめている。
こうして、浮浪者につれそわれた子どもたちは、目的地のマノンゴル村にむかって、歩いていった。







第四章
1,ミンダナオ子ども図書館の子どもたち 2,あなたがジサね! 3,母さんとばあちゃんも 4,助けにゆくための準備
1,ミンダナオ子ども図書館の子どもたち
マノンゴル村に入ると、小さな教会があって、その前を少しくだると、小川が流れていた。
小川をわたって、家々のあいだをぬけて、でこぼこ道をいくと、果樹園の緑のなかに、ミンダナオ子ども図書館(Mindanao Children's Library Foundation, Inc.)と、書かれた看板が見えた。
門のそばには、大きなファイアーツリーが、まっ赤な炎のような花をつけている。なかからは、たくさんの子どもたちの声が、きこえてきた。
広い敷地には、壁らしいものもない。建物は、おもっていたよりも、ずっと大きくよこ長で、鳥が飛びたつようなかっこうをしていた。
家の前は、緑の庭で、たくさんの子どもたちが、鬼ごっこをしたり、ハンカチ落としをしてあそんでいる。
ファイアーツリーの下を通ったとき、ギンギンは、町でシンカマス(砂糖大根)を売っていた、お母さんの話をおもいだして、つぶやいた。
「ここに住んでいるのは、おもに、父さんや母さんがいない子たちなのよね。」
すると、木の上のほうから、声がきこえてきた。
「それだけじゃないよ。何ヶ月もでかせぎして、学校もいけずに、サトウキビ刈りをしたり、田んぼの草刈りやゴム農園で、働かなくてはいけなかった、子どもたちもいるよ。」
ファイアーツリーのこずえに咲いている、まっ赤な花たちが、話しかけてきたような気がして、ギンギンは、こずえを見あげていった。
「わかるよ、それ。
わたしたちもそうだけど、子どもでも、食べるためには、学校なんかいかないで、働かなければならないのよ。」
「お父さんやお母さんが、逃げてしまった、子たちもいるよ。」
「わたしもしってる。
その子、いく場所がなくなって、親戚やしりあいをたらいまわしになっていたわ。学校になんか、いかせてもらえなくて、豚の世話や便所掃除をやらされていた。
ここにいる子たちは、そんなところからきた子なんだ。
庭で鬼ごっこをしていた子たちが、ギンギンたちが、入ってきたのを見ていった。
「だれか、きたよ!」
子どもたちは、いっせいに、訪れてきた人たちのほうを見た。
入ってきたのは、ボロボロの服を着た、ひげだらけの浮浪者と、五人のストリートチルドレン。それに、頭にタライをのせた、三人の山菜売りの少女たちだ。
子どもたちは、かけよってくると、ギンギンたちのまわりをかこんだ。浮浪者を見て、口をポカンとあけて、ビックリした顔をしている子もいる。
浮浪者は、そんなことにはおかまいなく、山菜売りの少女たちと、ストリートチルドレンをひきつれて、門のなかへと入っていった。
すると、集まってきた子たちのなかの、髪の短い女の子が、とつぜんストリートチルドレンにかけよると、そのなかの一人の少年に、抱きついた。
抱きつかれた少年は、少女を抱きしめると、さけんだ。
「スイーツ!」
外国に売られそうになった女の子が、仲間にいるんだ、といっていた男の子だ。
「やっぱり、ここにいたんだね。幸せそうだね。顔が明るくなったもん。」
スイーツは、大きくうなずいた。
「大きくなったね。」
浮浪者が、少女の頭をなぜながらいった。
「今年、小学校を卒業するの。」と、スイーツは、こたえた。
「ほほう。来年から高校生か。(註:フィリピンでは、中学校がなく、小学校を卒業するとハイスクールとよばれている高校にいく。)」
「美人になったなあ。」
ストリートチルドレンの男の子がそういうと、スイーツは、まっ赤な顔をしてうつむいた。
いっせいに、ほかのストリートチルドレンたちがはやしたてた。
浮浪者は、子どもたちの前に、歩みでるとたずねた。
「アオコイ酋長は、おいでかな。」
すると、子どもたちの一人がいった。
「アオコイ酋長って、パパ・トモのことだよね。」
それを聞くと、子どもたちがさけんだ。
「いるよ、いるよ!」
「まってて、今、よんでくるから。」
そういうと、「パパ・トモー!」と、さけびながら、子どもたちの何人かが、青い屋根の家に、かけこんでいった。
家の二階は、木造のポーチになっていて、手すりからも、たくさんの子どもたちが、のぞいている。
アオコイ酋長というからには、民族衣装に身をかためた、いかつい男がでてくるのかと、ギンギンはおもった。けれど、二階からおりてきたのは、白いシャツにジーンズをはいた、ごく普通の男の人だった。
子どもたちは、その男の人の手をにぎって、浮浪者の前にひっぱりだすといった。
「パパ・トモ。ほら、この人たちだよ!」
パパ・トモは、浮浪者の顔を見ると、満面笑顔でちかより、両手をにぎるといった。
「ようこそ、マオガゴン酋長。お元気ですか。」
ギンギンは、名前をきくとびっくりして、浮浪者の顔を見あげてつぶやいた。
「えっ、この人が、マオガゴン酋長なの?」
ギンギンは、山からとってきたばかりの、山菜のはいったタライを置いたとき、おばあちゃんが、タライを見ながら、いっていたのを思いだしていた。
『マオンガゴン酋長に、おねがいがあるんだって。そうかい、そうかい。会ったら、わたしからもよろしくって、つたえておくれ。もうじき、そっちにいく日も近いだろうって。』
ギンギンが、おどろいた顔をして酋長を見あげていると、浮浪者は、ニヤッと笑って、ギンギンに目くばせをした。
浮浪者は、パパ・トモを見ると、笑顔でいった。
「おひさしぶりです、アオコイ酋長。一族が、いつもいつも、たいへんお世話になっています。」
「いえいえそんな、こちらこそお世話になっています。
まあまあ、なかにお入りください。どうです、コーヒーでも一杯いかがですか。庭にはえているコーヒーの実で、つくったものですが。」
「いやいや、つぎの機会にでも、ゆっくりいただくとして。じつは今日は、おねがいがあってきました。」
「どんなことですか?」
「いつもながら、むりなおねがいで、もうしわけないのですが、ここにいる三人の、山菜売りの子たちのことなんです。
この子たちのお父さんは、死んで、土地もなくなり、母さんと子どもたちだけで、苦労して山菜を売りながら、なんとか食いつないでいるんだが。
学校にいきたくても、いけなくて、そのーーー、つまりーーー。」
浮浪者は、頭をかいた。
パパ・トモは、にこにこしながらいった。
「学校にいかせて、あげたいんですね。」
「ええ、まあ。実の孫娘のような、子たちで・・・。」
「喜んで、おひきうけしましょう。マノボ族ですか?お父さんが亡くなられたとか。病気ですか?」
「ちょっと、ここでは、いいにくいんだが、わけあって殺されて・・・。」
2,あなたがジサね!
「ちょっとまって、今、妻をよびます。」
パパ・トモは、子どもたちのほうを、ふりかえっていった。
「ママ・エープリルをよんできて!」
酋長にいわれて、数人の子どもたちが、家にかけていった。
しばらくすると、こがらな、しっかりした感じの女の人がでてきて、夫のよこに立つといった。
「まあまあ、山菜売りの少女たちね。頭の荷物、重いでしょ。おろしなさい。
だいじょうぶ、山菜ぜんぶ買ってあげるから。ここにはね、子どもたちが、80人ぐらい住んでいるのよ。だから、おかずにちょうどいいわ。」
そういうと、ママ・エープリルは、地面におかれた、タライの前にしゃがむと、そばにいた子どもたちにいった。
「台所に、はこんでちょうだい。夕ごはんに、みんなで、お料理しましょうね。」
そして、ポケットからお財布をとりだすと、クリスティンに、お金をわたしていった。
「これでたりる?」
「多いわ。」
「それなら、おこづかいとして、とっておきなさい。あなたたち、どこに住んでいるの?」
「あっちの山の谷そこ。」
「畑はあるの?」
「ない。」
「そうでしょうね。山で山菜をつんで、なんとか生活しているんでしょ。
学校にいきたくて、ここにきたの?」
ギンギンとクリスティンとジョイジョイは、大きく首をたてにふった。
ギンギンがいった。
「市場のそばで、シンカマス(砂糖大根)を売っている、お母さんにあったの。その人が、ここにいったら、毎日3食たべられるし、学校にもいかせてもらえるよって。
自分の娘も、目の病気をなおしてもらったあと、あそこに住んで、学校にいかせてもらっているって。」
それをきいて、そばにたっていた、髪の毛がふさふさした少女が、ビックリしていった。
「それ、わたしの母さんよ!」
ギンギンは、一歩前に進みでると、自分とおなじ年ごろの、その少女にちかよって、しっかりと両手をにぎっていった。
「あなたが、ジサね!わたし、ギンギン。」
ママ・エープリルは、後ろにひかえている、ストリートチルドレンたちを見ていった。
「あなたたちも、学校にいきたくてきたの?」
男の子たちは、はげしく首をよこにふった。
浮浪者は、そんな男の子のようすを見て、声をたてて笑った。
「まあ、学校だけが、すべてではないし。ほんとうは、この世のすべてが、学校なんだ。
自分の村につたわっている、マノボ文化の伝統を、おじいちゃんやおばあちゃんから学ぶことだって、すばらしい学問なのさ。町にでて、お金をもうけるだけじゃなくてね。」
するとパパ・トモが、ストリートチルドレンたちにいった。
「君たちも、ここに住だらいいのに。
大学まではいく気がなくっても、高校を卒業したら、運転手やお裁縫などの、技術学校にも、いかせてあげられるからね。」
すると、子どもたちの何人かが、いった。
「ぼく、運転学校にいって、運転手になるんだ!」
「ぼくは、大工さんになりたい!」
「わたしは、お裁縫を勉強して、お洋服をつくるの!」
ジサのとなりの、女の子がいった。
「わたしは、がんばって大学を卒業して、教師の資格をとるんだ!
ふる里の学校の先生になって、学校にいけない子たちを、こんどはわたしが、お給料でいかせてあげるの!」
それをきいていた、ストリートチルドレンのなかの、小柄な少年がいった。
「ぼく、トライシクルの運転手に、なりたいなあ。」
それを耳にして、ママ・エープリルがいった。
「あなたたち、食べるものを見つけるだけでも、たいへんでしょう。レストランの前に駐車した、車の窓ガラスをふいて、お金をせびったり。道ばたに寝て物乞いしたり。
それだったらいっそうのこと、ここに住んで、学校に通うほうがよさそうね。」
「お弁当もって、学校にいけるの?」
「すぐそこが学校だから、お昼には帰ってきて、食堂でみんなで食べるの。」
ストリートチルドレンの少年たちは、目を見ひらいていった。
「一日三回、お米のごはんが食べられるなんて、夢みたいだなあ!」
すると、まわりの子たちが、いいだした。
「朝はやく起て、ごはんをたいて、おかずをつくるの、わたしたちの仕事よ。」
「みんなで庭で、野菜もそだてているの。」
「お米を干すのは、ぼくら男の子たちのやくめさ。」
「お庭も、わたしたちでつくったのよ。お花を植えたり、木をそだてたり。」
「果物もとって、みんなで食べるんだ。」
「ドリアンもマンゴスティンも、バナナもマーランもランブータンもあるよ。」
「おやつには、カサバイモを掘ってきて、バナナといっしょに、蒸し焼きにするんだ。」
ストリートチルドレンのなかの、大がらな少年が、ビックリしてさけんだ。
「ぼくたち、果物やオイモを、盗んだことはあるけど、ここでは勝手にとっていいの!」
子どもたちがいった。
「いいんだよ!」
「だけど、とったらね、みんなでわけあうのが、決まりだよ。」
一人の子が、山菜売りの少女たちにいった。
「わたしも、父さんいないんだ。どっかにいっちゃったまま、帰ってこないの。母さんも、べつの人といっしょになったみたい。」
すると、そのそばにいた男の子が、話しかけてきた。
「ぼくのお父さんとお母さんは、戦争のまきぞえで、死んだんだ。
家族で家にいたら、とつぜん、武器をもった人たちが入ってきて、父さんと母さんは、その場で撃たれて、ぼくも撃たれた。ミンダナオ子ども図書館が、ぼくを見つけて、手術してくれなかったら、ぼくも死んでいたかもしれない。
ほらここだよ。」
服をたくしあげると、少年はお腹を見せた。そこには、手術のあとがあった。
「わたしもそう。
山に住んでいたら、鉄砲もった人がきていったの。
『ここに外国人のくるリゾートをつくる。1万円やるからでていけ!』って。
父さんは、マノボ族の酋長で、貧しくてもプライドがあったから、『いやだ、でていかない。ここは、マノボ族の先祖伝来の土地だ!』って、いったとたん、パンパンて撃たれて殺された。
母さんが、助けにかけよると、母さんもお腹を撃たれたの。母さんは助かったけれども、家を捨てて逃げるしかなかった。」
また、べつの子が話しはじめた。
「わたしねえ、父さんも母さんもいるんだけど。町外れのゴミ捨て場に住んでいたの。
父さんもしっているんだけど、母さんは、いろんな男の人といっしょになって・・・お腹がすきすぎると、頭がおかしくなるんだって。」
子どもたちは、山菜売りの少女や、ストリートチルドレンたちを取りかこむと、いろいろな身のうえ話をかたりはじめた。きくと、ビックリするような話ばかりだけれど、べつに隠しだてすることもなく、心をひらいて話しかけてくる。
浮浪者がいった。
「ここに住んでいる子たちは、みんな、たいへんな所からきた子たちなんだ。でも、だれも死にたいとおもわない。みんな、あかるく生きている。
生きる力って、何だろう?」
ストリートチルドレンのなかの、いちばん大がらな少年がさけんだ。
「生きる力は、一人でがんばることじゃなくって、おたがいに助けあうことなんだ。」
子どもたちは、口をそろえていった。
「そうだそうだ、友情と愛が生きる力!」
「ぼく、ここにきて、よかった!」
「友だちが増えて、わたし幸せ!」
「それに、将来の夢も広がるよ。」
「ぼくは、エンジニアになるんだ。」
「わたしは、ソーシャルワーカー(社会福祉士)!」
それを見て、クリスティンがいった。
「わたし、ここにすみたいなあ。」
すると、ママ・エープリルがいった。
「住だらいいわ。
でも、まずはお母さんに、相談しなくてはね。あなたたちのお家をたずねて、お母さんと話しましょう。」
パパ・トモは、浮浪者のほうをむくといった。
「ご同行、おねがいできますか。」
「もちろんですとも。」
パパ・トモは、四輪駆動のトラックの運転台にすわると、エンジンをかけた。
おくさんと浮浪者と、山菜売りの少女たちが、のりこんだ。
ママ・エープリルは、ストリートチルドレンたちにも声をかけた。
「あなたたちも、いっしょにきてくれない?荷台にのったらいいわよ。」
「わーーーい。」
ストリートチルドレンたちは、歓声をあげて、荷台に飛びのると、おたがいにつぶやきあった。
「ぼくらも、ここにすもうよ!」
3,母さんとばあちゃんも
車は森のなかを走り、急な山道を登りつめて、ギンギンたちの家にむかう、けもの道の前で止まった。
そこで、みんなおりると、ゴムの林のけもの道をぬけて、カブトムシとであった、大木のそばをよこぎって、谷間にでた。
ジョイジョイが、流れの向こうがわの斜面にたっている、ぼろぼろのほたって小屋を、ゆびさしていった。
「あそこが、わたしたちのお家よ!」
ジョイジョイがさけぶと、少女たちは、ウサギのようにすばやく、斜面をかけくだり、川をわたった。そのあとを、5人の男の子たちが、猿のように負けじとかけていく。
家につくと、だれよりもさきに、訪問者をむかえにでたのは、ばあちゃんだった。
ばあちゃんは、杖をつきながら、興奮したようすで、まっすぐに浮浪者にちかよると、手をにぎりしめた。まるでずっと前から、親しかったように。
「よう、来てくださった。ほんとうに、よう、来てくださった。」
家のなかから、母さんと、赤ちゃんを背負った、インダイ姉ちゃんがでてきた。
母さんは、たくさんの訪問者を見て、少しおどろいたようすだった。
ギンギンたちは、母さんのもとにかけよるといった。
「おきゃくさんよ。アオコイ酋長のパパ・トモさんと、こちらはおくさんのママ・エープリル。わたしたちを、学校にいかせてくれるって!」
母さんは、興奮したようすでいった。
「ぞんじています。ぞんじていますよ。
娘たちを、学校にいかせてくださるって、ほんとうですか!
おねがいできたら、どんなによいかって、前からわたし・・・。」
そういったきり、母さんは、言葉につまって涙をふいた。
ばあちゃんも、大喜びでいった。
「よかった、よかった。これで、いつでも安心して、あの世にいけるというもんじゃ。
それにしても、一つ気がかりなのは、十四歳で結婚して、山に住んでいる長女のことじゃが・・・。」
ギンギンが、ハッとしていった。
「わたし、姉ちゃんにあったよ。」
「わたしも。」
「わたしもよ。」
クリスティンとジョイジョイがいった。
ママ・エープリルが、たずねた。
「娘さんは、どこの村に、住んでいるのですか?」
「アポイ集落です。」
「えっ。それはたいへん!」
ママ・エープリルは、いっしゅん絶句するといった。
「あそこで、政府軍と反政府軍の戦いがはじまったっていう、情報が入っているわ!」
「そうよ。森で、鉄砲の音がしたもん。」と、ジョイジョイがいった。
「なんで、そんなことわかるの。」母さんがいった。
ギンギンたちは、だまってしまった。
すると、パパ・トモがいった。
「アポイ集落の人たちは、下のボアイボアイ村に、緊急避難したときいています。しかし、住む家も食べるものもない。着のみ着のまま、大あわてで逃げてきたようだ。」
それをきいて母さんが、泣きだしそうな顔をしていった。
「わたしの長女も赤ちゃんも、だいじょうぶかしら!」
動揺している、母さんのようすを見て、ママ・エープリルが口をはさんだ。
「お母さん、おばあちゃん。じつは明日、わたしたちは、子どもたちといっしょに、ボアイボアイ村にいくんです。戦争で逃げてきた、避難民の人たちを助けに。」
ママ・エープリルは、山菜売りの少女と、ストリートチルドレンたちのほうを見ていった。
「あなたたちも、明日いっしょにいって、避難民を助けるお手つだいを、してくれない?姉さんにも会えるだろうし、勇気のある男の子たちもいっしょなら、心強いし。」
それをきいて、山菜売りの少女たちも、ストリートチルドレンたちも大喜びだ。
ばあちゃんはいった。
「どうか、孫娘を助けてやってください。おねがいします。」
母さんは、ギンギンたちのほうを見るといった。
「あなたたち、明日から、ミンダナオ子ども図書館にすみなさい。」
それをきいて、パパ・トモが口をはさんだ。
「もうこうなったら、みなさん全員、うちに住んだらどうですか。
山菜売りで家計を助けてくれている、娘さんたちがいなくなったら、みなさん、食べていくのもたいへんでしょう。
小さな家なら、わたしたちで建ててあげますよ。」
それを聞いて、ママ・エープリルが、うなづきながらいった。
「それは、良い考えね。
ちょうど、子どもたちが食事をつくるときに、めんどうを見てくれる、台所のスタッフが必要だから、お母さん、あなたがなってくれたら、よいのだけど。」
おもわぬさそいに、母さんは、ぼんやりして言葉がでない。ばあちゃんは、そばにいた浮浪者に抱きついて、大喜びしている。
ギンギンたちは、ストリートチルドレンたちといっしょに、家にある、わずかな古着やお鍋をはこびだして、車にのせた。
子どもたちも浮浪者といっしょに、荷台に飛びのった。
「しゅっぱーーつ!」
車が走りはじめると、子どもたちはうれしさのあまり、大声で荷台で歌った。
ミンダナオ子ども図書館につくと、車は門の前でいったん止まった。すると、浮浪者が、荷台からとびおりた。
ギンギンは、浮浪者がおばあちゃんに、車の外から話しかけているのを耳にした。
「近いうちに、大岩で会おう。」
そういって浮浪者は、一人でわきの小道にはいると、大岩のほうへと、去っていった。
おばあちゃんは、いつまでもその後ろ姿を、見おくっていた。











第五章、避難民救済
1,ボアイボアイ村をめざして 2,村についた 3,姉ちゃん
4,読み語り 5,ギンギンの昔語り
1,ボアイボアイ村をめざして
よく日、子どもたちは、朝の4時半に起て、マキを使って、かまどでごはんをたきはじめた。
よこで寝ていたジサにつつかれて、ギンギンも目をさました。ギンギンは、ジサにつれられて、竹壁の寝室をでると、二階のポーチに立った。
「わーっ、あれアポ山ね!」
ギンギンは、カブトムシにみちびかれて、空からアポ山を見たことをおもいだして、となりにいるジサにいった。
「あの山の向こうには、海が広がっているのよ。」
「わたし、まだ海見たことないな・・・。」
「わたしも、いったことはないの。でも、カブトムシさんが・・・。」
そういったとたん、ギンギンはだまってしまった。
空を飛んだ話、信じてくれるかなあ・・・。
ギンギンは、ジサと手をつなぐと、ポーチから下の台所におりていった。山にいくための、お弁当をつくるためだ。
すでにテーブルには、大きなお釜に、たきたてのごはんと、煮こんだ鶏肉がおいてあった。そのよこには、バナナの葉っぱ。
「このバナナの葉っぱ、何に使うの?」
ギンギンがたずねると、ジサがいった。
「これはね、夜明け前に、男の子たちが、庭でつんできたの。お弁当箱の、かわりにするのよ。」
「お弁当箱?」
「そう、バナナの葉っぱを、手ぬぐいぐらいの大きさに切ってね、その上に、ごはんをよそうのよ。そして、熱々のごはんに、煮こんだ鶏肉をおいて、くるっと丸めてつつんだら、できあがり。
パアテルといってね、イスラムの伝統料理なの。バナナの葉っぱの香りもただよって、おいしいよ。」
そういうとジサは、ハサミでバナナの葉っぱを、切りはじめた。
「アッチチー。」
ごはんは、たきたてだから、ごわごわしたバナナの葉っぱの下からさわっても、けっこう熱い。その上に、煮こんだ鶏肉をおいて、ぎゅっとつつむと、できあがり!
ほかの子どもたちも、起だしてきて、ポーチや玄関や庭を、ホウキではいて、朝の掃除をはじめている。トイレの掃除をしている子もいる。畑にでて、植えてあるインゲン豆や、トマトの世話をしている子もいる。
カンカン、カンカン!
鐘の音が、ポーチから響いてきた。
「朝食の準備が、できたしらせよ。」
鐘の音をきいて、あちらこちらから、子どもたちが集まってきた。
子どもたちは、食堂に入ると、テーブルにずらーっとならんですわった。
「さあ、みんなでお祈りをしましょう。今日はだれかな?」ママ・エープリルがいった。
ジサが、ギンギンにささやいた。
「いつも、お祈りしてから食べるのよ。毎日一人ずつ、順番にするの。」
ノルミアがいった。
「イスラムの子は、アラビア語でアッラーのお祈り。マノボ族の子は、マノボ語でモナマ(神さま)のお祈り。クリスチャンの子は、イエスのお祈り。
そして、最後にみんなで、いっしょのお祈りをしてから、いただきまーーーす。」
お皿には、小さな魚と野菜がのっている。一日に、三回もごはんが食べられるなんで、夢みたい!
朝食がおわると、自分たちのお皿は、パパ・トモもママ・エープリルも、ふたりの娘のアイカとマイカも、ほかの子たちといっしょに自分で洗うと、そのあとは、当番の子たちが仕上げをして、食器だなにいれた。
ボアイボアイ村にいくために、えらばれた子どもたちは、トラックのところに集まりはじめた。大きなトラックが一台と、小型の4輪駆動のトラックが一台、門のそばにならんでいる。
荷台には、山のように支援物資がつまれて、すでに数人の子どもたちが、荷台の上からさけんでいる。
「いくよーー!」
「はやくのってーー!」
ギンギンとジサは、お弁当のたくさん入った袋を、ストリートチルドレンたちと、手わけをしてかつぐと、車のほうへとはこんでいった。
子どもたちは、大きなトラックの荷台にのりこんだ。
「しゅっぱーつ!」
2,村についた
ボアイボアイ村は、とっても遠い。
でも、みんなでトラックの荷台にのって、大きな声で歌っていくからたのしい!
道いく人も、笑顔でわたしたちのほうを見て、手をふってくれる。
田畑の広がる平野をぬけ、谷をわたり、尾根をいくつもよこぎっていくと、やがて峠の向こうに、アポ山が見えてきた。
「わーっ、アポ山!」
ジョイジョイが、興奮してさけんだ。
道は、しだいに、山のふかくへと入っていった。
高い木々と、巨大なシダの生いしげった、ジャングルをぬけ、水しぶきをあげて流れている川を、車にのったまま、ジャブジャブとわたった。
「ほんとうに、こんなところ通れるの?」
クリスティンが、ビックリして、姉さんの手をにぎっていった。
集落をぬけるときは、道ばたであそんでいた子どもたちがよってきて、手をふってさけんだ。
「わーーい、ミンダナオ子ども図書館がきたよ!」
「わたしたち、いろいろな村で、読み語りをしたり、医療をしたり、奨学生をとったり、保育所を作ってあげたりしているから、村人や子どもたちも、わたしたちの事をしっているのよ。」と、ジサがいった。
「ときには、はじめていく村でも、口コミで噂話がつたわっていてね、わたしたちが入っていくと、大人も子どももかけよってきて、手をふってくれるのよ。『ミンダナオ子ども図書館が、この村にもやってきたぞ。ばんざーい!』って。」と、スイーツもいった。
二台の車は、最後の急坂を登りきって、ようやく、ボアイボアイ村にたどりついた。
あちらからも、こちらからも、いっせいに村人たちが、大喜びでかけよってきた。見まわすと、ふだんしずかな小さな村が、大さわぎになっている。
たった今、山からたどりついた若者が、興奮したようすで話しだした。
「この上の山のジャングルでは、今も戦闘がつづいているんだ。はげしい撃ちあいになっている。」
広場を見ると、山から逃げてきた人たちが、とほうにくれて、しゃがみこんでいた。
ほとんどが、マノボ族といわれている、先住民の人たちだ。着のみ着のまま、泥に汚れた服を着て、大人も子どもたちも裸足だ。赤ちゃんを腕に抱いたまま、とほうにくれている母親も、たくさんいる。
パパ・トモがたずねた。
「みなさんは、どこに、寝ていらっしゃるのですか?」
「どこって、道のわきとか、家の軒下とか、大きな木の下とか。」
人々は、当惑したように口々にいった。
「それじゃあ、雨がふったら、たいへんでしょう。」
赤ちゃんをだいた女性たちが、こんわくした顔でいった。
「子どもも、わたしも、ずぶぬれになって・・・。」
「病気になっても、お医者さんにかかったり、薬を買うお金もないし。」
ストリートチルドレンの子たちも、荷台の上から、あぜんとして人々を見おろしている。
「ぼくらも経験あるけど、道ばたに寝るって、たいへんなんだよなあ。」
山仕事をしている父親たちが、怒りをこめていった。
「いつまで避難しなきゃ、ならないのか。森のなかに植えてきたトウモロコシも、このままじゃ全滅だ!」
絶望したように、天に両手をさしだして、さけんだ男もいる。
「まったく、何を家族に、食べさせたらいいんだ!」
3,姉ちゃん
そのとき、トラックの下にいる、赤ちゃんをだいた女性が、上を見てさけんだ。
「ギンギン、クリスティン、ジョイジョイ!」
ギンギンたちは、トラックから身をのりだすと、さけんだ。
「姉ちゃーーーん!」
「あぶない!」
ストリートチルドレンの男の子たちが、ギンギンたちを抱きかかえて、トラックの荷台からおろした。
姉ちゃんは、赤ちゃんをご主人にわたし、妹たちを抱きしめた。目から涙があふれ、頬をぬらした。
ママ・エープリルは、山菜売りの子どもたちに、ちかよるといった。
「ギンギン、クリスティン、ジョイジョイ、よかったね。お姉ちゃんに会えて。」
そのとき、遠くの山のほうから、銃声がきこえた。
パンパンパン!
パン、パパーン!
トラックをかこんでいた人たちは、おもわず頭をさげた。
「だいじょうぶ。ここまで弾は、とんでこないよ。」
「アポイ集落のほうだ。」
「おいてきた山羊たちは、全滅だな。」
頭にバンダナをまいた、男がいった。
「毎年のように、戦闘がおこされて、避難民にさせられて、帰ってみれば、家畜も畑もメチャクチャ。食べるものもなく、とほうにくれていると、『土地を買ってやろう。』という話が、町の金もちからだされるんだ。
べつの男が、うなずいていった。
「失意のどん底に、いるものだから、たいして考えもしないで、田畑を安く手ばなしてしまう。あげくのはてに、おれたち先住民は、自分の土地をうしなって、さらに山の奥にうつるか、町にでて、浮浪者になるしかないんだ。」
パパ・トモが、つぶやいた。
「まるで、アメリカの西部開拓で、居留地をうしっていったアメリカインディアンの運命と、おなじ事が、今でもおこっているんだなあ。」
黒く日焼けした、若者がいった。
「山をおわれて町にでても、出生届もなければ、学校教育もうけていないし、字も読めないおれたちに、仕事をくれるところなんてないしなあ。」
「こがらだし、色も黒いし、髪の毛もチリチリだから、へんな目で見られたりもするわ。」
「あげくのはてには、物乞いになるか、子どもたちは、ストリートチルドレンになるのが、おちなんだ。」
ストリートチルドレンの男の子たちも、首をたてにふって、うなずいている。
杖をもった、老人がいった。
「マノボ族は、昔は、この山の下の平地の、地味も肥えたところで、畑をたがやしたり、川で魚をとったりして、貧しいなりにも、みんなで食べものをわけあって、心は豊かな生活をしていたんだがなあ。」
ママ・エープリルが、トラックの上に立つと、大きな声でいった。
「みなさん。わたしたちができることは、小さな小さな事ですが、ヒナイヒナイ・バスタカヌナイ、ゆっくりゆっくりたえまなく、みなさんとともに、歩んでいきたいとおもいます。水牛みたいにね!」
笑いと拍手が、どうじにおこった。
「そんなわけで、とりあえず今日は、ビニールシートと古着をもってきましたので、うけとってください。」
ワーーーッという、歓声がわきおこった。
「みなさん、トラックの前に、一れつにならんでいただけますか。
ビニールシートは、外で寝なければならない家族の方々が優先です。古着は、たくさんありますから、ボアイボアイの村の方々にも、ゆきわたるとおもいますよ。」
パンパンパン
パン、パパーン
ふたたび、遠くで銃声がした。
銃声のあとに、ドドーン、ドドーンと、お腹をゆするような迫撃砲の音もした。下の村から、大砲を撃ちこんでいるのだ。
イスラム教徒の男の子がいった。
「ぼくたちのところで、起ている戦争にくらべたら、ここの戦闘なんて小さなもんだよ。
ぼくたちのところだと、無人偵察機もとんで爆弾をおとすし、戦車も走りまわるんだ。
2000年から3年間もつづいた戦争のときは、120万人いじょうの避難民だったんだ。ぼくの父さんも母さんも殺されて、一年半いじょうも道ばたで、避難生活をおくったんだよ。」
それをきいた、若者たちの一人がいった。
「戦争は、いやだなあ。」
すると、ママ・エープリルがいった。
「ビニールシートと古着をうけとったら、子どもたちは、向こうの大きな木のところに、いってください。鶏肉の入ったおかゆを、いっしょに食べましょう。木の下で、読み語りもしますよ。そのあと、古着をくばります。」
子どもたちが、歓声をあげた。
パンパンパンという銃声と、ドドーンドンという大砲の音が、遠くからきこえてきた。
けれども、だれもふりむきもしなかった。
4,読み語り
トラックのそばで、ビニールシートと古着がくばられているあいだに、広場では、炊きだしがはじまった。
山菜売りの少女たちは、ジサとスイーツと、ストリートチルドレンたちいっしょに、大鍋をもって大木の下にいくと、村人たちがマキをもってやってきて、さしだしていった。
「このマキ、よかったら、使ってください。」
「ありがとう、助かります。」
子どもたちは、マキをつみあげると火をつけた。
ストリートチルドレンたちは、大鍋をもって井戸にゆき、水をいっぱいにしてはこんでくると、マキの上においた。
子どもたちは、そのなかに、といだ米を注ぎこんだ。
お鍋は、たちまちぐつぐつ煮え、煮たつと、切りきざんだ鶏肉をいれてふたをした。よいかおりが、まわりにただよいはめた。
「うまそーう!」と、さけんで、ストリートチルドレンたちは、よだれをたらし、鼻をくんくんさせながら踊りだした。
それを見て、ギンギンがいった。
「でも、食べちゃだめよ。戦争で逃げてきた、子どもたちのためだからね。
あなたたちのためには、ちゃんと、バナナの葉でつつんだパアテルを、つくってもってきているんだからね。」
スイーツが、ことばをついだ。
「おねがい、トラックからビニールシートをもってきて、木かげに広げてちょうだい。子どもたちが、すわって食べられるようにしてあげたいの。」
「オッケー!」
「レッツ、ゴー!」
ハロスカルドとよばれている、鶏のお粥ができあがると、お鍋がたき火からおろされて、ギンギンとジサとスイーツは、お粥をお皿によそって、つぎつぎに子どもたちにさしだした。
子どもたちは大喜びで、ハロスカルドをうけとると、シートにかけていき、すわって食べはめた。
「わー、おいしい!」
「ひさしぶりの、お米だね!」
「鶏の肉なんて、クリスマスのときにしか、食べられないもんね!」
子どもたちは、むちゅうでほおばっている。
「なぜ、お米を、そのままわたさないの?」と、ギンギンがジサにたずねると、ジサが耳もとでささやいた。
「そのまま、お米をわたすとね、子どもたちに食べさせないで、どっかに売られたりして、なくなっちゃうことが多いのよ。
だから、わざわざ炊きだしをして、その場で子どもたちに、食べさせてあげるわけ。ちゃんと子どもたちの、お腹に入るようにね。」
スイーツが、お粥をほおばっている、子どもたちの前に立つと、よく通る声でいった。
「ねえみんな!
食べながらでも、よいからきいてね。これからここで、わたしたちが、絵本の読み語りをはじめます。」
「わーーーーっ!」
子どもたちの歓声が、村にひびいた。
「わたしは、マノボ族のスイーツです。
こちらが、イスラム教徒のノルミアさん。
そして、こっちが、クリスチャンのジサさん。
さあみんな、最初に、歌って踊りましょう!」
すると、ギターを抱えたドドンくんが、勢いよく演奏を開始した。それにあわせて、ミンダナオ子ども図書館の子どもたちが、声をそろえて、歌って踊りはじめた。
ロラロラ ローラ ロラロラレ!
ロラ ローラローラ ロラロラレ ヘイ!
すると、村の子どもたちも立ちあがり、見よう見まねで歌って踊った。
ロラロラ ローラ ロラロラレ!
ロラ ローラローラ ロラロラレ ヘイ!
子どもたちの元気で明るい歌声で、くらい気もちだった避難民の人たちも、光が闇をふきとばすように明るくなり、希望が見えてきたような気もちになった。
歌と踊りが終わると、さいしょにスイーツが前にでて、絵本の読み語りをはじめた。
子どもたちは、目を輝かせ、真剣に耳をかたむけている。
それが終わると、イスラム教徒のノルミアが、お話をした。子どもたちは、むちゅうで耳をかたむけている。
5,ギンギンの昔語り
読み語りも終わりに近づいたとき、ジサが、子どもたちにいった。
「最後のお話しは、わたしのとなりにたっている、ギンギンさんが、語ります。」
とつぜんの紹介に、ギンギンは、ビックリして、まっ赤になった。
「わたし、絵本なんて見たこともないし、読んだこともないし・・・。」
するとジサが、耳もとでささやいた。
「絵本なんか、なくてもよいの。
あなた、おばあちゃんからきいた、昔話しっているでしょ。それを、語ってあげたらよいのよ。」
ギンギンは、当惑したけれども、そういわれてみれば、おばあちゃんからきいた昔話なら、たくさんしっている。
そこで、ギンギンは、みなの前にすわるといった。
「これはね、わたしが、おばあちゃんからきいた、お話です。大きな大きな木のなかから、たくさんの妖精さんたちといっしょに、白い女がでてきた、不思議なふしぎな物語。」
そういうと、ギンギンは、山菜つみでいった、沼のほとりに立つ、大木にまつわる話を、子どもたちに語りはじめた。
子どもたちは、むちゅうになってききいっている。
話し終わると、大歓声がおこった。
「その話、きいたことある!」と、さけんだ子もいた。
するとギンギンの耳に、大木の上のほうから、声がきこえてきた。
「お話しにでてきた、沼のほとりの大木って、ぼくのひいおじいちゃんのことだよ。」
「えっ!」
ギンギンはびっくりして、背後にたっている、大木のこずえを見あげた。
「不思議だなあ、大きな木が、しゃべったのかなあ?」
読み語りが終わったあと、子どもたちが、地元の子どもたちに、きれいな布袋に入った、古着をわたしはじめた。
古着といっしょに、袋のなかから、ぬいぐるみやおもちゃがでてきたときには、歓声があがった。見まもっている親たちも、満面笑顔をうかべて、子どもたちといっしょに、袋のなかをのぞいている。
子どもたちを前にして、ジサがいった。
「これはね、日本の仏教徒の子どもたちから送られてきた、贈り物なのよ。子どもたちは、一日一食たべないで、お金をためて、プレゼントを買って、送ってくれたのよ。」
それをきいて、一人の子がこたえた。
「ぼくも、ときどき学校に、お弁当もってこられないときあるよ。そんなときは、お昼ごはんがない、べつの子たちといっしょに、大声で校庭であそぶんだ。
お腹がすいたことを、忘れるためにね。」
ストリートチルドレンの男の子たちは、山の子どもたちに、袋を手わたしながら話している。
「なんだか、不思議な気もちだな。
ぼくら、つい数日前まで、道ばたで物乞いしていたのに、今はこうやって、お腹をすかせた子どもたちに、お粥を食べさせてあげたり、贈り物をわたしてあげたりしているなんて。」
「でもたのしいね。だって、子どもたち、とってもとってもうれしそうだもん。」
「あの笑顔を見ただけで、なんだか心が、救われるような気がするな!」
それをきいて、スイーツとジサがいった。
「そういえば、日本からきた、仏教徒の子どもたちも、おなじ事をいっていたわ。救ってあげることで、自分が救われていく感じがするって。」
「仏教では、もっている人が、もたない人にひざまずいて、供物をさしだすんだって。『私欲を捨てますから、わたしを救ってくださいな。』って。」
ストリートチルドレンの、大がらな子がいった。
「なんでも、ひとり占めするんじゃなくって、ある人はない人とわけあって、みんなで生きていくことが、大切なんだよね。」
よこできいていた、イスラム教徒のノルミアがいった。
「それって、イスラムの教えと、まったくおなじ!」
スイーツがこたえた。
「わたしたちマノボ族も、土地も家もお米も作物も、自分のものじゃなくって、神さまがつくってくれたものだから、みなでわけあって感謝して、お祈りしてから、いただいていたんだよ。」
ジサがいった。
「貧しい人ほど、食べさせてもらえるありがたさを、心から感じて、おたがいに助けあうことができるもんね。
聖書にも書かれてあるよ、『貧しい人は、幸いである、天国は彼らのものである。』って。」

















第六章:いそいで病院へ
1,お腹を撃たれた少女 2,病院にむかって 3,手術室へ
4,手術がおわった 5,二つの歓迎会
1,お腹を撃たれた少女
そのとき!
パンパンパン
パン、パパーン
ふたたび遠くで銃声がして、「おーい、助けてくれ!」と、助けをもとめる叫び声が、きこえてきた。
見ると山の上のほうから、少女を背なかにおぶった父親が、お腹をおさえながら歩く妻を、ひっしに肩でささえながら、山道をおりてくるのが見えた。
村はおおさわぎになり、ストリートチルドレンの男の子たちは、村の男たちといっしょに、きゅうな斜面をかけのぼっていくと、ふらつきながら歩いている母親をささえた。
パパ・トモとママ・エープリルは、傷をおった少女と、母親のもとにかけよると、たずねた。
「どうしたんですか?」
少女をおぶっている、父親がいった。
「撃たれたんだ。鉄砲で撃たれたんだ。このままでは、娘と妻は、死んでしまう!」
母親が、お腹をおさえながら、よわよわしい声でいった。
「村で戦闘がおこって、娘が、さいしょに逃げようと、家から外にでたとたん、パーーーンと銃声がして、娘が『キャーッ!』とさけんで、しゃがみこんだんです。
そして、わたしが、あわっててかけよったとき、また、パンパンと銃声がして、こんどは、わたしのお腹に・・・。」
そういうと、母親は、言葉につまって泣きだした。
そんな妻を見かねて、少女をおぶったまま、夫が言葉をついだ。
「おどろいて、わたしも家から飛びだすと、妻と娘は、お腹をかかえて泣いている。よく見ると、なんと、銃弾があたっていたんです!
わたしは、荷物も家畜も、ほったらかしにして、すぐに娘を背なかにかつぐと、妻の手をわたしの首にかけて、ここまで・・・。」
その傷あとを見ると、パパ・トモがいった。
「これは、ひどい!
早く病院に、つれていかなくっちゃ。このままでは、娘さんは死んでしまう。」
すると、父親がさけんだ。
「病院ですって!
薬を買うお金さえないのに、どうやって医者に、診てもらえばいいんだ!」
すると、ママ・エープリルが、すかさずいった。
「ミンダナオ子ども図書館では、医療支援もしているんです。だいじょうぶ、薬から手術まで、わたしたちが、すべて責任をもちますよ。」
「いそいで。わたしたちの車に、のってください。」
パパ・トモがいうと、ストリートチルドレンたちが、お母さんをささえ、ジサとスイーツが、娘をおぶった父親の手をひっぱって、車まであんないした。
ギンギンも、あとについていった。
車までくると、パパ・トモは、少女と両親をうしろの座席にのせた。
ママ・エープリルは、子どもたちにいった。
「あなたたちは、ここに残って、スタッフといっしょに、あとかたづけを、てつだってちょうだいね。」
子どもたちは、さけんだ。
「わかった。ちゃんとやるから、だいじょうぶ!」
すると、ママ・エープリルは、ジサとスイーツにいった。
「これからまっすぐに、病院にいくけれども、あなたたち、いっしょにきてくれない?女の子の、お世話をしてあげてほしいの。患者さんにつきそった、経験があるから、わかるわよね。」
「ハーイ!」と、ジサとスイーツはさけんで、車の荷台にとびのった。
ママ・エープリルは、助手席にのりこんだものの、友だちがいってしまうので、さびしそうな顔をしてたっている、ギンギンにきがついて、窓ガラスをあけるといった。
「ギンギン。あなたもいっしょにきて、お手伝いしてくれる?」
ギンギンは、ビックリしたけれども、「ハイ!」と、答えると、ジサとスイーツに手をひっぱられて、車の荷台にとびのった。
「しゅっぱーつ!」
ジサがさけぶと、パパ・トモは、みずから車のハンドルをにぎって、エンジンをふかして走りだした。
クリスティンとジョイジョイ、そしてストリートチルドレンの男の子たちは、スタッフとほかの子どもたちといっしょに、「どうか無事でありますように。」と、お祈りしながら見おくった。
「この世に、戦争が無ければ良いのに。」
2,病院にむかって
パパ・トモの運転する車は、きゅうな山道をかけくだり、ジャングルをぬけ、石ころだらけの川をじゃぶじゃぶよこぎると、まっしぐらに町にむかってはしった。
うしろの荷台には、ジサとスイーツのあいだにギンギンがのって、イスのかわりにおかれた古タイヤに、こしかけていた。
「ギンギン、しっかりとロープにつかまって!」と、ジサがいった。
ゆれる車から落っこちないように、三人は、目のまえにはられているロープを、しっかりとにぎりしめていた。
それでも、川をわたったり、大きな石をふみこえるときには、車はひどくかたむいた。ときには、ポンととびはねて、おしりがくうちゅうにはねあがった。でもだいじょうぶ。しっかりロープにつかまっているし、ゴムでできた古タイヤは、やわらかいから痛くないよ。
「これから、まっしぐらに、病院にいくのよ。」と、スイーツがいった。
「病院のなまえはね。メディカル・スペシャリストっていうの。お医者さまが、たくさんいらしてね。内科も小児科も外科も、みんなそろっているの。」
「レントゲンもあって、手術もできるわよ。わたしも、そこで眼の手術をしてもらったの。」と、ジサが、ことばをついだ。そして、思いだしたように話し始めた。
「そして、手術がおわって、ベッドに寝かされているときに、ママ・エープリルが、話しかけてきたの。
『あなたのお父さんは、病気で亡くなられたのよね。だからお母さんが、いっしょうけんめいに、道ばたの台に、シンカマス(砂糖ダイコン)をならべて、売っているのね。
でも、家族が食べるだけでもたいへで、あなたを学校にもいかせてやれないって、いってたわ。』
わたしは、うなずいたの。そしたらね、ママ・エープリルが、こういってくれたの。
『もしあなたさえよかったら、ミンダナオ子ども図書館にすんで、学校にいったらどう?がんばれば、大学までいけるわよ。』
もうびっくり!わたしさけんだわ。
『学校にいきたい。大学を卒業して、家族を助けたい!』」
ギンギンは、町でジサのお母さんが、話してくれたことを思いだした。
するとこんどは、スイーツが話しだした。
「イスラムの子たちも、大変なのよ。
戦争があってね、お父さんとお母さんが撃たれて死んで、自分もお腹を撃たれた男の子もいる。
『ミンダナオ子ども図書館が、ぼくを、病院につれていってくれなかったら、ぼくは、死んでた…。』って、いってたわ。でも、だんだんお腹がふくれてきてね、手術したんだけれど、亡くなった子もいる。」
すると、ジャングルのなかから、不思議な声が聞こえてきた。
「爆弾のなかに、劣化ウランというへんなものが、混じっているんだ。それが、奇形をつくるんだよ。」
子どもたちは、ビックリしてジャングルを見まわしたけれど、だれもいない。
ギンギンは、つぶやいた。
「戦争って、いやね。イスラムの子たちもかわいそう。わたしたちもそうだけれど、貧しいと病気をなおせないもんね。熱がでても、薬も買えない。
わたしたちの村では、マナナンバルという人がいて、病気になると来てもらって、お祈りしてもらうのがやっと。
薬といえば、野原や山に生えている草を煎じて、飲むぐらいがせいぜいよね。病院にいくなんて、夢のまた夢。」
3,手術室へ
車が病院につくと、緊急病棟の入り口がひらき、なかから看護婦さんたちが、移動ベッドをひっぱりながら、飛びだしてきた。
助手席の扉がひらき、ママ・エープリルが車からおりると、うしろの荷台にのっている、わたしたちに向かっていった。
「みんな、車からおりて、手つだってちょうだい。子どもとお母さんを、移動ベッドに寝かせてあげなくっちゃ。」
わたしたちは、荷台から飛びおりると、うしろの座席の扉をあけた。
看護婦さんたちが、よってきて、お父さんのひざによりかかって寝ている少女を、ゆっくりと外にはこびだして、移動ベッドにねかせた。少女は、目を開くと、痛そうに顔をしかめながら、不思議そうにあたりをみまわした。
つぎにわたしたちは、反対側のドアにかけよって、扉を開いた。なかには、お腹を撃たれたお母さんが、お父さんの肩によりかかって、座っていた。
べつの看護婦さんたちが、もう一台の移動ベッドを、ドアの横につけると、お父さんもてつだって、注意ぶかくお母さんを車の外にだすと、ベッドのうえに寝かせた。
お母さんは、寝かせられると、必死に娘のほうをみやった。
ママ・エープリルがいった。
「だいじょうぶですよ、お母さん。すぐに、娘さんを手術室に運びますから。あなたも、手術しなければなりません。あまり、動かないでね。」
お母さんは、ママ・エープリルのほうに、顔をむけるといった。
「ほんとうに、ほんとうに、どう感謝してよいやら。あなたがたが、助けてくださらなかったら、娘もわたしも、今ごろは・・・。」
そういうと、母親の目から、涙がドッとあふれだしてきた。
わたしたちは、看護婦さんから、シーツを受けとると、少女の体にかけてあげた。少女が、ニッコリとほほえんだ。
ギンギンは、おもった。
「なんて可愛い笑顔だろう。こんな笑顔で、ほほえまれたら、とっても幸せ!
わたし、将来、看護婦さんになろうかな・・・。」
白いシーツをかけられると、少女と母親は、移動ベッドにねたまま、緊急病棟の入り口から、なかにはいっていった。わたしたちも、ママ・エープリルにくっついて、後につづいた。
ギンギンにとって、病院のなかに入るのは、はじめての経験だった。緊急病棟には、いくつも寝台がおかれていて、治療をまっている人たちと、その家族たちがいた。
「まずは、この女の子の命を、救わなくては!
ここで着がえさせているひまはないわね。レントゲン室のほうに、つれていってちょうだい。すぐにレントゲンと、CTスキャンを受けさせるのよ。終わったら、まっすぐに手術室に運んでね。」
看護婦さんの一人が、ほかの看護婦さんたちに、指示をだすのをみて、ジサがいった。
「あのひとが、婦長さんよ。わたしが目を手術したときも、あのひとが、指示をだしてくださったの。」
少女をのせた移動ベッドは、待合室をとおりぬけ、まっしぐらにレントゲン室へと運ばれていった。
レントゲン室のドアがひらかれて、少女を、なかに入れようとしたとき、少女は、ギンギンのほうを見て、両手をさしのべた。
「ひとりじゃ、こころぼそいのね。」
そういうと、婦長さんは、わたしたちの方をふりむいた。そして、ジサを見て、驚いていった。
「あらあなた、ここで目の手術をした、ジサちゃんじゃない?」
ジサは、うなずいた。
「そうね、あなたたちも、いっしょに中にはいって、そばにいてあげてくれる?」
わたしたちは、うなずくと、レントゲン室にはいった。
なかは、まっ白なカーテンと、黄色い電気、そして鼻をつくような、不思議な臭いにみちていた。
看護婦さんたちは、ちゅういぶかく、少女の服をぬがすと、寝間着をきせた。
ジサは、血のついた少女の服を、看護婦さんから受けとるといった。
「この服、あとで、わたしたちで洗います。」
「おねがいね。」と、婦長さんは、ほほえんでいった。
ねまきに着がえた少女も、にっこりほほえんだ。
その笑顔をみたとき、おもわず、わたしの口から、言葉が飛びだしてきた。
「わたし、看護婦さんになる!」
すると、よこにいたスイーツのいった。
「わたしも!」
そこにいる、ほかの看護婦さんたちが、笑顔でわたしたちをみていった。
「なったら、いいわよ!」
「ミンダナオ子ども図書館のスカラシップで、大学を卒業して、この病院で、看護婦さんになっている子もいるわよ。」
スイーツは、わたしと顔を見あわせていった。
「わたしたち、がんばって、看護婦さんになろうね!」
わたしたちは、手をとりあうと、しっかりにぎりしめた。
スイーツは、よこにいるジサを見ていった。
「ジサ。あなたは、大きくなったら、何になるの?」
ジサは、わたしたちの耳もとで、そっとささやいた。
「わたしね。目の手術がおわって、右の目が見えるようになったときに、決心したの。
お医者さんに、なるって!」
4,手術がおわった
女の子とお母さんの手術は、午後までつづいた。
娘と妻の手術のあいだじゅう、お父さんは、心配そうな顔をして、手術室の外にあるイスに、じっと一人でこしかけていた。
ママ・エープリルとパパ・トモは、手術が終わったあとに、患者さんがはこばれてくるはずの、病室のベッドのそばにこしかけていた。
わたしたちが、少女と母親の、血のついた服をかかえて、病室にはいっていくと、スイーツがいった。
「わたしたち、これから外で、この服を洗ってきます。」
ママ・エープリルがいった。
「あなたたちだけで、だいじょうぶ?」
「だいじょうぶ。」と、ジサもいった。
「だって、鶏の丸焼きを食べるときだって、生きているのを殺すでしょう。そのとき、血がとびちって、服に血がつくわよね。それ、なんども洗ったことあるもの。」
ギンギンは、そばにいた看護婦さんにたずねた。
「このあたりに、お水のでる場所、ありますか?」
「洗濯機もあるけれど、かわいた血のよごれまでは、なかなかとれないわね。病院のうらに、ふるい井戸があるけれど、そこでやってみる?」
スイーツがいった。
「井戸のほうが、いいな。みんなで、おしゃべりしながら、洗濯するほうが、たのしいもん!」
看護婦さんは、ママ・エープリルとパパ・トモのほうを見るといった。
「おたくのお子さんたちは、ほんとに、しっかりした、いい子たちですね。」
ママ・エープリルがいった。
「ええ。いつも川で洗濯している子たちだから、だいじょうぶ。」
パパ・トモがいった。
「ミンダナオ子ども図書館でも、子どもたちは、まいにち井戸で、洗濯をするんですよ。
わたしは、この町にきた当初のころは、上から目線で、『電気もない、まずしい村に子たちは、かわいそうに、洗濯機なんか、つかったこともないだろうから、便利な文明の理器を使わせたら、感動するんじゃないか。』って、思って、洗濯機も買ったんですよ。使い方も、教えたんです。
けれども、子どもたちは、ぜんぜん使おうとしない。
そこで不思議におもって、聞いてみたら、こんな言葉がかえってきた。
『洗濯機つかって、洗濯したってつまらないよ。みんなで集まって、おしゃべりしながら洗濯するほうが、楽しいもん!』」
それをきいて、ジサがいった。
「そうよ!
みんなで、お話しながら、洗濯するのって、とっても楽しい。いやなことでも、なんでも聞いてもらって、石けんつけてゴシゴシあらって、水にながせば、服もすっきり、心もすっきり。さいごに、水をかぶって、自分を洗濯すれば、心も体も、きれいさっぱり!」
看護婦さんたちは、おおわらいしていった。
「文明が発達して、便利になったからといって、かならずしも幸せとは、かぎらないわよねえ。」
「洗濯物も干さないで、スイッチおすだけで、乾燥までできるなんて、なんだか寂しいのかもね。」
パパ・トモがいった。
「そうですね。
子どもたちがおしゃべりしながら、井戸ばたで洗濯をしている姿を見るのは、楽しいですね。それに、洗ったあと、たっくさんの洗濯物が干されて、そよ風にゆれているのをみると、生活が感じられて、ほっとしますね。」
ママ・エープリルは、おさいふをだすと、ジサにお金をわたしていった。
「これで、石けんをかってちょうだい。残りは、返さなくっていいから、サリサリで、お菓子とジュースをかって、食べたらいいわ。」
「わーーーい!」
外の井戸で洗濯をして、ぬれた服を、干しばにかけおわると、ギンギンとジサとスイーッは、病院のまえの小さなサリサリというお店で、ビスケットとジュースをかってのんだ。
ひと仕事したあとにのむ、ジュースとビスケットはさいこう!
そして、ふたたび病室にもどって、しばらくすると、入り口から、移動ベッドにねかされた、少女と母親が、看護婦さんたちとはいってきた。そのあとからは、白い服をきた男が、少女の父親と話ながらはいってきた。
胸に聴診器をぶらさげた男をみると、パパ・トモとママ・エープリルは、すかさず立ちあがって、その人をむかえた。
「あのひと、ドクターよ。お医者さまなの。」と、ジサがいった。
男の人は、パパ・トモとママ・エープリルをみると、えがおで握手をかわしながらいった。
「手術は、ぶじにすみました。だいじょうぶです。」
「よかった。」パパ・トモがいった。
「いつもいつも、ほんとうに、ありがとうございます。
もう、何人の子どもたちを、助けていただいたことやら。しかも、ご自身の給与を、返上されて・・・。」
お医者さんは、こたえた。
「貧しい子どもたちを、学校にいかせたり、病気をなおしたり、保育所をたてたり。そちらが、なさっていることこそすばらしい。少しでも、おやくにたてればと・・・。」
そういうと、お医者さんは、子どもたちのほうを見ていった。
「看護婦さんたちが、いってたけれど、きみたちも、患者さんのために、いろいろと、つくしてくれたんだってね。えらいなあ。
あれ!あなたは、ジサさんじゃないの?」
ジサは、まっ赤な顔をして、お医者さんのまえに進みでた。
「目の手術をしてくださって、ありがとうございます。」
「そのご、目の調子はどうだね?」
「ええ、すっかりよくなって。見えるようになりました。」
ジサのよこに立っていた、スイーツがいった。
「お医者さま。ジサはね、将来は大学を卒業して、医者になりたいんだって。」
ジサは、まっかな顔をしてうなずいた。
「ほほう。それは、いい考えだね。楽しみにしているよ。
医者の仕事は、たいへんだけれど、ほんとうに人のやくにたつ、いい仕事だと思うよ。」
そういうと、お医者さまは、ジサの頭をなぜた。
スイーツがいった。
「ギンギンとわたしは、看護婦さんになるの!」
看護婦さんたちが、にこにことほほえみながら、うしろから、ギンギンとスイーツをだきしめてくれた。
婦長さんがいった。
「医療は、たいへんなお仕事だけれど、おおぜいの人に、喜んでもらえるから、とってもやりがいがあるお仕事よ。
ぜひ、お医者さまや、看護婦さんに、なってちょうだいね。」
すると、パパ・トモがいった。
「それは、いいことを聞いた。
もう、ずいぶん前から考えていたんだけれど、ミンダナオ子ども図書館に、小さなクリニックを、作りたいと思っているんだよ。
もし、きみたち、大学を卒業して、医師と看護師の免許をとってくれたら、クリニックをはじめよう。貧しくて、医療を受けられない子どもたちは、ただで診察が受けられる、MCLクリニックをね。」
「とっても、楽しみ!」
ママ・エープリルがいった。
「がんばろうね!」
わたしたちは、顔を見あわせて、ニッコリとほほえみあった。
5,二つの歓迎会
わたしたちが、病院から帰ってきた日の夜、ミンダナオ子ども図書館で、歓迎会がひらかれたの。
夕方、二階のポーチに、木の長イスがおかれて、わたしとクリスティン、ジョイジョイと母さん、そしてインダイとビビィがこしかけた。その前には、五人のストリートチルドレンたちが床にすわった。
「おばあちゃんは、どこにいるの?」と、わたしがきくと、母さんがこたえた。
「ちょっと、いくところがあるからっていって、でかけたわ。近くだって、いってたけど・・・。」
前には、おおぜいの子どもたちが、床にすわって、わたしたちのほうを見あげている。
元気なギターの音がして、全員が立って歌いはじめた。そのとき、わたしは、ポーチの一番はじっこの、手すりのよこにすわって、ふっと夜空を見あげたの。
木々のあいだを、たくさんのホタルさんたちが飛びまわり、遠くにアポ山が、黒いかげになって見えた。アポ山の上からは、まんまるのお月さまが、明るく輝きながら、わたしたちを見おろしていた。
「おばあちゃんは、どこにいったんだろう。」と、わたしは、お月さまを見ながらおもった。
すると、不思議な声がきこえた。
「おばあちゃんは、べつの歓迎会にでているよ。ほら、あそこの大きい岩の所。」
「エッ?お月さまがしゃべったの?」
「・・・・・・。」
わたし、おどろいて、大きな岩のほうを見つめると、ファイアーツリーの下にある岩のまわりに、たくさんのホタルさんたちが、飛びかっているのが見えた。
そして、さらに目をこらしてよーく見ると、色とりどりの服を着た、大ぜいの妖精さんたちが、集まっているのが見えてきたの。
大岩の上には、刺繍がほどこされたズボンをはいて、姿もしぐさもりりしく、かっぷくのよい酋長がたっていた。ひげは長くて、胸までたれている。
その顔を見て、わたし、とってもビックリした。
「あの人、しってる!
ストリートチルドレンたちが、ボスとよんでいた浮浪者だわ。やっぱり、酋長だったんだ。」
すると、不思議な声がきこえてきた。
「そうよ、あれがマオガゴン酋長よ。あなたの亡くなった、おじいちゃん。」
「えっ!」
「そのとなりにいるのが、カンコンとタクワイとパコパコの妖精さんたち。あなたたちが、頭の上のタライにのせて、山からはこんできたのよね。」
マオガゴン酋長は、大岩のうえに立つと、まわりに集まっている、大ぜいの妖精さんたちにむかって、よくとおる声でかたりはじめた。
「みなさん、今日は、神聖な祭りの日です。
ここでこうして、みなさんがたと、つどえることを、わたしは、心からうれしくおもいます。こよいは、おおいに歌い、踊り、語りあかしたいとおもいます。」
まわりから、おおきな拍手がおこった。
拍手がおさまると、マオガゴン酋長はつづけた。
「このとくべつな日に、わたしたちは、あたらしい方を、ここにおむかえできる喜びで、胸がいっぱいです。
あらためて、みなさんにご紹介します。」
そういうと酋長は、したにむかって、りょう手をさしだした。すると、すぐしたにいた、刺繍のはいった黄色い服と、ビーズのかざりをまとった年かさの女が、フワッと、浮いたかとおもうと、大岩のうえまでのぼってきた。
「あっ、おばあちゃん!」
わたしは、ビックリした。
おばあちゃんは、岩の上に立つと、妖精さんたちを見おろしていった。
「ようやく、こちらに、くることができました。
ほんとうに、感謝の心でいっぱいです。この気もちを、どうあらわしたらよいのか、わかりません。」
おばあちゃんは、カンコンとタクワイとパコパコの、妖精さんたちの肩をだきながら、つづけた。
「みなさん。そして何よりも、最後には、浮浪者の姿にまでなって、孫娘たちをみちびいてくださった、マオンガゴン酋長さま。
みなさまがたのおかげで、貧しく父親のいない孫娘たちも、ねんがんの学校に、ゆくことができることになりました。
くわえて、アポイ村で、戦争にまきこまれていた、長女たちまで、すくってくださって、感謝の言葉も・・・。」
そこまでいうと、おばあちゃんは、言葉につまり、目からは涙があふれだした。
マオンガゴン酋長は、それをきくと、ギンギンのおばあちゃんに近づき、よりそって、しっかり抱くといった。
「わたしのいとしい妻よ。こここそが、あなたのふる里です。さあ、息子よ、のぼってきなさい!」
すると、岩の下から、一人の男が、ふわっとうかびあがって、大岩の上にたった。
おばあちゃんは、びっくりしてさけんだ。
「わたしの息子!」
わたしも、さけんだ。
「あっ、お父さん!」
ギンギンの死んだお父さんと、おじいちゃんであるマオガゴン酋長と、おばあちゃんが、大岩の上で、しっかりと抱きあっていた。
大岩のまわりに集まってきた、大ぜいの妖精たちはさけんだ。
「妖精の世界に、ようこそ!」
「わたしたちのファミリーに、ようこそ!」
とつぜん、わたしの耳に、ジョイジョイの声がきこえてきた。
「姉ちゃん、姉ちゃん。どうしたの?
なんで、大岩のほうばっかり見て、ぶつぶつ、いっているの?」
「エッ!」
おもわず目が覚めたように、前を見ると、たくさんの子どもたちが、ビックリした顔をして、わたしを見つめている。すかさず、クリスティンが、みんなの前で、わたしを紹介してくれた。
「これが、わたしのお姉ちゃんの、ギンギンです。どうぞ、よろしく。」
それに答えて、子どもたちは、いっせいにさけんだ。
「MCLファミリーに、ようこそ!」
そして、立ちあがると、いっせいにかけよってきて、抱きしめてくれた。
山菜売りの少女たちは、ストリートチルドレンたちと、目くばせしていった。
「ここにきて、よかったね!」