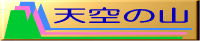無用?な道具たち
このコーナーでは、「えっ?そんなものもってくの?」というものから、
「普通は持って行く事になっているけど使った事ない」というものまで、
山では見かけないものや、あまり使用頻度が高くないものを中心に紹介します。
→見かけるけど使わない…もの
→見かけないけど使える!もの
地図
ガイドブックなどの山行道具一覧表には必ず入っている必須アイテム。
しかし、奥多摩や、奥秩父くらいの山道や指導標がしっかり整備された山では、あまり使ったことがありません。
南アルプスに行った時は、さすがに現在高度や残りの行程を知ったりするのに使いました。
ちなみに、本格的な山行では、国土地理院の五万分の一地形図を使うのでしょうが、
僕はもっぱら、ルートラインとコースタイムが記載された、昭文社の『山と高原地図』を使っています。
コンパス
これもまた山の必須アイテムでしょう。しかし、こちらは地図以上に使った経験がありません。
(tanaが歩くような、指導標がしっかり整備された山では使わない人がほとんどではないでしょうか。)
山座同定の為の方角確認に何回か使っただけでしょうか。
なので、本物(?)の登山用コンパスではなく、どこぞで拾ってきた、
キーホルダータイプのちっこいやつをウエストポーチにつけているだけです。
手笛
遭難時に鳴らして危険を知らせるために、常に持つように昔から言われ続けているものです。
が、しかし僕が持っているのは、プラ製の軽いものではなく、金属製の結構しっかりしたものです。それというのも…、
鉄道の駅員が警笛用に持っているあれです。ちなみに会社から支給された訳ではありません。
今まで一度だけ使いかけました(自分が遭難しかけたわけではなく、同行の友人が行方不明に…。その後無事発見。)。
しかし、実際に使ったことはありません。
これからも使わないでいることを願う道具です。
 塩
塩
決して調理が主目的ではありません。
というのは、僕は足に攣り癖(つりぐせ)があり、ちょっと無理すると、すぐに太股やら足首やらが攣ってしまいます。
それで山岳部時代に、顧問である生物先生に相談したところ、
・低温
・電解質(簡単に言えばナトリウムやカリウムなど)の不足
の2つが、足の攣りの原因だ、と教えていただきました。
それ以来、山行の度にコショウのビンに入れた塩を、大休止ごとになめるようになりました。
もちろん味のしない朝食のおかゆの友にもなれる大変なすぐれものです。
ちなみに、はじめはフィルムケースに入れて持って行っていましたが、
一度蓋が外れて、ザックの天蓋の中が真っ白になってしまったので、
今では、蓋がネジ式で簡単には外れない、コショウが入っていたガラスビンに入れて持って行っています。
 小型合図燈(通称:電気カンテラ)
小型合図燈(通称:電気カンテラ)
駅員がホームが暗い時間帯に、車掌に合図を送る為に持っているあの大きな合図燈です。
なお、別に鉄道係員の立場を悪用して、不正に入手したわけではありません。
(もしそんな後ろめたい事情があるものだったら、こんな所で紹介しません。)
この合図燈が普通のヘッドランプより優れているのは、
- 光量が強い
(電球は普通の豆電球ですが、電球の周りに反射鏡とレンズがあるので、光がかなり強いです)、
- 普通の白色以外に赤、青の光がスイッチひとつで出せる(緊急時の合図用に?)、
- 大きな持ち手がついている(どこかに引っ掛けるのには便利)
といったところですが、一方のデメリットは、
というのがダントツです。
それでも、くだらない僕は、毎度毎度懲りずに山に持っていくのでした。
 大気圧・高度計
大気圧・高度計
一般にアネロイド大気圧計と呼ばれるものです(写真は外にカバーがかかっています)。
標高の分かっているところで、外側の高度リングをで現在気圧と合わせておけば、その後よほど大きな気圧の変化がない限り、おおむね正確な高度が分かります。
地図とこの高度計を併用する事によって、現在位置を特定する事が容易になります。
ではなぜ併用するはずの地図が、『使わない…もの』に分類されていて、高度計が『使える!もの』に分類されているか、というと、それは、山頂の標高と現在高度の比較だけで『あと、○○mくらいだ〜』などと自分の目安にする事が多いからです。
地図を広げる事なく手っ取り早く、残りの高低差を素早く推定する事が出来るので、結構重宝しています。
![[天空の山]のTopへ戻る](../top.gif)
![[撮影♪な道具たち]へ進む](../next.gif)
![[有用!な道具たち]へ戻る](../back.gif)
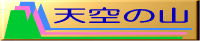 このページは、[天空の山]の分室です。
このページは、[天空の山]の分室です。
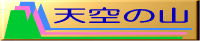

 塩
塩 小型合図燈(通称:電気カンテラ)
小型合図燈(通称:電気カンテラ) 大気圧・高度計
大気圧・高度計![[天空の山]のTopへ戻る](../top.gif)
![[撮影♪な道具たち]へ進む](../next.gif)
![[有用!な道具たち]へ戻る](../back.gif)