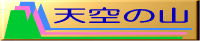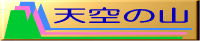
このページは、[天空の山]の分室です。

それは学園祭も近づいた、ある日のことだった。
珍しく、薔薇の館で志摩子と二人きりになった。
紅薔薇ファミリーも、黄薔薇ファミリーも、
たまたま用事が重なったらしく、ついさっきまで
この場にいた祥子も、「お先に…」といって帰ってしまった。
志摩子とこの部屋で二人きりになるなんて、
なんて久しぶりのことだろう。
まだ、志摩子が私の妹になる前以来かな。
そんなことを窓際に立って考えていたら、
志摩子が、両手を組んで、少し俯き加減で私のほうに歩み寄ってきた。
いつもと違う志摩子の態度に、私は、首をかしげた。
「お話したいことがあるのですが…」
「話?いいわよ。なに?」
「いえ、ここではなく、外でお話させていただきたいのですが」
「ふーん、外ね。じゃぁ、行きましょうか!」
なにを話されるかはわからないが、
志摩子の雰囲気から、何か真面目なことだと察しがついた。
私まで真剣になってしまったら、話しにくいだろうと、
いつもと同じ調子で、志摩子を外に連れ出す。
ビスケット色の扉を開け、階段を下りていく。
「どこで話がしたいの?」
「お姉さまと初めてお会いした場所で」
それを聞き、ますますただごとではないと感じた。
姉妹を解消したいとか。…ありえない。
結局、なにを話されるかわからないまま、
真剣な表情を変えずに歩く志摩子の後ろをついていく。
高等部校舎の裏手にある桜の木々。
秋も深まりはじめる今の時期。すでに虫の姿はなくなっている。
志摩子はそのなかの一本の桜の木の前に立つと、私に話はじめた。
自分は寺の一人娘だから、この学園にはいてはいけない。
それなのにみんなを欺いて、通いつづけている…話の内容はこんな感じだ。
(あいかわらずなんて生真面目な…)
寺の娘がキリスト教の学校に通ってはいけないという法律がどこにある?
そもそも、そんなことをいちいち細かくいっていたら、
この学園に通える生徒などホンの一握りになってしまうだろう。
日本人という国民は、「宗教」という面では、とてもおおらかだ。
何せ、正月とお盆とクリスマスが仲良く暦にのっているのだから。
それを何の疑いももたず、小さな頃から過ごしてくる人々が大半なのだ。
志摩子のような考え方の人間の方が稀有な存在といって良いだろう。
そう志摩子に伝えようと、志摩子の名を呼んだ瞬間だった。
まさに、電光石火のような速さで、白き稲妻とともに、
まだ1年と経っていない過去が私の頭をよぎった。
(栞…)
忘れていた…。私は志摩子の宗教観や信仰心に対して、
何かを言える立場にいないことを。
私は一度、結果的にとはいえ、一人の人間の信仰を、
その人間の心の支えを奪おうとした人間なのだ。
まだ、その傷がいえぬうちに、私は過ちを犯そうとするのか…。
もちろん、志摩子と栞では違うことはわかっている。
告げて志摩子の心の重荷を軽くすべきなのかもしれない。
…だけど、それは私の役目ではないように思える。
志摩子も私に何かをしてもらうということは望んではいないはず。
ただ、藤堂志摩子という人間を知ってもらいたいだけなのだ。
(よし…)
大きく息を吐いてから顔を上げると、
私は志摩子に近づき、手を肩に乗せた。
そして志摩子に伝えた。いつもより優しい笑顔とともに。
「志摩子…よく今まで一人で背負ってきたわね…」
今の私にできる精一杯の思いやり。
「お姉さま…」
そういうと、今まで張り詰めていた心の緊張が解けたのか、
志摩子の目が涙ぐんでいるようだった。
うなずいてあげると、志摩子は私の胸に飛び込んできた。
左手を背中に回し、右手で柔らかい髪を撫でてあげる。
志摩子のすべてを受け止めてあげるように。
(志摩子、あなたの心の束縛から解放してくれる人間が、
きっといつか、あなたの前に現れる。その時までこの学園にいるのよ…)
当サイト公開:01.09-04
![[告白3]へ進む](../next.gif)
![[告白1]へ戻る](../back.gif)