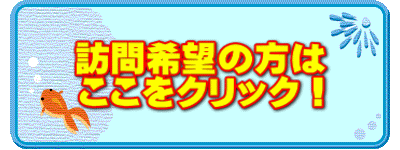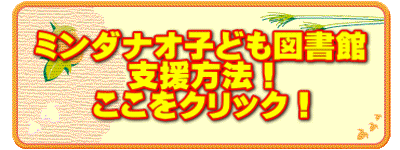1,出会い
ピキットは、『ミンダナオ子ども図書館』があるキダパワン市から車で一時間。途中にカバカンという小さな町があり、そこを越えて滔々と流れるトンゴル川を渡ってしばらく行くとピキットに着く。
たった一時間・・・・・であるにもかかわらず、キダパワンに住む人々にとってというか、むしろ一般のフィリピン人にとってもそこは遠い町。そして、同じことはピキットに住む人々にも言えるのだった。
ピキットに行く、と聞いただけで、人々は顔をしかめて言う。
「気をつけなさいよ。道路に障害物が置いてあって、止まった瞬間襲われたりするからね。例のそら、あの人たち。」
コアーン、カットーンというのは、例のそら、あの人たちといったニュアンスで、はっきり言わないまでも明確にモスリム、つまりイスラム教徒のことを指している。
モスリムの人たちも、ダバオに行くと言うだけでひどくおびえる。
途中で警察か軍隊に止められて、尋問されたあげく、無実の罪を着せられて刑務所に放り込まれ、場合によっては殺されはしないかと思うのだった。ミンダナオを夜、車で走るのは危険である。トラックの運転手だって夜は走らない。高校の先生のお通夜に近くの村に夜行ったとき、道路上に変な男が飛び出してストップをかけられ、車のスピードを緩めて、男がフロントから脇によってドアをつかもうとした瞬間に猛スピードで発進し難を逃れたのは、数ヶ月前のことだ。
彼はモスリムではない。なぜなら胸にイエスの大きな顔をプリントしたTシャツを着て、イエスの名を叫んでいたからだが、それにしても酔っているのか、異様にぎらぎらした目が今でも脳裏によみがえってくる。
障害物の噂は、本当にあった事件だろう。
確かにトンゴル川を境にして向こう側はイスラム文化圏で、キダパワンとピキットは、この川を境にしてにらみ合っているのだった。
ピキットは、僕が初めてここで読み聞かせや子ども図書館活動をやりたいと思った場所だった。
そう言う意味では、『ミンダナオ子ども図書館』の活動の原点となるような場所なのだ。2年前のこと、初めてキダパワンを訪れたときに、キダパワンの司教館に住むバリエス司教は、私たちをピキットの側の難民キャンプに連れて行ってくださった。
その印象は強烈だった。
難民キャンプというのも初めてだったが、雨が降ればそこら中から水滴がもれてくる椰子の葉やビニールシートの下に、まるで縮こまるようにして生活している家族の姿を見るのは哀れだった。
しかも、その数たるや半端ではない。3万を超える難民が、政府軍とイスラム解放戦線の戦闘を畏れて、国道沿いの安全な場所に避難してきているのだった。その多くは町から離れた平地や丘陵地帯で、トウモロコシを中心に細々と畑を耕している純朴な農民たちで、女と子どもたちがほとんどだった。
彼らは、最初は道端で路上生活をしていたのだが、混乱を避けるために、政府機関によって指定された難民キャンプに収容される。モスクの側、学校の側、公共の広場や建物が難民センターにあてられるのだが、その数があまりにも途方もないので、収容場所からはみ出してあちらこちらの道路脇に乞食小屋よりもさらにひどい感じの家とも言えないものが立ち並ぶようになる。
難民たちは、本当に骨の髄から疲れ切ったという顔をしている。何しろ数年おきに同じことがくり返されるし、水も不自由でトイレもなく、食料も全くないような暮らしが数ヶ月も続くのだから。不衛生な環境で病気になり、薬もなく、たとえあっても買えるだけのお金もないので、キャンプで死んでいく人も多い。
子どもたちの疲労困憊ぶりはさらにひどい。
日に二度の、トウモロコシを薄くとかしたようなお粥ぐらいしか食べるものがないのだから、父さんも母さんも絶望的に機嫌が悪いし、ひもじいし、泣きはらした顔がそのまま固まってしまったような顔をして、なかなか笑おうとしない。
僕がここで読み聞かせをしたいと思ったきっかけは、何よりも、わずかの間でも良いから彼らの笑顔を取り戻したいと思ったからだ。
その時、まわりに集まってきた母親たちと、言葉を交わす機会を持てた。モスリムの人たちは、ビサヤ語を話さず、独自のマギンダナオ語を話すし、僕はからっきしタガログ語がわからないので、ビッショップ自からが通訳をかって出て下さったのだ。
政府機関や大きなNGOの団体が、かろうじて生きていられる程度の食料援助と薬品の支給をしているので、何とかかんとか生きては行ける、しかし、涙も枯れ、戦闘の恐怖におびえきった心のすさびをどうしても埋めることができないでいるし、教科書もすべて失っているし、もしもちょっとした絵本やお話があって、寝る前にでも子どもたちに見せてあげられたら、それはもうどんなにか気持が違うことだろうと、熱心に話していた姿が忘れられない。
その時、僕の頭にボックス文庫の発送が初めて浮かびあがったのだ。
難民キャンプに家庭文庫は無理だろう、それよりももっと小さな、絵本や童話を箱詰めにしたボックス文庫を置いたらよいのではないだろうか、そして、異なった本が詰まった幾種類かのボックス文庫を作って、数週間にいっぺんほど、取り替えていったら良いのではないか。訪ねたときは、スタッフが子どもたちに読み聞かせをする。歌もうたう、踊りも踊る。
こちらの貧しい人々は、食べ物が無いときには、ますます愉快におしゃべりをしたり歌ったりしてひもじさを紛らわすのだけれども、結局はその後落ち込んで、隅で黙ってうずくまっていたりする。
そうした視点から見ると、妻や子どもたちを食わせるために、国道で車を止めておそいたくなる気持もわからないではないのだった。
それから2年後、僕は、ここキダパワンに住み、『ミンダナオ子ども図書館』を作る活動を始めることになる。


それから2年と少したって、僕はキダパワンで『ミンダナオ子ども図書館』を始めた。
そのころは、ピキットでの戦闘もなく、難民はすべて自分の村に帰って田畑を耕していたし、家を失った人々も、NGOなどの援助で建てられた家にうつってそれなりに平和に暮らしていたのだった。
ピキットで戦闘が再び始まったことを耳にしたのは、2002年暮れも押し迫ったころのことだった。
「再び、ピキットで戦闘があったようだ。どうやら数万人の難民が出ているらしい。」
風のたよりに聞こえてくる噂は、キダパワンでは実感のないものだった。パレンケと呼ばれる市場では、大勢の人々が買い物をしてたし、店先には肉や魚や色とりどりの野菜がところせましと並べられていたし、売り子の人々も景気のいい声を張りあげていたからだ。町には、トライシクルと呼ばれる三輪オートバイがミツバチのように走り回り、近くで戦闘が起こっているとはとても想像しがたい平和な光景が町にはあった。
僕がはじめて戦いの存在を実感したのは、難民キャンプを訪れた時だった。
トンゴル川をわたった時から、何か別の世界に入ったような雰囲気が、茶色に淀んだ川面を吹いてくるような気がした。透き通っているのだけれど鉛のように重く、幽霊のように冷たく湿った風。
道路際に難民キャンプが見え始めた。
破れかけたビニールと椰子の葉で吹かれた小屋は、小屋というよりは、山で切ってきた薪にシートをかぶせたように見えた。青のビニールシートは、政府から援助された物資だったけれども、安物だったので隅からほつれ、熱帯の強い日差しのなかで劣化しバサバサにほつれていた。
それは、とても人の住める家には見えなかった。これらに比べれば、上野公園の浮浪者村のビニール小屋はまるで御殿である。2人が横になればいっぱいのスペースの中に家族5人が住んでいたりする。それは、寒さに対応する必要のない熱帯のフィリピンだからこそ、生きていけるようなしろものだった。