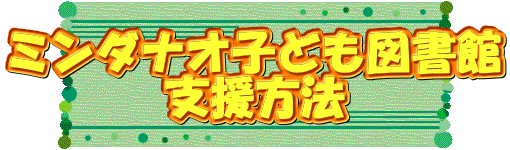わたしの少女時代の想い出から
松居 エープリルリン
ミンダナオ子ども図書館を立ちあげてきた
松居エープリルリンの子ども時代からの体験記です。
感想等をお寄せいただければ幸いです。
mcltomo@gmail.com
わたしの少女時代の
想い出から(1)
松居 エープリルリン
(これから、妻のエープリルリンが、
少女時代からミンダナオ子ども図書館に至るまでの、
自分の体験を書いていきます。
初回は、すでに拙著『手をつなごうよ』(彩流社)に掲載された文の引用です。)

1985年4月20日、わたしは兎口で生まれた。5人兄弟姉妹の2番目。
わたしが生まれても、母さんは、わたしを自分の子どもと思ってくれなかったし、何の世話もしてくれなかった。
おばさんが、めんどうを見てくれただけ。普通とちがう顔で生まれたから、それからあとの人生でも、さんざんいじめられて育った。
でも、恥ずかしいとは思わなかった。
それどころか兎口で生まれたことを誇りにおもった。兄弟姉妹のなかでも、ユニークな顔立ちだから。
しかし、思った以上に人生はきびしく、そう簡単ではなかった。
「なぜ、わたしの顔はこんななの?」
「なんで、こんな顔になってしまっりぐちまで押しやって、外になげだそうとした。わたしは、あわてて、母の服をつかんだ。
それを見たおとなりさんが、すかさずさけんだ。
「自分のむすめに何ということをしているの!頭がおかしいんじゃない!あんた、娘を殺すつもり!」
おおきな叫び声に、隣近所のひとたちが、家からでてきた。それを見て、母さんは、わたしを外においたままドアを閉めた。
その後、おばがわたしを引き取って、数ヶ月そこですごした。そのごも、親戚から親戚へとたらい回しに回されて、一年たって家へもどった。
わたしは、小学校に行きたくてしょうがなかった。一年生になれることに、興奮していた。友だちには、クラスメートになる子もいた。でも、予想したとおり、彼らは、わたしを「兎口!」といって、ばかにした。
それでも、わたしはそれを受け入れて、かえって勉強に精をだしたので、クラスでトップになった。でも、両親は、表彰式の日にはこなかった。わたしがクラスでトップになって、授賞式の日がいつか、知っていたのに。
下の妹がわたしを呼んで、人混みのなかをいっしょに両親を探したけれど、どこにもいなかった。しかたなく、わたしはひとりステージに立ち、リボンとメダルを受けとった。涙がほおを伝わって流れるのを感じた。
家に帰ると、家のなかの様子がおかしくて、そっとカバンとメダルをテーブルにおくと、バケツを持って水くみにいこうときめた。
そとにでて、家の扉をしめようとしたとき、父にあった。父は、わたしを家におしもどした。中にはいると、メダルとリボンは、めちゃくちゃになりこわされていた。わたしは、泣いた。
その夜、母は弟と妹をつれると家を出ていった。
姉は祖母のところにいき、わたしは、下の妹と残された。その後、父も友だちと仕事をさがしてどこか遠くへ行ってしまい、わたしは下の妹と叔母の家に住むことになった。





わたしの少女時代の思い出から(3)
松居 エープリルリン
おばあちゃんが叔母の家に滞在している間だけは、私は本当に幸せだった。なぜこんなに幸せな気持ちになれるのか、わからないほど幸せだった。
初めて私は、じぶんが本当の普通の子どもになれたような気がしたの。
友だちと外で遊ぶこともできたし、いつも台所仕事をし続けなくても良かったし・・・。
私は、外に飛びだしていくと、ゴム段飛びや石けりや缶けり、鬼ごっこやかくれんぼ、ハンカチ落としもしたわ。ジャンケンポイや、後ろの正面だーれ、花いちもんめみたいな遊びもした。
とってもとっても幸せで、時間のたつのがわからなかったぐらい。そして、気がついたら夕暮れで、あたりは暗くなり始めていた。狭い路地裏で、虫たちやカエルの声が聞こえてきた。
私は、急ぎ足で家へとむかった。胸はドキドキ、息を切らしながら・・・。
暗闇から、誰かが私の名前を呼んだような気がして振り向いたけれども、何も見えなかった。大きなマンゴーの木が、小道の横に生えていて、大枝が伸びて小道を真っ暗におおっていたわ。
とつぜん、冷たい風が顔に吹きかかって、耳につぶやき声が聞こえたような気がして、髪の毛が逆立った。
私は、そこを必死に駆け抜けたの。息が詰まったような感じで、喉がかわいたの。ちょっとでも良いから、お水が欲しい!
そしたら、向こうの方に、明かりが見えて、人の話し声が聞こえたわ。とってもうれしくなったけど、一方で悲しくなってきた。なぜなら、叔母さんの家だったから。
家に近づいて、扉の前の段を上がってドアをたたこうとしたとき、中から声が聞こえたわ。
「いったい、あの子は、どこに行ったのかね。大丈夫かね。」
ほとんど夕食をたべる時間で、おばあちゃんが叔母さんにたずねたのね。
すると叔母さんは答えた。
「あの子は、いつもあんな調子なのよ。帰りが遅いし。私には、あの子がどこに行ったのか、さっぱりわからない。まったく、心配ばかりかけるんだから!」
私がいつも外に遊びに行って、夜遅く帰ってくるなんて嘘よ! ドアの後ろに立っている私の耳には、叔母さんが、沢山の嘘を言っているのが聞こえてきた。
私は、ドアをたたいて、こんばんわを言って中に入った。そして、叔母さんとおばあちゃんの手を額につけて、祝福をうけた。
「おそくなって、ごめんなさい。お友だちと夢中で遊んでいて、暗くなるのがわからなかったの。」
謝ると、おばあちゃんが言った。
「わかったわ。でも、二度と遅くならないようにね。女の子でしょ。夜道を歩いていて、襲われて、レイプでもされたら大変だからね。」
すると今度は、叔母さんが言った。
「暗闇だったら、だれも助けることが出来ないのよ。そうなったら、私の責任になるんだからね。」
「わかりました。ごめんなさい。もう二度としません」と、私は答えた。
その日の夜、夕ご飯が終わると、みんなでお皿を洗ったり台所の後かたづけをしたので、私、ビックリしたわ。
叔母さんは私に、台所を全部きれいにしたら豚に餌をやって、それが終わったら外の井戸で水を汲んでこいと、命令しなかったし、洗濯もさせなかった。そのうえ、真夜中の12時に、叔母さんの妹を国道まで迎えに行かなくても良かったから・・・。
そのかわり、私はまだ小さいし、夜遅くまで起きていないで早く寝なさい、と言ってくれた。
私、本当にビックリ。
何故こんなになったの?おばあちゃんがいるからかしら?本心から、言っているのかしら?いつまで、続けるかしら? 沢山の困惑と疑問が、パズルのように飛び交った。
私は、子どもの頃から、沢山の試練を経験したの。
本当だったら、大人になってから体験するような試練をね。避けることの出来ない試練だったし、私の意志では、どうすることも出来なかったから。
本当に、ときどきおもったわ、人生って不平等だって。
ある人たちは、必要以上の物を所有しているのに、ある人は何も持っていないんだもん。ある人たちは、貪欲にたくさんの物を得ていくけど、他の人たちは、ちょっとしたものでも得られない。
コケコッコー!
鶏の鳴き声がして目が覚めた。早朝、お日様が顔をだした。
朝食の用意が出来ていて、学校に行く支度がすむと、私は浴室で水浴びをした。
すると、おばあちゃんが叔母さんに、こう話しかけているのが聞こえてきた。
「わたしは、妹のジェクを家に連れていくわ。あなただけで、二人の子どもの面倒をみるのは、大変そうだから。エープリルを、ここに残してね。」
とつぜん、私の目から涙がこぼれてきた。
何も聞いていなかったような顔をして、部屋のなかに入っていくと叔母さんが言った。
「学校に行く用意はできた?」
「ええ。」
そう答えたものの、妹が私を置いてきぼりにして、行ってしまうかと思うと、寂しくって言葉を継ぐことも出来なかった。
妹のジェクは、申し訳なさそうに言った。
「私、おばあちゃんの所に行くことになったの。」
「ええ。」私は、それしか答えようがなかった。
おばあちゃんが、叔母さんに言った。
「ビン、それじゃあ、私たちは、出かけるからね。」
「わかったわ。お気をつけて。またいらっしゃってね」
私たちは小道に出ると、私は学校に向かい、おばあちゃんと妹のジェクは、おばあちゃんの家に行くために乗り合いジープの停留所に向かった。
私は、妹に言った。
「元気でね。おばあちゃんのところで、いたずらっ子したら駄目だよ。いい、わかった。」
そして、私たちは、抱きあってそれから、さようならを言った。そして、手をふりながら、私は、妹とおばあちゃんの姿が見えなくなるまで見送った。
わたしの少女時代の思い出から(4)
松居エープリルリン
学校に向かって歩きはじめたけれど、あいかわらず涙がほおを伝わって流れ落ちていった。
そのとき、ふっと頭の中に、学校に行くようになる前に、まだ山のなかの祖父母の家のそばに住んでいた頃の懐かしい想い出が浮かび上がってきた。
まだ小さな子どもだったころ、わたしたちは山の奥の集落に住んでいたの。まわりに親戚の人たちの家が5軒ほどしか建っていなかったわ。セブから移住してきたわたしの祖父母をのぞいて、みな先住民のマンダヤ族の人たちだった。
マンダヤ族の人たちは、精霊を信じていて、森や野原には、たくさんの妖精たちや先祖の霊たちが住んでいると思って生活していた。
斜面にトウモロコシを植えて、わずかばかりの陸稲を育てて、ココナツと地中に植えたサツマイモやカサバイモ、紫イモやサトイモを掘って生活をしていたの。
わずかばかりの鶏を飼って、川から魚を捕って、ときには山の奥でイノシシや鹿を捕獲して来たりしたけれど、現金収入は山の下の村の人々が持っている田んぼのあぜの草刈りや、家々をまわって洗濯物を集めて日銭を稼ぐぐらいがせいぜい。
学校に向かって歩いている私の心に浮かんできたのは、おばあちゃんと下の川に洗濯に行ったときの想いで。
おばあちゃんといっしょに洗濯に行くとき、川は私の大好きな場所だったの。
「リン!」おばあちゃんが、わたしを呼んでいる声がする。
「こっちにおいで!」
近くに行くと、おばあちゃんは言った。
わたしの少女時代の思い出から(5)
松居エープリルリン
とつぜん、学校の鐘が鳴る音が聞こえた。
わたしは、びっくりして子どものころの想い出から、目を覚ました。
学校にいそがなくっちゃ、国旗掲揚にまにあわなくっちゃ!もう少しで遅刻しそう!
どきどきしながら、幸せな子ども時代の想いでから飛びだすと、国旗掲揚式の列に飛びこんだ。
クラスメートの友だちは、わたしの顔を見るといぶかしげに言った。
「どうして、そんなに悲しそうな顔をしているの?」
「何かあったの?」
けれども、何も答えられず、ただ首を横にふるだけだった。しかし、友だちは心配して、なっとくしなかった。
「何かあったんでしょ。言ったら良いのに。」
わたしは、自分のほおに涙が伝わって流れているのに気づかなかった。そこで、友だちたちは、わたしを抱きしめると、慰めてくれた。
わたしたち生徒は、イスにこしかけて、先生の話に耳をかたむけた。
先生は、試験の日が近づいているから、ちゃんと準備をはじめるように、と話し始めた。けれど、教室はうるさくて、外からも話し声が聞こえてくるので、クラスの子どもたちに向かって、静かにするように言った。
わたしは、すわったまま、ぼんやりと生徒たちを見ていた。
静かにするように、といわれても、どうしたらいいのか、何を言ったらいいかがわからなかった。
自分の意識は、どこかはるか遠くにいったままだった。
わたしは、一方向に顔を向けたまま、ぼおっと思いに沈みこみ、ただぼんやると遠くを見つめていた。
外は明るくてさわやかだった。
太陽の光が、窓のひさしをとおして流れこみ、緑の花のもようがプリント
「たぶん、やつらだよ!」
もう一人の子が、ドアの近くに座っている男の子たちを指して言った。
それと同時に、少年たちは、笑い転げた。
しかし、私たちの幾人かが笑わず、怒っているのをみて少年たちもだまった。
少女の名は、クリスティーナ。
彼女は、いすに座ったままぶつぶつつぶやきながら、親友のジェイデュにたずねた。
「紙くずを投げたのは誰か知っている?」
しかし、彼女も誰が投げたか知らなかった。
クリスティーナは、それでもときどき後ろを振り向いた。
「エープリルリン!エープリルリン!エープリルリン!」
先生が三度わたしを呼んだ。でも、わたしには聞こえなかった。先生は、欠席や退席がいないか、確認していたのだ。
とつぜん、わたしの方に、誰かが触れたのをわたしは感じた。そのとき、わたしは、不思議な幻想からめざめた。
「フーーッ!」驚きのため息が口からこぼれた。
「先生が、三度も名前を呼んだんだよ!」
隣の席に座っている、オマールがいった。
「エッ!ほんとう!」
クラス中の子どもたちが、まゆげをあげて目をまん丸にして馬鹿にしたように笑った。
「あなたの心は、寒風に吹き飛ばされて、どこかかなたの人がいない場所をさまよっていたのね、エープリルリン!」
クラスの子どもたちは、大笑いをした。教室がどよめいた。お腹を抱えて笑う子もいた。
「いったい、どうしたというの!なぜそんなに一人で寂しそうな顔をしているの?」先生はいった。
なんと答えたら良いのかわからなかった。
わたしはうつむいて、床をみつめた。
長い髪が、肩からたれた。
わたしは沈み込んで、どうやって今の気持ちを伝えたら良いか、と考えた。
しかし、どこから説明して良いかわからなかった。
どう話したら良いの?どうやって説明したら良いの? 困惑したし、話すことに躊躇もあった。
「どちらにしても、いいわ、エープリルリン!今、話さなくってもだいじょうぶ。」
先生は、そう話した。
わたしは先生の顔をみつめた。
わたしの少女時代の思い出から(6)
松居 エープリルリン
一日で、いちばん待ちに待った時間がきた。クラスメートの一人が叫んだ。
「さあ、わたしたちの大好きな、あの場所に行こうよ!」
「行こう!」
「行こうよ!」
「行こう、行こう!」
みんな教室から駆け出すと、食堂に向かった。そこには、学校のなかに小さなカフェテリアがあるの。
わたしもいっしょに駆け出したけれど、わたしは、食べものを買うお金が無いから見物だけ。
でも、ふだんは、教室にすわって、授業が始まる前まで、宿題をするの。
食堂では、みんな座りこんで、サンドイッチや地元のおいしいおやつを食べながら、楽しくおしゃべりをしているのよ。地元のおやつは、甘焼きバナナ、お団子、カサバイモのケーキなど。そして飲み物は、コカコーラ、スプライトやジュースがあるわ。
食堂の入り口には、チラシがはってあって、こう書いてあるの。
「かならず最初に来た人から、順番に並ぶこと!」
だから、何か食べたいものを買いたい人は、いち列に並ばなければならないの。でも、生徒のなかには、並ばないで駆けこんでくる子もいるわ。特に、男の子たち。
「ビバリー!ビバリー!」
ジョナサンが、名前を呼んだ。
ビバリーは、前に並んでいたけれど、自分の名が呼ばれるのを耳にしてふり向いて、誰が自分を呼んだのかを見届けようとしたわ。
「なあに?ジョナサン!」
ビバリーは応えた。
「頼みたいことがあるの! わたしのために、マンゴーのジュースを一缶と、カサバケーキを買ってくれない?お願い!」
ジョナサンは、そう言うと、ビバリーに駆けよって、お金を彼女の手のひらにわたした。
ビバリーはうなずくと、言われるままに、ジョナサンのお金をにぎりしめた。
先生の何人かは、家で作ったアイスキャンデーや氷菓子を持ってきて、また生徒も、家で煎ったピーナッツ持ってきたり、ときにはピーナッツバターやキャラメルを作って持ってきて、休み時間に売っている。
わたしも、することが無いときには、先生が家で作って持ってきたお菓子を売るのを手伝った。そうすると、先生は、わたしにアイスキャンデーや氷菓子を食べさせてくれたし、ときには、学校のプロジェクトや授業で使う用紙代を払ってくれたの。 ベルが鳴った。
教室にもどらなくっちゃ。つぎは算数で、足し算と引き算の問題を解く授業。私にとって大好きな科目だから、授業に集中して、問題を解いたり計算をしたりするのよ。 クラスメートの何人かは、算数の授業中に居眠りしていた。だから、試験になっても答えが解らないのよね。
そして授業が終わりに近づくと、先生は、生徒たちに課題をだした。
「つぎの単元に入る前に、今のところをちゃんと理解することが大切ね。だからそのためにも、この宿題をやっておきなさい。」
クラスメートの何人かは、席に座ったままぶつぶつと文句をいった。算数は難しくって、どうしたら良いか解らなかったから。
「みなさん、さようなら。」と、先生はいった。
「先生、さようなら。」わたしたちは応えた。
先生が、教室からでると、クラスメートたちは、さっき先生が出した課題について話し合った。
「エープリルリン、先生の説明、わかった?」アレクシスが聞いた。
彼は、教室で一番のっぽで、のんびりやの楽天家だ。でも宿題やプロジェクトが嫌いで、ときどき落第点をとったけれど、それでも気にしない子だった。
「たぶん、わかったと思うわ。」と、わたしは答えた。
お昼時間の30分前に、午前中の授業は終了した。さあ、早くお家に帰って、お昼ごはんの用意をしなくっちゃ。叔母さんと叔父さんが、畑から帰ってくるし、3人の従姉妹たちも、お弁当を持って学校に行っていないから、家に食べに帰ってくるし。
わたしは家に帰ると、といだお米を火にかけて、豚の所に行ってエサを与え、山羊には、少しお塩をとかした、水をあげた。
豚と山羊にエサをやり終えて、ごはんを炊いている場所にもどって来ると、学校から帰ってきた従姉妹たちに、作ったお昼を出して、いっしょに食べた。
その後、わたしは、学校に駆けもどった。
1時5分前には、教室に戻っていなくちゃいけないのに、でも、いつも10分ほど遅れてしまう。なぜって、学校まで15分から20分ほど、歩かなくてはならないから。
でも、いつも遅れてしまっても、先生たちは、わたしの立場を良く理解してくれていたわ。
先生は、「明日からは特別な授業の日で、学校の創立記念日の準備をします。ですから、一週間のあいだ、お昼は家に帰らずに、お弁当を持ってくるようにしなさい。」といった。
校長先生は、父母宛に手紙も書いた。
このイベントの間、たくさんのスポーツ競技が開催され、学校の催し物が行われるの。でもわたしは、家に帰ってお昼の準備をしなければならないから、お弁当を持ってこられなかったし、スポーツも催し物にも参加できなかったの。
クラスメートたちは、とっても興奮して、どのスポーツと、どのイベントに参加しようかと話し合っていたわ。
私たちの住んでいるところは海に近く、「埋め立て地」とも呼ばれていて、高潮になると、泥だらけになるので、通り道には、サックに石と土をつめたものが置かれて固めてあった。
海に向かっている道や小道の近くには、たくさんのマングローブが植わっていてね、小さな穴が空いていて、小蟹や小魚が、マングローブの根元に隠れていたりするのよ。
わたしたちの家の床下にさえ、小蟹が穴から穴へ駆け抜けたり、ときには家の食器棚に入っていたりしていたわ。
その日の午後、わたしは一人で、古い錆びた橋をわたってから、狭くてきゅうくつな脇道に入っていた。
人々のうわさでは、このあたりは一人で歩いちゃ駄目、とのことだった。
「特に錆びた橋の近くは、急いで通り過ぎなさい。ときどき、物騒なことが起こっているからね。仕事が無くって、ギャングのような若者たちの、たまり場になっているから、とっても危ない場所だよ。」
あるとき真っ暗闇の中で、若い少女が襲われてレイプされて、亡くなったという話も聞かされていた。電灯はあったけれども、古くて道を照らすほどは、明るくはないの。
でもわたしは、みんながそんな話しをしていても、今までそこを通るのを、怖いと思った事はなかったわ。
ときには、人が立っていて、話したり笑ったりしているけれど、笑いかけて通り過ぎたし、人々もわたしを見て微笑んでくれたわ。わたしが、兎口であったにもかかわらず。
わたしはいつでも、どこでもお祈りして、神様を信じていた。でも、その日の帰り道に、橋を渡って、すぐに細い横道に向かったら、後ろから、誰かが、わたしの名を呼ぶ声が聞こえた。
「エープリルリン、エープリルリン!」
だれかが、わたしを呼び止めている。
心臓がどきどきして、髪の毛が逆立ったわ。怖くて心配になったけれども、怖さに負けまいとして、一瞬立ち止まって、ふり向くと、遠くからわたしを見て手をふっている、数人の人たちが見えたの。
「エープリルリン!なぜ、一人なんだ?友達はいないのかい?」
その中の一人がたずねた。汚れたズボンをはいて、灰色のシャツを着て、色の違った外履きを履いている。
「わたし、みんなよりも、先に帰ってきたの。だって、みんなスポーツやイベントの準備で、いそがしいんだもん」と、わたしは応えた。
「そうかい、気をつけて帰りなよ。」
「ありがとう!」
わたしは、笑顔で応えた。
「みんなは、午後に、いっしょに学校から帰るけれど、わたしは先に帰って、家族の夕食の支度をしなくっちゃならないのよ。」
そういうとわたしは、彼らに手をふって、わきの細道を帰っていった。
わたしの少女時代の思い出から(7)
松居 エープリルリン
午後5時をまわった頃、私は家につくと、日常の仕事をするために着替えた。そして、いつものようにまずご飯を炊いた。そして、竈の上にかけたまま、山羊を捕まえに裏庭に出ていった。
叔母は、山羊を5匹飼っていた。1匹は雄山羊で2匹は雌山羊、そして2匹の子ヤギがいた。私は毎朝、山羊たちを裏庭に連れ出すと、草を食べさせるために木につないだ。そして、お昼になると、彼らの喉を潤すために水辺につれていった。
午後には、縄をほどくと柵に入れ、塩の入った水をあたえ、イピルイピルの葉を夕ご飯に食べさせた。
オイン オイン オイン! とつぜん裏庭から豚の鳴く声がした。あわてて台所にとびこむと、私はナイフをもってカンコンの葉をとり、細かく刻んでモミ殻と水に少し塩を加えて豚に与えた。
私が近づいていくと、豚たちは大騒ぎする。少しでも前に出ようと、お互いに押しあいながら食卓に駆けてくると、必死に鳴き声をたてながら寄ってきて、木の器にエサを入れてやると、互いに鼻で押し合いながら真っ先に食べようとした。そして、お腹がいっぱいになると、静かになって、数匹は眠った。
私は、ホースの水で豚小屋を洗った後に、豚の体も洗ってあげた。くさい臭いが外をただよって、隣近所に迷惑をかけないように。
そのあと、私はココナツのなっている場所に行くと、三つのココナツの実をとって半分に割り、中身をこすってニワトリのエサを作った。ニワトリのエサは、普段はどこにでも生えているココナツの実だった。
しかし、ちょっとお金があるときは、モミ殻を買うことが出来た。そしてトウモロコシの収穫があったときは、その種を蒔いてあげるのが一番簡単なエサのやりかただった。
ニワトリにエサをやったあと、巣をのぞいて卵を産んでいないか確かめた。でも、卵が一つも見つからなければ、そのまま台所にもどるしかなかった。
「わあ!」
台所にもどったとたん、私は叫んだ。お米を炊いていたことを忘れていたのだ。
ご飯は、ほとんど炊きあがっていたので、私はあわてて竈から石炭をかきだした。幸い、ごはんはまだ焦げていなかった。もし気づかなかったなら、真っ黒焦げになっていただろう。
夕方の6時半になると、魚のスープを作るための野菜と香辛料を用意しなければならなかった。
野菜は西洋ワサビ、香辛料はレモングラス、ショウガ、タマネギ、トマトにコショウとネギの葉、それが魚のスープの下味だった。
鍋に水を入れると、まず水をわかすために炉の上においた。
煮立つと、ネギの葉以外の香辛料を鍋の水のなかにいれて、味付けのための塩を加え、さらに数分煮立たせながら塩が溶けるようにかきまぜた。
その後、野菜を入れる前に、まずは魚を先に入れてから煮えるまで数分おき、煮すぎないところで最後に西洋ワサビとネギを入れた。そしていよいよ魚のスープが出来上がると、炉から鍋を降ろして安全な場所に移した。
そのとき私は、誰かが来たような気配を感じた。ドアの開け口の方で足音がして、胸に手を当てた!私は家に一人っきりのはず、もしも何か起こっても、誰も助けてくれないわ!
するとドアの取っ手が動き、突然開いた。
私の胸が高鳴った。
ビックリして、心臓が飛ぶような気がしたけれど、見ると叔母さんだった。農場から帰ってきたのだ。
「まあ!どうしたって言うの?なぜ、そんな目で私を見つめているの?まるで幽霊みたいに!」と叔母はいった。
「ああ!何でもないの。誰が入ってきたのか不安になったの。ノックも無かったから」と私は答えた。
「わかったわ。とりあえず採ってきた野菜を台所に運んでちょうだい」と、叔母はいった。
「はい、おばさま」私は答えた。
テーブルの準備は出来て、夕食の支度が完了すると、家の人たちは7時から夕食を食べ始める。
その間に私は、服とシーツと他の洗濯物を洗うために、洗濯場に行った。
洗濯機はないから、手で洗うほか仕方が無い。最初に、洗濯物の仕分けをしなければならない。
まずは、農作業用の服と普段着をわけた。なぜなら、農作業用の服は汚れがひどかったから。その後、色の付いている服と白い服を分け、さらに厚手と薄手の服を分けて下着を別にした。
それが終わると、ポンプから水を汲んで来て、洗濯物を洗い流すために使う二つの大きなゴムバケツに水を満たした。そしてバケツを持ってくると、そのなかで洗濯を始めた。
その時また、だれかが私の名を呼ぶのを聞いた。
私は当惑してどこから声がするのか耳をそばだてた。しかし、声は突然聞こえなくなった。
たぶん空耳ね。そうおもって、洗濯を続けた。
そして9時15分を過ぎた頃、洗濯をし終わり干し場にかけた。そしてとってもお腹がすいていたので台所の裏に行って食べものを探した。
よく見ると籐籠のおおいの下に、家の人が食べ残した夕食が置かれているのを見つけた。
魚の残りが半分と、トウガラシとお酢と小さな塩魚を見つけたとき、お腹がグウグウ鳴った。とてもお腹がすいていたから、食べものを見つけるなりあっという間に平らげた。そして食べ終わると、すぐに食器洗い場にいった。
食器洗い場には、沢山の食べ終わったお皿が重なって置いてあった。家の人たちは、食べ終わったお皿を洗うこともしなかった。
私が全てをきれいにしてきちっと整理整頓してから、再度外に出てポンプから水を汲み、明日のための水をゴムバケツに満たした。なぜなら、私たちの村から水源は遠かったし、村には沢山の人がいたから。特に昼間は水を使う人が多くて、夜のうちに汲んでおかなければ足りなくなってしまったから。
「わあ!何て明るくてきれいな空!今日は、満月ね!満月の日は、満潮ね!」
私は、お月様が本当に明るいので驚いた。
海辺からは、まるで木々の間を風が吹き抜けるかのように潮騒が聞こえてくる。波の音が、子守歌のようにザブンー ザブンーと耳をくすぐる。波音は、私の心を穏やかにしてくれ、私の想いは波に包まれて浜辺へと飛んだ。
浜辺に立って夜空を見あげている間、またたいている美しい星々の事を想わずにはいられなかった。
周囲を見わたしていると、月と星の明かりで宇宙全体が輝いて見えはじめた。冷たい風の音が、まるで浜辺の波の音のように聞こえてくる。
波打ち際を歩いているあいだ、波が私の足を洗ってくれる。周囲の砂がクリスタルのような美しさで輝きだした。
「へい、どうしんだい!なぜ空を見つめているの。ぼおっとして、まるで目と心がどこか遠くに行ってしまったみたいだね。」
私の肩がたたかれて、後ろから叔母の声がした。
「ああ、叔母さん!」私はいった。そして、とつぜん瞑想から目覚めた。