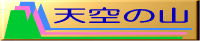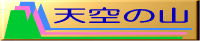
このページは、[天空の山]の分室です。

| すぐ役立つ 山の雑学 |
| 岳人編集部・編 |
| 東京新聞出版局・1999・ISBN4-8083-0662-X・\1400 |
| 前回に続いて、今回も、『学』が付くご本だが、 今回ご紹介するご本は、主に山についてのよもやま話集。 その内容は、食事の献立や摂り方から始まって、地形、天気、技術論、道具、伝承まで、 山に関わりのあるいろんな事が、1話2ページのコラム形式で、多数収録されている。 普通、この手の本だと、保守的で、旧態堅持的な論調が目立ち、辟易とさせられる事が多いのだが、 このご本は、今現在一線で活躍されている達人たちが書かれたコラムの集大成なので、 山への持ちこみに依然として賛否両論ある携帯電話についても、比較的賛成な見解が述べられているし、 一方で、海外からの帰化動植物についてのページがあるなど、 最近の風潮流行にのった、読んでいて容易に納得することが出来るものである。 山岳会などに入っていれば、山についての、最近の潮流や山岳伝承などを 先輩や仲間から耳にし、自然と覚えて行くことが出来るのだろうが、 そういった組織に基盤を持たないtanaのような一匹狼的な山屋にとっては、 この種の本は、自分の知見を広げることが出来る手っ取り早い近道であると思う。 特にこのご本は、話題も多種多様で、堅苦しく系統立てられている訳でもないから、 興味本位で楽しく読みつつ、いろいろと新しい話題に接する事が出来る。 本当は邪道なのかもしれないが、そういった読み方の出来るご本である。 No.2/02.08-18
|
| 山の自然学 |
| 小泉武栄 |
| 岩波書店・岩波文庫・1998・ISBN4-00-430541-1・\660 |
| この本は、『山の自然学』を提唱していらっしゃる、小泉武栄という人の書いた、 簡単に言うと、まさに表題そのままの内容のご本である。 もう少し詳しく中身を見てみると、礼文島の海岸線で、高山植物が見られる理由とか、 北八ヶ岳の縞枯山や蓼科山の山腹の針葉樹林が縞枯れる原因とか、 或いは、珍しい亀の甲羅型をした地面の模様(亀甲状土)と氷河期の関係とか そういった、地形と植生と、そして気候にまたがった、総合的な山の自然についてのご本である。 この本の気に入っているところは、(著者も『まえがき』で言っておられるが) 『学』と付きながら、素人にとっては、あまりに小難し過ぎる地形学や気象学、植物学といった、 いわば『学問』に深く触れる事なく、それでいて、地形と植生と気候の確かなつながりを示してくれる、 そういう、専門知識・基礎知識を持たずとも読みやすいことである。 そして、現象の解説だけにとどまらず、それが実際どんなところで発生しているのか、 それが一体どれ程すごいことで、貴重なことなのか、といった 学問的にはそれほど重要ではないのかもしれないが、 しかし、アマチュア山屋が一番知りたい話の核心部分を的確に突いてきてくれる、 そんな、いわば素人向けの入門者なのである。 だが、よく読んでいくと、入門書といってはばかられるほど、いろいろと考察されている。 tanaもこのご本を読んで目から鱗が落ちたことがいくつもあった。 さあ、このご本を持って、実際に野山の自然の中へ飛び出してみよう! No.1/02.07-26
|
![[天空の山]のTopへ戻る](../top.gif)