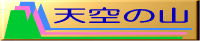あんなこと、こんなこと
随想集
このページでは、“山”をメインに据えながら、それだけにはとどまらず、
tanaの心がとらえた日々のうつろいを、少しずつながらも紹介して行きたいと思います。
▲(6)『フェイルセーフ』
今回も前回に引き続いて、山における『安全』に関するお話。
『フェイルセーフ(failsafe)』という言葉がある。
これは『万が一故障した場合に、できる限り安全な方向へ物事を進める為に、設計すること』を意味する、主に工学的な分野で用いられる言葉である。またも鉄道の例を引用して恐縮だが、鉄道においては、数限りなく、フェイルセーフ思想に基づく設計・行動がとられている。
例えば、鉄道信号機では、故障した場合には、必ず赤が点灯するようになっている(実際にはフィラメントが2系統入っており、1本が切れた段階で、電圧が変化し検出できる、という話だが)し、霧や信号機の故障などで信号の確認が出来ない場合、運転士は、列車に対して最も速度制限をかける信号(つまりは停止を意味する赤信号)が現示されているものとして取り扱うことになっているし、或いは線路内に何か支障物があった場合には、防護無線といわれる列車緊急停止信号を発報して、関係がないかもしれない列車も含めて、とりあえず、近隣を走るすべての列車を止め、安全が確保されてから、各列車の運転を再開させたりする。
ここに挙げたのはほんの一例であるが、要は、安全を保つ上で疑わしいことがあったら、もっとも危険な状態を想定し、それに対する備えを執った上で、原因の究明なり、復旧なりをする、とそういうことである。
ひるがえって、山の世界でのことを考えてみよう。
tanaは山岳会や登山団体に属している訳ではないので、母校の山岳部の山行に同行する時以外は、たいてい単独で山に入っている。tanaだけではないと思うが、初めて歩く山だと、仮に地図を確認しながら歩いていても、時として、道に迷うことがある(そして、ほとんどの場合、あとから考えてみると、何でこんな場所で?、と首を傾げたくなるようなところで迷っていたりする)。そんなルートを喪失してしまった場合、山の教科書はどう教えているだろうか。そう、地図と地形に最大限の注意を払いながら確実に分かるところまで戻りなさい、と言っているのだ。
しかし、果たして、ルートが分からなくなってしまった人のどれくらいが、一旦後戻りをして確認をしているのだろうか。tanaの場合、さらにちょっと進んで分からなければ戻って確認するようにしているが、周りの登山者の方々を見ていると、『あれ〜、この道でいいんだっけ?』などと言いながら、どんどん進んでいく人が結構目に付く。きっと、結果的にその方々にとってはその道でよかったからこそ、遭難のニュースが流れていないのだろうが、もし、本当に違う道を進んでいたとしたら、どうするつもりなのだろう。
別の登山口に下りてしまったくらいならまだかわいいものだが、例えば、林業用の作業道を進んでしまい、全然分からないところに出てしまったり、或いは、獣道に入り込んでしまい、いつの間にやら前後踏跡不明という事だってありえる。そうならないためにも、疑わしくなったら、すぐに地図と対照して分かる地点、すなわち安全な所まで戻ることが大切なのだ。すなわち、フェイルセーフの方針を採る事が重要なのである。
山でフェイルセーフ思想を生かせるのは、ルートが分からなくなってしまった場合だけではない。水が足りなくなりそうだったら、早めに給水して不慮の事態に備えることが肝要だし、落石の危険が見てとれる場所は、避けて通ったほうが安全である。避けて通ることが叶わぬなら、せめて、写真を撮ったり草花を愛でていたりせずに、すばやく通過することが大切である。その他、広い意味でのフェイルセーフ思想が生かせる場面は五万とあるだろう。
最近、山での遭難事例が相次いでいる。(もちろんフェイルセーフを意識しすぎると、それはそれで問題があるが)山的フェイルセーフ思想を常に心のどこかに持ちながら歩いていれば、その遭難の幾分かは発生せずにすんだのではないかと思う。山は危険な場所である、そしてわずかでも不安を感じたら、なるだけ安全な方策を採らなければならない。自戒を含めて、改めて深く考え直さなければならないと思う。
(03.10-17)
▲(5)安全の『綱領』
山登り、或いは山歩きというのは危険な行為である。単独山行はなおの事であるが、当然、団体山行でも充分に危険である。何が危険かと、容易に思いつくものだけでも、滑落、転落、転倒、火傷、ルート喪失、雪崩、溺れ、消耗など、いくつもの遭難例を挙げられる。それに輪をかけて、救助、収容、救命が容易でないという、二次的な要因も『山』を危険にしている。
しかし、その一方で、年間何万人という人が、北・中央・南アルプス、八ヶ岳、富士山などの中部山岳や、それこそ全国各地の『山』と名の付くあらゆる場所に行き、大自然と山そのものを楽しんでいる。(もちろん、予測・回避が不可能な止むを得ない事故、というのもあるものの)多くの人たちは、自分なりの遭難防止策を考え、実行に移しているからこそ、遭難せずに、無事に下山できるのであるが、ごく一部の人たちが、無謀にも、自分の技量や考えを確固とせずして山に入り、そのさらに一部の人たちが、不幸にして遭難の憂き目にあっているのである。そして、山に理解のない世間やマスコミは、そういう人たちを『それ見た事か』と罵り、なお一層『山は危険だ』というイメージを浸透させて行くのだ。
ところで、一転して話は変わるが、当サイトの管理人であるtanaは鉄道職員である。日本の鉄道の大きな特徴は、定時運行の確保率とともに、もうひとつ、安全性の高さも挙げられる。過去起きた幾多の大事故を教訓にしながら、日々運行しているわけだが、ここ最近では、鉄道側の責任事故において、死傷者が発生したというケースは極めてまれである。
鉄道関係者であれば、桜木町事故(列車火災)や三河島事故(多重衝突)といった鉄道の教科書に載っている歴史上の事故、一般の方なら、信楽高原鉄道事故(正面衝突)や日比谷線中目黒駅事故(競合脱線)などの比較的最近の大事故を思い起こされると思うが、列車の運行本数と、死傷者の数を比率にするならば、実は、責任死傷事故は驚異的に少ないのである(飛び込み自殺などの、鉄道の責任に因らない事故は除く)。
事故の発生率が驚異的に少ない理由は、もちろんお客様の協力というものが大いにあるが、さらに、鉄道職員に浸透した、安全に対する意識の高さというのもある。その一端を示したのが、国鉄の『綱領』と呼ばれる、安全確保に関する標語である。
綱領
1.安全は、輸送業務の最大の使命である。
2.安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によって築きあげられる。
3.確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。
4.安全の確保のためには、職責を超えて一致協力しなければならない。
5.疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。
現在では、JRも含めてすべての鉄道会社の『綱領』は、もっと簡潔なものになっているが、上に掲げた国鉄の綱領は所々を置き換えさえすれば、何にでも応用できる。そして、山に在る者にとっては、まさにピッタンコ(古!)なフレーズではないか。
前書きが長くなってしまったが、今回言いたいことは何かといえば、それは、
山に入り、山を歩く時に、すべての人が、
『安全は、山行最大の使命である』と考えて、
『安全の確保は、ルールの遵守及び行動の厳正から始まり、不断の修練によって築きあげられる』ものであり、
『確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である』ことを肝に銘じ、
『安全の確保のためには、パーティを超えて一致協力しなければならない』のは当然であると認識し、
『疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない』旨の判断をする事が出来る様になれば、過去に起きた不幸で悲しい山の上での多くの事故が、きっと、将来においては防ぎ得るのではないか、と、そういうことである。
(03.10-07)
▲(4)行動記録のすゝめ
山歩きが他のスポーツと違うところは、『記録』を求めないことである。もちろん、山岳マラソンや競技登山、未踏峰登山などは、『優勝』や『初登頂』といった名誉的記録を手にするために登っているのであるが、大多数の"山歩き"をする人達は、その登る理由はさまざまであろうが、決して、陸上競技や球技のような『優勝』とか『最高タイム』とか言うモノを求めて、山に足を運んでいるのではない。今はやりの日本百名完全踏破も、ある面から見れば『記録』を得ようとしているのだが、しかし、反面から見てみると、それは山に登る口実を作る、ひとつの目標に過ぎない。
『楽しむ』為に山に登っている以上、最低限のルールと常識さえ弁えていれば、どんな登り方、どんな楽しみ方をしようが、まったくもって各人の自由なのだが、その事を承知の上で、tanaには敢えて言いたいことがある。それは『山行中の行動記録を採ってみてはどうだろうか』と言うことである。
下界の煩わしさから逃げるために山に来たのに、なんで、余計に面倒臭いことをしなくてはならないのか、と言う意見もあろう。しかし、tanaは記録を採る事によって、ただ単純に山に登って降りるという以外に、新しい楽しみ方も出てくるのではないか、と思うのである。例えば、草花を愛でるために山に登る人。当然写真撮影やスケッチ、標本採集などをするだろう。その時、撮影位置や採取地点が分かっていた方がどれほど楽しいことだろう。美しい景色を写真に映しに山に入る人。この人達も、撮影場所や時刻は後に写真を整理する時に重要な記録である。みんなでワイワイガヤガヤ楽しむために山に行く人。山の上で楽しかった場所、苦しくて励まし合った場所を記録しておけば、帰宅した後も、話のネタに困ることはない。山関連のWebサイトを開いている人。そんな人にとっては、当然、重要な『サイト更新の源』である。もちろん、すべての山歩きをする人にとって、次に同じ山に登る時の、ペース配分を考える最良の材料にもなる。
記録をつけるということは、後からその記録を読み返した時に、もう一度その時の景色を思い出せ、その時の気分に浸れる、と言うことなのである。山に登って、楽しんで降りてくる。それはそれでいい。それはそれでいいのだが、しかし、降りてきた後にもう一度楽しめる手を放っておく事もないのではないだろうか。
で、行動記録を採る、と言うと誰もが真っ先に思い出すのが、鉛筆とメモ用紙というオーソドックスな記録方法である。確かに、この方法が一番確実だし、いろいろと書きこみも出来て便利なのだが、苦しい思いをしてやっと到着した休憩の貴重な時間を、メモ採りに奪われると言うのは、慣れないと大変苦痛である。慣れたって楽しいものではない。ましてや、行動中に書くなどと言う神業が出来るようになるには相当の修練が要る。
そこでtanaはデジカメ記録を勧めたい。かなり廉価になり、一気に普及しているデジタルカメラであるが、このデジタルカメラで撮影した1枚1枚の画像ファイルには、大抵の場合、ファイルの情報として、撮影時刻(ファイル作成時刻)が記録されている。そこで、これを生かして、思いつくままにどんどんデジカメで撮っていくのである。休憩の風景や分岐地点、迷ったところや景色が良かったところなど、どうせ不必要な画像は後で消せるのだから、構図や美術性を気にすることなく、バンバン撮影していけばいい。そして、家に帰ってきてから、それらの思い出の写真と画像ファイルのプロパティ(情報)を同時に見ながらメモに起こしていけば、さほど手間もかからないで、しっかりした記録を作ることが出来る。
『写真を撮る』というデジタルカメラの本来の使い方とはちょっと違うかもしれないけど、気楽にスナップ撮影するつもりで写真を撮り、その撮影時刻情報から、行動記録を作っていく。一見遠回りなように見えるが、やってみると意外なほどカンタン。デジカメの価格が唯一の難点だが、それさえ克服できるのならば、皆さんも一度試してみてはいかがだろうか。
(02.10-01)
▲(3)ザックの中身
最近、中高年の登山ブームが益々強くなっている。花を愛でる山登りだったり、日本百名山の制覇を目指していたり、又は、ごく実用的に山菜採りが目的だったりと、その理由は様々であろうが、オジザマ・オバサマの集団(時にペア、時に数十人規模)が、山の中を闊歩する姿を頻繁に見かけるようになったのは事実であり、山登り・山歩きが社会的な認知を得始めてきた証拠として、とてもうれしい事である。
ところで、この中高年登山というのには、いくつかの特徴がある。ひとつに、騒々しい事。しかし、これはtanaも人の事を言えた義理ではないので、触れないでおこう。ふたつめに妙に装備が整っている事。貧乏学生などとは違って、ある程度お金に自由が利く年代ならではの特徴であろう。みっつめにパーティーの装備が全員そっくりな事。きっと、みんなで買い物に行って、横並び意識で同じようなものを買ってきたのだろう。そして、最大の特徴は、ザックがやけに小さい事。
みんながみんな、立派なストック持って、雲ひとつない真っ青なお空を無視してレインスパッツつけて、やる気満々の重装備なのにもかかわらず、どの人のザックも『その中に一体何を入れる事が出来たの』と思わず聞きたくなるくらい、小さい。その割に、休憩になると、その小さなザックの中から、オバサマ方はこれでもかと言うくらいの量の行動食を取り出して食べている。じゃあ、行動食を除くとザックの中には一体何が入っているのであろう。
山登り、或いは山歩きでの基本的は『自己完結』である。すなわち、自分に必要なものは自分で持って行く、なにかあっても自力下山出来るように最低限度の用意をしておく、という事である。当然、大人数のパーティになればなるほど、必要なものは増えていくから、パーティ内での分担という事は必要になってくるけれども、でも、基本はなにも変わらないと思う。
加えて、山登りや山歩きというのは、『石橋を叩いて渡る』慎重さが必要だと思う。
- 日帰りの予定であっても、途中で道に迷って暗くなってしまうかもしれない→ヘッドランプを持っていこう、
- 天候が急変して雨が降るかもしれない→雨具と下着と靴下くらいは着替えを持っていこう(いざ本当に遭難すると、乾いた下着や靴下と言うのが、命を救う場面もある)、
- 途中でころんで擦りむいてしまうかも知れない→洗浄用にも使える様に水をほんのちょっと多めに持っていこう、
いろいろと考えられる『起きてもおかしくないトラブル』が本当に起きてしまった時に、無事に下山出来るよう、そして、そのことでかけなくてもいい心配を、周りの人にかけなくても済むように、山へ行く時は容易周到に、そして、準備万端整えて行く事が大切だと思うのである。
ひるがえって、オジサマ・オバサマについて考えてみると、どうもこういう考え方が浸透していないように思われるのである。雨が降ってきてキャーキャー騒いでいるオバサマたち、ろくな装備も持たずに山菜採りに山へ入り、無残な報道の対象者となるオバサマたち、どこでくっちゃべって時間を浪費していたのかは知らないが、暗くなり始めてから立ち往生しているオバサマたち、どれもこれも、『自己完結』と『慎重さ』がないが為に起きてしまう事故である。
もちろん、不必要なものまで(持って行きたければ持っていっても構わないけど)持って行く必要はないし、慎重になり過ぎてしまって、日帰りのくせにやけにデカいザックをしょって歩いているのも、滑稽であると同時に逆に危険でもある。要は、ある程度のトラブルは自力で乗り越えられるように、装備は常識の範囲内で、という事になるのである。オジサマ・オバサマたちにももう少し最低ラインの常識をお持ち頂き、事故・トラブルを未然に防いで、楽しい山歩き(今でも当人たちは充分に楽しそうだけど)と、『山は危険』というイメージの払拭にご協力を頂ければ、と、常々石橋を叩きすぎてしまって、ザックがやけに大きくなってしまうtanaは思うのである。
(02.08-11)
▲(2) (続)山はスポーツか。
tanaは放送大学の学生として科目を選択し勉強しているが、今学期の履修科目のひとつに『保健体育〜生涯スポーツへの誘い〜』と言うのがある。これは文字通り、運動生理学や体育論、それにスポーツ医学や健康管理学の立場から、体育というものについて考える科目である。その第1回の講義の中に『スポーツの概念』という単元があり、そこに、前回の本欄で考えた『山はスポーツか』という疑問の手がかりとなる説明があったので、それを紹介しながら、前回に続いて考えてみたい。
印刷教材(放送大学では教科書の事をこう呼ぶ)によると、『スポーツ』という語の意味的内容を歴史的変遷から眺めてみると、次の3つに分ける事が出来るという。1つ目は、15〜16世紀の、スポーツという語のもとになったラテン語に由来する『気晴らし・娯楽一般』という意味。2つ目はイングランドの支配階級の青少年によって行われたクリケットやフットボールなどから生れた『成文ルールを持ち、体力と技術を必要とする組織的競技』という意味。そして3つ目は先進国で生まれたSports For All運動(条件の如何に関わらず、全ての人にスポーツを、という運動)によって提唱された『多用な人々の必要に応じ得る多様な身体活動』という意味。さて、あなたの心にある『スポーツ』とはこのうちの一体どれであろうか。
多くの人がイメージするスポーツというのは、やはり2番目の『競技』としてのスポーツではないだろうか。もちろん『登山』という領域にはそのイメージにあった、競技登山やマラソン登山といったものも存在する。しかしtanaには、『山』というカテゴリーの身体活動が持つとして意味を考えると、1番目、或いは3番目のスポーツがそれに似合っているような気がする。それは『山』というものが、ただ単に『頂上を極める事だけを目的とした身体活動』とだけでは定義できないからだ。蒼く深い空を愛でる人あり、大地狭しと咲き誇る草花を慈しむ人あり、急峻に挑むスリルを味わう人あり、そして、山に在るという雰囲気を楽しむ人あり。ピークハントという目的の他にも、山にはとても多くの楽しみ方、接し方があるのだ。
先に挙げたスポーツの歴史から見た意味の1つ目は、趣味登山に見事に当てはまる。tanaなどはまさに日々のストレスから逃避し『気晴らし』の為に『娯楽』として山に登っているのだから。一方、最近増えている中高年層以上の人たちは、と見れば、それは3つ目の意味が適当だろう。友達作りや体力の維持、達成感の追求の為に百名山を登る姿は、『体力の向上、精神的充足感の表出、社会的関係の形成』を掲げたヨーロッパスポーツ憲章の定義する『スポーツ』にそのままである。もちろん、インターハイや富士山登山駅伝などで争われる競技登山やスピード登山は、2つ目の意味で言うところの『競技』スポーツである。
すなわち、『山』という身体運動のカテゴリーは、考えられる『スポーツ』のすべてを満たしうるパーフェクトなものだ、ということである。さあ、みなさん。もう悩む事はないのです(というか、悩んでいたのは自分だけ?)。山は立派な『スポーツ』なのです。あとは『年寄り臭い』とか『危険だ』とかいったイメージを抱いている世間のイメージを変えていけるように、自分たちが行動するだけなのです。目についたゴミを拾おう!、でも、美しい自然を広く紹介する!、でも、いやもっと小さく、絶対事故を起さない!、でもいいから、そんな小さな、しかし新しい思いを胸にtanaも山に登ることにしようと思う。
(02.01-28)
▲(1) 山はスポーツか。
先日、職場の球技大会に誘われた。絶対に参加できないというほどの用事はなかったのだが、複数溜まっていた細事を理由に、参加しなかった。別に参加しても良かったのだが、参加したら参加したで、絶対にいい気分で帰れるはずがない、と分かっていたからだ。なぜか。その理由は簡単。自分が世間一般でいうところの『スポーツ』に向いていない性格だ、と言うことを理解しているからである。
どうも自分は団体競技や球技という奴に向いていないらしい。チームの他の人と心を合わせて、他人が失敗したらそれをフォローしあって………という世界がことのほか苦手なのだ。もちろんよっぽど気の合った仲間と一緒に馬鹿騒ぎしながら、なら楽しいかもしれない。しかし、さほど親しくない職場の人たちと一緒にやっても、辛くなっていくのがオチだと思う。そんなわけで参加しなかった。
以前から気になっている事に『山はスポーツか』というものがあった。模範解答としてはどこだかの外国の登山家が言ったという『山登りは観客のいないスポーツである』というのあるが、どうもうさんくさい言い方だ、と思う。こんな言い方が出来るのは、登頂や踏破など、記録に挑戦していて、一般からもその価値を認めてもらっている前衛登山だけではないか、と思うのだ。
自分は『スポーツ』と聞くと、『競い合い、対戦、観衆』というキーワードが一緒に浮かんでくる。このキーワードを元にすれば、一人や何人かで散策するように山に登るのは、『スポーツ』ではない。しかし、他に良い言葉が見つからない。『運動』ではどうか。確かに山登りはかなりのエネルギーを消費して行っている運動ではあるが、なんか堅苦しい。ラジオ体操じゃあるまいし。『山行』ならどうか。確かに仲間内では意味が通じるが、普通の人には説明しにくい。
というわけで、この疑問は自分の中で継続中である。良いご意見があれば教えてください。
(01.08-01)
このコーナー(だけには限りません)では、皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。
メール、またはご意見・ご感想のページにてお便り下さい。
お待ちしております。
![[天空の山]のTopへ戻る](../top.gif)


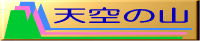 このページは、[天空の山]の分室です。
このページは、[天空の山]の分室です。



![[天空の山]のTopへ戻る](../top.gif)